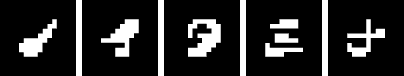NOITAMINA
OFFICAIL WEBSITE
SHARE
ツイート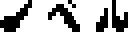 NOVEL
NOVEL
ノイタミナノベル「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」 第4話

『願いの代金』
「んー、まぁ……ざっと、二十万はかからいな」
ぽっぽのバイト先の偉い人、兼、花火師のオヤジさんは、太くて短い指でタバコを揉み消しながら言った。
「! に、二十万……」
「ええ、おいさん! ディスカウントプリーズ!?」
「かなりディスカウントしての、そいつだで」
「う……」
オヤジさんの家に出向いた俺とぽっぽは、玄関先で顔を見合わせた。謎の作業道具が野ざらしにされた中庭で、オヤジさんちの猫がバッタを前足で踏んでいる。
「うー……バイト増やしゃ、なんとかなるか?」
「あ、ぽっぽ。俺も、バイトする……」
言いかけた俺の言葉を、オヤジさんが遮った。
「あんた、高校行ってんだろ?」
「え? あ……行ってはいな……あ、所属はしてます」
「だったら、バイト許可証が必要だいな」
「バイト、許可証?」
「前よ、ガキ仕事場に入れたらトラブル起こしやがって。それから高校の許可ないと、うちの現場は難しくなったんよ」
許可証が必要……ってことは。
「学校行って、取ってこなきゃ……ってことか」
思わず呟いた俺を、ぽっぽがじっと見つめていた。
「いーって、じんたん! 金は俺にまかせてよぉ!」
帰り道にある自販機で、ぽっぽはなぜかコーヒーを買ってくれた。
学校に行って、バイト許可証をとってくる。
なんでそんな単純なことが、こんなにも大きく俺の足を引っ張ってくるんだ。どうしてそんな簡単なことが、俺には……。
「じんたんはリーダーなんだから、どーんっと! しんがりとってくれよ、な?」
「…………」
「それに、めんまが見えるのじんたんだけなんだからよ! しっかり、めんまの気持ちフォローしてやってくれよ。そういうの、超重要だって……お、そうだ。あなる達にも連絡しとこうぜ!」
携帯を取り出し、安城に電話をかけているぽっぽ……どう考えても、俺に気ぃ使ってんだよな。これ。
「なんだよー。あなるの奴、電話でねぇでやんの」
「まだ、学校なんじゃねぇの」
「あ、そか。んじゃ、ユキアツらにはメールにしとくか!」
あの頃、みそっかすだったぽっぽに、こんなに助けられて。
なんて情けないんだろな……俺。
まだ、空は高かった。
午後からバイトに行くってぽっぽと、交差点で別れた。まだクソ暑いけれど、吹く風にほんの少しスッとする草の匂いを嗅ぐ……空の青に浮かんだでっかい雲は、すでに秋の形をしていた。
「…………」
ほんの少しのことも、難しくなった現状。
けど、めんまがここに戻ってきたことは、少しのことなんかじゃない。
*
翌朝。こういうのを、勢いっていうんだなと感じていた。
歯を磨いて顔を洗って。ここんとこの儀礼の、学校に行くフリ……をしながら家を出ようとした俺に、めんまが不思議なことを言った。
「あのね。じんたん、ごめんね」
「? なに、謝ってるんだよ」
「あのね、謝るのはタダだからだよ!」
「……タダだと、必要なくてもとりあえず謝っておくのか」
「んっ、そうだよー!」
どうしてめんまは、俺に謝ったのか。
もしかして、やっぱり空気を察したんだろうか。俺が、バイトのことやら学校のことやら考えているのを。
そんなことをもやもや思い出しつつ、歩いていたら。気づけば、俺の歩くその道は通学路だった。
「きゃはは……!」
黄色い笑い声。制服姿の生徒達が、脇を通り過ぎていく。相当、歩幅は大きめに取ってるはずなのに、どんどん追い抜かれていく。
気にすんな、勢いだ。そして平常心。
余計なことを考えれば、学校へ行けなくなっちまう。
学校に行けなくなれば、バイトだってできない……めんまを、成仏させてやることができないんだ。
「じっんったんの、最近はぁ……♪」
景気づけに、小さく口の中で歌ってみた。
俺のムリヤリの平常心は、かなりの成果をあげた。なんと、昇降口までやって来れたんだ。久々の、シューズの裏のゴムがむれたようなにおいを嗅ぐ。
「うわー、まじかよ」
「よく平気な顔して学校これるよなぁ」
声が聞こえてくる。
さすがに、平常心が揺らぎかける。そもそも、俺の通常運転ってどんなんだっけ?
とりあえず下を見つめ続けろ。目なんて会っちまった日には、それこそ……。
「あれだろ、一年三組の――……」
「そうそう、安城鳴子!」
「!?」
安城の名前に、ポリシーとして俯いていた顔を思わず上げてしまった。
「!」
廊下の先に、教師の後をついてふてくされて歩いて行く安城の姿。
俺と目が合った瞬間。安城は、すぐに泣きそうな顔に変わり、視線をそらした。
教師と共に去っていく安城の背中に、生徒達の噂話が重なっていく。ただ、廊下ってシチュエーションもあって、微妙に反響して文字通り『ざわつく』音の塊にしか聞こえない。
どういうことだ……?
噂話の内容は、すぐにわかった。
教室では、安城の話題で持ちきりだったからだ。
自分の席をいまいち忘れていたため、そこらにいた地味目の野郎に声をかけると、「あそこが空いてる」と教えてくれた。俺にたいした興味はいだかなかったようだ。
それでも中には「あれって、誰だっけ?」なんて、俺の存在に注目してくれたりする目ざとい女子もいる。けれど、その注目に持続力はない。久しぶりに、学校に来た珍しい人種。それをいじることよりも、いつも学校にいる奴の珍しい行動のほうが、ずっとおいしいらしい。
安城がやらかしたこと――……それは。
「ぬかったよねぇ~、鳴子。ラブホテルぐらい、いいじゃんねぇ」
「PTAに見られたんだってぇ。相手、おっさんだったらしいよ」
「援交~!?」
安城と仲のいいチャーシューみたいな女達は、さっきまでの俺みたいに、こそこそとしている。
なんとなく、何が起こったか想像はつく。
でも……想像がつくのと、信じるのは別だ。
安城が、ラブホだなんて。いや、今の安城だったらなんの不思議もないルックスなんだが……でも……。
そのとき、ガラッと扉が開いた。
「はい、席に着いてぇ~……」
久しぶりに見た、気の弱そうな担任の顔。その後ろに、挑むような視線を中空にむけ安城が立っている。
生徒達の視線が、一斉にそちらに向けられる。もちろん、俺の視線も。
「えー……授業を、はじめます。安城もほら、席お願いね~……」
安城は、好奇の視線の大海の中を、モーゼみたいにつっきって来る。
あの状況は、もともと俺に与えられた舞台だったはずなのに。
安城は俺の後ろの席についた。うん、確かこんな並びだったはずだ。安城の隣の豚女が、さっそく軽く身を乗り出し、親しげに声をかける。
かすかに聞こえてきた、その言葉。
「運悪かったよねぇ、鳴子」
「…………」
安城は、チャーシューの言葉を無視した。チャーシューは、気まずそうに席に座り直す。安城のラブホ事件に、なんかしらの関わりがあるんだろう。
「はい、教科書ひらいてぇ~……」
気の抜けた教師の声に、ぬるぬると授業がはじまる。
もう、俺のことを気にとめてる奴は、皆無になった。
頼りない教師を無視し、安城をちらちらと盗み見る。噂話の塊の中に、ときおりまざる『ラブホ』『エロ』などのわかりやすいワード。『頼めばやらしてもらえるかも』なんて、野卑た声も。そして、こらえた笑い声……。
なんて、不条理なんだ。
これらの責め苦は、全部俺に与えられるはずだったのに。
ときたま『ヒキコモリ』やら『めずらしい』なんて声が聞こえてくると、なぜか小踊りしたくなるくらいだ。
背後から、シャーペンが走る音が響いてくる――安城だ。
こんな時でもあいつ、ノートとってんのか。見た目あんなになっても、相変わらず生真面目なんだな……。
昔から安城は、ほんっと頭悪くて。いっつも誰より綺麗にノートとってんのに、テストじゃ点数低くて。
それでも、やっぱ真面目にノートとることやめなくて。いつでも必死こいて、几帳面にびっちり小さな字で……。
「…………」
思わず、ちらっと振りかえる。安城が心配だったから……いや。それよりも、『安城のノート』を久しぶりに見たかったのかもしれない。
自分でもよくわからないけれど、その動作をした。すると、目に飛び込んできた安城のノートは、几帳面さのかけらもない。乱雑な文字が、大きさも場所もランダムに書き連ねられていた。
そこにある文字。『やってねー』『違うっての』『勝手なことぬかすな』『永遠に黙れ、死ね』そして、片隅に小さく書かれた文字は――。
『助けて』
「!!」
安城は、できるかぎりのぶっきらぼうさを装いながらシャーペンを動かし続ける。
その音はもう、泣き声にしか聞こえなかった。
『ギャハハ……!』
どこからかあがる下品な笑いに、安城の肩がびくっと跳ねた。でも、跳ねたのは俺も一緒で――……。
バンッ!
「え……?」
気づけば俺は、立ちあがっていた。
両手を大きく広げ、クラスの奴ら全員にアピールする。
「お前ら――……俺を見ろッ!!」
「じ……じんた……?」
「俺を見ろ! 久々に学校に来た男だ。入学してからこのかた、入学式と最初の一週間しか来てねぇっ……どうだこの顔、さぞめずらしかろう!」
担任は、やっと俺の存在に気づいた様子で、名簿を慌てて見る。
「あれ……君? えっと、宿海君……?」
ざわつきを構成する言葉に『なんだあいつ?』『宿海ってやつじゃねぇ?』なんてのが混ざってくる……多くの視線が、俺に集中する。
そうだ、この視線は全部俺のもんだ! そう簡単にはわたさねーぞ! ってな思いを存分に込め、びしっと安城を指さした。
「こいつなんて、いつでもどこでもホイホイ会える。ラブホ? それぐらいで大騒ぎか? こいつはどっからどう見たって、ラブホの一つや二つぐらい行ってそうなラブホ顔じゃねぇか!」
「ら、ラブホ顔!? ちょっと……」
「だがなっ!」
「!?」
もう、止まらなった。
かあっと耳が熱くなるのを感じながら、熱をそのまま、言葉に乗せる。
「言っておくが、こいつに限って援交やらはない! なにしろ、こいつはA型のおとめ座で、眼鏡で! 冒険なんて無縁な眼鏡のくそ真面目、くそつまらない女で……うっ!」
「余計なこと言うなッ!」
慌てて俺を、背後から羽交い絞めにしてくる安城。
そこで、やっと気づけば。俺に集中する好奇の視線とざわつきは、見事に消失してた。かわりにあるのは、幾つものぽかーんとした半開きの口……。
「あ、あの~……」
「! あっ……い、行くよ宿海!」
「安城……お、おい!」
安城に腕をひかれ、転びそうな勢いで教室から出ていく。
誰も追いかけてくる奴はいなかった。担任の間延びした声だけが、
「ま、待ちな~……さいよ~……?」
と、かろうじて呼び止める『真似』をしてくれた。
「あはははは……!」
鳴子は、笑いがとまらなかった。隣でむすっとしている仁太のとんがらせた唇が、幼いころの『ふてくされ』とまったく変わらなくて、それがさらに笑いを加速させた。
「俺を見ろ! だって。どー考えたって変態じゃん!!」
「う、うっせーぞ!」
公園のあずま屋に二人、腰をかける。まだ小学校も終わっていない時間、がらんとした公園には自分達だけ、それを晴れた空までふくめて『許された場所』のように感じて、鳴子は笑いつづけた。
「あは………はあっ。もう、お腹痛いよ!」にじんだ涙を、ひとさし指でぬぐう。今朝からずっと重苦しかった胃のあたり、そこにたまっていたもやもやした気持ちが、笑いとともに一気に吐き出されたような感覚があった。
「………でも、ありがと」
「え……」
「私のこと、かばってくれた」
「安城……」
「あっ……でもっ。ラブホ顔はない! ほんとにラブホ、行ってなんかないよ。ってか入ったこともないし!!」
「はいはい、わかったから」
「はいはいってなに!」
知らぬ間に、形勢逆転。でもそれが、鳴子には心地よかった。公園の片隅には、ボール遊び用のネットがぶら下がっている。ずっと距離のあった仁太と、ぽんぽんと会話の応酬ができること。夏空の下の、キャッチボール。
仁太の変化は――正しくは、仁太が『昔の仁太』の面影を取り戻したのは。
(めんまが戻って来たから、なんだ)
鳴子の胸の上に、ずっとのしかかっていた感情。
(あの日……自分が、あんなことを言いださなければ。もしかして、めんまは)
だからこそ、めんまに向きあうのが辛かった。けれど、本当にめんまが戻ってきているのなら。このまま目をそらしつづければ、めんまを『また』遠ざけてしまうことになるんだ。
鳴子の鞄には、秘密基地から持ち帰ったままの交換日記が入っている。
「あのさ……」
「ん?」
「宿海んち、行ってもいいかな。皆も誘ってさ」
一瞬、面喰った表情をみせ。しかし次の瞬間には、仁太はあまりにも自然な笑みをみせた。
「ああ……さんきゅ」
さんきゅ。その、暖かなひびき。感謝されることなんて、ひとつもないのに。
あんなことを言ってしまった自分が、許せなかった。じんたんを――好きだった自分が、許せなかった。
だからこそ、もしかしてわざと、仁太に嫌われるような方向ばかりを向いていたのかもしれない。こんな暖かな言葉を、間違っても受け取れないような状況に、自分を置こうとしていたのかも。
でも、もう逃げたくない。
めんまのためにも、仁太のためにも――……自分のためにも。
*
「あなるぅうう!!」
どすんと、めんまは安城に突進していった。
かすかに安城の身体が揺れる。安城の表情が、わずかに強張る。
「わああ。あなるのおしり、女の人のおしり。おっきくなったねえ!」
「はは……尻、でかいってさ」
「こ、こらっ。めんまっ!」
安城は、真っ赤になってめんまを叩くふりをした。あっという間に、強張った表情はどこへやら消失していた。
その振り上げた腕は、まったく見当違いな方向を向いている。それでも、めんまはきゃっきゃっと頭を押さえてはしゃいで……。
「ごめんごめんご!」
「なんだよそれ……だったら、ごめんまのがよくね?」
「え、なにそれ宿海。ごめんまって」
「え? あ……」
「ごめんま? ごめんまって、なぁにー?」
この間は不発だったごめんまを、几帳面な安城は救い上げてくれた。助かった……とは思えない。
「あー……えっと。ごめんの、変形。めんまに、謝るとき……にのみ、有効。みたいなやつ……」
「あはは! なにそれ、一ミリも面白くないっ!!」
「おもしろくない、ですYO!」
「面白くないなら、笑うなよ!」
会話が、成立している。
めんまが安城には見えないだなんて、信じられなくなる。不思議な居心地の良さを感じていた俺に、インターホンの音色が声をかけてきた。
「めんま、しっぱいしたぁ。蒸しパン、作っておけばよかったのに!」
夏でも電源をいれずに、ちゃぶ台として使用してる掘りごたつ。その三辺に、ぴったりと収まった松雪、鶴見、安城……その場に流れる、無言を気にしつつ。俺はめんまに手をひかれ、台所にやってきた。
「えええ。じゃあ、カントリーマアムあったよね、あれ出してもいい? お客さんだから!」
「はいはい……好きにすりゃいいだろ」
松雪達から見える位置にある、台所の戸棚。めんまは躊躇なく開き、そこから菓子入れを取りだした。
「!!」
「……あっ」
背後の空気の変化に、やっと俺も気づく。
……すっかり忘れていた。
めんまが何かに触れて、何かが動く。この超常現象を、奴らがあからさまに目にするのは、あの∞の花火以来なんだ。
「さあさあ、どぞどぞ、マアムどぞー!」
めんまは陽気に口にしながら、菓子入れを居間へと運ぶ。
俺にはめんまが見えているから、奇妙な光景には見えない。だけれど、めんまが見えてない奴からなら、こりゃ立派なホーンテッドマンションだろう。
「あ……」
鶴見の動揺する顔、ってのを見るのは初めてだ。それでも安城なんかは、さっきの会話の応酬の実績のせいか、ちょっと笑顔までみせている。
「カントリーマアム好き。チンすると美味しいよね」
「ちんかぁ! じんたん、ちんしてちん!」
「うっせえ。そのまま食え」
「なっ……別に、頼んだわけじゃないでしょ!」
「あっ。今のは、めんまが……」
すると。黙って菓子入れを見つめていた松雪が、呟いた。
「めんま……そこにいる、のか」
「え? あ、ああ……うん」
「いますよー、ユキアツ! ここですよ、ここ!」
「お、おい。めんま……!」
めんまは、松雪の髪をわさわさと動かしてみせた。
「っ! か、髪が……」
鶴見は思わず、声をあげた。エアドライヤーでも使ってるみたいに、勝手に松雪の髪が揺れている。
「めんま! ほら、こっち」
俺はめんまの腕を、慌てて引っ張った。
「めんま……まだ髪、長いのか」
「ん? ああ。ってーか……俺らとおんなじに、成長してんだよな。こいつ」
「!!」
またも、空気が変化する。俺に視線が集中する。
「成長してる? どういうことなの……?」
「ねー、なんでだろうねぇ?」
鶴見と安城は、困惑としかいえない表情をしている。しかし松雪は、さらに視線を鋭くして。低い声音で、
「……美人か?」
「な……ッ!?」
想像もしていなかった角度からの台詞に、頬がかあっと熱くなる。
「松雪! おま……何言ってんだよ! こんな……!」
言葉を続けようとして、めんまの顔に視線をうつした時。
めんまの、くるっと丸い瞳に――……よぎった、映像があった。
あの日。「めんまを好きなのか」と問われて、あまりにも考えなしに、めんまにぶつけてしまったあの言葉。
「だーれが、こんなブス!」
ずっと、俺にまとわりつく。後悔にべたべた塗りたくられた言葉……。
「宿海……?」
我にかえると、まだ皆の視線は俺のもとにあった。
めんまの顔を、再度確認するのは気恥ずかしい。わざと別の方を向いて、もごもごと口の中で呟いてみる。
「……ほ、ほどほどに、まあまあ、美……人、つか。可愛い……系」
すると、どがっ。めんまが、首にしがみついてきた。
「えええ? なにー、まあまあって!」
「う、うっせえ………あっ!」
ちょうど、神の助けのように携帯が震える。
「ちょ、ちょい待て! メールきてるから……」
「メール?」
安城も、身を乗り出してくる。
「あ、久川から? そろそろ来るって?」
「あ……なんだよ、バイトぬけらんねえってさ」
「えー、ぽっぽに会いたかったのにぃ!」
ぽっぽからの携帯には、添付ファイルがくっついていた。開いてみると、『俺からめんまへの愛』の書き文字とともに、むちゅーと唇を突き出すぽっぽの、ひたすら気色悪いキス写メだった。
「なんだこれ……」
「きゃははは! ぽっぽ、ルージュラだぁ!」
喜ぶめんまの横顔に、ふっとこの状況に対する緊張を忘れかけたが、「めんまに返信させてやれば?」松雪の冷たい声で、すぐに緊張がよみがえる。
「めんまに、返信……?」
「ああ。蒸しパン作れるんだから、携帯のメールぐらい打てるだろ?」
「え……でも」
めんまはぱあっと瞳を輝かせ、俺の手から携帯を奪い取った。
「そっかあ! かしてかして……えっと、こうやるんだよね?」
めんまは、見よう見まねで液晶画面を押し始めた……けれど、やはり反応しない。
「……あ」
「無理……みたいだな」
「ねえ。めんま、文字とか書けないの? 筆談」
「ああ。試してはみたんだけど……」
そう、めんまはとりあえずのことはできる。シャワーの蛇口をひねることも、メシを作ることだって。だけど……なぜか、感情を形にして残そうとすると。それは全て、上滑りしていく。
「ふーん……理屈にならない理屈だな」
松雪はあからさまに、不審げな態度をとってみせた。
「……なんだよ、それ」
「だって、おかしいだろ。ペンは持てる、でも字は書けないなんて」
「は? めんまが、嘘ついてるっていうのかよ!」
松雪の嫌みったらしい物言いに、思わず声を荒げてしまう。しかし、松雪はこともなげに。
「お前が、嘘ついてるんじゃないかって言ってるんだよ」
「! な……っ」
「ユキアツ! じんたんは、そんなことしないよ!」
「ちょ、ちょっと! 待ちなってば二人とも……あっ、そうだ! 私、交換日記持ってきたんだった……ほら、めんまこれ!」
流れてしまった険悪な空気を、必死に変えようとして。安城が鞄から日記帳を取り出した。安城がそれを差し出した位置に、ちょうどめんまがいた。
しかし――めんまは、そのまま固まってしまった。
「これ……ママから、もらってきたの?」
「あっ! い、いや……」
俺が言いよどんだのに気づき、安城もハッとなる。
めんまが、なんとなく自分の親のことを気にしているのなんて、そばにいなけりゃ見逃してしまうことだ。それでも、あの母親のオーラを目の当たりにした安城は、すぐに日記を見せようとする行為が『間違ったことだ』と気づいたらしい。慌てて、日記を鞄にしまおうとしながら、
「あ、あの。ごめ……やっぱ……」
「見せて、あなる!」
めんまが、バッと日記を奪い取った。
「あっ……」
めんまは、日記のページをめくりはじめた。一枚一枚を、じっと見つめる……安城も、松雪も、鶴見も。その動きを、食い入るように見つめている。
「め、めんま……」
「あ、ここ。こんにちはが、こんにちわになってるやー! しっぱい、しっぱい!」
めんまは明るい声音で、そのまま日記帳にくっついた小さなペンをかまえてみせた。
「えっ……おい! めんま、やめろっ……」
どうせ書けないとわかっていても、それでもめんまはペンを取った。そして、紙の上を滑らせ……。
「!!」
驚いた。ペンの軌跡が、するすると気持ちよく描かれていく。
『こんにちは』
「! めんま……」
めんまも、目をぱちくりさせている。俺よりずっと、驚いているはずだ……でも、にかっ。なんでもねえっすよ、てな感じの笑みをみせて。
「へへー、これでせいかい!」
「…………」
そして、俺よりめんまよりずっと驚いているのが、松雪達だ。
「めんまの字……だね」
じっと『こんにちは』を見つめ続けていた安城の瞳から、涙がこぼれる。
「そうね……」
鶴見の声は、どこかふわふわしてる。感情と声が、うまくリンクしてない。
そして、松雪は……。
「めんま、元気だったか? ……って、へんな言い方だな」
「うんっ。えーとねぇ……」
書かれていく文字『めんまは、げんきです』。それを見つめる松雪の瞳の奥が、ゆらりと揺れた気がした。
松雪は、顔をあげた……笑顔というには微妙な、ぐにゃりと歪んだ口元。ごくりと、唾を飲む音が聞こえたような気がした。
「だったらさ……交換日記、はじめないか。また」
「! えっ……」
*
九月に入ってから初めて、少し肌寒いと感じる夕暮れ。
集と知利子、鳴子は、宿海家からの帰り道を並んで歩いていた。
「喜んでたね、めんま。交換日記……」
自分の影を見つめて、鳴子が呟いた。
集の提案のあと、日記帳のページは『わーーーーーーーーい』の文字で埋め尽くされたのだ。最後に、奇妙な二つのコッペパンのようなものも描かれ、めんまはご丁寧に『Vサインです』と注を入れていた。
「交換日記には、文字が書けるって。どういうことなのかしらね……思い入れがあるものには書ける、ってこと?」
「あ、そうかも!」
知利子と鳴子の会話をただ聞いていた集は、そこで眉をひそめた。
(そんなこと、信じられるものか)
日記帳に付属していたペンで、めんまは文字を書いた。だったら仁太は、家にあるペンに細工をしていたのかもしれない。インクがでないようにしたり、いくらでも方法はある。
(あいつは、俺達とめんまが意思疎通するのを、拒んでいた)
それが、一番自然だと集は思った。すべては、仁太がめんまを独り占めしようとしていただけ。
「めんまと――……これで、気持ち。通じるんだね」
「通じる?」
集は、思わず鳴子を睨みつけた。
「気持ちなんて、文字だけじゃわからない。なんとでも書ける」
「松雪」
「だったら、質問したらよかったじゃないか。『めんまが死んでからも、すくすく大きくなった私達のこと。許してくれますか?』とでもさ」
「!!」
鳴子の肩が、びくんと大きく揺れる。知利子が間に割って入った。
「ちょっと、松雪……」
「めんまは、『全然OK』って言ってくれるだろ。そういう奴だからな……でも、だったらどうして戻ってきたんだ? 許してないからこそ、俺達を責めるために現れた。それが、一番簡単な答えなんじゃないか?」
「だ、だったら! どうして、宿海の前だけに出てきたのよ!?」
「…………」
集は、思わず口を閉ざした。
もう、めんまが戻ってきたことを疑う余地はない。
ずっとめんまに焦がれていた。めんまの夢を見られただけでも、その一日は集にとって特別になった。幽霊でもいいから戻ってきてくれと、願い続けていた。
それが叶ったのに。嬉しいはずなのに……なのに。
芽衣子に触れられるのは、仁太だけだなんて。
『誰かに取られるくらいなら、壊してしまいたい』
そんな昔の流行歌の気持ちが、初めてわかるような気がした。
「安城、バイト代はちゃんとためとけよ」
「えっ?」
「俺も、なんとか、金。工面してみせる」
「あんた達の学校って、バイト禁止なんじゃ……」
「なんとかしてみせる……花火、作ってみせる。絶対に……」
集は、暗い瞳をあげた。
「絶対に、めんまを、成仏させる」
その言葉の裏に潜んだ強い感情に、知利子と鳴子は言葉を失った。
(めんま……お前の願いを叶えられるなら、いいよな……?)
めんまを成仏させて、仁太から引き離す。
これは、芽衣子のためでもある。まったく、問題がないんだ。集は自分を騙そうとしているかのように、何度も何度も、心で繰り返した。
そうでもしなければ、バラバラに壊れそうだった……。