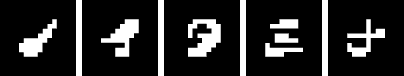NOITAMINA
OFFICAIL WEBSITE
SHARE
ツイート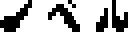 NOVEL
NOVEL
ノイタミナノベル「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」 第1話

『きおくのうろうろ』
ぽっかりと《うろ》が開いている。
秘密基地の裏に生えてる、でっかい木に開いた《うろ》。
どこまでも続く闇は、あっちの世界にまで続いている気がするほど。
そこから、彼女が見ている。
その瞳からは、これっぽっちの感情も読みとれない。怖くなって、石を《うろ》にひたすらぎゅうぎゅうとつめこむ。
これできっと大丈夫、わずかにホッとしてふりかえれば。
石と石との隙間から、彼女が……めんまが見ている。
もっともっと怖くなって、《うろ》にめちゃくちゃに石をつめこみ続ける。だってめんまに、石投げるとかできない。あの日、「また会えますように」なんてお願いしなきゃよかった。
めんまは《うろ》にいる。
あの日から、ずっと息をひそめて、ここにいる。
『あれからの人たち』
「よーよー、ウェルカム! コーヒー飲む?」
「あーうん。サンキュ」
秘密基地での、松雪のビジュアルショックナイトからとりあえず一週間が過ぎた。
それからの朝と夜は、やたらと短かった。
めんまがいる朝、めんまがいる夜。他愛もないお喋りはどこまでも続き、はしゃぎあってこづきあって疲れたら眠って。そんな始まりと終わりが一日に存在することは、とても新鮮だった。
一方で、それからの昼はやたらと長かった。
学校に行こうとしても足が向かず、それでもめんまに登校拒否の事実を知られたくなくて、一日中辺りをうろうろうろうろ……本屋が一軒しかない、マン喫もない、ゲーセンだってこないだ潰れたこの町でうろうろするには、限界がある。
仕方なく、三日前から秘密基地に入りびたることになった俺。
最初はちょっと抵抗があったけど、ぽっぽは昔と全然変わらねぇし、山の上ってのは下界よりもいくぶん涼しい風が通るし、すぐに居心地よくなった。学校に行けない自分を情けねぇなとは思うが、家にいるだけの日々よりは数段の進歩なのかもしれない。
秘密基地のソファにぽすんと腰かければ、わずかに埃が舞った。
「な、めんまさんどんな感じ?」
「まあ……普通じゃね」
普通なんてどこにも存在しない関係に、わざとそんな言葉を吐いてみる。
めんまが、帰ってきたということ。
しかも、いたってめんまらしく呑気に日々を送っているということ。
その現実を、超平和バスターズのメンツは信じたはずだった。けれど、それでも俺の家には来なかった。
「めーんまちゃん、あーそーぼ」には、ならなかった。
普通の日常をぽんと飛び越えてしまった違和感に、そうそう簡単にはついていけないんだろう。まあそうだろうな。俺だって、最初は戸惑った。
しかも、俺にはめんまが見えてるけど、みんなには見えないわけだし。
「ほい」
ぽっぽが差し出してきたのは、鶴見がくれたマグカップだ。全てが形違いのものだけれど、いつの間にかぽっぽは『俺用』のカップを決めたらしい。必ず、いつも、同じカップを使って俺にコーヒーを淹れてくれる。
俺も、いつの間にかぽっぽとあだ名で呼ぶのが通常になってた。まるで、あの頃のように。
「あのさ、俺さ、かなりのスパンで考えちゃってたんだけどよ」
「どうしたよ、ぽっぽ………へ?」
ぽっぽは、いきなり俺の前にがばっと正座をした。
「めんまのお願い――……ほんっきで、うそっこなしの絶対に叶えてやろうぜ」
「えっ……」
うそっこなしの絶対に、叶える。
「だったら、今まではうそっこありだったんか?」
「あ、いや! そーいうんじゃねぇけどよ……でも」
わずかに言いよどんだぽっぽ。まあ、なんとなくわかる。
ぽっぽの今までの『願いを叶えたい』は、きっと墓場に飾る花のような、そんなものだったんだろう。めんまへの思いが強けりゃ強いほど、でかくて綺麗な花を手向けたいと思う。『自分自身への納得』のようなもの。
でも、リアルにめんまの存在を感じるようになってからは。『願いを叶えたい』が『めんまのため』に直結する……あの日、何もしてやることのできないままバッサリと切断されてしまった絆。だけど、きっと、今なら。
「超平和バスターズのみんなが、めんま信じたんだしよ。つるこも、ユキアツも誘ってさ」
「ユキアツ……」
そこで、ぴたり。俺達の動きが止まった。
脳裏をよぎったのは、憐れんでいいのか笑っていいのか怯えていいのかわからないあの強烈な姿だ。
……いや、笑っちゃいけないことはわかってるし、あの時もそんなつもりはさらさらなかった。
でも正直この一週間、風呂入ってるときとかトイレ行ってるときとか、それこそめんまと飯食ってるときとか、ちらちらとよぎってしまい……なんとも、複雑な気分にさせられつづけている。
ユキアツが、一緒に動いてくれるとは思えない。
だって、あんな姿見られたら。
「普通は、立ち直れねぇよな……」
「ああ。普通は、立ち直れねぇ」
「絶対立ち直れねぇ」
俺とぽっぽは、同時にうんうんと深く頷いた。眉間のあいだに、川の形の皺をくっきり浮かび上がらせて。
*
普通は、立ち直れない。
そんな仁太達の予想に反し、集は余裕の表情で優等生ライフを淡々かつ粛々とこなしていた。
声をかけてくる女子と軽く会話をし、プリントはさりげなく速やかに提出、食堂で注文するのは海老ピラフ。けして、うどんや日替わりの豚肉の生姜焼き定食ではない。
「本当に驚く」
知利子から出た感想は、それ以上でもそれ以下でもない、ごく当然のものだ。
「まあ、俺も驚いたよ。ああいうのを、魔がさしたって言うんだろうな」
「そのわりには、準備万端だったじゃない。脛毛まで剃って」
「もともと薄いんだよ。俺、男ホル少ないからさ」
「驚いてるのは、あの変態行為じゃないわよ。なんであっさり、日常に戻ってこられるわけ?」
「じゃあ、どうしてれば満足だ?」
「宿海仁太に続く、超平和バスターズ二人目のヒキコモリ」
「俺の神経逆なでするの、天才だよな。お前」
校舎の裏、新設校のやたらと白が目立つ壁によりかかって、集と知利子は昼休みを過ごしていた。通り過ぎる後輩らしき女生徒達が、ちらちら集を見て噂話をしている。対して、知利子に向けられるのは敵意のまなざし。
「ほら。俺のこといじめるから、睨まれてるぞ」
「……まあ。あんたの女装写真一斉送付したら、あの視線もきれいさっぱりするだろうけど」
「違いない」
「なかなか見ものだったわ。そのポーカーフェイスが、崩れたときのあの姿」
「……テンパりのマックスだったからな、思えばさ」
「え」
集にとっても、あんな姿を超平和バスターズにさらすのは本意ではなかった。
最初は、パッチンが始まりだった。
知利子と、地元に帰る電車を待つ間、駅ビルでうろついていた時のこと。
めんまにあげたはずの、そして受け取りを拒否されたはずのパッチンに、あまりにもよく似たヘアピンを見つけた。
なかば無意識に、集はそれを買ってしまっていた。
隣に知利子がいて、その視線を感じているというのに。
家に帰って、集はそれを髪につけてみた……馬鹿げていると、思った。
めんまに近づくための、儀式。
もしくはあの日、自分を受け入れてくれなかっためんまを、もう一度『上書きする』ための儀式。
少しずつ集めためんまの欠片を、どんどん自分に取り入れていった。
鏡に映る自分に、あの日の自分が『めんまに捧げてもらいたかった言葉』を繰り返し呟いたりした。
それは、あまりにも意味がなさすぎて、かえって意味のありすぎることに変質してしまった。集はいつしか、『今現在の』めんまを知っているのは自分だけだ、という感覚に陥っていた。
(だって、今現在のめんまは、どこにもいない)
自分が作りだしためんまが、もっともそれに近い。ついでに言えば、超平和バスターズの誰よりも、自分が一番めんまを思い続けていると信じていた。
それが――……仁太の『めんまのお願い』発言によって、揺るがされたのだ。
テンパりのマックス。
真夜中の奇行。普通ならば知利子の言うとおり、引きこもったり自我の崩壊を迎えたりしかねない、そんな強度の出来事だった。
でも、集はちょっとホッとしていたのだ。
彼にとっても『今現在の』めんまは大きくなりすぎて、自分の中で収拾がつかなくなってきていたから。
「あのワンピース、どうしたの?」
「まだある」
「まだ未練?」
「もったいないおばけが出るだろ」
そのもったいないおばけが、めんまだったら、そして仁太の家ではなく自分の家に来てくれたら……などと、集はちらりと思った。
*
「んー……まあ、それはそれとして」
俺とぽっぽは、松雪のことはとりあえず『それ』として、放置プレイをかましておくことにした。
わきに置いておかないと、衝撃映像がまたよぎってしまい、あのひるがえるスカートからちらちら覗く逞しいふくらはぎと、脛に浮かびあがるくっきりした男ラインを思い出してしまいそうで。
「なんか、手がかりねぇもんかな? めんまのお願いがわかる、ヒントみてぇなの……ほら、日記とかさ」
ぽっぽの発言に、ハッと顔をあげる俺。ぽっぽも思い出したようで、ほぼ同時に声をあげた。
「交換日記……!」
そうだ。今まですっかり忘れていた。
俺達は、夏の始まる少し前。なんとなく退屈な梅雨の時期から、ぐるぐるとノートを回していたんだ……。
「交換日記、はじめるよー!」
最初は、安城が言いだした。見たことのないキャラが描かれたノートまで用意してきて、鼻の穴ふくらませて。
「仲のいい子たちって、みんなやるんだって! 東京の子とか、みんなやってるんだって。ニコラに書いてあった!」
「えー、めんどくせー」
男子連中は、誰もが嫌がった。それでも松雪なんかは「やりたいやりたーい!」やらめんまが言えば、「ん……まあいいかもな……」なんて、今思えばわかりやすすぎる反応をした。
そして交換日記は始まる。
安城は、やたらと几帳面にちっちゃい字で、まるで夏休みの読書感想文みたいなきっちりしっかりした日記を書いてきた。読んでると眠くなるから、ついスルーしたもんだった。ぽっぽのは、字が汚すぎて読めないからスルー。松雪のは、明日学校に持っていかなきゃいけないものなんかがメモがわりに書いてあるから、時々役にたった。
まともなのは鶴見ぐらいなもんで。担任や校長なんかの顔をデフォルメした落書きをしてきて、みんなで爆笑したもんだった。
めんまの日記は……当たり障りがない、感じだった、と思う。
正直、あまりよく覚えていない。ただ、あいつの特徴的なまるっこい字だけが、頭にぽんぽんと浮かぶ。
そう、結局たいした記憶なんかないんだ。だって、すぐに終わっちまったし。そう、交換日記で強く覚えているのは。
俺が終わらせたこと。
最初の数回はなんとなく合わせたけど、やっぱり面倒くさくなって。それを、安城と鶴見に責められるのにもいい加減うんざりしてきた。
「じんたん、交換日記とめてるでしょ!」
「しらねーよ、ぽっぽじゃねぇの?」
「お、おれじゃねぇよー。神にちかっておれじゃねぇよー!」
俺の苦しい言い逃れとなすりつけを、くるくるした瞳でめんまが見てた。
ああ、見透かされてるな、って思いながら。それでも、日記を止める気満々な俺はしらばっくれることにした。
ちょうどその日の帰りは、俺とめんまの二人っきりだった。
みんなそれぞれに、用事があったり風邪ひいてたりで。二人じゃ遊んでもつまらねーから……っていうか、めんまと二人っていうのが、妙に照れくさくて居心地悪くて。ただまっすぐ家に帰ろうと思った。
休耕田のわきんところの狭い道を一列になって歩いていると、めんまが後ろから声をかけてきた。
「ねえ、じんたん」
「なんだよ」
「じんたんが、とめてるんでしょ。日記」
「しらねぇよ、だからぽっぽじゃねぇかって……!」
「めんまね、おこらないから。みんなにも、内緒にしとくから……だから、めんまにちょうだい?」
めんまの言葉の意味が、最初はわからなかった。
きょとんとしてる俺に、めんまはゆっくり、もう一回くりかえした。
「めんまに、ちょうだい?」
「ぬぁあああ! やっぱり、じんたんが止めてたんじゃねぇかあれ! ひでえよじんたん、極悪人じゃねーの!!」
あの頃とは違い、すっかりでかくなったぽっぽが鼻息を荒くする。
「過去の罪だ、水に流してくれ」
「ハッピーセットで流してやるよ。ワンピースなんだよ、今!」
「あー、わかったよ」
「ひゃっほー! 待ってろよハンコック!!」
それにしても。どうしてめんまはあの時、交換日記を自分の手元に置きたがったんだろう。自分の死を予見して? 仲間達との思い出を、少しでも自分の近くに集めたくて?
……まさかな。
「ま、とりあえず。交換日記は、めんまんちにあるってことだよな?」
「ああ、だろうな」
「だったらさ、めんまの母ちゃんに会ってみねぇ?」
「えっ……」
めんまの葬式に、俺達は行かなかった。
正確には、行けなかった。親父はその日、俺をとしまえんに連れて行こうとした。休みの日には必ず、お袋の病院に行くのが決まりだったのに。
俺は、行きたくないって言った。
めんまの葬式がその日にあることは、学校で聞いてたから。葬式に行きたい行きたい行かせろって。さんざんごねた。
親父はしばらく無言だったけれど、結局は俺の言葉を受け入れてくれた。ぽんと俺の頭にでかい手をのせて「いっしょけんめだよ、仁太」って、母ちゃんの口癖を呟いた。
親父は俺に黒いショートパンツを着させて、葬儀場まで行った。
その道中、俺は何を考えていたんだろう。
めんまの死に関しては、感じていたことがわんさとあった。だけどたぶん、『めんまの葬式』が抱えることの意味は、あまり理解してなかったんだと思う。
でも、その事実はすぐに、嫌ってほど理解させられた。
葬儀場の入口近くで、親戚らしいおばさんに肩を支えられながら、泣き崩れているめんまの母ちゃんを俺は見た。化粧もまったくしなくて、髪すらきっと梳かしてない、最初はめんまのばあちゃんなのかと思った。それぐらい、一気に年をとってた。
俺達がやってきたことに気づいて、そこにいた何人かの大人達が身構えた。
めんまの母ちゃんが、泣きぬれた顔をあげた……その顔は、今でも忘れられない。
悪魔ってきっと、こういう顔をしてるんだ。
そう思った。すべての力がぬけたような無と、すべての憎悪がつまったような闇をいっぺんにぺたっと、顔にはりつけて。
「どうして、あなたはここにいるの」
めんまの母ちゃんは、背中に氷の釘を打ちこまれたぐらいの冷たい声で、呟いた。そして、二、三歩こちらに歩みよってきた。
親戚の人らが、あわててめんまの母ちゃんの肩を止める。
同時に、めんまの母ちゃんの口から、悪魔の呪いが発せられた。
きっと何かを喋っていたんだと思うけれど、もう、聞きとれるようなものじゃなかった。ただただ、恐ろしくて。俺は立ち尽くすしかできなかった。
親父が頭をありえないぐらい深く下げて、俺を引っ張っていった。
蝉の鳴き声と、めんまの母ちゃんのうめき声、そしてお経の声がひとつになって追いかけてくる。なのに俺の足は、借りものになったみたいに動かなくなってた……。
めんまの葬式には、超平和バスターズの誰も参列しなかった。やっぱり、うちと同じで、親が止めたんだと思う。
ただでさえ狭い町だ。それからも、めんまの母ちゃんと道で鉢合わせすることはあった。
それでも、めんまの母ちゃんと視線があうことはなかった。
お互いに目をそらしてしまうからなのか。それとも、めんまの母ちゃんは……あの日からずっと、下を向いて歩いているからなのか。
「めんまの、母ちゃんに……か」
ぽっぽの提案に蘇ってきた思い出は、俺を俯かせた。
たしかに、めんまの母親に頼めば……子供の遺品を捨てるような親はいないと思うし、交換日記を手に入れられるはずだ。
だけど――……。
「やめたほうがいいよ!」
「いっ!?」
でかい声にふり返れば、そこには安城が立っていた。
「なっ! お、お前っ。いつからいたんだよ!?」
「便所、長かったなーあなる」
「っ……だ、だって! ここ、トイレないんだもん!」
「やだなぁ、裏の土んとこに穴あけてんじゃねぇの」
「あんなとこでするなんて、無理! 橋んとこまで降りて、公衆トイレ行ってきたんだから!」
安城は、制服を着てた。壁かけ時計を見上げれば、まだ昼過ぎだ。
「……安城、学校はどうしたんだよ」
「え? まあ……ちょっと今朝は、その気、なんなくてさ」
「こいつ、俺のとこ誘いに来たんだよ。一緒にじんたんち、行ってみねぇかって。めんまに会いに行こうって」
「! なっ、ナイショって言ったでしょあんた!」
「素直になれよあなるよぉ」
顔を真っ赤にしている安城に、なんだか嬉しくなる。そうだよな、未知の出来事と向き合うのがちょっと怖いだけで、みんながめんまを気にしてるんだ。
めんまをこれだけ考えてくれる奴らが、ここにいるんだ。
「ほら、言ったとおりだろ」
「え?」
呟いてしまった言葉に、安城が反応してきた。
「あ、いや……別に」
言って、めんまに命名された『いやべつに星人』を思い出し、ふっと笑いがこみあげる。
「? なんなのよ、宿海。気持ち悪!」
なあ、めんま……やっぱお前、ノケモノなんかじゃないぞ。