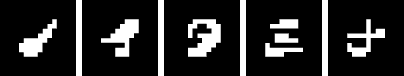NOITAMINA
OFFICAIL WEBSITE
SHARE
ツイート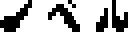 NOVEL
NOVEL
ノイタミナノベル「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」 第2話

『交換日記』
「んー………ひまだよう」
芽衣子は、仁太から借りたDSで遊んでいた。五年前のゲームよりもずいぶん画面が綺麗になり、最初はそれを喜びもし目新しくも思ったのだが、あっという間に飽きてしまった。
外には真昼の日差しがあるはずだけれど、居間には窓が一つもなく、いつもぼんやり薄暗い。仁太がいてくれる夜のほうが、蛍光灯と楽しいおしゃべりとでよっぽど明るい。
仁太が学校に行っていないことには、なんとなく気づいていた。
(じんたん、どこ行ってるのかな……)
仁太が学校に行きたくないと思う気持ちは、芽衣子にも理解できた。なのに『じんたんが学校にいくことが、めんまのお願いかもしれない』などと不用意に言ってしまったことで、仁太にプレッシャーをかけてしまった。
集のことだって、母親のことだって同じだ。
自分の『不用意な存在』が、集を、母親を傷つけた。
仁太には謝ることはできる。でも、集と母親にはそれすらできない。
(なんでだろうなぁ?)
ノートを開いて、ペンを手にとって文字を書いてみる。しかし、その文字はするすると紙のほんのわずか上を滑っていくのだ。
芽衣子は、仁太に抱きつくこともできる。塩ラーメンを食べることもできる。
なのに、どうして字を書いたり、声を残したり……みんなに、気持ちを伝えることはできないんだろう。
(やっぱり、ノケモノかな)
仁太は、芽衣子のことを『ノケモノじゃない』と言ってくれた。
でも、どうしようもなくしょうがなく、芽衣子は感じてしまったのだ。
それは、両親と弟のいる家に帰ったとき。
あの居間で、コップを落とした。ただそれだけで、小石を放りこんだ湖面にうまれる水紋のように、ぶわっと険悪な空気が広がっていった……。
自分は、この世界に『何も残しちゃいけない』のだ。
やっぱり自分は、この世界からの、ノケモノ。
(いじわる……だなぁ)
芽衣子は思い出す。超平和バスターズに入る前の、自分を。
髪や瞳の色素が薄いせいで、幼稚園の頃から『がいじん』と呼ばれていた。
芽衣子は最初、がいじんの意味がわからなかったので、母親に聞いてみた。母親はどこか寂しそうに微笑んで「それは、考えなくていいのよ」と答えた。
答えになっていない、答え。
やがて芽衣子は、がいじんとは外国人のこと……そして、『外の人』と書くのだと知った。
がいじんという言葉から、芽衣子が連想する情景。寒い冬の夜に、裸足でドアの外に放り出された。お情けのように、何かが入ったビニール袋をもらう。そこには、外で生活する外の人用のご飯がちょんまりと入っている。ごま塩のふりかけしかかかっていないご飯だ。
窓にはオレンジの暖かなあかり、みんなの笑い声が響いてくる。でも、自分は中に入れない。今日は犬小屋で寝るのだ。芽衣子のうちは犬を飼っていないので、お隣さんの家に行って、犬小屋をちょっと貸してもらう。いつも吠えられる、怖いわんこだ。仲良くできるかな、噛まれたりしないかな――そんな自分を想像し、芽衣子はわんわんと泣いてしまった。
仁太達と会うまでは、芽衣子は外の人だった。
だけど……仁太達は、まるきり自分を、普通に扱ってくれたのだ。
学校に行きたくないという仁太の気持ちは、よくわかる。仁太は今、学校での『がいじん』なのかもしれない。
でも、今の芽衣子には、仁太を中に引きいれてやることができない。だって芽衣子は、この世界での『がいじん』だから。
あんなに優しくしてくれたじんたんに、何もできない今の自分。
最初から、ずっと一人だったらよかったのにな。
だったら、こんなふうに寂しくなったりしなかったのかもしれない。超平和バスターズのみんなと一緒にいる楽しさを知ってしまったから、一人の時間が辛くなる。はがゆさが二倍にも、三倍にもなる。
「じんたん、はやく帰ってこないかな……」
ちりん。
(ん……?)
開け放たれた窓から、風。
涼しげに鳴る風鈴の音にふりかえれば、仁太の母親が芽衣子を見つめていた。仏壇に置かれた遺影、その小さな窓枠から。
ちりん……ちりん。
「めんまちゃん」
それは、記憶だった。
バスクリンの入ったお湯のような、なめらかで、湿度を軽くふくんだ風にカーテンが揺れる。仁太の母親は、一人でお見舞いに行った芽衣子の髪を撫でてくれた。その指は骨ばって、いくつもの点滴の痕が痛々しかったけれど、それでもその感触を柔らかいと思った。
「あのね。めんまちゃんに、お願いがあるの――……」
「あ……れ?」
芽衣子の瞳、その焦点が軽くぼやける。
(お願いがあるのは、めんまじゃ……ないの?)
*
秘密基地から続く橋を渡って、商店街のはしっこに出る。
なぜか俺と安城は、一緒に帰ることになってしまった。
かつかつかつかつ五月蝿いヒールの音が、斜め後ろからくっついてくる。俺とそんなに身長は変わらないのに、歩幅はずいぶん違う。
女って、めんどくせぇな……。
仕方なく、歩幅を狭める。夕暮れの陽射しに濃く浮かぶ安城の影の、二つに結んだ髪がひょこひょこと揺れる。
その影が、俺に、何かを話したそうにしている。
ほんっと、女。めんどくせぇ……。
すると、安城の影がぴくっと今までにない揺れをみせた。
「! ね……ねぇ、あれ」
「え?」
安城の視線の先を見る。クリーニング屋がある。そこから、ぱんぱんに洗濯物のつまった袋を持った婆さんが出てくる。
婆さん、って言っても小奇麗な。すっと背が伸びて、膝丈の上品なスカートを着て。シルエットだけだと、婆さんどころか若い女に見える。
どうして、婆さんに見えるかっていえば……ちょっとも染めてない、完全な白髪だから……。
「!!」
めんまの母親だ。
なんだってこんな、安城と一緒にいるときにかぎって?
それでも、いつか道で偶然すれちがったときのように、向こうから視線をそらしてくれるかと思った。なのに、これもやっぱり今日にかぎって……。
「仁太君に、鳴子ちゃん……?」
こちらに声をかけてくる、めんまの母親。緊張し、汗が一気にぶわっとふきだす。
「あっ……こ、こんにちは!」
緊張に裏返った、情けない声がもれる。めんまの母親は、俺が明らかに緊張しているのに気づきながら、余裕をもって微笑んでみせた――。
「どうぞ、散らかってるけど」
……どうして、こんなことになっちまったんだろう。
俺達は、めんまの母親に激しく誘われて、めんまの家で茶をすることになってしまった。
「芽衣子も喜んでるわ。二人とも、よく遊びに来てくれたものね」
嘘だ。
めんまんちの父親は怖くて、俺達はビビりまくってた。挨拶しても、新聞読んでむすっとしてるし。「外で遊びなさい」って不機嫌に声かけられるし。
だから、ここに来たのは二度……三度だったろうか。それぐらいのものだ。
めんまの母親は、どうしてそんな嘘を言うんだ?
「芽衣子に挨拶、してあげてくれる?」
言って、めんまの母親はちらりと部屋の片隅に目をやった。
「!!」
そこには仏壇と――……そして、めんまの笑顔の遺影があった。
俺の隣に現れた、少し大人になっためんまじゃない。記憶のままの、そのまんまのめんま……あまりにまんますぎて、逆に違う少女にすら見えてしまうその笑顔が、ぽつんと置かれていた。
「…………」
胃をぎゅっと掴まれたみたいな鈍い痛みに、思わず視線をそらしてしまう。
安城も同じ気持ちだったんだろう。背後で、激しく気持ちが揺れているのが空気で伝わってくるみたいだ。
なんでだか知らないけれど、安城を『味方』だと思った。
死者を悼む、なんて殊勝な気持ちもなく、ただただ手をあわせて鈴を鳴らす。その一連の動作を、何かをチェックするみたいに監視していためんまの母親は、
「あのね、あなた達に渡したいものがあるの」
そう言って、微笑んだ。
でも、その瞳には、こちらに挑みかかるような色があった――。
「ちょっと待ってね……」
通されたのは、がらんとしたオレンジの部屋だった。
壁紙に色がついているわけじゃない。家具がひとつもない、窓からカーテンすら取り払われてるせいで、夕陽が室内の隅から隅までみっしりと充満している。
寒々しい眺めと、むっとする夏の温度のギャップに汗がにじむ。もしかして、冷や汗なのかもしれない。
ここが、めんまの部屋だなんて、言われなければわからなかった。
思い出が残るほどに、ここに来たことはないけれど……それでもこの場所は、ぬいぐるみやらなんやらで埋め尽くされてた……はず。
でも、あまりにも雄弁すぎる殺風景の圧力にやられて、もう思い出せない。とにかく暑くて、なのに汗もでなくて……。
俺と安城は、顔を見合わせることもなかった。ただひたすら、はやく時間が過ぎてくれと、そればかりを祈っていた。
タンスをがさがさと漁っていた母親は、
「これで、全部なの」
そういって、小さなダンボール一つを部屋の中央に置いた。
「…………」
言葉を失う、ってのはこういうことなのか。
開かれたダンボールには、幾つかのアルバムと、めんまの書いた絵と、読書感想文やらと。
めんまの母親の言うとおり。めんまの生きてきた『全ての証』は、小さなダンボール一つにつめこまれていたのだ。
「お父さんがね、いつまでも芽衣子の物をとっておくなって」
めんまの母親は、穏やかな笑みをたやさずに続けた。
「それでね……これなんだけど。本当は持っておきたいけれど、あなた達のものでもあるでしょう? お返ししたほうがいいのかなって」
めんまの母親が、ダンボールから取り出したもの。
タイミングが良すぎる……いや、悪すぎるのか。それは、ちょうど俺達が求めていた、俺達の交換日記だった――。
*
まわれ右をして秘密基地へと戻った俺と安城は、ぽっぽにその顛末を話した。
ぽっぽは「こいつは、持ち主みんなの同意のもとに読まなくちゃ駄目だ」と、松雪達にも召集メールをだした。
「いきなり呼んでも、来ないんじゃないの? 先に読んじゃおうよ」
「いーや。こーいうのは、縁起もんだからな!」
「縁起もんってなんだよ」
松雪が来るはずなんてないだろう。そう思っていたが……。
「よう、おつかれ」
……来た。
ちょうど駅についたばかりだという松雪と鶴見は、俺の大嫌いな進学校の制服を身にまとったまま現れた。
「交換日記、見つかったんだってな……」
あんな醜態をさらしてから最初の対面だってのに、松雪はいつもの、こちらを見下すような視線を向けてきた。悔しいから、ちょっと『プッ』て感じの顔でも作ってやろうか……と思ったけど、やっぱりやめた。
「集まったな! じゃあ、さっそく交換日記。見てみっか……」
ぽっぽの太くてでかい指が、日記帳をめくる。
基地内にちょっと緊張が走った、気がしたけれど、空気の読めないぽっぽはそんなのおかまいなしだ。
一枚目のページには、やたら小さい几帳面な字がびっしりと並んでた。ぽっぽが、はしゃいだ声をあげる。
「おおっ。一発目は、あなるでキメたか!」
「変な言い方やめてよ!」
「これなんだ、お前のイミフメイだな。人生のなかでつらいことがあっても、誕じょう日にはおいわいをしたいと思います。だって、本当に……」
「!!」
安城がいきなり真っ赤になって、慌ててページをめくった。
「どうしたんだよ?」
「ななな、なんでもない! はやく、めんまの見よ!」
ページをめくっていく安城。すると今度は、特徴的な丸っこい字が現れた。
めんまの、字だ。
「あ……」
みんな、内容を確かめることなく、しばしめんまの文字だけに気を取られてた。そこに、時を越えてめんまが現れた気がしたからだろう。
いつもめんまを見てる俺でさえ、そんな気分になったんだから。
「! あ、えっと……今日は、ひみつであそびました。楽しかったです」
安城が、めんまの担当の日だけを選んで音読していく。
「今日は、いもほりがありました。たのしかったです」
「こ、これはイミフメイ……じゃねぇけど、テキトーだな」
音読は続き、何日分かのめんまの日記が読みあげられた……けれど。
「面白かったか、楽しかったか、それっきゃ差がねぇ……」
「あいつ……作文、苦手だったもんな」
やたらシリアスな気持ちで交換日記に向かったぶん、半端のない脱力感が襲ってくる。
「あ、これちょっと違うじゃん。今日は、みんなとあそんでるとき、ころびました。いたかったです」
「お、ここも違うぜ? 今日は、みんなでじんたんのおかあさんのおみまいに行きました……」
「!」
じんたんの、お母さんの……?
「お見舞い……か」
「そういや、よく行ったよなぁ。みんなでぞろぞろよー……」
そうだ。お袋がそこまで具合が悪くなかった頃、俺はやたらと病院に見舞いに行っていたんだ。超平和バスターズのみんなと一緒に。
お袋が、心配だったってのはもちろんだ。
でも、死への具体的なイメージなんて俺らにはなかった。病院っていう今まで身近になかったでっかい場所に遊びに行くこと。そして病院のすぐ近くに今はもうない養豚場があって、豚を見て「でっけー!」「くせぇ!」「ぶーぶー」なんてさわぐのが、ちょっと楽しみだった。
お袋はいつも、俺達を笑顔で出迎えてくれた。お袋の具合が目に見えて悪くなっていったのは、ほんの二か月ぐらいのことだから。その頃の俺達は、どうしてお袋が入院しつづけてるのかぴんとこなかった。
「ねー、じんたんのお母さん。いつ、退院できるのかな?」
病院からの帰り道。安城がそう言いだすと、めんまは目を輝かせた。
「そうだ。神さまにお手紙おくろうよ! じんたんのお母さん、はやく元気にしてくださいって!」
「お手紙、神さまに……?」
突拍子もないアイディアだったけど、それはいいって、すぐに意見がまとまった。ぴんとこないことや謎なことは、とりあえず神様のしわざ。ガキの頃は、そう思ってた。
「でも、どーやって?」
うーんとみんなで、首をひねる。そこでぽっぽが何かに気づいた。
「じんたん、あれ!」
さびれた掲示板に、隣の市で毎年行われてる龍勢花火のポスターが貼られていた。火花が華やかに散るタイプの花火じゃない。筒で、紙吹雪なんかを飛ばす原始的な花火だ……。
「! そうだ……あんとき」
思い出した俺は、ぽっぽの手から交換日記を奪うとページをめくりつづけた。
「じんたん?」
「みんなで、花火をつくろうってきめました……むずかしいとおもいました。でも、がんばります……」
「あ!!」
「そうよ、思い出したわ……ロケット花火に神様への手紙入れて、神様に届けようって」
鶴見の言葉に、ぽっぽが勢いよく立ちあがる。
「! うおおおっ、すげぇ! おいじんたんっ、これじゃねぇか? めんまのお願いってさあ!」
「…………」
「そうだよ! きっとそう、あのとき作ろうとして、結局駄目だったじゃん。ねえ、宿海………、あ……」
俺の……お袋のために。
めんまの書いた『むずかしいとおもいました。でも、がんばります』の文字を、思わずそっと撫でた。指の先から、めんまのあたたかさが伝わる気がした。
もし、めんまの願いがこれだったとしたら……いや、これじゃなかったとしても。めんまが……みんなが、俺のおふくろのためを思って……。
「盛りあがってるとこ、悪いけど。無理だろ」
松雪の冷たい声に、ハッと顔をあげる。
スマホをいじっていた松雪は、開いたページを俺の目の前につきつけてきた。それは火薬類取り扱いのページだった。
「ほら、ここ読めよ。花火の火薬の取り扱いは『火薬類取締法』において、十八歳以上で国家資格を持っていないと行えない……」
「げ、マジで?」
「玩具花火のくくりなら、なんとかなるらしいけどな。それもライセンスが必要だ」
ぽっぽは、力が抜けたようにその場にへたりこんだ。
「まー、考えてみりゃそうだよな……花火なんて、普通に考えたら資格がいるか……」
「……でも」
「? どうしたのよ、宿海」
「これが、めんまの願いなら……俺、叶えたい」
思わず、口に出してしまった。
みんなの視線が、一斉に俺にそそがれるのを感じて、かあっと耳元まで熱くなる。
「い、いや……その。なんていうか、まあ無理だとは思う……けど、その……」
慌てて取り繕おうとしたそのとき、ぽっぽが顔をあげた。
「あっ……そうか! あれってこれのことか!」
「はぁ? あれって、これ? 意味わかんない」
「半年ぐらい前よぉ。掃除してたら、見つけたんだよ!」
言いながら、わさわさと部屋の隅をあさるぽっぽ。そして、
「あった、じゃじゃーんっ!」
突きだした右手には、丸めたわら半紙があった。
「ロケット花火の、つくりかた……?」
わら半紙を広げると、汚い字や図形やらでロケット花火の作り方がびっしりと描かれていた。松雪は、呆れたように呟いた。
「これ………本気か?」
鶴見も、眼鏡をかけなおすようにしてしげしげと見つめる。
「花火をたくさんあつめて、かやくをばらばらにしてから、いっこにまとめる……」
「トイレットペーパーのしんに入れる→もえるからダメ……当たり前じゃん!」
「こええ! ガキこええ!」
ひとしきり、わら半紙に描かれた荒唐無稽な花火の作り方に盛りあがっていると、松雪がぽつりと口にした。
「でも……昔は、これでイケると思ってたんだよな」
「ああ。昔は、こんなんでも本気で飛ばせると思ってた……」
わら半紙に描かれた、不格好なロケット花火。
本物のロケットみたいにでっかくて、とても花火としての体をなしてなくて。
でも、祭のロケット花火より全然かっこよくて、全然つぇえって、思ってた。これを、雲をつきぬけて空の上へ……神様のところまで、飛ばせるって。思ってた。
「高校生なんてよ。えれぇおっさんに見えて、なんだってできるようになる気がしてたけど……」
「うん。あの頃のほうが、なんだってできたような気がする――……」
なんとなく、ガキの頃の自分達に負けたような気がして。俺達は、ただぼうっとわら半紙を見つめつづけてた。
その無言をやぶったのは、ぽっぽだった。
「……やってやろうぜ」
「え?」
「俺の、バイト先にさ! 祭んときにだけ、花火作ってる親父さんいるんだよ。聞いてみっからさ!」
「本当!?」
ぽっぽの発言に、場の空気がまた、上向きはじめ……たと思ったけれど。
「待てよ。宿海、まず先にめんまに確認してみたらどうだ?」
松雪の発言により、また場の空気は下向きになった。
「えっ……めんまに?」
「ああ。本職巻きこんで、本格的に花火を作ることになったとして。これがお前の言う『めんまの願い』ってやつじゃなけりゃ、ただの徒労だろ?」
松雪は、薄い唇を意地悪くゆがめた。
なんて言葉を返せばいいか、一瞬迷った。下手なことを言って、また松雪に傷つけられるのもいやだったし、逆に松雪を傷つけちまうのもごめんだった。
でも、久しぶりに子供の頃のめんまの文字を見て。めんまの気持ちにふれて……俺は、余計なことを考えるのをやめた。
「……今度、みんなさ。めんまんとこ来てくれよ」
「! えっ……」
「めんま、みんなに、会いたがってる。さみしがってるからさ」
「…………」
答えは、すぐには返ってこなかった。
しばらくして、ぽっぽあたりが「そうだな!」なんて明るめの声をあげたけれど。秘密基地で『昔のめんま』を懐かしむのには抵抗がなくなったというのに。『今のめんま』をどう扱っていいのかは、やっぱりみんな、掴みあぐねていた――。
*
「宿海の家行くなら、つきあってあげてもいいわ」
隣を歩く知利子に声をかけられ、集は視線を落とした。秘密基地をくだる、軽い坂道。夏とはあきらかに違う、初秋の虫の声が川のせせらぎを遮って響いてくる。
「保護者の人がいなくたって、お友達の家にぐらい遊びに行けるさ」
「友達って、宿海のこと?」
嫌みのつもりの言葉にひそむ、妙に痛いところを知利子に突かれてしまう。それになお気の利いた返しをするには、頭の中がごちゃごちゃしすぎていた。
集はただ黙りこみ、知利子もそれ以上は追及してこなかった。
欝蒼とした夜の木々、そのあちこちに貼りついたあの無様な記憶。バーベキューの夜空に描かれた手持ち花火の∞マークは、集の心に深く刻まれて、消えない。
超平和バスターズのマーク。永遠に友達だっていうしるし。
芽衣子が本当にいる、ということを、もう集は疑っていなかった。
あの∞マークは、白いワンピースの延長線上にあるものだろうと感じていた。あまりにも強い執着は、いつかは『本当のめんま』に辿りついてしまう。
そんなことは、きっとある。
だからこそ、集は仁太の家に行くのが怖かった。
芽衣子に、ぎりぎりにまで近くなってしまえば……芽衣子の次に消えるのは、自分のような。そんな気がしていた。
*
「はーあ……」
家に帰った鳴子は、すぐにベッドにもぐりこんだ。
あの交換日記を、秘密基地に置いてきたことの後悔。でも、自分が管理するとも言いだせなかった。
自分の書いた日記の内容なんて、すっかり忘れていたが、あのページを見た瞬間にまざまざとよみがえってきた。
『人生のなかでつらいことがあっても、
誕じょう日にはおいわいをしたいと思います。
だって、本当にショートケーキはおいしいです。
いつでも幸せなきぶんになります。
すばらしい、ケーキを考えた人はあたまがいいです。
きっと、やさしい人だと思います』
本当に、どこまでも意味不明な日記だったが、あの頃の鳴子には一大決心の日記。凄まじい意思をもったラブレターだった。
少女漫画のヒロインの行動により、知った知識。立て読み。
あの文章の頭文字だけをとれば、『じんたんだいすき』になったのだ。
「じんたんだけが、気づいてくれないかな」そんな淡い期待を胸に提出した交換日記だったが、あっさりとスルーされた。
他のみんなも気づいていないと思っていたが、秘密基地でのあの時。知利子はこちらを見て、訳知り顔の笑みをうかべた……気がした。
きっと、絶対に、気づかれた……。
(あの頃の自分、なぐりたい。あんなヒキコモリなんかに)
ふと、仁太を思い出すとき。かならず、鳴子は、ヒキコモリと連呼することにしていた。まるで、効力の強い呪文のように。
そうしないと、どんどん過去の気持ちがよみがえってしまうような、そんな怖さがあったのだ。
なぜ、なんだろう。
仁太の目を引きたくて、染めた髪、塗りたくった爪、それはいつしか『仁太から離れるため』の小道具になっていた。
こんな私、宿海は嫌いなはずなんだ……私だって、好きじゃないんだから。だから、ちょうどいいはずなのに。
ベッドの下で、携帯が鳴っている。
ディスプレイに浮かび上がる、高校の友人の名前……多少おっくうに感じながらも、仁太のことを考えつづけるのが嫌で、それを手に取る。
「もしもし、どしたの?」
携帯のむこうで、カラオケの音楽とはしゃぐ声が響いてくる。今日は、合コンがあったのだ。鳴子は気乗りしなくて参加しなかった。
「ねー、ようちゃんが待ってるんだけど。今からでもいいから来なよ」
「え? 無理って言ったじゃん」
すると、遠くから『無理やりこさせろよ!』と男の声が聞こえてくる。その乱暴な物言いを、やたらと怖く感じた。
それを受けたのか、友人が低い意味深な声音を作ってくる。
「最近さぁ。鳴子、つきあい悪くね?」
「え……」
「あんまりノリ悪いと、嫌われるよ? 全然顔見せないとか、まじ無理だから。少しでもいいから来なよ」
「…………」
友人の声が、鳴子の身体を素通りしていく。
携帯を切っても、まだ鳴子はぼんやりとしていた。秘密基地で、仁太達とかわした会話。とくに気負うこともなく、どう見られてしまうかなどとは考えず、ぽんぽんと出てくる自分の言葉。
でも、そうだ。新しい友人達とは、そうはいかないんだ。鳴子は思う。
本当の自分で接するなんて、無理だ……だって、今の私は『無理やりつくった自分』なんだから。
ふぅと息をつくと、鳴子はクローゼットを開けた。もう夜の八時を過ぎているけれど、これから合コンに顔を出すために。
宿海に嫌われること確定の、自分になるために。