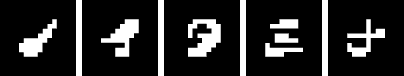NOITAMINA
OFFICAIL WEBSITE
SHARE
ツイート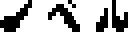 NOVEL
NOVEL
ノイタミナノベル「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」 第3話

『きおくのうろうろ、その思いつき』
《うろ》に閉じこめたはずのめんまは、いつまでも消えてはくれない。あたりまえだ、ただ『閉じこめただけ』なんだから。
それどころか、小石と小石の隙間をぬうようにして、声がもれだしてくる。
夜。布団を頭からすっぽりかけても、遠くからめんまの声がする。うーんうーんと、唸っているような、泣いているような声。
どうすればいいんだろう。このままじゃ眠れない。
母親が言っていた。よく寝ないと大きくなれないわよ、って。
そうだ、このままじゃ大きくなれないし、大人になれない。
閉じこめるんじゃなく、消さなきゃダメなんだ。めんまを。でも、かわいそうなことなんて絶対にしたくない。いじめはダメだ、ゼッタイ。
そうだ、こうしよう。
「めんまのお願いを、叶えてあげよう」
*
「……お帰りなさーい」
家に帰ってきた俺を出迎えためんまは、語尾を伸ばした甘ったるい声とは真逆の、むすくれた顔をしていた。
「あ、おう。ただいま……何してた?」
「息してた」
「子供かよ」
……て、まあ子供なんだよな。中身はなんも変わってないんだから。
「じんたんのパパが、いっかいお昼ごはんに帰ってきたよ。そんで、またお仕事行っちゃった」
「そうか……」
なんとなく後ろめたくて、めんまの顔が見られない。明らかにコイツ、俺のこと責めてるし……やっぱ、俺が学校行かずにいること……。
「えっ?」
いきなり、ぐいっ。めんまに腕を引っ張られる。
「こっち来て!」
「おい、なんだよめんま……」
居間まで俺を引っ張ってくると、ぱっとめんまは手を離した。そしていきなり両手を広げ、にぱっといたずらっぽく笑んでみせた。
「じゃーんっ!」
めんまが示す、こたつの上にのせられたもの。うちで一番でっかい白い皿に、ごつごつといびつな形のベージュの塊がてんこ盛りになっている。
「こ、これは……」
「蒸しパンだよーう!」
「! っ……」
あの頃。よく、母ちゃんが作ってくれた。
学校に行く前に、おやつに蒸しパン作ってくれるって言ったら。皆に声かけて、授業中もずっと楽しみにして。給食のお代わりもほどほどにして。
放課後、皆連れて走って。玄関を開けると、甘い香りがして……。
『母ちゃん、あれあるー?』
『あるよー』
母ちゃんの笑顔と、ほかほかと湯気をたてる蒸しパン。
なんて、懐かしいんだろう……。
……って、事象だけでは思ってみたけれど。目の前のそれはとくに懐かしい形状をしていなかった。見た目だけじゃなく臭いもなんだか物騒だし、作ってから時間がたってるみたいで湯気もたってない。
だけど……めんまが、作ってくれた。
「たべて、たべてじんたん!」
かぷっと一口、かじってみる。
「…………」
前歯にあたるやわらかな感触と、そこにコントラストとしてぶつぶつとまじる粉のかたまり。さらに歯を進めれば、とろりとした舌触りと共に、口の中にぶわっと広がる荒磯の香り……。
磯?
「……なんで蒸しパンに、海苔がはいってんだよ」
「あのね! 夜だから、おやつじゃなくて『ごはん』だからね! ごはんですよがはいってるんですYO!」
その他の蒸しパンも、めんまの言う『ごはん仕様』だった。
蒸しパンの中に潜んだ、梅干し、ふりかけ、そしてめんまがこっちに戻ってきてからやたらお気に入りらしい食べラー……。
「これは……独創的、だな」
「へへぇ。にんにくがね、じゃくじゃくしてるのがおいしいの!」
ちらっと台所を見る。この恐怖の味が生み出された工場を。
洗っていない料理道具がごっちゃと積まれ、新味蒸しパンが生み出されたプロジェクトXの壮絶さを物語っている。
……俺が外でうろうろしてる間に、ずっとこれを作ってたのか。
そりゃ、暇だよな。めんまには、DSは渡してあるけれど。
何もやることがなく、家に閉じこもってることのキツさなんて……ヒキコモリの俺が、一番よく知ってるはずなのに。
「おいしい?」
「うん」
あっさり、そんな相槌が口をついた。おいしいはずはなかった。
でも、味なんて関係ない。めんまが母ちゃんの蒸しパンを覚えていてくれたことと、寂しい思いをさせたのに、それを責めずに笑ってくれていることと……一口飲みこむごとに、めんまの優しさが、胃にじんわり広がっていくような気がした。
「……そういやさ」
「なあに?」
「お前のお願いって………花火、と関係ある?」
「花火? ――……ああっ!!」
めんまは目を真ん丸くして叫んだ。忘れていた願いはそれだったかもしれないと、何度も何度も興奮気味に繰り返した。
「でも、なんで!? すごい、どうやって思い出したの?」
「ん。ぽっぽとか……みんなで、お前のこと。話してたらさ」
「ええっ。みんなで、集まってるの?」
「え? い、いや……うん。たまたまだよ、たまたま」
「めんまも、みんなに会いたい!」
「そうだな。花火作るために、また集まろうって……そう、学校帰りに秘密基地行こうって話になったからさ。今度、お前も呼ぶよ」
この期に及んで、学校に行っている素振りをする自分が情けなくもあるが、どうしてもめんまを前にするとかっこつけてしまう。
「みんなが? 花火、つくってくれようとしてるの?」
「ああ」
「そっ、かぁ……みんなが……」
めんまは、ふと黙りこんだ。
しかし、すぐに思いきりの笑顔ではしゃいでみせる。
「じゃあ、めんま! そのときまで、いっぱいいっぱい蒸しパン練習するよ! それでね、みんなにあげるの!」
「ああ」
「それでねっ! みんなで蒸しパン食べながらね、花火の絵描いてねっ。それで、それで……!」
「……おい、めんま」
「なぁに? なぁに!?」
「なみだ、出てるぞ……?」
きゃっきゃと明るい声をあげながらも。その瞳からはぽろぽろぽろぽろ、涙がこぼれていた……。
「あれれぇ? どうして、悲しくないのに、うれしいのに……?」
「…………」
次から次にこぼれおちる涙を、めんまは、手の甲で何度も何度もぬぐった。ふにゃっとした笑顔を絶やさないままで……その姿を見つめながら、俺はふと思いだしていた。
ガキの頃、すぐ泣くめんまが嫌だったこと。
でもそれは、泣き虫うぜぇとか、そんな理由じゃなくて……。
めんまが泣くのは、いつも自分のためじゃなく。他人のためだったから。
自分が泣かせてるみたいな、そんな気分になって。いたたまれなくなったんだ、きっと。
夜が更けていく。
ソファに寝転がって、ベッドの上でゆっくりと上下するめんまの下腹を眺める。とても柔らかな、時間だ。
ずっと……めんまが消えたあの日から、縮こまってた心。
何かを好きだとか、楽しいとか、そんな簡単な感情すら忘れてた気がする。
めんまの願いを叶えてやる、なんて言いながら。俺は……ずっと抱いていた願いを、めんまに叶えてもらっている。
めんまに、会いたいって、泣いたあの日の願い。
この、当たり前みたいになった優しい空気の中で、叶えてもらった。その願い……。
「すぅ……す……」
今夜は、ここんとこうるさかった、夏の終わりの虫の音も聞こえない。
めんまの寝息だけが、夜に響いてく。
眠るめんまは睫毛が長くて、こんな時間がずっと続けばいいって。つい思っちまうけど……。
「……お返し、しなきゃだよな」
こうやって、俺の願いを叶えてくれてるめんまに。
他人のためにだけ泣く、めんまのために。