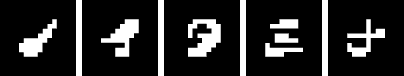NOITAMINA
OFFICAIL WEBSITE
SHARE
ツイート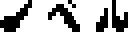 NOVEL
NOVEL
ノイタミナノベル「PSYCHO-PASS サイコパス/ゼロ 名前のない怪物」 第一章

「俺は、女好きが高じて潜在犯落ちした男だぞ」
これが、執行官・佐々山光留(ささやまみつる)の口癖だった。
第一章
1
深夜、巨大なファンがうなりを上げる公安局刑事課一係の刑事部屋で、監視官・狡噛慎也(こうがみしんや)と執行官・佐々山光留は睨み合っていた。いや、正確に言えば狡噛だけが佐々山を睨んでいた。
「おい、」
我ながら情けない声が出たもんだ……、狡噛は心の中で独りごちる。力ない発声はすぐさま巨大ファンに絡め取られ、目の前の佐々山に届くことはない。
「お前のやっていることは重大な職務規程違反だぞ」
自分の発した言葉がそばから霧散し、排気ダクトの彼方へ吸い込まれていくようだ。むなしさに嘆息し天井を仰ぐ。
こんなやりとりを、今までもう何回しただろう。
怒りはあるのにその感情すら形骸化していて、自分でも妙に白々しいと思う。平面的な蛍光灯の明かりが、この茶番を演出する優秀な小道具のようだ。
執行官を監視し職務遂行のため使役するのが監視官の勤めである。
公安局入局当初、新人研修施設で狡噛は確かにそう教わった。教わったのだが……。
今目の前にいるこの男が、狡噛の指示通りに任務を遂行したことは一度もない。いや、一度くらいはあったのかも知れないが、ほぼない。狡噛が理想と現実のギャップに頭を抱え続けて、すでに5年半が経過しようとしていた。
狡噛は、『佐々山光留に執行官の適性有り』としたシビュラシステムの神託を少しばかり恨めしく思い、本日何度目かのため息をつく。
シビュラシステム――厚生省が管轄する包括的生涯福祉支援システムの名である。
人間の精神的形質を数値化することにより、各個人に最良の社会福祉を提供するための巨大演算機構。心理状態、性格的傾向、趣味嗜好、職業適性など、あらゆる精神的特質がシビュラの前につまびらかにされ、人間は自ら求めることなく最適な職、最適な住環境、最適な人間関係、最適な生涯を得ることが出来るようになった。
人生の選択に付随する苦悩はもはや古典的創作の中にしか存在せず、
『成しうる者が為すべきを為す。これこそシビュラが人類にもたらした恩寵である』
といううたい文句が示すとおり、シビュラの司る世界においては誰もが何らかの適性を持ち社会構成に必要とされる、欠けざるピースなのである。
もちろん、今狡噛の目の前で大あくびを書いているこの男であっても。
「とりあえず、まー、狡噛。お前髪の毛拭けば?」
狡噛の煩悶はどこ吹く風、佐々山は脳天気に切り返すとフェイスタオルを差し出した。
雨の多いこの街では、出先で不意に降られることが少なくない。今夜も任務のため繰り出した先でにわかに降られ、狡噛の黒髪はくったりと質量を増していた。
佐々山の思わぬ気遣いに目をやる。𠮟責中の気まずさを悟られぬよう小さくうなずきタオルに手を伸ばしたが、その手はすぐに静止した。
差し出されたタオルはくたびれくすみ見るからに臭気を放ち、滲んだ文字で「大山温泉スパランド」と印字されている。
「佐々山、お前そのタオルどうした……」
誕生以降、精神形質測定の精度を上げ続けたシビュラはついに個人が今後犯罪を犯すであろう予測値『犯罪係数』までをも解析することを可能にした。これにより、高い犯罪係数を保持するものは潜在犯として社会から隔離され、全ての罪は犯される前になきものとされる。
潜在犯の中にはしかるべき治療を受けて社会復帰するものもいるが、犯罪係数が一定以上を超え医学的措置が不可能と判断されたものは、矯正施設でその一生を終える。そんな矯正施設送りの潜在犯の中から、シビュラに適性を判断されたものが、執行官となり厳重な監視のもと社会的奉仕活動に従事するのである。
そんな執行官には日用品一つ自由に購入する権利がない。もちろん、余暇を温泉で過ごすことも出来るはずがない。その執行官が温泉施設名の印字されたタオルを手にしていることの違和感。問い詰めたところでろくな答えはかえってこないだろうと思いつつも、狡噛は質問した。「執行官を監視する」という職務に対する誠実さの現れ、と言うよりも、5年間佐々山と職場をともにしたことで身についてしまった反射神経がそうさせたのだ。
「さっき拾ったんだよ、扇島で。道に落ちてたからさ」
予想通りのろくでもない答えに、深くため息をつきうなだれる。狡噛の前髪から水滴が一粒二粒したたって、刑事部屋の無機質な床に滲んでいった。
「ああほら、濡れてんじゃねーか! 使えよほら」
「いらん!」
「あそー」
それなりに激しい拒絶を示したにも関わらず、佐々山は傷ついたそぶり一つ見せず拾得物のタオルで自分の頭をガシガシと拭き始める。激しくかき回される佐々山の短髪から水滴が飛沫して狡噛の頬を濡らし、それが余計に彼の心を波立たせる。
「任務中にそうなんでもものを拾うな!」
「じゃあいつ拾うわけ? 非番中に? クソ殺風景な官舎の中で? なんかいいもの落ちてるわけぇ?」
「そういう問題じゃなくて……! 任務中に勝手なことをするなと言ってるんだ! そもそも――」
そもそも任務以前の常識的な問題。
「汚いだろお前、廃棄区画の道に落ちてたタオルでよくそう豪快に頭を拭けるな!」
狡噛の脳裏に今夜訪れた国内最大の廃棄区画――扇島の光景がよぎる。
日本にまだ海外貿易という概念が存在し、主要エネルギーが石油だったころ、そこは様々な私企業の工場が建ち並ぶ一大工業地帯であった。しかし時代の変遷とともに海外貿易が廃れ日本国民の人口も最盛期の十分の一ほどに減少し巨大生産レーンの需要が減少した今は、その本来の役目を終え、公式には無人の巨大廃棄区画となった。公式には、というのはつまり実際には人が住んでいるということだ。いつの時代も秘密の場所を見つけるのが上手い人種というものがある一定度は存在するようで、現在はシビュラシステムと馴染まない後ろ暗い人々の吹きだまりとなっている。
東京湾に横たわる、巨大な怪物の影。
不潔で、暗い、社会を拒絶した人々の終着駅。
住人たちの手によって違法に増改築を繰り返された工場群はもはや原形をとどめず、鉄の建造物からはダクトが無数に触手を伸ばし、あるところでは断ち切れ、あるところではまた別の建造物と結びつき幾重にも重なり、有機的な陰影を湛えている。
古い油がほこりと混ざり合い、黒く、そこかしこににこびりつき、どこから流れ込んでくるのか、奇妙な色をした汚水には痩せ細ったネズミの死体が浮かぶ。
足下には吐瀉物にまみれた浮浪者が横たわる。
思い出すだけで臭気が鼻腔をつきそうなあの場所。
あそこに落ちてたタオルで頭を拭いているのかこの男は。さらにいえば、悪びれる様子一切なく貸そうとしたな俺に。水分を含んだ頭がさらに重くなる。やはり潜在犯は度し難い。
「別に汚くねーけど。臭わないし。ほれっ」
と鼻先にタオルを突きつけてきたので思わずのけぞって小さく声をあげると、その様子がツボにはまったのか、けたけたと笑っている。
能天気な笑い声が、狡噛の膨れ上がった怒りを爆発させた。
側にあった適当な机を叩きつけながら声を荒げる。
「今夜のお前の勤務態度について、始末書の提出を命じる! 」
「えー!!」
「お前自分が何をしたかわかってるのか?!」
「社会奉仕活動?」
ハンッ! と大げさに鼻を鳴らしてみせてから、狡噛は我ながらちょっと芝居がかりすぎたかと思う。
「聞いて呆れる。明らかにイリーガルな数値をたたき出した潜在犯を取り逃しておいて奉仕だ?」
「女を撃つのは趣味じゃねー。俺は――」
佐々山の声にすかさずかぶせて言う。
「俺は女好きが高じて潜在犯落ちした男だぜ、だろ? 聞き飽きた」
長らくアンタッチャブルな存在だった廃棄区画だが、近年解体の気運が高まっている。扇島もその例外ではなく解体作業が進められていたのだが、今夜解体業者と住民たちとの間に小規模な衝突が起こった。
事態沈静の命を受け現場に向かった狡噛たちだったが、佐々山は現場の潜在犯たちに逃亡を促したのだ。しかも女性潜在犯のみ。
佐々山はオフィスチェアーの背もたれに大きく上体を投げ出しクルリと回転すると、いたずら心を湛えた瞳を狡噛へ向けぺろりと舌を出して見せた。
「だってよー」
今度は勢いよく上体を起こし反論する。
「だいたいなんで今更扇島解体なんだよ。あそこはもう何十年も政府に無かったことにされてるとこじゃねぇか。おかげで俺達がさばききれない潜在犯も、ある意味監禁状態。あそこにいるぶんにゃ害もねぇ。しょうみな話、公安も扇島には助けられてんだろ?」
確かに、慢性的な人手不足に苦しむ公安局にとって、各所に点在する廃棄区画はあえて触れる必要のない藪。そこで何が起きようと職務範囲外、公安局含め行政が廃棄区画に対してそういう扱いをしてきたのは事実である。
「それをわざわざ引っかき回してあそこにいる連中一網打尽にしたところで、そんだけのキャパ引き受けられる矯正施設なんてあんのかよ」
佐々山は粗暴ではあるが、無知でも、バカもない。すれた視線の奥には知性が煌めいていることを、狡噛はよく知っていた。
佐々山のまっとうな切り返しにたじろぎながらも何とか二の句を継ぐ。
「そんなこと……お前や俺が考えるは必要ない。潜在犯とわかってる人間を見逃す、その行為が問題だと言ってるんだ。お前は潜在犯が更正して社会復帰する権利を奪ってるようなものなんだぞ」
「更正して社会復帰、ねぇ……さすが公安局のエリートは崇高な理念をお持ちだ」
佐々山は白けたように一息つくと、スーツの胸ポケットからつぶれたタバコを取り出し火をつけた。
「吸う?」
「俺はタバコは吸わん。何度言ったらわかるんだ」
「そーでしたそーでした」
はき出された紫煙が、なに気にすることも無しと言った風情で二人の間を漂う。
軽度の潜在犯ならばサイコパスの治療は可能だが、ある程度まで数値が悪化してしまえば更正はほぼ不可能である。そうなれば潜在犯は矯正施設で拘禁されたまま一生を終えるか、執行官のように厳重な管理のもと社会奉仕活動を続けるしかない。
どんなに崇高な人権理念を掲げようと、潜在犯の行く末というものはそういうものなのだ。俺は知っているぞ、潜在犯の俺は……と佐々山の沈黙が語る。
紫煙がファンに勢いよく吸い込まれていく。
2
「ねえ、用がないならもう帰っていーい?」
睨み合う二人の男のあいだで視線を行きつ戻りつさせながら、桐野瞳子は声を上げた。
寒い。
目の前にいる男達は、制服のプリーツから雨露したたらせる自分に対して、ホットドリンク一つ、タオル一つ差し出さずに、口論を続けている。ただでさえ一二月の寒風にさらされ冷えていた瞳子の身体が、男達の寒々とした空気に当てられ余計に冷えるようだ。
「ていうか寒いんだけど。空調もっと温度上がらないの?」
瞳子は今年一六になるが、生まれてこの方こんなぞんざいな扱いを受けたことがない。
幼少時から私立の名門桜霜学園に所属し、深窓の令嬢達に囲まれながら蝶よ花よと育てられてきたのである。たとえ学園の外であっても、ある種のシンボルであるセーラーカラーの制服を身にまとっているときは、一定の敬意を持って扱われてきた。
それが今はどうだ。
古式ゆかしいセーラー服も自慢の豊かな黒髪も、水を含んでみすぼらしく身体に張り付き、厳格な父親が見たらその場で泣き崩れそうな惨状であるにも関わらず、大の大人が二人してフォローを入れるそぶりもない。
我慢の限界だった。精神的にも、体力的にも。
気色ばむ瞳子の様子に気づいたのか、短髪の男が先ほどまでとは打って変わった人なつこい笑顔で振り向いて言った。
「おーわりぃな! ほうっておいて。こいつの頭が固くてさ」
くわえタバコであごをしゃくらせながらもう一人の黒髪の男を指す。
先ほどからの会話を見るに、黒髪は短髪の上司のようだが、短髪に黒髪を恐れ敬うようなそぶりは微塵もない。
瞳子が二人の関係を訝しんでいると、その視線に気づいたのか黒髪はばつが悪そうに肩をすくめた。
「すまない。すぐ部屋の温度を上げさせよう。ついでに身体を拭くものも持ってこさせる」
そういうと黒髪は背を向け、腕につけた端末に話しかけ始めた。「タオル二枚……」と自分の分も取り寄せているようだ。
公官庁の職員にのみ支給されるという特殊なホロデバイス。一般に支給されているものとは違う仕様になっているらしいという噂が本当なのかどうか、わき上がる好奇心にあらがうことなく身を乗り出してのぞき込もうとする瞳子の視界に、短髪が無遠慮に割り込んできた。
「かわいいねー。その制服、桜霜学園のだろ? すっげーお嬢様学校の」
躊躇ない距離の詰め方に驚くより、視界を遮られたことの不快感が勝って至近距離でにらみ返すと、短髪は目を丸くしてからくしゃりと笑った。
「なかなか活きのいいお嬢様だ」
そういうと満足げにタバコに吸い付き、ぷくぷくと煙をはき出す。
タバコなんて前時代の遺物をいまだに嗜好している人
間がいるなんて。好奇心に忠実な瞳子の丸い目が、今度はタバコに釘付けになる。
「ん? なんだ、珍しいのか。吸う?」
くしゃくしゃにひしゃげたパッケージを差し出す短髪の頭部に、黒髪の平手が打ち込まれる。
「今君の学校に連絡したから、ここで迎えが来るのを待っててくれ」
黒髪のその言葉に自分の身体が余計に冷える思いがして、瞳子は小さく身震いした。その様子に黒髪が問いかける。
「まだ寒いか?」
寒い。
ヒステリックな女教師の青筋だった表情が思い浮かんでなお寒い。枯れた砂漠のようにひび割れた顔を引きつらせて、こう言うに決まってる。「瞳子さんまたあなたなの?!」
「別に……一人でも帰れるのに」
「未成年をこんな時間に放り出すわけにいかないだろ。廃棄区画で補導されたようなヤツならなおさらだ」
口を尖らせてむくれる瞳子に、黒髪が釘を刺す。
「深夜に廃棄区画を徘徊とは感心しないな。今は色相にも問題ないが、繰り返せばどうなるかわからんぞ」
𠮟責の対象が短髪から自分に移ったことがわかって、瞳子はますます寒々しさに表情をゆがめる。
十六歳の多感な時期に全寮制女子校という巨大な牢獄にとらわれた健全な女子が、ほんの少しばかりの自由を求めて街へ繰り出すことの何がそんなに悪いというのか。
たしかに繰り出した先が日本最大の廃棄区画というのは、思春期の小さな暴走としては可愛げがないことは自覚していたが、それでも今、素直に頭を垂れる気にはなれない。
目線をわざとらしく外すと、セミロングの毛先をクルクルともて遊ぶ。
大人にはこういう態度が一番効くのだ。
徹底していると相手はかってに激昂するし、それを目の前にすれば自分は自然と冷静さを獲得できる。そうやって精神的優位性を確保しながら内心で大人をこき下ろすのが思春期の正しい渡り歩き方だと瞳子は知っていた。
「おい、聞いてるのか」
案の定、黒髪は瞳子のふてぶてしい態度に閉口しているようだ。
瞳子は満足して、濡れた毛先を指ではじいてみせてから、心の中でぺろりと舌を出した。
隣から押し殺した笑い声が聞こえる。
「さすがの狡噛も女子高生にはかたなしだなぁ」
肩をふるわせながらそういうと、短髪は瞳子を見据えた。
「まあ、お嬢様にはわからんかもしれねぇが、世の中には想像も出来ねえようなわりぃやつもいるんだよ。俺みたいなね~」
途端、立ち上がり瞳子の上に覆い被さろうとして来る短髪に、瞳子は悲鳴を上げながら鞄を振り上げた。
しかし短髪は初めからその鞄が振り上げられるのを知っていたかのように片手でそれを軽くいなすと、そのまま瞳子の手首をつかみ机に押しつける。
手首に付いていくように、瞳子の上体が机に倒れ込む。その衝撃で鞄の錠前が開き、中身がばさばさと投げ出された。
「っ……!!!」
「あら、声も出ないか。けっこうかわいいとこあるじゃ――」
言い終わらぬうちに、今度は短髪の手首が高くひねりあげられ、瞳子から引き離される。
「痛い痛い痛い痛い!!」
「お前……いい加減にしろよホントに」
あきれきった表情で短髪の手首をひねったまま、黒髪が瞳子に詫びる。
「すまない……よく言い聞かせておくから」
なんだこれ?
瞳子の中におかしみがこみ上げて、思わず笑いがこぼれてしまう。
びしょ濡れで、補導で、説教で(たぶんこれから女教師にも食らうだろう)、最悪だけど、それを補えるくらいには面白い。教師や父親の言うとおり、厳重に守られた女子校の中でぬくぬくと安全を享受していてはこんな経験はできない。
これだから外の世界をのぞき見るのはやめられないのだ。
ある男の面影が胸をかすめる。
「あの人」も、自分と同じような気持ちでいるに違いない――そうであればいいのに。笑いににじみ出る涙をぬぐいながらそう思う。
3
さっきから怒ったりふて腐れたり笑ったり、一時として同じ表情をしない瞳子を前に、狡噛と佐々山は顔を見合わせた。
今夜彼女は、雨降る廃棄区画の片隅で、しょんぼりと立っていた。
何もかもが薄汚れているその場所で、黒い革製の学生鞄を持ち、ぴんと角の立ったセーラーカラーに折り目正しいプリーツスカートを身にまとう彼女は、明らかに異質だった。
雨に濡れた影が廃棄区画の雑多なネオンに浮かび上がる様は、いつか見たSF映画のワンシーンを思い起こさせて、佐々山の足を止めた。
掃き溜めに鶴、とは随分使い古された表現であるが、まさにそれだなと佐々山は思った。
水を含んでだらりと下がる黒髪の間から白く凍えた肌が覗き、その白い肌がネオンで青や赤や黄色に染まる。そのうつろいがそのまま少女の内面の揺らぎを表しているようで、その一過性の輝きに佐々山は目を奪われたのだった。
今の彼女は、公安局の平面的な明かりに照らされているが、クルクルと変わる表情はやはり複雑な色彩を湛えた天然の鉱物のように思われた。
「まあとにかく俺が言いたかったのは、自分を大切にしろってこと!」
宝石は、己の輝きが他者の目にどう映るのか知ることはできない。
それがいかに魅力的で、時として暴力的衝動を誘うと言うことも。
「お前ぐらいの年代は、自分を過信しすぎる傾向があるからな。さっきみたいなことがあっても何とかできると思ってたろ」
佐々山の言葉に、瞳子はぐっと口ごもる。
「いいか、今お前は世の中に自分ができないことなんてなにひとつ無いくらいに思ってるかもしれねーが、その自信を支えてるのは、無知だ。自分の無知に泣かされるほど、惨めなことはねぇぞ。大人が言うんだから間違いない」
「なによ……偉そうに。潜在犯のくせに」
「ははっ、ちげーねー」
佐々山は軽く笑ってから瞳子の頭を二度軽く叩くと、机の上に投げ出された瞳子の私物を拾い上げ始めた。
女の子らしい色使いの小物を一つ一つ丁寧に拾ってゆく。
タブレット端末やデータスティックなど近代的なデジタル機器に混じって、今時珍しい紙でできたテキストやノートもある。おそらく瞳子の通う桜霜学園ではアナログな記憶媒体の使用が推奨されているのだろう。
「古式ゆかしい名門」の所以ここに有りってとこだなと、感心しながらちらばる小物に目をやっていると、あるものが佐々山の興味を惹いた。
「一眼レフじゃねえか……」
ピンクや黄色、パステルカラーの彩りの中で、黒光りするぼってりとした機体と、男性の拳以上ある大きさのレンズが異様な存在感を湛えている。
「しかもこれNICHROME D7000じゃん! とんでもねぇ名機だぞ? これお前が使うの?」
すぐさま持ち上げてファインダーを覗く。
「うおっ! いいねぇこのずっしりくるかんじ!」
「ちょっと! 勝手にやめてよ!」
慌てて手を伸ばす瞳子をさらりとかわし、カメラの各部位を観察する。
「まだ使えるんだこれ? 何十年も前の製品だぞ? まだ日本が産業国だったころの」
瞳子はぴょんぴょんと跳びはね愛機を奪還しようとするが、佐々山は全く意に介す様子がない。さらには
「ちょっとデータみせてよ」
というと承諾もないまま、官製のホロデバイスで画像データを表示した。
瞳子の黄色い叫び声が室内にこだまするのと同時に、3人の目の前で大量の画像データが展開された。
「人のデータ勝手に見るなんて最低!!」
「なんだよ、ハメ撮り画像でもあんのか?」
「ハメ……え?」
「だったらなおさら検閲の必要があるなぁ♪」
「おい佐々山……」
友人とのスナップショット、校舎や食事の様子など、平和で、どこか貴族的でさえある瞳子の日常風景の点描。その中にいくつか廃棄区画の写真が混ざっている。
「これは? 今夜撮ったものか?」
狡噛はその写真の異質さを訝しんで尋ねる。
「そうよ! 廃棄区画なら少しは面白い写真撮れると思ったの! もういいでしょ返してよ!」
顔を真っ赤にして食いつく瞳子を制して、今度は佐々山が尋ねる。
「面白い写真て、お前本気か?」
「はぁ?」
「ピントも露出もぐちゃぐちゃ。お前これ面白いどうこう以前の話だぞ」
赤かった瞳子の頬がさらに赤くなる。まるでカラーフィルムを透しているようだ。
「だからッ……それは……! 勉強中!!」
憤怒と羞恥に任せて佐々山の手から愛器を奪い返すと、目の前の画像データは跡形なく消えた。
刑事にはプライバシーって言う概念がないんだ……。激しい動悸を必死で押さえながら瞳子は思った。
ポーン、と言う機械音に目をやると、ガラス戸の向こうに庶務用ドローンがタオルを抱えて所在なげに佇んでいる。佐々山は何事もなかったかのように扉まで向かうとタオルをつかみ、そのまま瞳子に投げて寄こす。
上質なパイルの肌触りと柔軟剤の香りにめまいがするほど安らぐ。途端に先ほどの激情は霧散し、身体がどっと重くなるのを感じる。その身体的反応に自分の幼さを実感し、瞳子は小さくため息をついた。
こういう幼さが「あの人」の自分に対する興味をそぐのだ。
4
それから数十分後、瞳子は青筋たてた中年の女教師につれられて公安局をあとにした。
「瞳子さんまたあなたは……! 今度こそお父様に報告しますからね!」
貴重な眠りを邪魔されてことさら不機嫌な女教師は、瞳子の華奢な腕をちぎれんばかりに引っ張りながらそう叫んでいた。
佐々山は女教師の「また」と言う言葉が気にかかる。
瞳子の深夜徘徊は常習性のものなのだろう。
遠からぬうちに自分とあの少女は再会する、そう予感した。
なぜなら、悪ガキは懲りると言うことを知らないから。
そう思うと少しだけ胸の中でざわめきがおこる。楽しいおもちゃを発見したときのような、原始的なときめき。
コツンと足下に何かが触れた。パステルピンクのデータスティックである。瞳子の鞄からこぼれ落ちたものだろう。予感が確信に変わる。
データスティックをひょいと拾い上げ、ふふふふん、と上機嫌で鼻を鳴らし、本日何本目かのタバコに火をつけ紫煙をはき出すと、背後からわざとらしい咳払いが聞こえた。
狡噛である。
煙たそうにしかめる彼の目が、「話はまだ済んでないぞ」と語っている。
「悪かったよ」
なるべく殊勝そうに言う。
狡噛の険を含んだ眼差しが、みるみるうちに飼い犬に手を噛まれた少年のそれになる。
佐々山の目の前にいる青年は、公安局きっての優秀な成績で、鳴り物入りで刑事課に配属された優等生である。機知に富み、素早い判断力を有し、激しい研鑽を積んだ肉体は他の追随を許さない。その有能さに裏打ちされた健常な精神は、公正・誠実をモットーとし、佐々山のような不良執行官にも職業上の仲間としてそれ相応の信頼関係を求める。つまり裏切られれば、全うに傷つく。
ようはいい奴なんだよなぁ、紫煙越しに狡噛を見つめながら、佐々山は思う。
ただ、その清廉潔白な眼差し故に、世界の暗部を見落とす危険性をはらんでいる。
まっすぐに明るいところにつき進んでいたかと思いきや、明るいのは目の前だけで本当は暗闇のただ中に身を投じていた、なんてことになりかねない危うさを持った男だ。
つまり無知なのだ、人間の後ろ暗い、全うとはほど遠い、卑しい暗部について。
佐々山はこの男が嫌いではない。嫌いではないが、時々自分の暗部に無遠慮に抵触されているような感覚を覚えることがある。
強い光源の元に浮かび上がる、自分の真黒き影。
それを突きつけられて喜ぶ人間はそうはいまい。勿論佐々山も。
「ちゃんと職務規程に従い潜在犯は連行します」
もっともらしい言葉にわかりやすく安堵する狡噛を見ていると、どうしても彼の清廉潔白な内面を引っかき回してやりたいという意地悪な心がうずく。
「ただし、好みの女は別だがな」
特に今夜は。
佐々山の様子がおかしい。
今までも執行官の職務について真面目だったとは言えないが、今夜のようにあからさまな職務規程違反をすることはなかった。
執行官は職務に忠実であることにおいてのみ、社会にその存在を許容されている。職務を遂行できなかったり、反逆行為が認められればすぐさまその存在は社会から抹殺されるのだ。
8年間も執行官の任に就いてきた佐々山がそれを知らないはずはない。それなのに――
今夜の佐々山の振る舞いは、自殺行為に等しい。
「佐々山、お前どうした」
狡噛の実直な質問に、佐々山の表情が微かに硬直する。
「……別に」
「今月頭におこった衆院議員殺害事件が広域重要指定事件になったと連絡があった。おそらく今後は係の垣根を越えて事件捜査にあたることになる。俺だけがお前の行動を監視する訳じゃなくなるんだぞ」
長らくアンタッチャブルだった廃棄区画の解体運動の高まりには、一つの大きな推進力があった。
衆院議員橋田良二殺害事件である。
廃棄区画解体運動の急先鋒であった衆院議員・橋田良二が何者かにより殺害され、プラスティネーション加工(死体に特殊な樹脂を浸透させることにより保存可能な標本にする技術)された上で、微に入り細に入り解体され、橋田の行きつけだった赤坂の高級料亭の前庭に、人体標本宜しく、堂々と展示されたのだ。
遺体は全裸で料亭前庭に正座し、三つ指をつき、頭部は円形に切開され、脳がくり抜かれていた。検死の結果、脳の一部が切り取られ肛門に挿入されていることがわかった。
その部位とは、海馬――記憶を司る器官だ。
以前から、廃棄区画の解体を求める人権団体から賄賂を受け取っているのではとの疑惑を追求されていた橋田は、国会の証人喚問で「記憶にございません」と連発し、そのふてぶてしい態度が批判の的になっていた。肛門に挿入された海馬はそんな彼への皮肉なのか。
とにかくそのあまりに常軌を逸した犯行に、遺体発見時、周囲のエリアストレスは跳ね上がり、市民のサイコパス悪化を懸念した厚生省により、報道規制が引かれたものの、規制の外にいる公人達は震え上がった。
手口としては大がかりな事件だったが、被害者が消息を絶ったのが視察に訪れた都内の廃棄区画であったため、犯行の記録が一切残っておらず捜査は進展せず。関係各所から廃棄区画の解体を求める声が上がったのである。
おかげで厚生省を初めとしたお役所各所は廃棄区画解体に手をつけざるを得なくなり、ほぼ保留状態になっていた廃棄区画解体が現実のものとして大きく動き出したのだ。そして、廃棄区画解体運動のシンボルとして今もっとも注目されているのが、今夜狡噛たちがかり出された扇島である。
ある事件が起こったときに、事件そのものの解決を試みるよりも、事件を発生させた環境を改善しようとするところに、この時代特有の気風が見て取れる。
シビュラシステムに管理された環境ではそもそも犯罪など起こるはずが無く、犯罪が起こるとすればまずその環境に欠陥がある、と考えるのがこの社会の基本的論理思考である。
しかし、ある一定の歴史と特異な文化が形成されている扇島の解体は一筋縄ではいかず、結局、刑事課が事件解決のために尻を叩かれることになった。
通常であれば刑事課の一係二係三係は担当事件が明確に分かれているが、広域重要指定となった衆院議員殺害事件において、その区分は棄却される。全係総員で事件を解決することが求められるのだ。
つまり、普段の佐々山を知らない監視官が佐々山の監視権を握る可能性もある。
人間関係が形成されていない状態で、佐々山が放蕩な行為に出たらどうなるか、狡噛はそれを危惧しているのだ。
狡噛の進言に佐々山の口元かいびつに歪む。
まだ火をつけて間もないタバコを灰皿にこすりつけながら狡噛をにらみつけた。
「ほう。それは、『俺だから見逃してやってるんだぞ、感謝しろ』ってことか?」
佐々山の扇情的な返答に、狡噛の頬がカッと熱くなる。
言い返すまもなく佐々山が二の句を継ぐ。
「そういうことだろ。『俺じゃなかったらお前なんて速攻ドミネーターでズドンだ。それがわかってたら俺の言うことに素直に従え』、違うか? だかな狡噛、俺に言わせりゃ、そいつはお前の怠慢だ。言うこときかねえ執行官はドミネーターで排除する。それが狡噛、監視官の役目だろ」
『ドミネーター』
刑事課に所属するものだけが携帯を許される、特殊拳銃である。
シビュラシステムとオンラインで繋がり、銃口を向けた人間の犯罪係数を瞬時に読み取り、各人の犯罪係数に即して鎮圧を執行する。
犯罪係数が一〇〇以上三〇〇未満のものに対しては、電気麻酔銃――パラライサーと化し、それ以上のものに対しては強烈な殺人銃――エリミネータと化す。その鑑識眼はシビュラシステムのもとで生活するあまねく市民に平等に注がれる。当然、執行官である佐々山に対しても。
ゆっくりと立ち上がり、視線を上目遣いにギラつかせながら狡噛に迫る。
「清廉潔白なお前は忘れてるかも知れねぇが、俺は潜在犯だぞ。いつだって社会に牙むく。いまだってな」
そういうと佐々山は狡噛の眼前に手を伸ばし視界を遮るのと同時に、額をそのまま強く後ろへ押す。急な後方への圧力に思わず体勢を崩しのけぞる狡噛の脚を、今度は前方へ引っかける。すると屈強な狡噛でも簡単に尻から倒れる。身体を起こそうとする狡噛の胸にすかさず右足の靴底を押し当てて床に貼り付けにすると、銃口をかたどった指先を向けた。
「狡噛慎也監視官、任意執行対象です、ってか」
指先の銃口越しに見る佐々山の瞳は、凶暴な光りを湛え、この一連の行動が先ほど瞳子にしたものとは全く別の意味合いのものであることを物語っていた。
突然の出来事に思考が追いつかず酸欠の魚のように口をぱくつかせる狡噛の様子に満足したのか、佐々山は鼻で笑うとゆっくりと脚をどける。
「狡噛はあれだな、実戦経験が足りねぇな」
そういった佐々山の瞳にはすでに先ほどまでの眼光はなかったが、それでもその余韻は狡噛の胸中に留まっている。
「おまえ……冗談にも程があるぞ」
佐々山の思わぬ行動に血の気が引いてゆくのがわかる。自分が使役しているのは潜在犯、紛れもない狂犬。その事実を狂犬本人から突きつけられたのだ。
「冗談じゃねえよ。お前が甘いっていってんだ。気に入らなければ俺を撃て。それがお前の仕事だ」
佐々山はそういうと、狡噛に背を向けて座り、沈黙した。
世の中の音という音が、みんな黙り込んでしまったかのようだった。
そんな中で巨大なファンの回転音だけが空間を埋め尽くし、息苦しいほどに迫ってくる。
少しばかり自棄になっている自分を、佐々山は自覚していた。普段ならここまで監視官にたてつくことはない。
反逆行為がそのまま死に直結する世界だ。
何故自分がこうまでして狡噛に食い下がるのか。考えればすぐさま陳腐な答えが浮かび、佐々山は苦笑する。
今朝、自分の端末に届いたメールの文面が頭をよぎる。
自分にとってもっとも不都合な事実が、そこには綴られていた。執行官としての自分を足下から揺るがす、不都合な事実が。
八つ当たりなのだ、単に。
自分のふがいなさに対するいらだちを、狡噛にぶつけているだけだ。そうとわかっていても、自棄に転がり落ちてゆく心を止めようという気が起きない。
これが世に言う、「やきがまわった」って状態だなと、心の中で独りごちる。
もし仮に狡噛が今自分を背後から撃ち殺したとして、感謝こそすれ恨みはしないだろう。
そんなくだらない仮定をもて遊んで、佐々山は沈黙に身をゆだねていた。
耳が痛くなるような沈黙の中で、狡噛は佐々山の言葉を反芻していた。
「お前が甘いっていってんだ。気に入らなければ俺を撃て。それがお前の仕事だ」
確かに、佐々山の言う通りかも知れない。
自分は執行官に寛容なふうを装っているが、その実、ただ執行官に銃口を向けることを恐れているだけなのかも知れない。
紛れもない、自分自身の人間性を守るために。
何事もなかったかのようにタバコをくゆらせる佐々山の背中を見つめる。
狡噛の口からこぼれたのは、
「すまない」
謝罪の言葉だった。
その言葉を聞くやいなや佐々山は振り返った。目を丸く見開いている。無理もない。狡噛自身も自分の言葉に驚いているのだ。
自分が何故謝意を述べたのか、言葉を発した瞬間には狡噛自身にもわからなかった。
ただ、思わずこぼれ出た言葉に後押しされるように理論が明確になっていく。確かに――
「確かに俺の態度は怠慢だったかも知れん。ただ――」
ただ、自分が謝りたいのはそのことではない。
「俺はお前を撃ちたくない。お前は潜在犯だが仲間だ。仲間を撃つような惨めな思いはしたくないんだ。これは俺の問題だが、やはりお前には無茶をして欲しくない」
佐々山の丸く見開かれた目が、徐々に、見慣れたいつもの形になっていく。
しかしその瞳は、同意でも反発でもない、複雑な感情の色を湛えていた。
結局その夜のうちに狡噛と佐々山の関係が好転することはなかった。
他の一係の面々が、任務を終え帰局し、二人の間に横たわる沈黙を破っても、二人の間の空気が変わることはなかった。
一係のもう一人の監視官である宜野座伸元が、衆院議員殺害事件の広域指定について申し送りを始めたときも、佐々山は協力的な姿勢を見せず、
「俺こういう知能犯っぽい事件をチマチマ捜査すんの性にあわねーんだわ。もっと、可憐なヒロインを悪い奴からバーンと助けるみたいなスペクタクルなヤツがいー。事件にヒロインが登場したら呼んでくれ」
と軽口を叩き、宜野座監視官の自慢のメガネを憤怒に曇らせた。
しかし、佐々山の「ヒロイン登場」と言う願望は、すぐにはたされることになる。
残念ながらすでに「悪い奴」の手に落ちきっていたが。
5
冬の朝の柔らかい光の中、彼女は翼を広げ、そこに舞い降りた。
いや、正確には吊されていた。
千代田区外神田パブリックパークの設営途中のアイドルコンサートのステージ上で、少女は陽光を一身に受けながらゆらゆらと揺れていた。
彼女の背後からは翼のようなものが広がり、腰には可憐なドレープがたなびいて、その様はさながら、ステージ衣装に身を包み、スポットライトを浴びながら観客の声援に応えるアイドルであった。
しかしその姿を間近で見て、彼女に声援を贈るものはいない。
彼女に贈られるのは、恐怖におののく悲鳴。
彼女の翼は、背面から綺麗にはぎ取られた皮膚であり、可憐なドレープは、筋組織にそって解体され付け根から放射状に広げられた、彼女の大腿部であった。
つづく