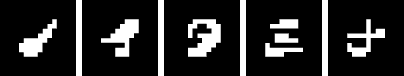NOITAMINA
OFFICAIL WEBSITE
SHARE
ツイート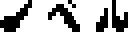 NOVEL
NOVEL
ノイタミナノベル「PSYCHO-PASS サイコパス/ゼロ 名前のない怪物」 第二章

第二章
1
「つまらないな」
桜霜学園社会科教諭、藤間幸三郎は、目の前に展開される扇島の風景写真のホロを一瞥して言った。藤間の指先では、今時珍しい金属製のボールペンがその切っ先を鋭く光らせながら、クルクルと小気味よく回っている。この男には、人と相対しているときにボールペンを弄ぶ癖がある。その様はすでに熟練の域に達し、ボールペンはあたかも生き物のように藤間の掌の上で踊る。その指先の器用さに釘付けになっていた瞳子は、この一言で、はっと我に返った。
「そう……ですか」
もうこれで何度目だろう。
目の前の男が自分の写真に興味を持ってくれたことは今まで一度もない。落胆に視線を落とすと、夕日に染まる廊下に、二人の影が長く、長く伸びていた。
瞳子がこの男に出会ったのは、今年の春。
瞳子の通う桜霜学園に、新任の社会科教諭として赴任してきたのが藤間であった。
この男は、初めからどこか異彩を放っていた、と瞳子は思う。
赴任当時、クラスの女子が藤間にいたずらをしかけたことがあった。
教卓に生理用品をしのばせておいたのである。
このいたずらは新しい男性教師になされる恒例の儀式であり、男という異質な存在に対する、少女たちの小さな威嚇である。
大抵の(特に若い)男性教師は顔を赤らめうろたえ、途端に少女達を異質なるものとして恐怖する。
そうして初めてその男性教員は、女の園の一員として迎え入れられるのだ。
当然少女たちは、藤間にも同じ反応を期待していた。しかし彼が彼女たちの期待に応えることはなかった。
藤間は教卓の生理用品に気づくと、だまってそれを黒板に貼り付け、何事もなかったかのように授業を始めたのである。その表情からは、少女たちに対する憤怒も戸惑いも恐怖も読み取れない。ただ、どこか諦観を湛えたような微笑みがあるだけだった。
その微笑みに、瞳子は釘付けになった。
くだらない儀式で小さな自尊心を満たそうとする少女たちに対して、小気味よい感情がわき上がったのも事実である。しかしそれ以上に、藤間の面差しそのものに、瞳子は惹かれたのだ。
彼女には、幼いころから繰り返し見る夢がある。
深い森の中、不思議な部屋に佇む少年のイメージ。
鬱蒼とした森の中で、その部屋だけはきらびやかに飾り立てられ、際立って輝いている。
部屋の中心には主のいない空の玉座と、その傍らに佇む少年。
何もかもが輝くその場所で、その少年はひときわ輝く笑顔を見せて、瞳子に語りかける。
「今度は君が、僕のお姫様になってくれるの?」
藤間の微笑みは、少年のそれを思い起こさせた。
それからというもの、瞳子は藤間へのストーキング行為に精を出した。
彼が写真部の顧問になったと聞けば写真部に入部し、ファインダーを覗いたこともないくせに、父親にねだって高価な一眼レフカメラを買ってもらった。
目に映るもの全てをカメラに納め、それを口実に藤間に話しかける日々。
シャッターを切った回数だけで言えば、瞳子は写真部の誰よりも勝っていた。いや、この国の誰よりもシャッターを切ったに違いないと瞳子は思っていた。
しかし、どの写真も、藤間の琴線に触れることはない。
どんな写真を見ても、藤間はその微笑みを微動だにせず、平然とボールペンを回しながら
「つまらないな」
と言うだけだった。
もはや瞳子の目に映る世界は全てが写真となり、藤間の前に晒され尽くしてしまった。藤間にとって瞳子の世界は、ペン回し以下の、つまらない世界と言うことなのだろうか。
否定できないな……と瞳子は思う。
全寮制女子校という閉ざされた空間。少女たちに、正しく、美しいものだけを注入し続けるための機関。そこに物心ついたころから囲われ続けてきたのである。自分の世界の狭さは自覚していた。
だからこそ藤間に食い下がった。
少女たちの牽制をものともせず、自分の世界を「つまらない」と一蹴する藤間は、自分の知らない世界から颯爽と現れた王子のように思えた。自分をここから連れ去って、見たこともない場所へ連れて行ってくれる王子。そして王子もまた、瞳子が自分の姫になることを望んでいるに違いない……。
幼いころから見る少年の幻影と相まって、瞳子の藤間に対する憧憬は、複雑かつ頑強なものへと変化してゆき、それに伴った彼女のストーキング行為は、学内にとどまらずついには学外へとそのスケールを広げた。
藤間は毎週末、学園敷地内にある教員宿舎から抜け出してどこかへ行く。
瞳子がそれに気づいたのは今から三ヶ月前の九月上旬のことである。
それ以来、藤間の後をつけては見失うということを繰り返した。(由緒正しき全寮制女子校には、先人達が築きあげた、由緒正しき抜け道もあるのだ)途中何度か教師に発見され指導室に連行されるというミスも挟みつつ、ようやくたどり着いたのが、巨大廃棄区画扇島だった。
扇島に踏み込むやいなや、そのあまりの広大さと、かつて自分が触れたことのない世界観にしばし呆然として、結局その日も藤間を見逃してしまったけれど……。
この経験は自分の狭い世界を、これでもかと拡張したように思えた。この場所の写真ならば、藤間も少しは心を向けてくれるかも知れない。そう思って、扇島の様子を何枚もカメラに納めた。
しかし、瞳子の期待は彼のいつもの言葉で、粉々に砕かれてしまった。
「私の写真のどこがいけないんでしょう。この前見て頂いたモノよりも被写体も工夫したのですが……」
うつむいたまま尋ねる。
被写体を工夫云々というより、その写真達は紛れもなく、藤間が姿を消した扇島のものなのである。一介の女子高生が様々な困難を経て、巨大な社会の暗部に進入した痕跡なのである。そしてなによりも、自分が藤間という人間の世界に肉薄しつつあるという証拠なのである。
今度こそ彼の微笑みの先にあるものが見えるに違いない、そう思っていたのに。
徒労感に襲われる。
廃棄区画で雨に濡れ、妙な刑事二人に補導され、あげくそのうちの一人に押し倒され、なんというか、学校の友人達が何人集まっても経験しきれないほどのことを、一晩のうちにやってのけたと言うのに、それでも自分の世界の広がりは藤間に遠く及ばないのか。
自分があまりに寄る辺なく思えて、足下から伸びる二人の黒く長い影をたよって、目で追ってみる。
二人の影はどこまでも長く伸びてゆくが、どこまでも重なることはない。
二人の立ち位置と光の性質を考えれば当然のことのはずなのに、なんだかそれがとんでもなく不条理な現象のように感じられて、瞳子は軽く歯ぎしりする。
こんな気持ちも当然、藤間には届いていないのだろう。
「どこがいけないって……そんなことわからないよ。僕は君に感想を求められたからそれを言っただけ」
相変わらずの微笑みを湛えて藤間が優しく言う。優しいけれども決して、こちら側には踏み込んでこない。まるで今の、二人の影のような距離感。
藤間を見つめる。
深遠な眼差しも、柔らかく湾曲する口元も、まつげも髪も、すべてが夕焼け色に縁取られている。きめ細やかな皮膚を柔らかな産毛が覆い、それが夕日に照らされて顔全体が黄金色に輝いているようだ。
やっぱり似てるよな……。
どこからともなく激しい郷愁の波が押し寄せてきて、心を全てさらっていかれるような感覚に襲われ、瞳子は小さく身震いする。
「どうしたの? もうようがないならいくけど」
そういうと瞳子の回答も待たずに、背を向けて行ってしまう。
藤間の細身で少しなで肩気味の後ろ姿を見つめながら思う。
今度は絶対、あの男の行く先を突き止めてみせる。
そして、あの男の世界を揺るがすような写真を撮ってやるのだ。
2
人間の一生は、その死に様に現れるという。
自分の境遇を嘆き、他人を妬み、後悔に溺れ、悲嘆にくれながらその一生を終えるのか、周囲に笑顔と感謝の言葉を残して、惜しまれながらこの世を去るのか。
その人間が歩んできた人生の総括が、死の瞬間になされるというのだ。
だとすれば――狡噛は思う。
この二人の一生とは何だったのか。
公安局刑事課大会議室に黒スーツの一団がずらりとその身を並べている。
これから刑事課一~三係総員で、広域重要指定事件となった衆院議員殺害事件と少女殺害事件について、捜査会議が行われるのだ。
刑事課は総勢二〇名と規模は小さいが、一堂に会せばそれなりの迫力がある。
狡噛は配属以来初めての事態に多少の興奮を覚えながら周囲を見回し、はたと気づいた。
佐々山の姿がない。
今日この時間に捜査会議があることは、自分からも口を酸っぱくして言ってあったのに。
昨晩の言い合いが頭をよぎる。あいつのことだからどうせ公安局の執行官隔離区画の自室で、寝腐れているのだろう。
左腕に巻き付けられたデバイスはすでに会議開始時間を示しているが、遅刻したとていないよりはましだ。すぐに連れ出してこようと、歯噛みしながら席を立つと、誰かがスーツの裾を引っ張った。
一係所属の、征陸智己執行官だ。
白髪交じりの頭髪とその表情に深く刻まれた皺は、彼がすでに中年を通り越して初老にさしかかっていることを示しているが、同時に、スーツの裾を握る分厚い手やその大きくはった肩は、彼の肉体がいまだ若々しさを保ち躍動することも示してる。
「佐々山ぁ、ちょっと調子悪くてな」
意味深にウィンクして言葉を続ける。
「佐々山より、監視官のお前が会議のしょっぱないねぇほうがまずいだろ。やっこさん随分ぴりついてるようだし……」
征陸が顎をしゃくらせた先には二係の監視官、霜村正和がいた。
腕を組み背もたれに大きくその身を預け右膝を小刻みに揺らす彼は、なるほど征陸の言う通り苛立っているようだ。
「広域重要指定化で捜査本部長に任命って言っても、結局自分の係で成果を上げられなかったことへの当てこすりみたいなもんだ。いらつくのも無理はねぇが、ここでヤツの不興を買えば、腹いせに上層部にどんな報告されるかわからんぞ」
たしかに、自分が捜査にあたっていた事件が広域重要指定の憂き目にあった上に二人目の犠牲者まで現れたとなれば、霜村の心中穏やかでないことは間違いない。
お世辞にも人格者とは言えない霜村が、自分の評価のため、無闇なことをしないと言い切れない。
「佐々山のことは執行官の放蕩で片が付く。とりあえずお前は座っとけ」
老獪な物言いに困惑しながら、狡噛はベテラン刑事を見つめた。
征陸はシビュラによる犯罪抑制システムの確立以前から、警視庁に刑事として所属していた、いわば大先輩である。
ドミネーターが存在しなかった時代、刑事達は今よりもずっと深く犯罪捜査と関わっていため、犯罪係数が実用化されたときには、多くの刑事がその数値の悪化を理由に離職を余儀なくされたという。
しかし征陸は刑事の職にしがみつき、ついには執行官に降格した。
そんな征陸を、狡噛は「とっつぁん」と言う愛称で呼ぶほどに信望していた。
まっすぐに見つめ返してくる征陸の思慮深げな瞳に説き伏せられるように、狡噛はおとなしく席に着いた。
会議室の照明がゆっくりとその明度を落とし、それと同時に中空に二つの死体が鮮やかに浮かび上がる。
一つは贅肉を身にまとった中年男性のもの。もう一つは、まだ肉体的女性らしさの萌芽を見せ始めたばかりの少女のもの。
刑事たちを補佐する鑑識ドローンがスキャニングした、殺人現場の立体ホログラムだ。
二つの人生の総括を、刑事達が一斉に見上げる。
あらゆる角度から三次元的に解析され寸分たがわず再現されたそれは、あくまでも電気的数列の出力にすぎない。しかし、其れ相応の迫力を持って彼らの眼前に迫ってくる。
生者とは異なる皮膚の色、肉のゆるみ、毛穴の拡張、眼球の白濁、おおよそ死体というものが持ちうる多くの特徴を有しながら、両者は明らかに普通の死体とは異なっていた。
中年男性は、全裸で何を詫びるのか、丸く切り取られた頭蓋を地面にこすりつけあるはずのものがない空洞を顕示し、少女は頭部こそ無傷だったが、その背面は皮をはがれ筋組織を露わにし、臀部から大腿部にかけてはご丁寧にその筋肉をささがきにされ、ミニのプリーツスカート宜しく放射状に広げられている。
あるものは息をのみ、またあるものは驚きに身体を震わせながら、それらと相対していた。
みなこの死に様になにがしかの解釈を試みながらも、しかしあまりの異常さに混乱し、思考の着地点を見いだせず、視線を当てもなく泳がせている。
「こりゃあ……」
征陸が白髪交じりの髪をかき上げらながらつぶやく。刑事達の数十の視線が、ベテランなりの解釈を期待し藁をもつかむといったふうに征陸に注がれる。
しかし、そのつぶやきに続く言葉はなく、沈黙に漏れた息はむなしく刑事達の足下に転がり落ちていった。
幾多の死体と対面してきた彼でも、この二体の有様に混乱が隠せないようだ。
初老刑事の複雑に歪む表情から視線を戻し、狡噛は再び二つの総括された人生を見上げる。
この二人が生前どんな悪行を積んでいたとしても、この死に様に釣り合うものなのだろうか。
よどみきった会議室の空気を押しのけるように大きく咳払いをしてから、刑事課二係所属の監視官霜村正和は、空っぽの頭蓋の真下に立って語り始めた。
「この死体は、衆院議員の橋田良二のものだ。今月五日火曜に、赤坂の料亭イヤサカ前庭で発見された」
霜村は黒く磨き上げられた靴を鳴らしながら、ゆっくりと橋田良二の下を歩く。
「これまで、我々二係が本件の捜査にあたってきたのだが……」
霜村は歩みを止め、整髪料で固められたオールバックの側面を、両手で神経質になで上げた。その表情は、両腕で隠れてはいたが、声色に、仕草に、苛立ちが滲んでいる。
「昨日より本件は広域重要指定事件となった。以降は、ここに捜査本部を設け、係の垣根を越え情報共有を密にして、本件の捜査にあたって欲しい。何か質問のあるもの」
そういうと、霜村は両手についた整髪料をハンカチで忌々しげにぬぐい、刑事達に向きあった。
彼が事件の広域指定に納得していないことは、くしゃくしゃに丸められたハンカチが雄弁に語っている。
監視官の任期は10年。
その10年間自らのサイコパスを悪化させることなく職務を全うできた監視官だけが、省庁管理職という出世への階段を登ることができるのだ。
今年任期満了を控えた霜村は、橋田良二殺害事件解決を手土産にその階段を駆け上がろうと考えていた。しかし事件が広域重要指定となれば、解決したところで自分の手柄とは見なされない可能性もある。
霜村にとって今の状態は、目の前にぶら下がっている褒美を、むざむざと後方の衆人にばらまくようなものだ。
腹立たしさから彼の額に血管が浮かび上がる。
「あのー……」
まだ顔立ちに幼さを残す三係の女性執行官が、遠慮がちに手を挙げた。
「なんだ」
「この、女の子の方は……」
「今朝、千代田区外神田で発見された第二の被害者だ。犯行の手口からして、同一犯によるものと考えられる」
「なんで同一犯だと……?」
「資料に目を通していないのか?」
「だってぇ~、今日本当は非番だったんですもーん……」
職業意識のかけらもない返答に、執行官数人がクスクスと笑い声をたてる。
その様子を見ながら狡噛は、どこの係も執行官の扱いには手を焼いているようだ、と妙に安堵する。
しかし当然、執行官達の振る舞いが霜村の心中を和ませるはずがない。霜村は浮き上がる血管を頭蓋骨に押し戻すかのように、拳を額に強く押しつけた。
刑事課といえどもその構成員の三分の二が執行官――すなわち潜在犯なのである。
ならば、広域重要指定で捜査員を増員したところで果たしてそれが事件解決にどの程度有益だと言うのか、むしろいらぬ混乱を招くことになるのではないか、そうなったら自分の出世の花道はどうなる、霜村の明敏な頭脳が瞬く間に最悪のシナリオを作り上げる。
霜村は自分で描いたバッドエンディングに軽い目眩を覚えながら、不埒な執行官達を睨みつけた。
「唐之杜分析官、説明を」
自分を奮い立たせるように、再び堅く固められたオールバックを力強くなで上げて指示を出す。
「はぁーい」
分析官、唐之杜志恩が気怠げに返事をし、立ち上がった。
唐之杜は深紅のツーピースに身を包み、その上から無造作に白衣を羽織っている。
胸元は双房が今にもこぼれ出んばかりに開かれ、緩くウェーブのかかった金髪が二つのふくらみの上で軽やかに踊り、形の良い唇はその優美さをルージュによってさらに強調され、甘い影を湛えた瞳は見るものの劣情を煽り立てる。
『情報分析の女神(ミューズ)』とは彼女の自称だが、今のところそれに反論するものは刑事課にいない。
「この二つの事件、死体の展示方法もものすごく魅力的なんだけど……」
魅力的、と言う非常識な物言いに、霜村がたしなめるように咳払いする。
「あらごめんなさい? でも、死体にこーんなおいたしちゃうなんて、私が通ってた医科のバカどもにもいなかったから、興奮しちゃって」
にっこりと微笑みながら真っ赤な唇を舌先でぺろりとなめる。死体を見上げるその表情が「興奮した」という言葉が冗談でないことを物語っている。
彼女もまた、潜在犯なのだ。
霜村の血管がさらに浮きあがる。
「いいから続けろ」
「はいはい。分析官的に言わせてもらえば、この事件はね、二つの大きな特徴を有しているの。一つはごらんの通り、死体の展示方法ね。死体をまるで工芸品みたいに細工して飾り付けるなんて、一世紀も前に廃れた劇場型犯罪みたい。なかなかクラシカルよね」
そう言うと熱っぽく吐息を漏らしてから、今度は人差し指を唇の前で突き立てる。
「でも」
唇と同じ色に塗り上げられたツメが、あつらえのアクセサリーのように輝いている。
「それだけじゃ同一犯の犯行って考えるには心許ないでしょ? 重要なのはね、この細工を可能にしているプラスティネーション薬剤」
唐之杜は刑事達の目の前にいくつかの画像データを展開させていく。会議室に、白く血色を失った遺体がピンク色の薬液に身を沈めている様子や、薄いガーゼを身にまとい業務用冷蔵庫を横置きにしたような箱に収められている様子が浮かびあがる。
「プラスティネーションって言うのはわかるわよね。死体に樹脂を浸透させて固定化……つまり腐ったりしないようにして標本にしちゃう技術なんだけど……」
刑事達は唐之杜の言葉の示すとおり画像を目で追っていく。
「通常プラスティネーションって、何日もかけて人体にホルマリン溶液を浸して、さらに数日かけて脂肪と水分を抜いてアセトンにつけ込んで~、とかなんとかクソめんどくさい下処理してから、液体合成樹脂で固定化しなきゃいけないわけ。専門家が凄ーく頑張ったとしても、完成までに一ヶ月はかかる。それなのに……霜村監視官? 橋田議員が消息を絶ったのはいつだったかしら」
「十一月一日金曜日午後十時。赤坂近郊の廃棄区画での目撃情報を最後に、消息がつかめなくなっている」
「つまり、彼が殺害されたのは十一月一日午後十時以降よね? この有様で発見されたのは?」
「十一月五日、火曜日午前八時だ」
「すごくない?」
唐之杜はまるで自分の手柄を誇るように両掌を天に向け、興奮気味に刑事達に訴える。
「その間たった八二時間よ?!」
普段はアンニュイに伏されがちの瞳を、これでもかと見開いて言葉を続ける。
「普通なら一ヶ月……七二〇時間以上かかるプラスティネーション加工を、八二時間、ううん、殺して、頭蓋骨切ったり皮はいだりする時間を考えたらもっと短い時間で、プラスチックにされちゃってるのよ彼らは! おそらくこの加工に使われているのは従来のプラスティネーション薬剤じゃない、まったく新しい魔法の薬よ」
そういってから唐之杜は自分の興奮を治めるように一度大きく息を吐いた。「魔法」という情報分析の女神らしからぬ言葉に刑事達はざわつき、顔を見合わせる。
「組成はまだ分析中なんだけど、たぶん体組織に触れた瞬間に化学反応を起こして合成樹脂化するような薬剤……。どうやったらそんなものが作れるのか、残念ながらまだ検討も付かないんだけど……まあそんな薬が使われているの、この事件には」
遺体を工芸的に加工・装飾し衆目に晒す犯行手口、そして人類史上誰も作り上げなかった(もしかしたら考えもしなかった)人体を即座に樹脂化する特殊な薬物、この二つの特異点を結ぶのは、「同一犯」という存在。
唐之杜の説明に一応満足そうなそぶりを見せてから、霜村は事件の概要を語る。
橋田が、かねてより廃棄区画の住人たちについてしかるべき人道的処置を求め、廃棄区画解体運動を牽引していたこと。その運動の一環として一人で都内各地の廃棄区画に出向いては視察を行い、求められれば住民達に施しを与えていたこと。人権派議員として一定の評価を得ながら、その裏では一部の利権屋達から賄賂を受け取っているのではと取りざたされていたこと。たった一人の廃棄区画視察は、賄賂受け取りの隠れ蓑であった可能性もあるということ。現場周辺のサイコパススキャナーに、それらしい犯罪係数保持者の形跡がなかったこと。
霜村のよどみない説明を追うように、刑事達はホロデバイスからデータを引き出し、目の前に展開させてゆく。
橋田の略歴、遺体発見場所である料亭イヤサカの周辺地図、最後に目撃された廃棄区画内の居酒屋、断片的な情報はどれも橋田の死に様に関連づけるにはあまりにも脆弱だ。情報が少なすぎる。
当然だ。橋田が最後に訪れたとされる廃棄区画は、監視カメラや街頭サイコパススキャナーなどの設置が不十分であり、彼の足取りをたどるための情報が一切残っていないのだから。
「廃棄区画になんて関わるから……」
誰かが忌々しげにつぶやく。
シビュラにその存在を黙殺されている廃棄区画は、蛇の住み着いた藪。近寄りさえしなければ何の危険もないというのに、橋田はわざわざその藪に出向いていって、自ら蛇に飲まれてしまったのだ。
つるりと頭をそり上げた強面の監視官が不服そうに声を上げる。
「料亭の防犯システムはどうなってたんすか」
「残念ながら、何者かによりハッキングされ、推定犯行時間には停止している」
そこここでため息がこぼれる。
霜村率いる二係が捜査に行き詰まったのも無理はない。そんな哀れみの表情を浮かべるものもいる。
霜村が第二の被害者の資料に視線を落とし始めるころには、会議室には、打つ手無しといった気怠い空気が漂い始めていた。
狡噛は周囲を見回す。刑事達の気概をそがれた表情に違和感を感じる。
確かに、今日までシビュラシステムに依存して犯罪捜査にあたってきた刑事達は、シビュラの庇護する世界からするりと抜け出したような犯罪について、そう多くの対処法を持たない。しかしだからといって捜査への熱意までも投げ出すならば、人間の刑事など何の存在意義もない。
いかにシビュラシステムが頑強であろうと、それからこぼれ落ちるものは必ずある。だからこそ、いまだに人間の刑事なんてものが存在するのだ。
今こそ刑事としての真価が問われている。
狡噛は再び、背景をボンヤリと透過させながら浮かぶ二つの死体を見上げ、犯人に思いを馳せる。
何度見ても、異様だ。
無慈悲に切り取られ変形させられた、「形」としての異様さは勿論ある。しかしそれ以上に、固定化された組織という存在の有り様に、狡噛は奇異なものを感じていた。
人間に関わらずおおよそ生命というものは、生命活動を終えた瞬間から時間経過とともにその組成を変化させてゆくものだ。
とうとうと流れていた血液はその動きを止め重力の命ずるままに沈殿し、唇はひび割れ、眼球はそれを満たしていた水分を奪われ小さくしぼむ。体内細菌は制御を失い内臓を食い荒らし、身体を形作っていた細胞は一つ一つゆっくりと崩壊し、肉が崩れ落ちていく。
死後の身体の変化は、老いと同じように避けられない自然の営みなのだ。
しかし彼らは違う。その組織がこれ以上に形を変えることはない。
半永久的にその形をとどめることを余儀なくされた彼らは、もはや自然の営みの外側にいる。
犯人は、彼らを自然の営みの外へ連れ去ってしまったのだ。
脳裏に唐之杜の「魔法」という言葉がちらついて、狡噛は頭を振った。
魔法などではない。
犯人にこんな事を成し遂げさせたのは、魔法の力なんかではなく、悪意だ。
この犯罪の裏にいるのは魔法使いではなく、悪意をもてあましたただの人間だ。
それならば。人間である自分が、到達できない存在では無い。
狡噛は自分の中に滾るものを感じていた。
霜村は自分へ向けられる憐憫の中に、何か別の硬質な熱量の存在を感じ視線を走らせた。
狡噛がこちらを見ている。
その鋭い眼光に当てられて、霜村のほの暗い部分がうずく。
かつて「公安局始まって以来の優秀な成績で刑事課に配属されたキャリア候補生」とは霜村のための称号だった。しかし狡噛の登場により、霜村の雷名は影を潜め、今では彼がそんな称号の持ち主だったことを覚えているものがいるかどうかも怪しい。
もし狡噛が、本件の事件解決に大きく貢献するようなことになれば、自分の評価はさらに低くなるだろう。狡噛の鋭い視線が、自分ののど元を狙う矢のように思えて、霜村の胸がざわつく。
「なにか? 狡噛監視官」
敵に相対するときは必ず先手をうつ、それが霜村の勝負哲学である。
「いえ。二人目の被害者について、説明されるかと思いまして」
霜村の急な質問にも、特に慌てる様子もなく答えるので、それが余計に癪に障る。
狡噛の言い様は、まるで自分ののろまを糾弾しているかのようだ。
動揺を悟られぬよう、親指で額の血管をぐりぐりと押しながら狡噛から視線を外す。
先手を打つ、それが常勝のための法則だ。
なにか、なにか、なにか。なにか狡噛の動きを封じる一手が無いものか。必死で資料に視線を注いでいると、ある一言が霜村の目に飛び込んできた。
いいことを思いついた。
彼に一つ難問を与えよう。彼の心が枝葉でとらわれて、その幹に到達できぬように。
途端に霜村の胸のざわつきは収まり、思わず笑みまで浮かぶ。
「そのことだか、狡噛監視官。一つ、君たち一係に調査して欲しいことがある」
さっきまでとは打って変わった穏やかな声色で語りかける。
「彼女、今朝、設営途中のアイドルコンサートのステージ上で発見されたんだが、方々手を尽くして調査しているにも関わらず、未だに身元がわからないんだ」
霜村の言葉に、会議室がざわつく。
「身元がわからないなんて……、今時そんなことあるんですか?」
狡噛の困惑顔が心地よい。霜村は悠々と言葉を紡ぐ。
「あるとも。かなり特殊な事例だが」
現在日本人は出生届の提出と同時に、シビュラシステムにDNAとサイコパスを登録することが義務づけられている。つまり、通常であれば遺体が発見された瞬間に、現住所から家族構成、学歴職歴病歴まで、故人に関するありとあらゆるデータが照合可能なのだ。
しかしそれができないと言うことは、彼女がある特殊な境遇の持ち主だったことを示している。
「無戸籍者……ですか」
狡噛の言葉に、周りの刑事が身を引いて驚く。
「その通り。恐らく彼女は、何らかの理由で戸籍にもシビュラシステムにも登録されること無く今日まで生きてきた無戸籍者だ」
この時代、シビュラに登録されていない人間が、監視カメラや街頭スキャナーひしめく一般社会で暮らしていくのは不可能だ。無戸籍者とはつまり、廃棄区画生まれ廃棄区画育ちの人間を意味している。
廃棄区画で姿を消した男に、廃棄区画で育った少女。事件解決の糸口が、手にする前にほろほろとほつれて霧散していくようだ。
会議室に漂っていた倦怠感が、さらに濃厚になる。
「賄賂疑惑議員の肛門に海馬をねじ込んだ次は、社会から隠された無戸籍者の少女をアイドルステージに祭り上げる……か。 やっこさん、随分しゃれたことするなぁ」
征陸だけが楽しげに歓声を上げた。
征陸の場違いな歓声に一瞥くれると、霜村は狡噛への追撃を続ける。
「だからね、狡噛監視官。君たち一係にはまず、彼女の身元特定をお願いしたい」
3
「面倒を押しつけられたな」
会議終了後のざわつきの中で、監視官宜野座伸元が狡噛に声をかけた。
狡噛の隣に座ると、縁なしのスクエアメガネを押し上げる。
「無戸籍者の身元の特定なんて、くだらない言葉遊びみたいなものだ。特定すべき身元がないんだから」
ため息で宜野座の前髪が揺れる。
宜野座は狡噛と同期の監視官で、何度か行われた刑事課編成ののち、狡噛が一係に配属されてからはずっと共に役職に当たっている。
「どうするつもりだ」
眼鏡の奥に不安が滲む。
「とりあえず、聞き込みだろ。不幸中の幸いで被害者少女の顔は無傷だ。彼女の写真を手がかりに目撃情報を集めれば……」
「聞き込みか……」
忌々しげに頭を抱える。
「まるで旧体制の刑事だ」
そう言うとさも面白くないといったふうにほおづえをついた。
宜野座は優秀だが、杓子定規なところがあり、システムから逸脱した行動を嫌う。無戸籍者は、そもそもがシビュラシステムから逸脱した存在である。その身元特定など、彼にとってもっとも疎ましい仕事だ。
「大丈夫だろ。うちにはとっつぁんがいるんだから」
狡噛の言葉に、さらに顔をしかめる。
システムの神託より刑事の勘を信じる征陸と、システム信望者の宜野座はすこぶる相性が悪い。
「あいつが喜々として聞き込みしてる姿が目に浮かぶよ」
眼鏡を持ち上げて目頭を押さえる。今時眼鏡などかけている人間は珍しいのだが、宜野座は頑なにそのスタイルを変えない。
これも彼の遵守すべき「システム」の一つなのだろう。
眼鏡を定位置に戻して続ける。
「しょうがない……。人海戦術ができるほど人手いないが、しばらくは廃棄区画をしらみつぶしだな……」
「廃棄区画……。やはり扇島か」
「まあ、そうなるだろ。都内にも廃棄区画はいくつかあるが、人が一人ある程度の年齢までシビュラに触れずに生活できる規模ってなると、あそこしかない」
狡噛の脳裏に、昨晩足を踏み入れた扇島の光景が浮かぶ。
あれだけの広さと深さを持った廃棄区画をしらみつぶしとは、宜野座が頭を抱えるものよくわかる。
「狡噛お前、征陸と佐々山を使え。俺は六合塚と内藤を使う」
宜野座は、見事に自分の御しがたい駒をより分けて、狡噛に押しつけた。
想像はしていたが、その露骨さに苦笑が隠せない。
「なに笑ってるんだお前」
「いや」
片手で口角を押さえる狡噛の様子に、訝しげに眼鏡を押し上げながら、持論の展開を続ける。
「結局、被害者の身元特定なんていって、霜村監視官は俺達を事件捜査から遠ざけたいんだよ。体のいい締め出しだ。ま、せいぜい二係の足を引っ張らないように事に当たろう」
宜野座はそう自分自身に言い聞かせるようにつぶやくと、同意を求めて狡噛に視線を送った。狡噛はその視線を受け流して、資料に目を落とす。
無機物に成りはて吊される少女の表情は、不思議と穏やかな笑みを湛えている。
「言うほど悪い状況じゃないさ、ギノ。犯人はあえて無戸籍者を狙ったんだ。ここから重要な手がかりを見つけられる可能性は高い」
「……おまえ、楽しそうだな」
宜野座の唐突な指摘に狡噛の思考がハタと立ち止まる。楽しそう? そうだろうか。
「あまり、執行官達に毒されるなよ。ただでさえお前は奴らと距離を詰めすぎる。情報共有もけっこうだが。不可侵領域に踏み込むな。監視官の領分を忘れて、猟犬に成り下がるな」
確かに、一筋縄ではいかない事件との遭遇に、狡噛の中で何かが沸き立っている。その何かを形容するならば、狩り場に放たれる前の、猟犬のような高揚感と言ってさしつかえないだろう。
「無闇なことをするなよ。霜村監視官のやり方に異儀がない訳じゃないが、あの人は幹部候補生だ、わざわざ不興を買う必要もないだろう」
そう釘を刺すと、宜野座は会議室をあとにした。
宜野座の細くまっすぐな背中を見ながら、狡噛は「猟犬になり下がるな」という彼の言葉を反芻した。
4
公安局ビル内、執行官隔離区画――執行官宿舎一〇三。
打ちっ放しの床に無造作に置かれたソファー。
その上に仰向けになって、佐々山はクルクルと回るシーリングファンを眺め続けていた。
どのくらいの時間こうしているだろう。
窓のないこの部屋では、時間の流れは酷く曖昧だ。
ソファー横のローテーブルの天板を、電気スタンドが照らしているが、その光量は部屋全体を明るくするには頼りない。
部屋の四隅から、闇がじっと気配をうかがっている。
佐々山は電気スタンドの照り返しで微かに浮かぶシーリングファンの羽のうち一つを、意味もなく目で追う。
一回転……二回転……三回転……。すぐにどうでも良くなって、また漫然と見つづける。
変な装置だ。天井からぶら下がってその羽を回転させているが、真下にいる自分は微風すら感じない。執行官の宿舎に、装飾的な意匠を凝らすはずもない。ただそこにぶら下がって回転するだけの装置。
案外こうやって仕事もせずに寝腐れてる俺みたいなヤツを、バカにするために回っているのかもな、と佐々山は自嘲した。
ローテーブルには、幾枚もの写真が広げられている。データではなく、いまどき珍しい紙に印刷された本物の写真である。
佐々山はその身をソファーに横たえたまま、一枚の写真に手を伸ばした。
指先でつまみ上げ、鼻頭まで持ってきて見つめる。
その写真の中で、一人の少女が笑っていた。
佐々山の指から力が抜け少女の写真がハラリと落ちる。しかし、佐々山はそれを目で追うばかりで、拾おうとはしない。
写真はしばらく宙を舞うと、床の上をすっと滑って佐々山の視界から消えていった。
再び回転するファンに目を戻し、佐々山は思う。
はやく、この写真達を処分しなくては。
急かされるようにして重い身体を無理矢理起こすと、頭に激痛が走る。
飲み過ぎた。
足下に数本の空瓶が転がっている。
昨晩任務を終え自室に帰ってきてからというもの、佐々山は自分に課したこの作業を全うすべくずっと写真の山を目の前にしていたが、進むのは酒ばかりだ。
「作業」なんて大仰に言ってみても、ようはこの写真達をダストシューターに放り込むだけなのだが、それが、何故か、できない。
タバコに手を伸ばすと、それはすでに空で、灰皿に積み上げられたシケモクはどれも綺麗に根本まで吸われている。
何もかもが八方ふさがりに思える。
再びソファーに身を投げ出そうとしたその時、インターホンが鳴った。
舌打ちをしながら写真をかき集め、ソファーの隙間に押しこんだところで、狡噛が現れた。
「佐々山、いるんだろ」
部屋の入り口に立つ狡噛の表情は廊下の照明による逆光ではっきりとは見えないが、彼が怒っているだろうことは簡単に想像が付いた。
「何故捜査会議に来なかった」
「体調不良だって、とっつぁんから聞かなかったか?」
「体調不良の人間が、ベッドにも入らず酒かっくらってるわけか」
「酒が一番効くんだよ。ほれ」
そういって琥珀色の液体がほんの少し入った小瓶を、狡噛に放り投げる。狡噛はそれを片手で受け取ると、そのままキッチンシンクにおいた。
酒の誘惑は狡噛には効かないようだ。自分の安直な作戦が見事に失敗に終わって、佐々山は苦笑しながら溜息をついた。
「情報共有が捜査にどれほど重要か、わかっていないわけではないだろう」
無断で会議を辞した佐々山を、狡噛は正当に責める。その正当さが、佐々山の反抗心に油を注ぐ。
佐々山はわざと大儀そうに狡噛に言った。
「被害者は無戸籍者。俺達一係はしばらく廃棄区画で身元特定だろ? ちがうか?」
自分の言葉に、狡噛が身をたじろがせるのがわかる。
「おまえ、何故それを……」
「第二の被害者発見って知らせがあった時点で、身元不明だったろ。今の時代初手で身元がわからなきゃ大体そういうことだ。ついでに――」
ゆっくりと立ち上がる。頭が痛い。アルコール臭い胃液がせり上がってくる。
キッチンシンクに向かい蛇口から直接水を飲む。傍らで、狡噛が黙ってこっちを見ている。
「ついでに、霜村監視官殿は自分の手柄にご執心。成果の上がらなさそうな無戸籍者の身元特定は、俺達一係におはちが回ってきた。まあそんなところだろ。んなわかりきったこと、わざわざ会議に出張って情報共有でもねえだろ」
この男は――。キッチンシンクに顔を埋め、後頭部に流水を当てている佐々山を見ながら、狡噛は思った。
この男は、犯罪捜査における直感力・理解力は自分よりずっと優れている。
自分や宜野座が(またおそらく多くの監視官が)、与えられた情報を一つ一つ吟味し演繹を積み重ねて結論を得るのに対し、佐々山は直感的に必要な情報だけを拾い上げその断片からあっという間に青写真を作り上げてしまう。
これを征陸は「刑事の勘」と言い、宜野座は「猟犬の嗅覚」と言うだろう。
いずれにしても、犯罪者に近い思考を持つ潜在犯だからこそ持ちうる「犯罪に関わる才能」だ。
うらやましくない、と言えば嘘になる。しかしその才能を手に入れることは同時に、潜在犯落ちを意味する。精神の健常を保つためには、どこかで一線を引かねばならない。それが宜野座の言う「絶対不可侵領域」であり、執行官の存在意義なのだ。
「なに見てんだよ」
水滴をしたたらせながら佐々山が聞く。
「あ、いや……。明日から早速聞き込みを始めるから、ブリーフィングを」
「ブリーフィング? いいよそんなもん。聞いてまわりゃあいいんだろ?」
「そうはいうが」
「なんだよ。俺が言うことを聞くか不安か?」
そう言うとびしょ濡れの頭を振りながら、佐々山はソファにボスッと身を沈める。
「そんなことは……」
狡噛も佐々山のあとを追うように、部屋の中心部に歩みを進めたが、なんとなくソファに腰掛けるのは気が引けてそのまま立っていた。
「大丈夫だよ。お前の言うとおりに動く」
「んなこといって、お前俺のいうとおりに動いたこと無いじゃないか」
「そおかあ?」
ははっと笑うと、再び酒瓶に手を伸ばし、琥珀色の液体を直接口に流し込む。苦々しく顔をゆがめ口元をぬぐう様子を見ると、その液体が旨そうだとはとうてい思えない。
ストレスケア薬剤があふれかえるこの時代に、あえて酒を飲む人間の気持ちが狡噛にはわからない。もっと簡単に、手早く、安全に、心を安らげる方法があるのに、わざわざ頭痛や吐き気を誘発し、時には記憶まで失わせる酒を飲むのか。
いつか読んだ何かに、人は忘れたいことがあるときに酒を飲むのだ、と書いてあった。
佐々山は何かを忘れたいのだろうか。実際、目の前の佐々山は、昨晩の職務規程違反のことや、今日の会議欠席のことなどすっかり忘れているようだ。
酔いが回ったのか、深くうなだれて寝言のようにつぶやく。
「大丈夫だよ……」
「なにが大丈夫だ。お前昨日も」
佐々山は、狡噛の言葉をさえぎって、またつぶやく。
「大丈夫なんだよ狡噛。そんときゃお前、俺を撃て」
「だからそうならないように」
「撃つんだよ狡噛」
佐々山のうなだれてあらわになった後頭部を見下ろしながら、狡噛は困惑していた。
やはり妙だ。昨日から佐々山らしからぬ行動が続く。佐々山はいい加減なヤツだが、自暴自棄な人間ではない。しかし今の佐々山は全てを投げ出してリングに沈む、敗戦ボクサーのようだ。
こんな時どんな言葉をかけていいのかわからない。
狡噛の視線が何かを探すように床を彷徨う。もちろん、佐々山にかけるべき言葉が落ちているわけではないのだが。
言葉の代わりに、ソファの足下に落ちている紙のようなものが目に入った。
目をこらしてみると、どうやらそれは写真だということが分かる。
そういえば昨日も佐々山は写真の話をしていた、と狡噛は思い返して首をひねる。それまで佐々山がカメラを持っているところもファインダーを覗いているところも見たことがないからだ。
違和感に、思わず落ちている写真を拾い上げ、問う。
「佐々山お前、この写真……」
その瞬間、佐々山は顔を上げ、素早く手を伸ばすと写真をつかみ取った。
表情は激情に色を変え、瞳は凍え鋭く光っている。
「出て行ってくれ」
写真を握りつぶしながら声を漏らす。言葉尻は懇願の体をなしていたが、それは、明らかに命令だった。
「早く」
狡噛の背後で自動扉がしまり、廊下に施錠音が響く。
先ほどまでいた佐々山の部屋とは打って変わって明るい照明に、眼球の奥が痛む。
扉にもたれかかって軽く目を閉じ、深く嘆息した。
写真を奪い返したときの佐々山の顔が目に焼き付いて離れない。
空腹に殺気立つ野生動物のような、相対するものを脅かす表情。
また一つ、自分と佐々山の間に溝ができてしまった。その実感が、狡噛にさらに深い溜息をもたらす。
それにしても、あの写真のどこに、佐々山を激情させるものがあったのだろう。
風になびく細い髪を片手で押さえながら、眉をハの字に持ち上げ照れくさそうに笑う少女の写真。
少し下がり気味の目尻が、佐々山のそれに似ていた。
つづく