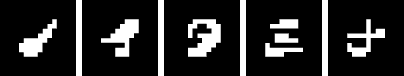NOITAMINA
OFFICAIL WEBSITE
SHARE
ツイート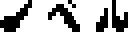 NOVEL
NOVEL
ノイタミナノベル「つり球」 第1話

まるで海の底にいるみたいだ。
といっても海の底なんて行ったことないから知らない。ただあれに似てる。プールに潜った時、外の音がすっと消えて、耳がきゅっとつまるあの感じ。このままずっとここにいたらどうなるだろう。そう思うといつも怖くなった。
「どうも、お世話になりました」
真田ユキは教壇の前に立ち、静まり返った空気の中に言葉を投げた。といっても実際は水の中で喋るみたいに、ボコっと小さな泡になってすぐに消えただけなんだろう。
生徒たちは誰も反応せず、石ころでも見るようにユキを見ている。
「どうせ」と、ユキは海の底で思う。
たった三か月の転校生なんて、どうせすぐに忘れられてしまう。そう思ってはいても、この儀式だけは避けて通れない。そう、これはただの儀式なんだ。一人の目立たない生徒が、学校から学校へと移る時にする儀式。もう何度目だろう。慣れているはずなのに、終わりの言葉がいつも出てこない。この水の中から抜け出すための言葉。このままずっとここにいたら、息ができなくなってしまう。「お世話になりました」だけじゃなんか足りない気がする。だってそもそもお世話になんかなってないし。でも「さよなら」も違う。だってこの学校でもまた、友達も、思い出も、何一つできなかったから。さよならなんて、ぜったい違う。
みんなまだこっちを見てる。
当たり前だ。「お世話になりました」と言って、その後に「あのっ」と短い言葉を発して、そのままずっと黙っている。
ユキは視線というものが本当に心や体に突き刺さることを知っている。「そんなに見ないで!」そのクールを気取った見た目とは裏腹に心が大声で叫んでいる。
大丈夫。今なんか言うから。すぐに言ってこの教室を出て行くから。そしたらみんな俺のことなんて一生思い出すことはないんだから。
誰かが筆箱を動かす音がした。動いた筆箱が恥ずかしくなるほどこの教室は静かだ。
生徒たちはぼんやりユキを見ている。教師はじっと前を見ている。まるで遠くの海で助かりそうにない子供が溺れてるみたいに。自分にはどうすることもできないよと、でもとりあえずは見ているよ、感じているよ、と。
わかってる。わかってるんだよ。
ユキは汗ばんだ手をぎゅっと握って思う。
何か言わなきゃ。でも、何も浮かんでこない。あぁ見ないで。頼むから。
ユキの思いは願いに変わる。
すいません、もう何もないんです。今、俺は、何も言うことがないんです!
その時、ユキは全身が激しく脈打つのを感じた。そしてその顔にいつものあの嫌なこわばりを感じた。
ヤバイ。アレが来る。助けて!
あぁぁぁぁ─!
その瞬間、生徒たちの表情が変わった。
教師も驚き、ユキを見ている。
無理もない。ユキの顔はついさっきとまるで違っていた。それは「怒ってる?」と聞かれて「別に」と答えられるレベルではない。寄り過ぎた眉間の皺や、釣り上がった二つの目や、極限まで下がり切った口角が、自分以外のすべてを拒むようにピクピクと震えていた。
あーあ、またやっちゃったな。
ユキは十七年間で六度目の転出の挨拶を終え、学校を後にした。
テンパるといつもああなる。自分でも驚くほど顔が変わってしまう。一度鏡で見て驚いた。あれは俺じゃない。できの悪い般若の面だ。俺はいつまでこんな感じなんだろう。
「お世話になりました」という自分の言葉が嘘なら、みんなも嘘つきだとユキは思う。
みんな友達がいないとか言うけど実際はそうでもない。勉強してないと言ってその割にいい点を取る奴と同じ。みんな実際は「友達がいない」と話せるぐらいの友達はいる。
でも俺は違う。友達がいないどころか、そのずっとずっと手前にいる。人と話せない。目もろくに合わせられない。そんな奴に友達ができるなら、それは奇跡か魔法みたいなものだ。
ユキはズボンの左ポケットからスマホを出し、水面を撫でるような手つきで検索を繰り返す。『転出』『挨拶』。何度も検索したから答は知っている。『今までの居住地を出て他の場所に移ること』。『新たに顔を合わせた際や別れ際に行われる、礼儀として行われる定型的な言葉や動作のこと』。
そんな答を知ることに意味なんてないけど、やめられない。
右手で髪に乱暴に櫛を入れる。
この髪が赤いせいもある。いきがって染めているわけじゃない。生まれつきだ。みんなと違う色の髪で、ほとんど言葉を発せず、最後は般若になって去ってゆく。それが今の俺。きっとみんな宇宙人でも見るような目で見ていたに違いない。
こういう日に限って責め立てるように晴れている。安っぽいペンキで塗ったような青い空の下、家の前に引っ越しセンターの車が停まっていた。妙に派手な柄のツナギを着た作業員たちが淡々と荷物を運び出している。
そんな彼らに笑みを振りまきながら、ばあちゃんもちょっと大きめの段ボール箱を持って家から出て来た。
「だめだよ、そんな重いの」
「大丈夫。これで最後」
ユキはばあちゃんから段ボール箱を受け取り、トラックの荷台に積み込む。
ばあちゃんのことだから、きっと引っ越しの人たちが「いいですよ」って言ってもずっと動いていたんだろう。金髪の髪が少し乱れている。もうとっくに追い越したけど年の割に背が高い。姿勢もいい。名前はケイト。もちろん日本人じゃない。フランス生まれ。でもフランス語を話すのはほんの時々だ。
「どうだった? 挨拶は」
ばあちゃんはどんな時も変わらない笑顔で俺に話しかける。俺が世界でただ一人まともに話せる相手。ばあちゃんと話してる時は悲しいことは思い出したくない。時々変な顔に変身しちゃうなんて絶対に知られたくない。
「うん。まぁ、それなりに」
もっとうまく答えられればいいのに。転校を重ねるたびに、なぜかどんどん不自然になってゆく。
「そう」ばあちゃんはそんな俺から何も感じなかったようにいつもの笑顔で答えた。
走り去る引っ越しの車を見送ると、ユキはケイトの赤いスポーツカーの助手席に乗り込んだ。
「さぁ、行くわよ、ユキ」ばあちゃんはお気に入りの黒いティアドロップ型のサングラスをかけてそう言った。まるで冒険映画の主人公みたいに。
「ばあちゃん、次はどんなとこ?」
するとばあちゃんはフランス語と日本語を
混ぜてこう言った。
「C'est un bel endroit.【素敵なところよ。】 きっといいことがあるわ」
「うん」とユキは答える。
ユキはフランス語が話せないが、その響きは好きだ。それは優しい歌のように、なめらかに流れてすっと耳に入って来る。
でも悲しいのは俺がまだ「素敵なところ」を知らないことだ。そんな場所が本当にこの世界のどこかにあるなんて、とてもじゃないが信じられない。
ユキとケイトを乗せた車は新しい場所を目指して走った。
転出したばかりの学校の前を通った時、ユキはスマホを見るフリをして、楽しげに話す生徒たちから目をそらした。
ケイトはそういう時、必ずユキを見るが、ユキは気づかない。目を伏せているからだけじゃない。いつもケイトが何も言わずに前を見るからだ。
夜はサービスエリアの駐車場で一泊した。
車の中で眠ったことは何度かある。いつもばあちゃんがトランクから毛布を出して、俺がコーヒーを買いに行く。
夜は嫌いじゃない。昼間のことが思い出せなくなるから。
ユキは眠るケイトの毛布を掛け直しながらそう思う。
すぐに眠れたらいいな。眠れないとまた余計なことを考えてしまう。あの星が本当は宇宙のゴミで、必ず朝が来て全部きれいに掃除してしまうこととか。朝になれば新しい制服に着替えて、また儀式に出なきゃいけないこととか。それが現実なら、こうしてばあちゃんの隣で毛布にくるまっている今はなんだろう。ここは海の底じゃない。ここは、ちゃんとここだ。ずっとここにいたい。いられないことはわかっていても、夜が昨日より少しでも長ければいいなと思う。
やっぱりだ。朝が来てユキは思う。
やっぱり空はまた晴れていて、ばあちゃんが言う『素敵なところ』を素敵に演出している。俺がこんな俺じゃなくて、些細なことに喜び、いつも笑っている明るい子ならよかったのに。そしたらばあちゃんももっと嬉しかったろうに。また頭の中がぐるっと色んな思いでいっぱいになった時、「ほら」というばあちゃんの声がした。突然視界が開けてそのまぶしさに目を細めた。
海だ。
海があるのか、次の場所には。
やがて車は弁天橋と呼ばれる橋にさしかかり、ユキの目の前に小さな島が迫ってきた。
ほんとうに島なんだ。
『江の島』。『神奈川県藤沢市にある湘南海岸から相模湾へと突き出た島』『人口は409人』。きっと少ないんだろう。
島は深い緑に覆われていて、後から慌てて突き刺したようにタワーが建っている。
離れてぽつんと建つ灯台が自分みたいだとユキは思った。
島の上空にはトビたちが小さな飛行機みたいにすーっと優雅に浮かんでいる。
見上げた先の雲はさっきと違う形に変わっていた。アナログ時計と同じで、いつも変わる瞬間を見逃してしまう。
ユキは突然開けた広い世界の下で、遠い記憶の中にふっと迷い込んでいた。
いつか海で溺れそうになるのを、お父さんが笑って見てた。どうして笑うんだろう。その時はそう思ったけど、今ならわかる。きっと俺が溺れそうになってるなんて思わずに、ただはしゃいでるように見えたんだろう。なぜか今でもあの笑顔だけははっきり覚えている。それがいい記憶なのかどうかはもう遠すぎてわからない。
そこまで思い出すと、ユキは自分から目をそらした。
やめよう。この辺はやっぱりちくちくする。
胸や心じゃない。もっと奥の方だ。
と、その時、ユキは、空に浮かぶトビたちのもっと向こう、お餅をちぎって投げつけたような雲のもっと向こうに、小さな光を見た気がした。
UFO? ばあちゃんに言おうと思ったけど、光はすぐに太陽のビームに吸い込まれた。
気のせいか。
そう思ったら現実が忘れ物を取りに戻って来た気がして、ユキは憂鬱な気分になった。
ぽちゃんっ。
その水槽は仲見世通りを入ってすぐの土産屋の外にある。
その水の中に何かが飛び込んだ瞬間、気づく者はいなかった。その音はとても小さかったし、この時間、観光客どころか店を開けている者もいない。違和感を感じたとすれば水槽の中を泳いでいた他の魚たちだけだろう。
まだ泡立つ水の中で、飛び込んだばかりの二匹の魚は泳ぎ始めた。ひとつが金色で、もうひとつが赤色。そのうろこが朝陽をはね返してちらちらと光っている。
赤い魚はニコっと微笑み、言った。
「さてと、にいちゃん、どうしよっか」
「う─ん」
落ち着きなく泳ぐ金色の魚はそう言って答を保留し、新しい水での泳ぎを楽しむ。
悠然と泳ぐ赤い魚は、くるくる回転したり、時々水面から顔を出したりする金色の魚を、いつものことのように眺めて言った。
「ちょっとね、寂しそうなのがいいと思うよ」
ユキとケイトを乗せた車がたどり着いたのは、さきほど車から見えた、島に突き刺さるタワーの近くの家だ。
ユキはスマホの検索でそのタワーが『シーキャンドル』という名前だと知った。海のろうそく。正直ろうそくには見えないけど、その形は嫌いじゃない。エレベーターで昇った展望台から湘南を一望できるらしい。
ユキとケイトの新しい住まいは、洋風の古くて趣がある二階建ての家で、立派すぎる門構えはまるでどこかの国の大使館みたいだ。
もちろん行ったことなんてないけど。
「ここ?」
「そう。いいでしょ」ケイトは車を降りながらそう答え、まぶしげに家を見上げた。
「それで、あそこが私が働くところ」
ケイトは自分のことを『私』と言う。ユキと二人きりの時も決して『ばあちゃん』なんて言わない。そのたびにユキはばあちゃんは女の人なんだと思う。ばあちゃんだからって立ち入ってはいけない場所があるように感じて、時々もやっとした気持ちになる。
ケイトが「あそこ」と言ったのは、家から少し離れたところに広がる庭園のことだ。
「サムエル・コッキング苑、だっけ」
「そう」
『江の島の名所の一つ』『1882年に貿易商のイギリス人サムエル・コッキングが建てた大庭園』。
ばあちゃんは花や植物の管理をするのが仕事で、そのためにいろんな町を転々としているのだ。
「近くてよかったね」
「そうね」
わざわざそう言ったのには意味がある。微笑むばあちゃんの顔を見るとつい忘れてしまうけど、ばあちゃんは肺の病気で何度も入院している。ふだんはあんまり考えないようにしてるけど、もしばあちゃんがいなくなったらと想像する時もある。そんな時、大体は夜、布団に入ってからだけど、俺は考えすぎの自分の脳みそをちょっとだけ呪う。考えたって答はない。『ばあちゃん』『肺の病気』で検索したってきっとどこにも辿りつけない。やめよう。ばあちゃんは今目の前で笑っているし、「素敵なところ」にいるのだから。
「ほんとに行くの? 明日からでもいいのよ」
「ううん。今日でも明日でも一緒だし」
ばあちゃんは着いて早々、新しい学校に行く自分を心配してくれた。でもはじめから今日行くことは決めていた。俺は悩んでなんかいない。新しい町に何も不安なんか感じてない。そうばあちゃんに思わせることだけが大事で、他のことは全部どうだっていい。
「お友達、たくさんできるといいわね」
「大丈夫。もう転校、ベテランだし」
新しい制服に着替えたユキが門を出ると、見送りに来たケイトが声をかけた。
「ユキ」その後にまた優しい歌が聴こえた。「Reste souriant et confiant.【笑顔で、胸を張って】」
「うん」
ユキは胸を張って笑ってみせた。
少し早めに家を出たのは学校までの時間が読めないからだ。実際、長い石段を下りて江島神社の前にたどり着くだけでけっこう時間がかかった。駅まではまだまだ遠い。
ユキは鳥居を背にして仲見世通りを下り始めた。
歩いている人はほとんどいない。いるのは店を開ける準備をしている人たちだけだ。
ちょっと坂になってるから仕方ないけど、歩みが速まるたびに不安になってゆくのを感じた。
道には猫が多い。みんな床にこぼしたマヨネーズみたいにだらんと寝転がっている。
仲見世通りの店はどれも造りが古く、狭そうだ。そして、やたらと目立つ『しらす』の文字。しらす丼、しらすアイス、しらすパンにしらすピザ、しらすたこ焼き、しらすドーナツ。どうやら一押しの名物らしい。ドーナツまではなんとかイメージできたが、しらすビールと言われてもどういうものかさっぱりわからない。ビールを飲んだこともないし、考えればしらすもそんなに食べた記憶はない。
ユキが検索に飽きて顔を上げると、準備前のしらす屋の店先で笑って話す商店の人々がいた。やがてユキに気づいてこっちを見た。
わ、見てる!
そりゃそうだよなとユキは思う。いきなりこんな見たことない奴が歩いてきたんだから。ユキがちょっと気にして赤い髪をいじった時、彼らが微笑みかけてきた。
わ、笑ってる!
どうしよう。ユキはたちまち焦り出す。
無視したら嫌な奴だと思われる。この道は今日から毎日通るわけだし、ここは思い切って。
「こんにちは」かすれた声でユキがそう言いかけたその時、「おはよう!」と大きな声で返された。
しまった! 朝じゃん!
そこからはもうお手上げだ。ユキは素早くうつむいて足早に通り過ぎる。高鳴る鼓動を抑えようと「どんまい」と自分に言い聞かせる。
どんまい。今日はまだ始まったばっかりだ。
ユキは恐る恐る土産屋の外に置かれた水槽に自分の顔を映した。
大丈夫。まだあの顔にはなってない。
顔に力を入れて笑ってみせる。
その時、落ち着きなく泳ぐ金色の小魚がユキを見た。
え、今、目合った? しかも、笑ってた??
金色の魚は驚きながら歩き去るユキを見送った。
「どうした、にいちゃん」
そう尋ねる赤い魚に、金色の魚はにんまりと微笑んだ。比喩でもなんでもなく、ちゃんと口角を上げて笑ったのだ。
弁天橋を渡り始めてすぐ、急いでいたはずのユキはふと立ち止まった。
風が、気持ちいい。
さっきは車の中にいたから気づかなかったんだ。目の前に広がる海も、さっき車の窓越しに見ていたのとは全然違う。太陽が海にぶつかって破片になって揺れているのがちゃんとわかる。こんな近くで海を見るのはかなり久しぶりかもしれない。
ユキは橋の途中で立ち止まり、手すりに手をかけ、線なんてまるで見えない水平線に目を細めた。
金色の髪が揺れている。白いシャツに薄いピンクのネクタイをしめた彼は、まるで地面に足をつけるのが初めてかのように、楽しげに体を揺らして歩いていた。
そのたびに肩にかついだそれも楽しげに揺れる。釣竿だ。
頭の上には、花びらみたいに口が開いた、まあるい金魚鉢が乗っている。その中に置かれた小さな水車の周りを、土産屋の水槽にいたはずの赤い魚が優雅に泳いでいる。
しかし彼がゆさゆさ歩くたびに水は揺れ、赤い魚はちょっと文句を言いたげに持ち主を見た。
でも彼はお構いなしに歩いてゆく。その顔は笑っている。まるで一年に一回の縁日へと急ぐ子供みたいに。その背中に背負った、通学には大きすぎるリュックから、まさしく縁日で売っているような透明で黄緑色の水鉄砲がぶら下がっている。
彼はシーキャンドルの前で立ち止まり、流れ星でも見つけたようにおぉーっと驚き、それを見上げた。
スカ─イ、トゥリ─!
金魚鉢の中で赤い魚がふーっと呆れてため息をつく。
金髪の彼はその間違いに気づくこともなく、ふと一方を見る。
「あ、あれいい!」
彼が駆け寄り、見上げたのはユキの新しい家だ。ニンマリ笑って金魚鉢に問いかける。
「どう?」
赤い魚は「うん、いいんじゃない」とばかりに頷いた。比喩でもなんでもなく、その首を縦に振って。
「こんにちは」
庭の方からちょっと大きめの表札を手にしたケイトが出て来た。
「こんにちは」
彼はまるで何年も前からのご近所さんのようにそう返した。
「僕、ハル」
「ハル君。素敵な名前ね」
「宇宙人」
「あら、そう」
相手との距離の近さではケイトも負けてはいない。まるで天気の話でもした時のようにごくごく自然にそう答え、玄関に刺さった釘に、表札につけた紐をするっとかけた。
ハルと名乗った金髪の少年は、ケイトのエプロンのポケットからサッとマジックを取り、表札に文字を書き足した。『真田ケイト』と『ユキ』という文字の下に、大きく『ハル』。
ケイトは、子供が砂浜に寝転がっているようなその文字を見て微笑んだ。
「僕、ここ住む」
ケイトは一瞬だけ、ほんの一瞬だけ黙って、またすぐに微笑んだ。
「じゃあ一つ約束してくれる?」
「ヤクソク?」
ハルはまるで生まれて初めてその言葉を耳にしたかのように、これ以上ない無防備な顔でケイトを見た。
そんな二人を誰かが見ていた。すぐ近くじゃない。二人の遥か頭上、シーキャンドルの展望台から、少しものものしい双眼鏡を覗き込んで。皺ひとつない黒いスーツに身を包み、頭にはクリーム色のターバンをしている。そしてその腕には、飼い慣れた猫のように純白のアヒルを抱いている。
「タピオカ」アキラは恋人と電話で話す時のような深い親しみを込めてアヒルに話しかける。
「クワっ」タピオカが答える。「ん? 何?」ちょうどそのぐらいのニュアンスで。
「あいつ、何しに来たと思う?」
「クワっ、クワっ」何を答えたのかは、きっとアキラにしかわからない。
「そうだよな。どうせただの観光だよな」
江ノ電の江ノ島駅は、お土産屋や古めかしい旅館を抜けたところに、看板の目立たないお好み焼き屋のようにひっそり佇んでいた。
ユキが切符を買い、こじんまりしたホームにたどり着いた瞬間、緑とクリーム色の可愛らしい電車が入ってきた。
よかった、間に合った。
ユキは同じ制服の群れに目を伏せ、電車に乗り込む。そして一つだけ空いた座席を見つけ、腰を下ろした。
と、その瞬間、気づいてしまった。
目の前に、ケイトと同じ年ぐらいの男の人が立っていた。
しまった! この人、ここに座りたかったのかな。
勇気を出してちょっとだけ顔を上げる。
よく見るとおじいさんって感じでもない。もし席を譲ったらかえって失礼かもしれない。でも譲らなかったら冷たい奴だって思われるかもしれない。どうしよう、どうしよう。
その時、男の人と目が合い、ユキは慌てて目をそらした。
何してんだ! 目をそらしたら無視してるってことになっちゃうだろ!
ユキは勇気を出して立ち上がった。
しかし次の瞬間、男の人はユキのこわばった顔にひるみ、立ち去ってしまった。
え、嘘?
すると向かいの座席から一人の男子生徒が立ち上がって席を譲った。
あ。
ユキはちらっとその男子生徒を見た。
子供が描いたライオンのたてがみのようなボサボサの黒髪、長細い長方形の黒縁の眼鏡。背は多分ユキよりちょっとだけ高い。
でもユキがもっとも気になったのは、彼が着ている制服だ。
同じ学校!
席を譲られた男の人は、ユキにひるんだ顔からは想像もつかない笑顔で「ありがとう」と、空いた席に腰かけた。
あぁ、なんでいつもこうなっちゃうんだろう。
ボサボサの彼はユキを一瞬だけ見て三角の吊皮をぎゅっと握った。
顔、覚えられちゃった。どうか同じクラスじゃありませんように。
ユキが心の中で祈ったその時、女子生徒たちがクスクス笑う声が聞こえた。
恐る恐る顔を上げると、窓際にかたまっていた四、五人の生徒たちがユキを見て笑いを噛み殺している。
しまった! 見られてた!?
女子の制服はどこの学校かわからない。でも男子は明らかにユキと同じ制服だ。
その生徒たちの中の、襟元が少し開いた、いかにもイケてる風の女子と目が合った。
慌てて目を伏せると、そこには短いスカートからすらりと伸びる脚があった。
目を伏せてからもその残像が消えなくて、ユキは自分の背中がマラソンのスタート地点みたいになっているのを感じた。無数の汗たちが一斉にスタートを切って走り出したのだ。
ぜんぶ見られてたんだ! どうすればいい?
ユキは顔がこわばっていくのを感じた。
まずい! このままじゃ、アレが来る!
ユキはまるで強引に金縛りから身をほどく時のように、今にも全身を覆おうとする水を押しのけ、決死の思いで一歩踏み出した。
どこでもいい。ここじゃないどこかに移動しよう。違うんだ。俺は行くべき場所があるから立ち上がったんだ! 多少遅れてはしまったけど、俺は今からその場所に行くんだ!
ユキがたどり着いたのはクスクス笑っていた彼らとは反対側の扉付近だった。
そう。俺はここに来たかったんだ。それで? ここに、この窓際に俺は何をしに来た? だめだ。ここから先は何も考えてなかった!
ユキが万事休すと顔を上げると、窓いっぱいに広がる海があった。
わ、海、でかい!
ユキは思わず漏れそうになる声をぐっとこらえた。
そう、俺は、海が見たかったんだ。
ユキはめいっぱい平静を装ったが、興奮は収まらない。
だって、海だよ。電車から海が見える!
しかしちらっと周りを見ても、みんなまるで家の時計でも見るように無表情で見ているだけ。中には一瞥もくれない人もいる。
なんで? 海なのに。
でもたった一人だけ、じっと海を見つめている人がいた。さっきのボサボサ眼鏡君だ。
やがて彼は視線に気づいてユキを見た。
ユキは慌てて海に視線を戻した。
右手に遠ざかる江の島が見える。
こんな海が近いところに学校があるなんて不思議だなとユキは思った。
その時、悲鳴を上げるような音を立てて、電車が腰越東高校前に着いた。
もう少し、見ていたかったな。
ユキはそう思った自分に驚いた。
駅のホームを抜けて、海を背にして左に伸びた急な坂を上ると腰越東高校がある。
どうしてだろう、とユキは思う。
この坂は誰が上っても同じ坂なのに、その先に楽しいことが待っている人と、自分みたいに処刑台にでも上るような気持ちの人間がいる。なんでこんなに違うんだろう。
ユキはどんどん足が重くなるのを感じて、一瞬水から顔を上げて息継ぎするみたいに後ろを振り返った。
あ。
海はまだそこにあった。踏切の向こうからユキを見送るようにキラキラと光っていた。
今度こそ、うまくやらなきゃ。
ユキはそう思った自分に驚いた。
まただ。今日はなんか、驚くことが多い。
「えー、今日は転校生が二人いるんだけど」
ドラマに出て来る会社の部長みたいな担任の教師がまだ少し騒がしい生徒たちに言った。
「ちょっと一人遅れてるのかな。じゃあ先に自己紹介しちゃおうか」
「はい」ユキは教壇の前に立つと、震え始めた手を誰にも気づかれないようにきゅっと握った。
うまくやらなきゃ。
いや、無難に、普通でいい。
ユキの中のふたつが、スキルがほぼ同レベルの格闘ゲームのキャラクターのようにずっと戦い続けている。
「どうも!」
声! 落ち着け。もっと小さめでいい。
「どうも、真田ユキです。東京から来ました」
そう。そのくらい。
「転校はもう数えきれないぐらいしてて、でも挨拶はいつも慣れなくて、なんか変な感じになったらすいません」
いいぞ。すごく落ち着いてる!
「あの、さっき」
さっき、なんだっけ? 焦るなよ。
「来る途中で海を見て」
そうだ。海の話を入れようって思ってたんだ。
「海はすごく大きくて、空も綺麗で、空気も美味しくて」
いいぞ! どうした俺!
「江ノ島は、とても素敵なところだと思いました」
いい! 完璧だ!
「それで」
そう言った瞬間、急に目の前が真っ暗になった。滑り出しがうまくいきすぎて油断したのか、思わぬ勢いがついてつい調子に乗ってしまったのか。
それで? なんで『それで』って言った?
その先何も考えてないだろ!
ユキはいつもの行き止まりに差し掛かった。
何か言わなきゃいけないが何も出て来ない。
今まで何度も苦しめられてきた行き止まり。
夕方に調子に乗って自転車で遠出して、見たこともない小道で途方に暮れるような、あの、行き止まり。
どうする? 知らないぞ。とりあえずなんか喋れ。なんでもいい。あぁどうしよう!
その時、神様が教師の姿を借りてこう言った。
「はい拍手ぅー」
それはユキにとってこれ以上ない助け舟だったが、なんのための拍手かわからない分、生徒たちの拍手の量は極端に少なかった。
いや、でもこれでいい。
ユキは『うまくやらなきゃ』という、自分に似つかわしくない希望をあっさり捨てた。
あと一問答えれば百万円でも、俺は今、その手前の五十万円を持って立ち去るのだ。
「どうも」
ユキはペコリと頭を下げて自分の席へ向かった。
しかしその先に、ユキの想像を超える展開が待っていた。窓際の後ろの方の席に着いたその時、安堵して視界をちょっと広げたその時、隣の席に見覚えのある顔がいた。
「あっ」
ユキは思わずそう口に出し、座ったばかりの席からガタン!と立ち上がってしまった。
隣に座っていたのは、電車の中でクスクス笑っていた女子だった。襟元の少し開いた、脚がスラリとした……
いや、それはいい、今は!
えり香は目の前の光景がつい数十分前の電車の中の光景とダブって思わずフフっと笑ってしまった。それは決して相手をバカにした笑いではなかったが、そう思えるほどの余裕はもちろん今のユキにはなかった。
「何事か」と一斉に見る生徒たちの中に、ユキはまたしても見つけたくない顔を見つけてしまった。
ボサボサ眼鏡君!
宇佐美夏樹はほんの一瞬ユキを見たが、すぐに興味なしといった顔で前髪をフッと吹いて前を見た。
みんなもそうしてくれればよかったのだが前を見たのは夏樹だけで、他の数十人の生徒たちは「何事か」の続きを待ったままユキを見ている。
や、やばい……
ユキはまた顔にあのこわばりを感じた。大事な儀式ではなんとか収めたアレが、今確実に俺の住所を突き止めてチャイムを押そうとしている。
お願い、見ないで。何でもないんです! 俺はただ立っただけなんです! この先行く場所なんて、どこにもないんです!
神様、とユキは思った。
今朝、電車の中でユキに海を見せてくれて、さっき教師の姿になって「拍手ぅー」と言ってくれたあの神様は今どこにいる? あと一回、あと一回だけ、助けてください!
そう思っているうちにユキは既に顔が変形しかかっているのを感じた。
もう、だめだ。今か。初日だぞ。初日から俺はあんな顔になるのか!
あぁぁぁぁぁぁぁ─!
その時、教室の扉がガラガラーっと開いた。
え、嘘?
ユキはその絶妙すぎるタイミングに、危うく本当に神を信じそうになった。
しかし入って来たのは神様にしてはあまりに頼りないヘナヘナした金髪の少年だった。
大きなリュックを背負い、片手に釣竿を持ったハルは「一体どんないいことがあったんだ」というほどの満面の笑みで現れた。
「え?」教師のその言葉を皮切りに生徒たちは一斉に囁き始めた。「だれ?」「え、釣り?」「なんで?」
「僕ハル。宇宙人!」
ハルはみんなの囁きを吹き飛ばすように、真夏の青空みたいな声で言った。
そしてその過激な一言は教室という水面にさらに大きな波紋を作った。「え、何何?」「宇宙人って言った?」「ヤバくね?」「いや、逆にすごいかも」
ユキも当然呆気にとられていたが、このピンチをチャンスに変える意識はまだかすかに残っていた。
なんかわかんないけど、今だ、座れ!
ユキがドサクサに紛れて席に着こうとしたその時、
「あ、いた! ユキ!」
え!? なんで俺の名前!
消えかけていたユキの存在が再びクローズアップされた。
いや、俺知らないから! 仲間じゃないから!
「ギュイ─ンっ!」
聞いたことのない擬音と共に、ハルが手にした釣竿を思い切り振った。糸はついていなかったが、教室にいるすべての人間は、見えない糸が弧を描いてユキへと届くのを感じた。
え、なに!?
「よっしゃヒットぉ─!」
ハルはそう叫ぶと釣竿についたリールを夢中で巻き始めた。
「よっしゃ来い来い来─い!」
ここまで来ると一切の批評は意味を持たなくなる。生徒たちはハルが起こした大波に身を任せ、ユキの反応を待った。
え、なに? 無理。無理だって!
ユキはこれ以上ないというぐらいに追いつめられながら、小学校の時のガキ大将を思い出していた。突然気まぐれに無茶な要求をしてきて、反応が悪いとキレる奴。ユキはいつだって彼を満足させる反応ができずに、時には文句を言われ、時には頭を小突かれた。
でも、とユキは夢中でリールを巻き続けるハルを見て思った。
たぶんあいつは違う。もし俺がいい反応をしなくてもキレたりはしない。そういうタイプの厄介さじゃない。
ハルはユキを見て笑っている。きっと彼の中には誰かを追いつめる意識なんて一ミリもない。ただ「楽しい! 楽しい!」と心の中で叫びながら、その手がもげんばかりにリールを巻き続けている。
そういうタイプじゃないけど、じゃあ、どういう……
ユキはそこであらゆる推測をあきらめた。自分と彼の間にある何万光年もの距離を感じて、ただ立ち尽くしていた。かすかに残る意識の中で思うことは、一つだけ。
俺、あいつ、ぜったい無理!
つづく