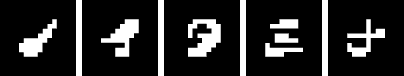NOITAMINA
OFFICAIL WEBSITE
SHARE
ツイート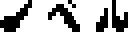 NOVEL
NOVEL
ノイタミナノベル「つり球」 第2話

【前回のあらすじ】コミュニケーションが苦手な男子高校生・真田ユキは、転校続きで友達がおらず、緊張が度を越すと顔が般若のようになってしまう。フランス人の祖母ケイトとともに新たに引っ越してきたのは江の島。転校初日から自称・宇宙人のハルに目を付けられ、なぜか釣竿を向けられる。
「よっしゃ来い来い来─い!」
弾けるような笑顔でリールを巻くハルを前に、ユキはヘビに睨まれたカエルのように、いや、宇宙人に睨まれた一般人のように、ただただ固まって立ち尽くしていた。
どうして、こうなっちゃうんだ……
もちろんすべてとは言わないが、うまくいっていた。いつもテンパッて失敗してきた転入の挨拶をなんとか無事に終えたところだった。あとは可もなく不可もない毎日を重ねてひっそり生きていこう。そう思っていた。
そんな矢先、突然やって来たハルという金髪の自称宇宙人が、クラス全員が見守る中で、俺を釣竿で釣ろうとしている!
きっと今日の占いのユキの星座の欄には『疑問符に注意』と書かれていたに違いない。
さっきからずっと頭の中で色とりどりの疑問符が渋滞を起こしてぶつかり合っている。
なんであいつは俺の名前を知ってる? なんで自分を宇宙人と呼ぶ? なんで俺を釣ろうとしてる?
しかしすべての「なぜ」がちっぽけに映るほど、ハルという少年は存在自体が意味不明だった。
そんな二人を見守る生徒たちはといえば、無責任と興味本位の塊となって、この筋書きの見えない物語のオチを待っていた。
いや、俺、何もできないって!
妄想好きのユキの脳は、ありえるかもしれないちょっと未来の自分を想像してしまった。あの猛烈にリールを巻くあいつに合わせて、魚みたいに釣られる自分を。「おっとっとー」「釣られちゃったよー」なんて言いながら。
そんなの、ぜったいヤダ!
転入初日からそんなことをしてしまえば完全にイメージが定着してしまう。それがどんなイメージかは前例がなさ過ぎてわからない。
この前代未聞の嵐を巻き起こしたハルはまだ叫んでいる。「ユキぃー! 来い来い来ーい!」
あぁ、ヤバイ、来る、アレが!
ユキはその身に恐れていた異変を感じた。心臓がわんぱくな子犬みたいに暴れ出し、顔面が気圧で潰れてゆく空き缶のように徐々に変化し始めた。
だめだ。アレだけは、ぜったい、ダメ!
あぁぁぁぁ─!
ユキは抵抗むなしくまたあの顔になってしまった。ジオラマの山脈のようにムクっと盛り上がる眉間、すべての引力を一手に引き受けて垂れ下がる口角、逆にすべての引力に逆らって釣り上がる目。般若のできあがりだ。
終わった……
絶望するユキに追い打ちをかけるように生徒たちのざわつく声が聞こえた。「怖っ!」「何あの顔」「めっちゃ怒ってない?」
違う、別に怒ってはいないんだ。テンパったらこんな顔になっちゃうんだよ!
でもそう説明したところできっと誰にも理解されないし、今更般若は人間に戻らない。
ど、どうしてくれるんだよ!
ユキは身も心もまさしく般若となってケタケタ笑うハルを睨んだ。
しかしユキはまだこの自称宇宙人を見くびっていた。どん底だと思ったこの状況にはまだ続きがあったのだ。
ハルはニコっと笑うと、腰に差した黄緑色の水鉄砲を取り出した。そして「ぴゅ─」というふざけた掛け声と共にユキに向けて発射した。
な、なにしてんだ?
その水は驚く生徒たちの頭上を一直線に走り、ユキの眉間山脈に見事命中した。
だっ!
次の瞬間、ユキはもう自分の席にはいなかった。目の前には、立てられる限りのあらゆる音を立てて爆笑する生徒たちの顔があった。
え?
一瞬何が起こったかわからなかった。
ユキはいつの間にか教壇の前に立っている。いや、立っているだけならまだいい。
え、俺、踊ってる?
そう、ユキは生徒たちの前で踊っていた。
盆踊りみたいな、全身で空気を撫でるようななめらかな動きで。
なんだこれ、なんなんだ!
やめようと思っても体は勝手に動き続ける。
何か言葉を発しようとしてユキは気づいた。
俺、もしかして、歌ってない?
『島の四月はヨ〜、初巳のまーつーりー サノヨイトサ〜ノサ〜♪』
な、なんの歌!?
ユキは自分の意思とは関係なく、聞いたことのない歌を歌っていた。しかもけっこうな音量で、それなりに上手に。
隣を見るとハルも歌い踊っている。二人の歌と踊りは、激しい特訓を重ねたアイドルグループのようにぴたりと揃っている。
そりゃみんな爆笑するはずだ。教師も苦笑いするしかないはずだ。普通は緊張して大人しいはずの転校生が、二人して初日から歌って踊っているのだから。
ユキの目に、今朝、電車の中でクスクス笑っていた女子、えり香の笑顔が目に入った。
違う、俺はこんな奴じゃないんだ! わ、わかってください!
しかしいくら心の中で叫んでも、歌も踊りもやめられない。
たとえ拳銃を突きつけられても、人前で踊ったり歌ったりなんて絶対にできないだろうこの俺が、歌って、踊っている。転入初日に、堂々と、みんなの前で、笑いながら!
え、俺、笑ってる?
ユキはその時初めて気づいた。自分は今、笑っている。さっきまでの般若顔はどこへやら、完全な笑顔になっているのだ。
なんでだよ! あの水鉄砲のせいか? 止めろ、今すぐ止めてくれー!
そこにとどめを刺すように生徒たちの囁く声が聞こえた。「なんか、二人ともヤバくね?」「でもいいコンビじゃん」
コンビ? こいつと俺が?
そしてその言葉に頷くえり香!
違う。認めないで! お願いだから!
そんな世にも滑稽な教室の光景を、白黒のモニター画面を通して眺めている男がいた。
彼がいるのは、学校の裏手に停められた、割と大きめなワゴン車の中。黒いスーツにクリーム色のターバン姿のアキラだ。アキラは助手席にちょこんと座ったアヒルに低い声で呟いた。
「タピオカ、あの水鉄砲、危ないな」
「ギュイ─ンっ!」
ユキは結局一日中、この叫び声から逃げ続けることになった。一人で海を見ながら歩こうと思っていた帰り道も、釣竿を振り回して追いかけるハルから逃げるために全速力で走るハメになった。
「ねぇ行こうよー釣り行こうよぉー!」
だからなんで釣りなんだよ?
でも今そんなことを考えても無駄だ。とにかく逃げよう。そして明日からは一切あいつには関わらないようにしよう。辛抱だ。クラス全員の記憶から、今朝の一連の恥ずかしい記憶が消え去るまで。それがいつの日になるのかはまるでわからないけど。
「ユキ、その髪、イカしてるね!」
無我夢中で逃げていたユキだったが、その意外な言葉に不意を突かれ、立ち止まった。
え、この髪? 今までからかわれたことは何度もあったけど、褒められたことは記憶にない。
ユキが荒い息で振り返ると、ハルは笑顔のまま、何のためらいもなくこう言った。
「ねぇユキ、僕とトモダチになろうよ」
え……
ユキは不覚にも左胸がビクっと動くのを感じた。般若になる前の暴れるような動きとは違う。左胸を人差し指で、絶妙な加減で、ツンと一度だけ突かれたような、痛みのない、正直に言えばちょっと心地よい感覚だった。
それほどハルの『トモダチ』という言い方には不思議な力があった。それはたとえば『ギュイ─ンっ!』という響きと同じように軽かったが、思いの外まっすぐに届いて、すっとユキの中に染み渡った。まるで『友達』という言葉はこうやって発音するんだよという正しい例のように。「トモダチになろうよ。リピートアフターミー」
いやいやいや!
ユキは慌てて離れかけていた現実の端っこを掴んで我に返った。
そんなわけないだろ! お前みたいなとんでもない奴と友達になんかなるわけないだろ!
無事現実に帰還したユキは、そのおかげで自分を見てクスクス笑う生徒たちに気づき、また顔がこわばってゆくのを感じた。
「その顔、イカしてない!」
ハルはそう言うと、またユキの眉間目がけて水鉄砲を撃った。
「だっ!」
気づくとユキは小さくカラフルな魚たちに囲まれていた。
どこだここ。時間が、飛んだ?
ユキは目を凝らして改めてそれを見た。
いや、違う。魚じゃない。これって……
それはルアーと呼ばれる釣り具だ。
見渡せば兵隊のように整然と並んだ釣竿があり、魚がジャンプして跳ねる写真も見えた。
え、釣り?
そこは江の島の片瀬漁港に建つ、江の島にしてはだいぶオシャレな『HEMINGWAY』という釣り具店の中だった。
またあいつか!
振り返ると、ニンマリ笑ったハルが水鉄砲を指でくるくる回しながらユキを見ていた。
あの水鉄砲、なんなんだよ!
その時、ユキの憂鬱な気持ちを一気に浄化するような爽やかな声が聞こえた。
「あら、朝の子だ。宇宙人君」
「よっ、海咲姐【みさきねえ】!」
ハルはまるで親戚のお姉さんとでも話すようにそう返した。
海咲姐と呼ばれるその女性はやたらと姿勢がよく、産まれた時から笑顔でポニーテールだったんじゃないかと思えるほどそれが似合っている。
き、きれいな人。
ユキは一瞬、自分が置かれた最悪な状況を忘れ、彼女に見入ってしまった。
「ほんとにお友達連れてきてくれたんだ?」
ユキはこんなきれいな人が自分について話していると思うと、鼓動が高鳴り、どうにかなりそうになった。
「宇宙人嘘つかないっ!」
いやいやいや!
我に返ったユキは心の中で叫んだ。
友達じゃ、ないから!
しかしユキは海咲に微笑みかけられると、否定することもできず、うつむいてしまった。すると彼女の胸につけられたプレートが目に入った。『店長 島野海咲』。
え、この人、店長なんだ? 若い。
そう思った時、海咲が一方を見て言った。
「あ、店長、どこ行ってたの〜?」
あれ、違うの?
ユキが顔を上げると、海咲の腕に抱かれた、丸々と太った猫が見えた。
猫かよ!
見ると、ハルはその『店長』という名の猫を異常に警戒している。さっきまでの弾けるような笑顔はどこへやら、表情は引きつり、頬がピクピクと震えている。
なんで?
ユキの中でまた新たな疑問符が生まれたその時、入口のドアが開き、制服姿の少年が入って来た。
あ、ボサボサ眼鏡君!
驚くユキと同様に、彼も驚いてユキを、そしてハルを見た。
そりゃそうだ。彼からすれば俺たちは、今朝教室で完璧な振り付けで歌い踊っていた奇妙なコンビなのだから。
「おはよう夏樹」
海咲がそう言うと、ハルがすかさず言った。
「僕たち同じクラス。トモダチ!」
「そうなんだ?」
無邪気に信じる海咲に、夏樹はすかさず「ちげーよ」と吐き捨て、店の奥へと去って行った。
「夏樹、うちのバイト君。けっこうすごいんだよ」
海咲はそう言って壁に貼られた釣り雑誌の切り抜きを指さした。そこにはやたらとポケットがいっぱいついた釣りファッションでクールに決めた夏樹の写真があった。その腕には大きな魚が抱かれている。そして大きな文字で、『釣り王子V2!』。
「ツリオウジ」
子供が初めて出会った文字を読むようにハルが言った。
なんか、微妙。ユキは心の中でそう呟いた。
「王子、釣り上手い?」
目を輝かせて尋ねるハルに海咲が答える。
「もちろん。高校生の中じゃ全国レベル」
海咲はまるで息子を自慢するみたいにそう言って仕事に戻った。
ハルは「ラッキー!」と叫んで、店の奥からエプロンをつけながら戻って来た夏樹の元へと駆け寄った。
「ヘイ王子ぃ─!」
夏樹は一瞬不意を突かれたが、すぐに険しい顔になってハルに詰め寄り、静かに言った。
「お前、学校でそれ言ったら、殺す」
ユキはさすがのハルも謝るだろうと思ったが、それは甘かった。ハルが次にとった行動はまたもや想像を軽く超えていた。
「死にたくないっ!」
ハルは元気いっぱいにそう言って、水鉄砲で夏樹の顔に水をかけたのだ。
「ちょっ!」
ユキが驚いたのもつかの間、ハルはユキに振り返り、またその眉間を水鉄砲で撃った!
「だっ!」
気づくとユキの目の前には海が広がっていた。振り返るとさっきまでいたHEMINGWAYがある。
また、時間と場所が飛んでる!
今度は服装も変わっていた。ユキはいつの間にか救命具らしきものを着て、手には釣竿を握っていた。竿の先には糸が垂れていて、先っぽには小魚そっくりのルアーがついている。
いつの間に……どういうからくりなんだ? あの水鉄砲を撃たれると意識を失うのか?
その間にあいつが俺にこんな恰好をさせたり、妙な踊りを踊らせるように洗脳したりしてるのか? 怖い! 怖すぎる!
隣では同じように釣りの恰好をした夏樹がいた。呆気にとられたその表情はやがて険しくなり、ユキを鋭く睨んだ。
違う。俺仲間じゃないから!
ユキはそう言いたかったが、すぐに言葉を飲み込んだ。慣れない人には一言だって喋ることはできないのだ。
見ると、ハルは一週間ぶりに散歩に連れて来られた犬のようにキャッキャと釣竿を振り回していた。
「王子、教えてくれるんだよね、釣り!」
「え、俺、そんなこと……」
「僕ら釣りたい魚がいるんだよー」
だから『僕ら』とか言うなって!
「王子に教えてもらったらすぐに釣れちゃうかもねー」
ハルはそう言って釣竿を振り、海に向かって真っ赤なルアーを投げた。
しかしルアーは竿の勢いとは裏腹に、見る見る失速し、かなり手前にぽちゃんと落ちた。
「そんなんで釣れるかよ」
突然怒ったようにそう言った夏樹にユキは驚いた。
ハルは辺りを見渡し、遠くの方で座って海に釣り糸を垂らしているオジサンを見つけ、
「あ、こうか?」
と、オジサンを真似してちょこんと座った。
「違う!」
ユキはその厳しい口調にまた驚いた。さっきまで冷たく周りを拒んでいた夏樹の目が、突然ギラッと光って、その場に妙な緊張感を放っている。
こいつ、なんでそんなに怒ってるんだろう。その怒りは『王子』と呼ばれたことや水鉄砲を撃たれたこととはまるで別の方向に向いているように思えた。
「あれは餌釣り。ルアーはこうだ」
夏樹はそう言うと手にした釣竿を左手で握った。
え、教えないんじゃなかったの?
夏樹は体の左側に竿を倒すと、それを一瞬で振り抜いた。
ひゅんっ。
空気を切り裂くような音と共にルアーが空を飛び、まるでそこに落ちることが決められていたかのように、遠くの水面にピシャっと落ちた。
「王子すご─い!」
ユキも「すごい」とまでは思わなかったがちょっと驚いた。何がどうなったのか速過ぎてわからなかったが、とにかくハルが投げた時とは明らかに何もかもが違っていた。
でも、なんで俺が釣りなんて……
ハルが興奮し、「教えて教えてー!」とはしゃいでる間、ユキは退屈そうにスマホを取り出した。
そんなの、オヤジがやるもんじゃん。
ユキは二人から少しずつ離れながらスマホで『釣り』と検索してみる。
『釣り針、釣り糸、釣竿などの道具を使って、魚介類などの生物を採捕する行為、方法のこと』
「だからなんだ」とユキは思う。わざわざ道具を揃えたり、こんな服に着替えたりまでして魚を捕まえて、一体何が楽しいんだろう。
あぁ、帰りたいな。
ユキがそう思った瞬間、夏樹の鋭い声が飛んで来た。
「おい、お前、やんないなら帰れよ」
え?
ほんのちょっと目を離した隙に、夏樹の放つ緊張感はさっきの何倍も強くなっていた。
たちまちテンぱってしまったユキは、夏樹をチラっと見て、すぐに目をそらした。
それが気に入らなかったのか、夏樹はさらに厳しい顔で睨んでくる。
え、なんでそんなに怒ってるの?
こんな時、はっきり自分の意見を言える人間だったらどんなに楽だったろう。相手が「帰れ」と言ってくれてるんだから、さっさと帰ればいいじゃないか。でも、できない!
ユキは夏樹の鋭い視線に負けて竿を構えた。
でも……どうすればいいんだよ……
ユキはさっきのハルみたいにその場にちょこんと座り、竿の端っこを持って、ぽちゃんと海にルアーを垂らした。
すると夏樹の目がさらにギラっとなった。
「お前、話聞いてたか?」
え?
「あれは餌釣りだっつーの。ルアーは魚がいるところに投げるんだよ!」
そうか。こいつ、あれだ。釣りになると性格変わっちゃうんだ!
ユキはもう夏樹の目を見られない。釣竿を握る手が小刻みに震え始めた。
あぁ、またここでも般若になるのか。
しばしの気まずい沈黙の後、夏樹は何もできないユキに愛想を尽かしたのか、フっと鼻で笑い、その場を立ち去った。
と、その瞬間、ユキは手元に衝撃を感じた。ユキの竿が、しなっている!
え?
夏樹が「嘘だろ?」という顔でユキを見た。
何これ、魚? マジで!?
ユキは手元の衝撃が全身に伝わって、体がガクガク震え出すのを感じた。
一人嬉しそうな顔のハルが叫ぶ。
「ユキガンバレぇ─!」
いや、頑張れって言われても! これ怖いって! だって、海の中からなんかが引っ張ってるんだよ! 手を離したいけど、そんなことしたらまた……怒られる?
ユキは様子を窺うように夏樹を見た。
夏樹はユキを見定めるようにじっと見ている。
ユキは目の前に立つ夏樹の恐怖と、目に見えない海中の恐怖の間で、何もできずに立ち尽くした。しかし猛烈に引っ張られる力に耐え切れず、震える声で夏樹に尋ねた。
「こ、これ、どうすれば……」
「喋れんじゃん」夏樹は呆れたように吐き捨て、言った。「竿立てろ!」
え、立てるって、どうやって?
「バカヤロ! こうだよ!」
とうとう駆け寄った夏樹がユキに手を添え、強引に竿を立てた。
竿がさらにグインとしなる!
あぁぁぁっ!
さらに怖くなったユキは、夏樹がまだ慣れていない人だということなど忘れ、すがるように問いかけた。
「そ、それから?」
「リール巻け!」
リ、リール?
スマホで検索したいがそれどころではない。
その時、ハルが自分の釣竿についたリールをくるくる巻き始めた。
「来い来い来ーい!」
あ、これか!
ユキは夢中でリールを巻き始めた。
「焦るなよ。竿立てて、巻け」
夏樹に言われるままそうすると、水面から銀色の魚が顔を出した!
「あっ」
ユキは思わず声を出した自分に驚く余裕などなく、必死にリールを巻き続けた。
「おぉ─でっか─い!」
そんなハルの叫び声さえユキの耳には入らなかった。気づけば般若になりかけていたユキの顔は元の顔に戻っていた。
なんだ、何なんだこれ!
ユキは今まで感じたことのない不思議な感覚の中にいた。
魚が、俺を引っ張ってる! その感触が釣り糸を伝わってこの手にビンビンきてる!
なんだこれ!
取りつかれたようにリールを巻き続けると、やがて魚が口を開けてジャンプした。
わっ、魚って、跳ぶの?
生きた魚を見たことなんて今までほとんどない。それが今目の前で、猛烈に頭を振って暴れている。
ちょ、怖い、怖いって!
「エラ洗いだ」と夏樹が言うのが聞こえた。
「エラアライ?」とハルが尋ねる。
「エラを広げて逃げようとしてんだ。焦んなよ」
ユキはやがて身の危険を感じ始めた。
こんなにめちゃくちゃ引っ張られたら、海の中に落ちちゃうよ!
夏樹はじっと魚を見ている。
ハルはひたすら「ガンバレぇ─!」を繰り返している。
ちょっと、誰か、助けてくれよ!
すると夏樹はそんな頼りないユキの心を読んだかのように、
「自分で上げなきゃ意味ねえぞ」
ユキはドキっとした。それは今の自分だけじゃなくて、今まで生きてきたすべてを叱られているように響いた。
自分で、上げる? 俺が? 無理だって!
次の瞬間、手元からすっと力が抜けて、目の前に釣り糸にぶら下がったルアーが見えた。
あれ、ルアー、外れちゃった?
すると、さっきまで暴れていた魚が、ユキをあざ笑うかのようにチラチラとうろこを光らせ、泳ぎ去るのが見えた。
「くそっ!」
ユキは思わずそう吐き捨てた自分に驚いた。
「焦んなっつったろ」
夏樹が吐き捨てた。まるで三振してベンチに戻った子供を叱るコーチみたいに。
「ユキ、すごーい。釣れそうだったー!」
いや、でも、あんなの……
「まぐれだよ」夏樹が甘い空気を一瞬で蹴散らした。「お前みたいなやる気ない奴に釣れるわけねえよ」
何も、そんな言い方すること……
ユキはビビりながら夏樹をちらっと見たが、夏樹はもう海を見ていた。
ユキは夏樹が投げたルアーを目で追った。それは空できれいに弧を描いて、青黒いゼリーみたいな水面にしゅっと吸い込まれた。
そんな三人を見る怪しげな釣り人がいた。お揃いの青い救命ジャケットを着たアキラとタピオカだ。
「なんで釣り? どう思う? タピオカ」
タピオカは何も答えない。
アキラは「仕方ないな」という顔でサバイバルナイフを取り出し、ハムの塊を器用に薄く切ってタピオカに差し出した。
タピオカは待ちきれないとばかりにサっとハムに食いつき、むしゃむしゃと食べながらアキラに「クワっ」と鳴いた。
するとアキラは深く頷き、答えた。
「俺もそう思う」
「ただいま」
釣竿を持ったユキが家に帰ると、ケイトが驚いて尋ねた。
「あら、それどうしたの?」
「え? あ、ちょっとね」
ユキは夕飯の支度を手伝いながらケイトに釣りの話をした。
「へぇー。初めてなのにすごいじゃない」
「でも、結局逃がしちゃったんだけどね」
「でもすごいわ。よかったわね」
ユキは嬉しそうに何度も頷くケイトを見て、もう少し喜ばせようと、思ってもいない言葉を口にした。
「また、やってみようかな、釣り」
ケイトはニコっと微笑み、ユキに尋ねた。
「一人で行って来たの?」
「え? いや、クラスの子と」
「お友達?」
「いや、友達っていうか、まぁ」
ユキは照れ臭さを隠すように運び終えた料理の前に座って言った。「いただきます」
「めしあがれ」
俺はばあちゃんのこの言葉が好きだ。よかった。今日もちゃんとここにいる。そう思うことができる。「おはよう」も、「お帰りなさい」も、「おやすみなさい」も、全部好きだ。それがあれば、外でのつらい出来事なんて全部忘れられる。そして今日の「めしあがれ」は今までで一番嬉しそうに聞こえた。
これでいいんだとユキは思う。
ばあちゃんにはとにかく安心していて欲しい。俺のことなんか何一つ心配しないで、毎日笑っていて欲しい。
そう思って大好きなケイトの料理を口にするユキは気づかなかった。ダイニングキッチンの隅に、前の家にはなかった金魚鉢が置かれていることを。そしてその中で金色の魚と赤い魚がブクブクと泡を立てながら話していることも。
「にいちゃん、あれがそのユキって子?」
そう聞かれた赤い魚は「うん」と答え、水の中をぐるぐると泳ぎながら言った。
「なんかうまくいきそうな気がするぅー」
夕飯を食べ終え、部屋に戻ったユキは、ふーっと息をつき、ベッドに寝転がった。
なんか、色々あったなぁ……
目を閉じると、ユキの脳裏に今日の出来事が次々と再生された。朝、ばあちゃんと車で走って、江の島に着いた。学校までの道はやっぱり憂鬱だった。江ノ電の中で席を譲ろうとして失敗した。それを見てクスクス笑うイケてる風の女子、えり香という名前だった。HEMINGWAYという釣り具店には笑顔が爽やかな海咲さんという人がいた。スイカみたいにまん丸と太った『店長』という猫もいた……いや、それよりも何よりも、あの自称宇宙人のハルという奴。あいつが現れてから、静かだった一日が突然騒がしくなった。まるで曲が突然変調したように、静かな映画が突然パニック映画に変わったみたいに……
こうして目を閉じて一日の事を思い出すのはユキの癖だ。そうしないと安心して眠りにつくことができない。
でも、といつもユキは思う。どうせ全部、忘れちゃうけど……
そう、俺は忘れるために思い出してるんだ。どんなことがあっても、結局今日だけのことだから。明日になれば全部リセットされて、何もかも忘れてゆく。そして俺はまたあらゆることから置いて行かれて、一人ぼっちになる……
しかし今日のユキの脳内再生はいつもとちょっと違っていた。いつもなら次から次へと今日の出来事が再生されてパタっと終わる。でも今日は二つのシーンで一時停止したのだ。
学校の帰り道、ハルが言った。
「ねぇユキ、僕とトモダチになろうよ」
そして、魚を逃した時、思わず漏らした。「くそっ」
なんで? なんでそこで止まった?
いいや、もうよそう。
ユキはベッドから起き上がり、カーテンを開けて外を見た。
海がある。
夜の海は不思議だ。その姿はほとんど見えないのに、ちゃんとそこにあって、動いているのがわかる。昼間はあんなにキラキラしてるのに、突然無口になる。まるでみんなの一日を吸い込んで呼吸しているみたいに。
ユキはカーテンを閉じ、床に無造作に置いたままの釣竿を見た。手に取り、ゆっくり触れてみる。釣竿を持ったのは今日が初めてだった。こんなに長いんだと改めて思う。持つとすぐに先端が天井に届いた。竿の先を恐る恐る指で押してみる。それは思った以上にしなって、泳ぎ去った銀色の魚を思い出させた。
あれって、なんだったんだろう。
魚に引っ張られて本当に怖かったのに、何度も竿から手を離そうと思ったのに、できなかった。
なんか、不思議な感じだったな……
いつもと違う一日の余韻に引きずられていると、玄関のチャイムが鳴る音がした。
こんな夜に、誰だろ。
ユキが階段を下りると、玄関の扉がバーン!と開いた。
う、嘘?
そこには大きな荷物を背負ったハルが立っていた。
「たっだいまぁ─!」
何のためらいもなくそう叫ぶハルに、ユキはただただ驚いた。しかしもっと驚いたのは、次に聞こえてきた言葉だ。
「おかえりなさい」
振り返ると、ケイトがハルを見て微笑んでいた。
は?
ケイトはハルの釣竿を見て、ユキを見た。
「あら、お友達って」
「いや……」
ユキはかすれた声でそう返すのが精一杯だった。唯一まともに話せるケイトとの二人だけの空間に、ずっと大事にしてきたこの場所に、よりによって一番ありえない奴が入って来たのだから。
しかしハルは、ユキのそんな動揺に微塵も気づくことなく、晴れやかに言った。
「そう、僕たちトモダチになったんだ!」
ユキは焦った。大事な大事なばあちゃんにこんなとんでもない奴を一秒でも見せたくない!
「ち、違うんだ、ばあちゃん」
しかしケイトはまったく動じることなく言った。
「ありがとう、ハル」
はぁ─?
なんでばあちゃんがこいつの名前を知ってる? なに、なに、どういうこと?
「ハルはね、今日からここで私たちと一緒に暮らすことになったの」
「ザッツライっ!」
ユキは狐に、いや、宇宙人に思いっ切りつままれたようにぽかんと口を開けて、かろうじてケイトに尋ねた。
「な、なんで?」
するとケイトはとっておきの悪戯を思いついた少女のように、フフっと微笑んで言った。
「Je pensais que c'était une bonne idée.【素敵なアイデアだと思って】」
いつもなら優しく響くはずの歌だが、今はユキをさらに混乱させるだけだった。
「ユキぃ─!」
そしてハルがまたユキを追いかけた。
ユキはまた逃げた。まだゆっくり見ていない新しい家の中を、必死で。
ケイトはそんな二人を微笑ましく見送った。春の初めの、じゃれ合う猫たちを見るように。
「ユキ、僕と一緒に地球を救おう!」
ハルは確かにそう言った。
地球? 救う? 俺が?
やっぱり今日のユキは疑問符に呪われている。
ど、どういうことだよ!
ユキは新たな、しかも大きすぎる疑問符に押しつぶされそうになるのを感じた。そしてまた顔が般若になりかけたその時、
「だからユキ、それだめっ!」
ハルが今日四度目の水鉄砲をユキに放った。
「だっ!」
その水はユキの眉間で花火みたいに弾けた……
つづく