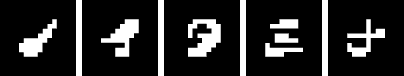NOITAMINA
OFFICAIL WEBSITE
SHARE
ツイート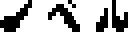 NOVEL
NOVEL
ノイタミナノベル「PSYCHO-PASS サイコパス/ゼロ 名前のない怪物」 第三章

第三章
扇島は勾配が激しい。
元は平らにならされた埋め立て地だが、無秩序に建築物を積み重ねていった結果、いまはどこへ移動するにも階段・梯子は避けて通れない。その上通路にはどこもかしこもゴミが散乱していて歩きづらいことこの上ない。
扇島に漂うすえた臭いには三日で慣れたが、この悪路には未だに慣れない。
慣れないどころか、日を追うごとに足に疲労が蓄積し、移動はますます険しくなる。
靴の買い換えを真剣に検討しようか……。すり減った靴底を見て、狡噛は思う。
「今日はもう終わりにしようや」
征陸が大きく伸びをして言う。便乗するように佐々山も「賛成デース」と手を挙げた。気がつけば勤務時間をとうに過ぎ、日もすっかり落ちた。確かに扇島にこれ以上いても、捜査効率がいいとは言えない。それでも――
「もう少しだけいいか?」
狡噛が引き上げを渋るのには訳があった。
成果が全く上がっていないのだ。
被害者少女の身元特定を命じられてからすでに二週間。毎日扇島に通っているというのに、少女に見覚えがあるという人物に一度も会っていない。
このままでは、本当に霜村の思惑通りになってしまう。そんな焦りが狡噛の足を止める。
「いや、今日はもう終いだ」
征陸がたしなめるように言う。
「聞き込みってのはこんなもんだ。焦ってやるより気長に根気よくやった方がいい。情報なんざ、そのうち勝手に飛び込んでくるもんさ」
征陸の年季の入った革靴は、狡噛のそれよりさらにくたびれ、靴底がすり減っていた。
公安局刑事課一係の刑事部屋に戻った三人を、一係所属の内藤僚一(ないとう りょういち)執行官が待ち構えていた。
「もー、三人とも遅いですよー」
一係構成員の中でもっとも背の低い内藤は、ストレートヘアーの短髪をゆらしながら狡噛たちに駆け寄ると、佐々山と征陸のコートの裾をつまんだ。三人とは言っても、彼が本当に待っていたのは佐々山と征陸の二人のようだ。眠そうに薄ボンヤリと開けた瞳で佐々山と征陸を交互に見る。
眠そうではあるが、眠いわけではない。こういう顔なのだ。
「僕今日夜勤なんですから、あんま時間ないって言っといたじゃないですか」
「狡噛がねばったんでな」
征陸の弁明に、内藤はむくれ面で狡噛を睨む。
「何か約束でもあったのか?」
「そうですよー。二係の神月さんも待ってたんですから」
廊下に目をやると短髪を整髪料で無造作風に固めた男、二係の神月凌吾(こうづき りょうご)執行官が、こちらをのぞき込みながら、両腕の一差し指と親指をコの字型に構え、何かひっくり返すようなそぶりをしている。
麻雀だ。
娯楽を極端に制限された執行官の中には、室内で手軽にできるテーブルゲームを好むものが多い。佐々山、征陸、内藤、神月は中でも麻雀を好むようで、シフトの都合が合う時を狙っては四人で勝負に興じているようだった。
「あ、わりー今日パス」
佐々山は、内藤の腕をふりほどくと、脱いだコートを机の上に丸めて置き、こともなげに言った。
「えー!」
内藤が声を上げる。
「なんでですか。四人の都合が合うの久々なんですよ? 今日逃したら、次いつ打てるかわからないんですよ? ていうか佐々山さんこの前の負け分払ってないんだから、今日打たなかったら、僕マジで請求しますよ? いいんですか? いいんですか?」
普段はわりとおっとりした語り口の内藤だが、今日ばかりはと立て板に水のようにしゃべる。負け分とか、請求とか、不穏な単語も並ぶが、狡噛はここは聞き流そうと決めた。
「あーいい、いい。払う払う。とにかく気がのらねーから今日はパス」
そう言うと佐々山はそそくさと執務室をあとにした。
廊下では、今まさに目の前で内藤がしたようなリアクションを、神月が佐々山に向かってしている。
「何ですかあれ?」
内藤はぷんすかと頬を膨らまし征陸に意見を求めるが、征陸は「んー」とか「なー?」などと身のない返答をするばかりだった。
神月が入り口から大きく身を乗り出しながら、内藤に語りかける。
「なーどうすんだよー。俺今日バキバキに麻雀気分なんだけど」
「僕だってそうですよ。えーと……」
欠けたメンツを補充しようと、内藤の視線が泳ぎ、音楽雑誌に目を落としていた六合塚弥生(くにづか やよい)執行官にとまった。
「えーと……弥生ちゃん、麻雀とかって」
「勘弁して」
内藤が誘い文句を言い終わらぬ前に、ぴしゃりとはねのける。きつく結んだポニーテールは微動だにしない。
執行官達のやりとりを見ていると、狡噛は、彼らが潜在犯だと言うことを忘れそうになる瞬間がある。一般人から隔離され、まるで社会の危険物かのように取り扱われている彼らも、自分と何ら変わらずに余暇を楽しむのだ。
自分も早く家に帰って、今日はゆっくり休もう。
進展しない捜査に張り詰めていた気持ちが、少し楽になる。脱ぎかけていたコートを再び羽織ると、狡噛は執務室に背を向けた。そのとき、誰かが自分の腕をぐいとつかんだ。
内藤である。瞳を潤ませ懇願顔で狡噛に身を寄せる。
「コーガミさん……。執行官達のストレスケアに付き合うのも、監視官の大事な役目だと思うんです、僕」
「ツモ」
「はあ? 狡噛さん、それロンです」
「はあ?」
「しかもそれフリテンじゃないですか。あがり牌捨ててますよ」
「イヤちょっと待て。捨てた牌で上がっちゃいけないのか?」
「上がっちゃいけないって言うかツモなら良いんですけど、ってかコレ説明しましたよね?」
「聞いてないぞ」
内藤はあきれ顔で天を仰ぐと、机上に整列する白と緑のツートンカラーの牌を大げさに引き倒した。
公安局執行官隔離区画のラウンジに、麻雀牌を混ぜるじゃらじゃらという音が響く。
狡噛は結局あの後、断る間もなく今夜の麻雀メンツに組み込まれてしまったのだ。
麻雀――四人のプレイヤーがテーブルを囲み一三六枚あまりの牌を引いて役を揃えることで得点を重ねていくテーブルゲームだ。狡噛はこのゲームの存在は知っていたが、いざ実際にテーブルを囲んでみると、その複雑な心理戦と計算に翻弄されてしまう。
「そんなにぷりぷりするな、内藤。初心者に声かけて付き合わせてんのは俺達なんだから。実際お前の説明もたいがいだぞ」
「そうだよ『とりあえず良い感じに一四枚牌をそろえたらあがりです』っておまえ」
征陸と神月のフォローがいたたまれない。
「えー。そうですかねー。だって狡噛さんですよー。監視官のエリートですよー。そのくらい言ったらなんかわかりませんかね」
「無茶言うなおまえ。ねえ狡噛さん」
征陸・内藤・神月の三人は歓談に興じながらも手をよどみなく動かし、牌を積み上げていく。その手際の良さに目を奪われているとすかさず内藤の指導が入る。
「狡噛さんも、早く牌積んでください」
「ああ……」
内藤に促されるままに牌を積む。
奇妙なゲームだと思う。ゲームスタートまでに手間がかかりすぎるのだ。
一七個の牌を数えて並べ、それを二段に積み上げ山を作る。さらに四方に積み上げられた山から、各プレイヤーに手牌が割り振られ、ようやくゲームをスタートすることができる。
一般的なコンピュータゲームであればこんな手間はかからない。
いくら娯楽が極端に制限されているとはいえ、全てのコンピュータゲームが規制されているわけではない彼らが、あえてこの手間のかかるゲームに興じる意味が狡噛にはよくわからなかった。
しかし、対戦相手と面と向かい、直接牌を見、触れる行為が、オンラインゲームとは違う高揚感を与えることは、ほんの数分の経験ながら何となく理解できた。
その高揚感のせいか、征陸も内藤も普段より饒舌な気がする。係の違う神月に関しては何とも言えないが、彼もきっとその例外ではないだろう。
狡噛自身も、目の前にある牌を指先で弄んでいると、心なしか舌先が軽やかになっていくように感じていた。
内藤が手元の牌をかちかちと鳴らしながら口を開く。
「ぶっちゃけどうですか、狡噛さんたちの方は。なんか手がかりつかめました?」
「いや……情けない話だが」
「ですよねー」
そういいながら、手持ちの牌を一つ捨て、言葉を続ける。
「実際問題無理でしょう。思春期までシビュラから隠れ続けた無戸籍者ですよ。それを今更身元特定なんて」
まるでゲームの手順かのように、征陸がその言葉に続く。
「いや、逆に言やぁ、そんだけ扇島に根ざしてた人間だってことだ。根気強く調査を続けりゃ、必ず何らかの情報に行き当たる」
「根気強くって言ったって、征陸さんの時代みたいに捜査員が何万人といる訳じゃないんですよー? たった六人で根気強くって、何年かかるんですか。どーせその前に二係が犯人つかまえますってー」
「や、それもどーかねえ……」
今度は神月が口を開く。
「うちの大将も鼻息だけは荒いんだけど、いかんせん捜査が進展しなくって」
「まじですかー」
「基本的には例の薬剤の線からあたってんだけど。医療関係、化学関係一切情報無し。現場周辺の街頭スキャナーにもそれらしい人物の形跡が残ってないもんだから、まー八方ふさがりだよねー。案外、一係さんが頼みの綱かもよ?」
そう言うと神月は狡噛にちらりと目配せした。順番に手持ちの牌を捨てていくように、順番に発言するのがこの場のルールのようだ。
狡噛は目の前の牌に視線を落として考え込む。
犯人は魔法使いじゃない。それならば……必ず痕跡があるはずなのだ。犯人の悪意の痕跡が。
「犯人の目的は何だ……」
狡噛の言葉に、三人の執行官が顔を見合わせる。
「とっつぁんも言ってただろ。なかなかおつなことをするって。賄賂疑惑議員の肛門に海馬を突っ込み、無戸籍少女をアイドルステージに祭り上げる……。わざわざリスクを冒してまでこんなことをする理由……」
思考に黙り込む狡噛をよそに、征陸と内藤がつづく。
「私怨じゃねえのは確かだな」
「そうですね」
二人の確信めいた発言に目を見張る。
「何故そう思う」
「私怨を晴らすためだけだったら、わざわざこんなめんどくさいことしませんよー。それこそ廃棄区画の闇に紛れてグサリ。あとは犬にでも喰わせますかね。僕ならそうします」
いたずらに微笑む内藤の、重たげなまぶたの奥が鈍く光っているのに気がついて、狡噛は薄ら寒くなる。
「自己顕示欲だろうな……」
征陸がぽつりとつぶやく。
「なんかアピールしたいことがあるんだろ。そうじゃなきゃあんな目立つ方法とらねえ」
征陸の言葉に、さらに内藤と神月が続ける。
「まず先にアピールすべき事柄があって、そのために殺人がある感じですかねー……」
「社会的メッセージの線かね……。賄賂撲滅? 廃棄区画解体反対……とか?」
「その割にはー、廃棄区画の住人だったであろう少女を血祭りに上げてますけどねー」
「いまいち趣旨が一貫してねぇな」
「手口は一貫してますけどねー」
「一つ一つの事件にっつーより、連作であるところに意味があるのかもしれねぇな」
「連作か……。芸術家気取りですねー」
「犯人は芸術家気取りの、政治犯ってとこか」
「さらに言えば、青二才」
「若いってことですかー?」
「何かのために費やせる労力ってのは、年々減ってくもんだ。お前さんたちにゃわからないかも知れないがな」
「うーん確かにそうかも」
三人の執行官達はまるで麻雀の手を進めるかのような軽やかなテンポで犯人像に迫っていく。
狡噛は三人の執行官の顔を見回して、なるほどと思った。
執行官達はこんな風に、普段から係の区分を超えて事件の所感について語り合っているのだ。
職域にとらわれ、自らのサイコ=パスの健康に気を配り、会議で提示されるデータを客観的に判断し業務に当たるだけの監視官とは違う。
自らの有機的思考で犯人に迫り、またそれを仲間と共有する。そうやって執行官達の捜査に対する優れた嗅覚は培われているのだ。
犯人の犯罪心理に寄り添うことで捜査の青写真を描く方法は、すでにサイコ=パスの濁った彼らにのみ許された行為である。もちろん、職務規定上常人以上に健常なサイコ=パスを求められる監視官にとって、この行為は忌避すべきものだ。
執行官は監視官にとって、盾であり、矛なのだ。
そして、その盾と矛を過不足無く利用することが、監視官に求められる職務なのである。
だとすれは――狡噛の脳裏に、先ほどの刑事課執務室をあとにする佐々山の後ろ姿がよぎる。
およそ自分は及第点に達していないだろう。
ここ二週間、佐々山とまともに会話していない。今目の前で繰り広げられたような有機的な思考の発展は、自分と佐々山の間では成しえなかった。
ただ現場を連れ回し、自分の言うとおりに聞き込みをさせ成果を報告させるだけ。佐々山はこのところ珍しく「お前の言うとおりに動く」と言う言葉通り自分に従っていたが、それだけではせっかくの盾と矛を闇雲に振り回しているに過ぎない。
以前から佐々山と自分の関係はこうだっただろうか。そんなはずはないと思いながらも、その問いを否定しきれない自分がいる。
しかしだからといって、自分に何ができるというのだろう。
監視官と執行官をつないでいるのは職務だけである。
執行官にそれ以上の関係を求めるのは、自らのサイコ=パスを危険にさらすことでもある。
今こうやって執行官達の余暇に付き合う行為さえ、宜野座が見れば途端に顔をしかめるだろう。
それでも今夜、狡噛が彼らに付き合おうと思ったのは、そこから何か佐々山との関係構築のヒントを得られるかもしれないと思ったからである。
しかし結果は、監視官としての自分の無力さを再認識させられただけだ。
「チュンビーム」
狡噛の正面に座る内藤が、急に声を上げ牌を切った。
狡噛が思考に沈んでいる間に、ゲームはすっかり進んでいたようだ。
執行官達はすでに犯人に思い馳せることをやめ、自分の手牌をそろえることにその全神経を注いでいる。殺人犯の話と麻雀を同じ机上で語れるのも、彼ら執行官の特異性と言って良いだろう。
狡噛が「チュンビーム」と言う聞き慣れない言葉に驚いて内藤を見つめると、彼は不満げに口を尖らせている。
神月が笑いをかみ殺し、肩をふるわせながら言う。
「狡噛さん、チュンビームっすよチュンビーム」
「は?」
「向かいの相手に、『中』って書いてある牌を切られたら、撃たれたふりするんすよ、グアーって」
「はあ?」
ビームだの撃たれるだの、このゲームにそんな狙撃要素が存在しただろうか。怪訝そうな狡噛に、もはや笑いをこらえきれなくなった神月は、肘で必死に表情を隠しながら説明を続ける。
「だからね……この……『中』の縦棒から……ビームがでるんすよ……ビーって……だから……向かいの人は……ビームに撃たれちゃうんす……ぶっ」
ついには大声で笑い始めた。
「それもルールなのか?」
真面目に問いかける狡噛がさらにツボに入ったのか、神月は地団駄を踏んで笑い続けている。困惑顔の狡噛に、哀れみの表情を浮かべながら征陸が注釈を入れた。
「くだらない冗談みたいなもんだ、麻雀やるときのお決まりのな」
わけがわからない。
「あーもうやっぱり狡噛さんじゃ駄目ですねー。佐々山さん呼んできます僕ー」
しびれを切らして内藤が立ち上がり、住居区画へ消えていった。
自分から誘っておいてその言いぐさはないだろう、しかも何だかよくわからない冗談に乗れなかったからといって。そんな腹立たしさも勿論あるのだが、何とも言えない敗北感もある。そしてその妙な敗北感がさらに狡噛を苛立たせる。
「メンツがそろうなら、俺はこれで……」
「コウ、まあちょっと待て」
さっさと立ち上がりその場を去ろうとする狡噛に、征陸が声をかけた。
狡噛はわざと憮然とした顔で振り向く。
「なんだよとっつぁん」
「お前もう少しここにいろ」
「なんで」
「お前、最近光留と話してないだろ」
この初老の刑事は佐々山のことを光留とよぶ。
それはおそらく征陸が佐々山に一定以上の信頼を置いている証だろう。
実際一係の中で、佐々山と征陸の付き合いは、誰よりも長い。そんな征陸に、佐々山との関係をずばり指摘されると、何だか同級生の肉親にお説教されているような居心地の悪さがあって、狡噛はただ黙るしかない。
「コウ、こうやって一つ机を囲んで手を動かしてると、普段言わないような言葉が不意に飛び出すもんだ。伸元もだが、お前もたいがい真面目だからなぁ。業務中にそう砕けた会話もできないだろう? もうちょっとここにいて佐々山と話してけ」
まさに親心、というような征陸の気遣いが気恥ずかしい。
しかし「一つ机を囲んで手を動かしていると言葉が出やすい」という言葉には、狡噛も納得できる。
もしかしたら佐々山との関係を好転させる良いきっかけになるかも知れない。
狡噛は幾分か素直な気持ちで腰を下ろした。
居住区画へと続く廊下の奥から、聞き馴染みのある佐々山の悪態が聞こえる。
なんだよーとか、ねむいんだよーとか、大体そんなことを言っているようだが、それでも強引に誘われれば来るあたり、佐々山らしい。
「なんだよ狡噛、お前カモにもならないって?」
狡噛をにやにやと見下ろして軽口を叩いてから、先ほどまで内藤が座っていた席に座る。
むっとしながらも、佐々山の態度に安堵している自分もいる。こんな風に佐々山と正面で向き合ったのはいつぶりだろうか。
「わーい。コレでいつものメンツですねー。じゃあ、狡噛さんありがとうございましたー」
と狡噛に離席を促す内藤を征陸が手で制する。
「ああ、内藤、お前今日は見学な」
「えー!」
「無理矢理引っ張ってきて、はいご苦労さんはねぇだろ。今日はコウに麻雀を仕込むことに決めた俺は」
内藤はその小柄な身体を精一杯引き延ばしながら抗議を続けてるが、刑事課の重鎮を前にその声はむなしく跳ね返されるばかりだ。
二係の神月は、我関せずといった風に手元の牌を弄んでいる。
「いいだろ光留」
佐々山が一瞬沈黙する。その沈黙が、狡噛の耳に痛い。
「まあ、カモになる程度にまでは醸しますかね」
そう言うと佐々山は人を食ったような顔でニヤリと笑った。
再び、執行官隔離区画のラウンジに、麻雀牌を交ぜるじゃらじゃらという音が響く。
「いいか。麻雀ってのは自分の手牌をそろえるゲームだが、だからって自分の手牌ばっか見て一喜一憂すんな」
まだ火の付いていないタバコを口端でくわえながら、佐々山は、あっという間に牌を積み上げる。当然狡噛より遥かに早い。
「最近の連中は本物の牌を握るってことをしない。オンラインでどれだけリアルに対戦していようが、本当の勝負ってのは相手と目を突き合わせて、目で耳で鼻で卓の雰囲気を読み取ってするもんだ」
そう言うと佐々山は片手で手早くタバコに火をつけ、一口目を深く吸い込むと勢いよく煙を吐いた。
「見るべきは、人だ。狡噛。相手の表情、目線、息づかいや発言の変化。そういうのを見て、相手の狙いを読むんだよ。そうすりゃ自ずと、自分の進むべき道が見えてくる」
「んな偉そうなこといって、佐々山さん前回僕にゴリゴリに振り込みましたけどねー」
内藤の突っ込みに、神月が「ちげーねー」と肩を揺らす。
佐々山はバツが悪そうに内藤をこづくと、再びタバコを深く吸い込んだ。
見るべきは、人。その言葉通り、狡噛は目の前の佐々山を見つめる。
今、なにかを、話すべきなのだろう。
征陸もそのために自分をこの場に引き留めたのだ。それはわかっているのだが、いざとなると何を話せばいいのか、もやもやとしたものが頭に浮かぶばかりで、何一つ具体的な言葉にならない。
手元の牌に目を落とす。種類も何もバラバラで、何をどうしたらあがりになるのか、皆目見当が付かない。まるで自分の思考とシンクロしているようで、面白くない。
「おい。だから自分の手牌ばかり見るなって」
佐々山の言葉にもう一度目を上げる。
「なら、何を見ればいい」
「だから人だって」
「人を見られない場合は、何を見ればいいのか聞いてるんだ」
「そんな場合はねえ」
「は?」
「そんな場合はねぇ。そういうときはたいがい、てめー自身に、人を見る気がないんだよ」
狡噛は自分の顔がカッと熱くなるのを感じた。これまでの自分の佐々山にまつわる逡巡を、全て否定されたような気がしたのだ。
手牌を伏せて立ち上がる。
「悪いが、今日はこれで帰らせてもらう」
征陸が止めるのも聞かずに、狡噛はその場を去った。
つづく