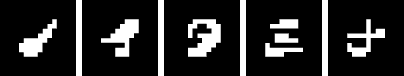NOITAMINA
OFFICAIL WEBSITE
SHARE
ツイート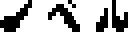 NOVEL
NOVEL
ノイタミナノベル「PSYCHO-PASS サイコパス/ゼロ 名前のない怪物」 第四章

大切なものは、自分の手元には置かない。
これが、佐々山の流儀だ。
幼児期に買ってもらった飛行機のおもちゃは、大切に持ち歩いているうちに鞄の中でその羽が折れてしまったし、生涯の相棒にしようと拾ってきた子猫は、触りすぎたストレスで三日で死んだ。
自分には何かを大切にするという才能が無い、佐々山は幼くしてそれを悟った。
それからは、自分が少しでも心惹かれるものには距離を持って接するようになった。
手に入れられない悲しみよりも、手に入ったものが失われる悲しみの方が、何倍も鋭く深く心をえぐることを佐々山は知っている。
はなから何も手にしないことこそ最良の処世術なのだ。
その点において、佐々山は執行官の生活に満足していた。
社会から隔離され厳しい制限を受ける執行官という立場は、佐々山自身を大切なものたちから遠ざけてくれる。
なんという、優しい牢獄。揺りかごに似た、棺桶。
佐々山は扇島深部の、排気ダクトが無尽蔵に這い回る地下通路を歩いていた。
時刻はすでに午前〇時を回ろうとしていた。
もう何度目の訪問になるだろう。いまだこの巨大な迷宮はその全貌を明らかにしない。
廃棄区画といえども、この規模のものになると独自に経済活動が形成される。島内には何ヶ所か繁華街が存在し、住民たちはその周辺に居を構えるのが一般的だ。
捜査開始当初、佐々山たちはそれらの繁華街を中心に聞き込みを続けたのだが、一切成果が得られなかったため、結局は全島しらみつぶしという方針をとらざるを得なくなった。
住民登録情報の無いこの場所では、どこに行けば聞き込むべき相手に接触できるか見当も付かない上に、何十年も上書きされていない地図のおかげで、自分の位置さえ把握できない。
佐々山は、自分が巨大な化け物の臓物にすっかり飲み込まれてしまったような感覚に襲われる。
定期的に入ってくる狡噛と征陸の動向からすると、二人もたいがい手を焼いているようだ。
すり減った靴底から、何が混じっているのかわからない排水がじんわりと染みこんでくる。この排水に濡れているうちに、自分までとんでもないに化け物に変身したりして、などというくだらない妄想で思考を弄ぶ。
「執行官なんてやってる時点で、じゅうぶん化け物だよなぁ……」
佐々山の独り言が排気ダクトに低く反響し、暗闇の奥へ吸い込まれていく。
ズボンのポケットからつぶれたタバコを取り出し火をつける。
苦く刺すような煙を深く飲み込み、指先に灯る赤い光をみつめる。
妙な既視感がある。
執行官隔離区画の薄暗い自室で、当てもなく煙の行方を目で追っているときの感覚。
この場所もまた、優しい牢獄なのだろう。
世の中の何もかもから捨てられたこの場所は、世の中の何もかもを捨てたい人間にとっては、最上の楽園なのだ。
いや、捨てたい、というのは適当ではないか。佐々山は自分の考えに頭を振る。
捨てたかったわけではない、捨てられたかったわけでもない。
ただ、自分の側にそれがあるのが辛い。いつかそれが自分の側から離れていくのではないか、壊れてしまうのではないか、その恐怖に耐えきれなくなったとき、人は孤独に安住するのだ。
この場所は、孤独の住処にふさわしい。
そう思うと途端に足が重くなる。なんならこのまま扇島の深部に沈み込んでしまっても良いような気さえしてくる。
暗く落ち込む思考の端で、佐々山を呼ぶ声がする。
左腕のデバイスが佐々山に語りかける。
『佐々山、今日はもう上がりだ。三十分後にCエリア2で落ち合おう』
執行官にはめられたリードはそう簡単に外れない。
佐々山は大きく息をつき、煙が流れて行く方向に向かって歩き始めた。
投げ捨てられたタバコが濡れた地面に落ち、ジュッと音を立てた。
無数の鉄骨に覆われた夜空に、人々の喧噪がこだまする。
時刻はすでに午前〇時を回っているというのに、人々は露天に群がり、その熱は冷める気配がない。
あらゆる場所で火がたかれ、そこここからもうもうと白い湯気がたちのぼり、様々な食べ物の臭いが漂う。路上に広げられた店舗には、皿を持った人がたむろし、硬貨と引き替えに我も我もとおかわりをねだっている。
まるで時代小説ね……。
露天の喧噪を古いビルの外付け鉄骨階段の上から見下ろしながら、瞳子はそう思った。
オートメーション化された飲食店に慣れた瞳子にとって、むき出しの炎で調理された食べ物も、それをリアルマネーで求める人々も、時代小説の中に出てくる創作物のように現実味がない。
しかし目の前で繰り広げられている光景、鼻腔をつく食欲を誘う香り、空腹に鳴く腹、それら全てが現実なのだ。
藤間のあとをつけて、初めて扇島に足を踏み入れてから、そろそろ一ヶ月が経つ。
あれからも、毎週末藤間は教員宿舎を抜け出し、瞳子はそれを追って扇島を訪れたが、何度来てもこの場所の有様には驚かされるばかりだ。
ホログラムではないネオン、すえた臭いのする人々、片付けられる気配のないゴミ、普段瞳子が身を置く画一化された美しい世界とは対照をなすそれらの風景。
足下には防寒具に身を包む人々の流れゆく様が見える。
着ているものは皆、どこからか拾ってきたものなのだろうか。どれもこれもそこはかとなく薄汚れて、コーディネートはちぐはぐだ。しかし、それを気にするものはいない。
ここにいるのは皆、シビュラによって保護された安全で豊かで美しい世界から抜け出してきた人々だ。
彼らには彼らの価値基準があるのだろう。
瞳子には想像も付かないけれど。
こんな世界があるなんて、ほんの一ヶ月前は思いもしなかったのに。
いつしか瞳子は、自分の価値観を揺さぶるこの街の景色に夢中になっていた。
今となっては、藤間のあとを追うのと同等に、この風景の中に身を置くことも瞳子の楽しみの一つだ。
恐らく藤間も、この街の魅力に取り憑かれているのだろう。
だからこそ毎週足を運ぶに違いないのだ。
だとしたらやはり、自分と藤間の精神は共鳴するところが大きい。自分の精神のどこかに、必ず藤間に通じる道筋がある。
これを、幼い思い込みだと人は言うだろうか。
年の瀬の夜風が、むき出しの膝小僧に染みる。タイツではなくハイソックスをはいてきたことを後悔しながら膝をさすると、瞳子はファインダーを覗いた。今夜も、扇島に足をふみ入れた瞬間に、藤間のことは見失ってしまったけれど、この場所が藤間の心に近い場所だという確信が、瞳子を奮い立たせる。
ファインダー越しの世界の中を、人々が行き交う。
その中に瞳子の目を惹く男がいた。
誰もがうつむきがちにそぞろ歩く中で、その男だけは凛と背を伸ばし、まっすぐに前を見つめて歩いていた。くすんだ色彩に沈む街で、彼の銀髪は美しく輝き、その存在感は小石にまぎれた水晶のように光を放つ。
思わず、シャッターを押す。
一枚。
ピントが合っていないかも知れない。カメラを構え直しているうちに、人の流れは容赦なく彼を運んで行ってしまう。
もう一枚。
小さな電子音が鳴る。そのとき、銀髪の男が立ちどまり、ゆっくりとこちらを見た。
まさか、自分が写真を撮っていることに気がついたのだろうか。シャッター音を聞かれたか。しかし、瞳子とその男の間はゆうに三〇メートルは離れている。その状況で、この喧噪の中、小さな電子音が彼の耳に届いたというのか。
そんなバカな、とは思うが、男の視線は明らかに瞳子に定まっている。
慌ててカメラをおろす。
それでも男は、瞳子を見つめ続ける。
その銀髪は朧月のように柔らかく発光し、色素の薄い瞳は、この距離からでもわかるほど、周囲のネオンの光を集め複雑に輝いている。
美しい男だ。
できることならもう一度、彼をファインダーに収めたい。そんな想いが瞳子の胸中にむくむくと沸き上がる。
頼んだら、撮らせてくれるだろうか。先ほど無断で撮ってしまった非礼を詫び、きちんとお願いしたら。しかし、いくら美しくても、扇島に出入りしている男である。藤間とは違って身元が明らかでない男と、そこまでの関係をもって良いものだろうか。
瞳子が逡巡しているうちに、男はゆっくりとこちらに向かって歩いてくる。
口元には微笑みを湛えているが、何を考えているのかは全くわからない。無断撮影を咎めるためにこちらに向かっている可能性も十分にある。このまま何食わぬ顔でこの場を立ち去った方が良いのかも知れないが、なぜか男から瞳をそらせない。
高速回転する自分の思考に足がすくむ。
二人の間の距離が縮んで行く。
一五メートル……一〇メートル……五メートル……。
瞳子のいる外付け階段に、男はゆっくりと足をかける。
もう、その銀髪が、瞳子の手に届きそうな位置にまで迫っていた。不思議な、甘く少しすえたような香りが漂ってきて、瞳子は目眩を感じる。どこかでかいだことのある香り。
瞳子の脳裏に藤間の姿が浮かんで、ジンとその身体を痺れさせた。
「おい」
その時、背後からいきなり肩をつかまれた。
あまりの驚きに悲鳴をあげて振り返ると、そこにはいつぞや自分を補導した、短髪の刑事が立っていた。
「まーたこんなところに出入りして。こりねぇなーお前も」
瞳子が口をぱくぱくさせているうちに、銀髪の男は二人の横を通り過ぎていった。やはり、目があったと思ったのは気のせいだったのだろうか。それとも短髪の男に気を遣って、声をかけるのをやめてしまったのだろうか。
華奢な後ろ姿を見送っていると、ホッとする反面なんだかものすごく惜しいことをしたような気がしてきて、目の前の男に怒りがこみ上げてくる。
「何すんのよっ!! 今せっかくあの人にっ――!」
言い終わらないうちに、短髪が鋭い視線を瞳子に向けて問いかけた。
「お前……今のヤツに何もされなかったか?」
わけがわからない。世の中の男が皆、自分と同じように野蛮だとでも思っているのだろうか。
「はぁっ?! わけわかんないっ!」
慌てて短髪の背後を目で追うが、すでに先ほどの男の姿は無かった。
イヤな汗が、佐々山の背中をつたう。
鼓動が速まり、皮膚は泡立つ。本能が危険を感じている。
今、自分と瞳子の横を通りすぎていった銀髪の男からは、明らかに血の臭いがした。
それも一人ではない何十人もの、人間の血の臭い。
いや、実際に鉄臭いとか、腐敗臭がするとかそういうことではない。男はこの街にはふさわしくないほどに清潔な身なりをしていたし、実際には無臭だった。
しかし、猟犬の嗅覚が、男に死の臭いをかぎつけたのだ。
今すぐ追いかけていってドミネーターを向けても良いのだが、目の前の瞳子の存在が佐々山にそれを留まらせた。今日の瞳子は、前回出会ったときとは違い制服の上に厚手のコートを羽織っている。だから、廃棄区画内でセーラーカラーが翻るという特異なことにはならないが、それでも彼女の若さとか、美しく整えられた黒髪がここの住人たちの目を惹かないとは言えない。
もちろん、ここの住人たちが皆欲に塗れた野蛮人かというと、そうではない。むしろこの街の外で生活している人間たちよりもよっぽど慎ましいということを、佐々山はここ数週間の聞き込みで実感していた。そうであっても……。人間の欲がいつどんな形で暴走するかなんて誰にもわからないのだ。
実際問題、先ほどの銀髪男のような人間が出入りする、それがこの街の偽らざる姿である。そう思うと、今瞳子の側を離れるのは気が引ける。
「お前ねー、あんまこういうとこうろつくなって。こないだ俺言ったよね」
後頭部を掻きながら言うと、瞳子は唇を尖らせてそっぽを向いた。一六歳という年齢の割には幼い抗議の態度に、思わず口角が緩む。
「なに笑ってんのよ」
「いやべつに……」
「キモイ」
不思議なもので、若い女から発せられる「きもい」という言葉には、なんとも言えない攻撃力がある。佐々山もみぞおちあたりをつかれたような思いがして、ぐっと息を漏らす。
「キモイとか言わないでくださーい」
「キモイもんはキモイじゃん」
「なんだてめー。逮捕すんぞ」
佐々山が緩く拳を持ち上げると、瞳子はギャーギャーとわめく。一挙手一投足に対する反応がいちいち大きくて、なんだかそういうおもちゃみたいだ。
そういえば、初めて瞳子にあったときも、彼女のことを新しいおもちゃみたいだと思ったのだった。再会に少しばかり気分が高揚する。
「っていうか、そこどいてよ! 写真撮りに行くんだから」
瞳子の言葉に高揚していた気持ちが途端に冷めて、佐々山は彼女の右腕を強くつかんだ。
「ったー!」
「写真ってお前……さっきの男か?」
「なんでもいいでしょ」
絶対に駄目だ。
「絶対に駄目だ」
「はあ?」
「知り合いか」
「ちがうけど」
「なら金輪際一切あいつに近づくなよ」
「なんで――っていうか、痛いんですけど」
自分で思っていた以上に強く瞳子の腕をつかんでいたらしいことに気がついて、佐々山は慌てて手を離す。
なんで、と言う彼女の問いに答えるのは難しい。血の臭いなんてことを言っても、理解できるはずがないし、何より無知な瞳子にとってその言葉が、あの男に対するさらなる興味を呼んでしまう可能性もある。
「あんなひょろ男より、俺の方がずっといい男だろ?」
とりあえずそんなところでお茶を濁した。
「はあ? バカじゃないの?」と言いながら自分の腕をさする瞳子に、すでにあの男を追う意志がないことを確認すると、佐々山は一息つく。
「ていうかお前、ここで俺にあってそのまま写真撮ってられるとか思うなよ?」
瞳子の動きが止まり、上目遣いで佐々山を見る。
「やっぱり……?」
「たりめーだ! 補導だ補導!」
途端に瞳子は佐々山に取りすがって懇願する。
「えっやだやだ! お願い見逃して!」
鼻頭を赤く染め、瞳を潤ませているが、その必死の表情がある種のパフォーマンスであることは明白だ。その程度で大人の男を籠絡できると思っているあたりが、愚かだ。
「おねがい! 次補導されたら、私謹慎になっちゃう!」
「謹慎結構。お前みたいなお転婆は謹慎食らってちょうどいいくらいだろ」
そう言うと先ほどよりは優しく、瞳子の腕をつかんだ。そのとたん、瞳子は身を翻して佐々山腕を払いのけ、階段を駆け上がる。
「おいバカッ!」
振り返るとちょうど目の前を、瞳子の白い太ももが登っていく。ここで目を逸らすほど佐々山は初心ではないが、かといってむやみにその足に飛びつけるほど無遠慮でもない。両手を行き場なく宙に浮かせたまま、佐々山はとりあえず瞳子のあとを追った。
段差の関係で、常に瞳子の臀部が佐々山の目の前で揺れる形になる。こうなるともはやどこをどう摑んでいいのかわからない。
「ついてこないでよ!」
「いやそういうわけにもいかねーんでな」
「てか、どこ見てんのよ!」
「ケツだケツ!」
「変態!」
「うるせぇ! 階段を降りなかった自分を責めろ! 俺は悪くねぇ!」
冬の寒空に二人の階段を駆け上がる足音が響く。
女子高生の脚力が、現役刑事のそれにかなうわけもなく、延々続く上昇運動に瞳子の足はすぐにもつれ始めた。全力疾走に向かない瞳子の硬いローファーの片方が脱げ、鉄骨階段の隙間から地面へ向けて落下する。
「あっ――」
ローファーを目で追う仕草が瞳子の体勢を崩れさせ、勢い後方に倒れかかる。
佐々山は瞳子の細い腰を片手で抱き留めた。
「はい、ゲームオーバー。おとなしく帰りましょうかね、お嬢様」
気の強い瞳子のことだ、すぐにでも佐々山に罵詈雑言を浴びせ反撃するかと予想したが、それに反して、瞳子は黙ってうつむき肩を震わせていた。
「おい……。どーしたぁ? 大丈夫かよ」
佐々山の問いかけにも答えない。こりゃ、泣いてるな……と、イヤな既視感が襲う。佐々山の経験上、黙って泣く女は、見渡す限りの地雷原と同じぐらい質が悪い。どこに足を踏み入れてもたいがい爆発する。
佐々山はこれ以上ない慎重さで、瞳子の震える肩に手を置き、ゆっくりとその顔を覗き込んだ。その瞬間、
「何よっ!」
瞳子が怒号とともに、佐々山のみぞおちに正拳を食らわせた。
「どぅおっ!!」
所詮女子高生の繰り出す一発だが、完全な不意打ちだったためそれなりの衝撃がある。痛みと驚きに口をぽかんと開けながら瞳子の顔を見ると、そこには涙一滴の影もなく、ただ二つの丸い瞳が、憤りに光っていた。その輝きに佐々山は再び高揚する。
うまく不意を突けたと思ったのか、瞳子は今度は階段を駆け下りようと佐々山の体躯を押しのけるが、勿論佐々山もそれを見逃すようなことはしない。
「はい、業務執行妨害確定ね」
と、瞳子の首根っこをつかんだ。
業務執行妨害などという概念は、ドミネーターによる犯罪捜査が一般的になってからは廃れてしまってはいたが、その仰々しい響きは無知な女子高生一人震え上がらせるには十分な効力があったらしい。
「し、死刑……?」
母親に運搬される子猫のようになった瞳子が、ゆっくりと顔だけを佐々山に向けて聞いた。
その問いの幼さに、言いようのない郷愁が沸き上がり、思わず表情がほころぶ。
もう少し、この少女の無知な怯えを堪能したいと厳つい表情を保とうとするのだが、堪えきれずついには声を立てて笑う。膝に力が入らず、鉄柵に身を預け、それでもなお笑いは収まらない。視界の端に瞳子の怪訝な表情を確認しながらも、佐々山は沸き上がる笑いを止められなかった。
自分の止めどない笑い声に戸惑いさえ覚える。なにしろ佐々山はここ一ヶ月、ほとんど声を出して笑うということをしていなかったのだ。
あの知らせを受けてから、とてもじゃないがそんな気分にはなれなかった。
しかし今自分は、笑っている。そのことに自己嫌悪さえ感じているというのに、それでも外れてしまった感情の箍を、再び締めることはできない。
目頭に熱い液体が沸き上がってくるのを感じて、佐々山は慌てて顔を伏せしゃがみ込んだ。
この液体がなんなのか、今は考えたくない。
「ねえ……大丈夫?」
急に体勢を変えた佐々山を訝しんだのか、瞳子も隣にしゃがみ込み佐々山の顔を覗く。
瞳子の丸い膝の上に乗っかった柔らかい頬は、冬の風にさらされまるで食べ頃の果物のように赤く染まり、その表情にはすでに、自身の裁定の行方に対する不安は存在せず、ただ佐々山への気遣いがあるだけだった。
その眼差しに、再び熱いものがこみ上げそうになるのを必死でこらえながら、佐々山は瞳子の頭を二回、優しく叩いた。
「なんでもねぇよ」
「あっそう……」
「あと、死刑にはならねぇから安心しろ」
「そ、そうなの……」
自分の取り越し苦労に気づいたのか、瞳子は視線をうろつかせながらも平静を装う。
佐々山はその様子を、素直に、可愛らしいと思った。
「ほれ」
コートを脱いで、瞳子に差し出す。
「なに?」
「それ腰に巻いとけ。パンツ見えるぞ」
「はあ?」
「おぶってやるから。それじゃあ歩けないだろ?」
瞳子の靴の脱げた片足を、顎で指す。
「いい……。私重いし……」
「何キロ」
「は? 言うわけないじゃん」
「いいから乗れ、ほら。小太りの女子高生一人くらいどってことねえから」
瞳子のローキックを受けながら中腰に立ち上がると、彼女に背を向ける。瞳子は、佐々山の背中を見つめ、ただ黙っていた。
もはや、補導に対する抵抗は無駄だということを、瞳子はわかっているようだった。しかし、それでも、抗いたい気持ちが彼女を石のように黙らせている。その葛藤が手に取るように伝わってきて、佐々山の胸中に憐憫の情を湧かせた。
彼女に、何か、伝えなくては、と思う。
職務上の必要に迫られたわけでも、青少年健全育成という社会通念に突き動かされたわけでもない。ただ、今目の前にいる、無知で、純真な存在が、なんらかの過ちのために傷つくことが、今の自分には耐えられないという予感があった。
佐々山はゆっくりと上体を起こし、瞳子を見据える。
瞳子ぐらいの年齢の人間に、嘘や、打算は禁物だ。ただ必要なことを、必要なだけ伝えるのがいい。佐々山は自身の、まっとうとは言えなかった思春期に思いを馳せながら、慎重に言葉を紡ぐ。
「俺も、お前がただの潜在犯なら見逃すさ。でも、違うだろ? お前は潜在犯でもなんでもない。ただの健康な未成年だ。そういう奴が、わざわざサイコ=パスを曇らせようとするのを見過ごすほど、不真面目じゃないんでな」
思っていたよりずっとぶっきらぼうな物言いになってしまったことに、自分の不器用さを呪う。過去自分に接してきた大人たちも、こんなふうに思いあぐねてきたのかと思うと苦笑を禁じ得ない。次の言葉を探して視線を泳がせていると、瞳子のほうが口を開いた。
「でも……」
「ん?」
「何かを犠牲にしてでも、手に入れたいものって、あるでしょ……?」
犠牲という言葉と、少女の幼さはあまりにも釣り合わない。幼い彼女はまだ、自分の価値を自分で計れないのだ。だからこそ、犠牲などという言葉が軽々と口から出る。
そのことがほんの少し佐々山の神経を波立たせ、先ほどまで大事に抱え込んでいた慎重さは、すぐに霧散した。
「犠牲なんて、そう簡単に引き合いに出すもんじゃねぇよ。特に、お前みたいな、まだ何が大事かもはっきりわかんねぇガキはな」
よせばいいのに相手の神経を逆なでするような言葉ばかりが口をついて出てしまう。佐々山は自身の不器用さに加え、短気さも呪った。
「私はガキなんかじゃ」
「ガキだ」
「私にだって、何が大事かぐらい」
「わかってねえ。少なくとも、自分を大事にできねぇやつに、何が大事かなんて語る資格はねぇんだよ。そんで、そういうヤツを、ガキっていうんだ」
我ながら偉そうに講釈たれるもんだ、と佐々山は胸の中で独りごちた。瞳子の表情が、しょげかえっていくのに同調するように、佐々山の心に自己嫌悪が広がっていく。
瞳子の主張を、若さ故の愚かさと断罪するのは簡単だ。しかしそれをできるほど、自分自身が大人ではないことを佐々山は自覚していた。
必要な犠牲と称して、ただただかなぐり捨ててきたものの数々が脳裏をよぎっては消える。
沈黙の中、瞳子の鼻水をすする音がいやに頭に響いて、もう何を言っていいのかもわからなくなって、とりあえず「なんか……わりぃな」と詫びる。
「説教したあと謝るのって、なんか自己満っぽくてむかつく」
少女に、自分の中にある後ろめたさを見事に見抜かれて、佐々山は胸をつかれた。
「おう……わるい」
「また」
「あ、」
「もういい」
「そうか……」
瞳子の切り返しに思考回路は完全にショートし、佐々山はただボンヤリと夜空を見上げた。
「変なの」
急に黙り込んだ佐々山を見咎めて、今度は瞳子が口を開く。
「あ?」
「あんたの方が謝って、私がもういいって言うなんて。何か逆じゃん」
「あー、まあ、そういうこともあるさ」
「変なの」
彼女の前では、自分の何もかも見透かされてしまうような感覚にとらわれて、もはや弁解する気力もない。
「世の中ってのはそういうもんだ」
適当に話を切り上げたい一心で、大人の常套句を口にすると、後ろめたさを隠すようにタバコに火をつけた。
白い息と混じり合う煙を目で追いながら瞳子が続ける。
「大人はずるいよね。子ども相手だと思って、すぐわかったようなこと言ってさ。子どもにはわかんない、大人の世界のことだって。そうすれば子どもは手も足も出ないと思ってる」
「……」
「だからちょっとでも子どもが大人の世界に顔を出すと、目くじら立てて怒るんだ。『あなたのためを思ってなんて』言ってるけど、全部嘘。大人が作り上げた安全地帯に踏み込まれるのが嫌なだけのくせに」
瞳子の言葉は、たしかに真実のある部分を射貫いている、と佐々山は思った。
大人は大人、子どもは子ども、そう境界線を引くことで初めて大人は子どもと対等に渡り合えるのだ。それは、大人にとって子どもが、脅威だからに他ならない。
佐々山の後ろめたさを瞳子が一瞬で見抜いたように、子どもは時としてその純真さで、大人がひた隠しにしてきた不都合な真実を探り当てる。それが恐ろしいから、子どもを隔離するのだ。自分とはほど遠い対岸へ。そうでなければ、この世界は居心地が悪すぎる。
ふいに狡噛の姿が浮かんだ。
純粋で真っ直ぐな光。その光に露わになる自分の影。
まさかこの状況で狡噛のことが思い浮かぶとは。思いも寄らぬ自分の思考に動揺する。
しかしたしかに、この少女は狡噛に似ている。いや、狡噛がこの少女に似ているのだろうか。いずれにせよ、自分が持ち得ない光を二人が持っていることは間違いない。
相対するにはあまりにも強烈で、影に隠れたり屈折させてみたり、様々な方法で直視を避けては来たが、それでもやはりその光を見たいと思わせる。
そういう魅力が彼らにはあるのだ。
要は狡噛もガキってことだな、と内心悪態をついてはみるものの、それがいかに白々しい行為か、佐々山はわかっていた。
自分は、その光を尊いと思っているのだ。
守るべき、失いたくないものだと。
「お前は大人になりたいのか?」
狡噛のようにバカ正直に純真でいることは難しい。きっと、彼女が大人になってしまったら、その輝きの大半は失ってしまうのだろう。そう思うと、背伸びする彼女が今までにもまして儚く愛おしい存在に見えて、思わず質問する。
「わかんない」
という答えに、少しばかりの猶予を感じて、煙に紛れて息をついた。
「でも、同じ世界にいたいの。共有したいの」
そう言った瞳子の瞳に熱がこもったのを、佐々山は見逃さなかった。途端に下世話な好奇心が頭をもたげてくる。
「なんだ、男か」
「べつに……。なんだっていいでしょ?」
寒さに赤く染まった頬を、さらに赤くする瞳子が可愛らしい。
「へー、図星か」
にやつきながら顔を覗き込んでくる佐々山から逃れるように、頭を大きく振る。その様子が佐々山のいたずら心に火をくべる。
「目当ての男がこの辺にいるんだな? まさか、さっきの銀髪か?」
だとすると、かなり問題があるが、瞳子の「ちがうわよ!」という返答に安堵し、追求はさらに加速した。
「なんだ? だれだ?」
「うっさいなー」
「桜霜学園のお嬢様が、廃棄区画なんぞにゆかりのある男にご執心とはね。どこで引っかけられたんだよ」
「引っかけって……! 先生はそんなんじゃないわよ!」
「先生?」
「あぅ……」
自分の失態を悔いながら、瞳子は唇をまごまごと動かす。
「先生。学校の?」
「うるさいうるさいうるさいっ」
「なんだって教員が扇島なんかに……」
「もうっ! いいでしょ?! 補導するならさっさとしなさいよ!」
「ありゃ。いいの?」
「だめって言ったって、するんでしょ」
「まあな」
「はやくおんぶして」
「なんだよ急に素直になって」
「だって……どうせ無理だもん」
「何が」
「さっき自分で言ってて気づいちゃった。先生は結局、私みたいなガキは邪魔なのよ。自分の世界に踏み込まれたくないんだわ。だから……」
そこまで言って口をつぐむ。目の前の変な男に煽られて、余計なことに思い至ってしまった、と瞳子は歯噛みした。
どんな写真を見せても、「つまらない」としか言わない藤間。
あれは、面白い写真を撮ったらどうにかなるという類いのものではなく、あらかじめ解の用意された問い。瞳子を自分の世界に連れて行こうなどという気ははなからない。あからさまな拒絶の言葉だったのだ。
「なんだよ。急に黙って」
「はやく、おんぶ」
「ああ?」
「もう、疲れたから……」
本当は、初めからわかっていたのかも知れない。
彼のガラスのような瞳には、自分が映りこむ余地なんか無いんだということを。
それでも彼の微笑みや、自分だけしか知らない彼の週末の秘密が、自分の無闇な期待を煽って、今、廃棄区画に裸足で佇むという醜態に帰結している。そう思うと、途端に夜風は暴力的に身体を冷やし、駆け回った足が鈍く痛み始めて、一人で立っているのもしんどい。
瞳子は、自分の目の前で背を向けてしゃがみ込む男の背中に、素直に身をゆだねた。
「なんだ、軽いじゃん」
「当たり前でしょ」
男は別段力む様子もなくすっと立ち上がると、ゆっくりと階段を下り始めた。
冬の空に、佐々山の鉄階段を下りる足音が響く。
背負う荷物を傷つけないように、ゆっくりと歩みを進める。
佐々山の背面で、瞳子の前面で、お互いの体温が交換される。その温もりが、両者の思考を少しだけ弛緩させて、不思議と言葉数を増やした。
「そいえばこないだ、お前、データスティック忘れてっただろ。俺、いつでも返せるようにって、持ち歩いてたんだぜ? あとで渡す」
「いらない」
「は?」
「もういい」
「なんでだよ。あんたにたくさん撮りためてんのに」
「どうせ私の撮る写真は、つまんないもん。先生は見向きもしてくれないし」
「ああ、お前の想い人ね」
「べつにっ……ただの写真部の顧問だよ」
「ああそう」
「むー……」
「で? その写真部の顧問がお前の写真つまらないって?」
瞳子の強がりも、かつてほど佐々山を拒絶しない。佐々山はこともなく質問を続け、瞳子もゆっくりとそれに答える。
「そう……。だからね、私、どうしてもその人が興味持ってくれるような写真が撮りたくて……それで……」
「こんなとこうろついてたわけか」
「先生はね、毎週末になると教員宿舎を抜け出してここに来るんだ。だから私も、ここにきて、ここの写真を撮れば、少しは先生の気を引けるんじゃないかって……思ったんだけど……なんかやっぱ……ね」
瞳子の吐息が、佐々山の首元にかかる。それが余りに暖かいので、彼女にこんな息をはかせる写真部顧問に、佐々山はほんの少しの敵意を覚えた。
「お前の写真、そんなに悪くねぇよ」
「あんただって、こないだぼろくそ言ってたじゃん!」
「そりゃ、へたくそだとは言ったけどよぉ。つまらないとは思わないぜ?」
「え?」
「いいじゃんなんかさ、必死になって、何でもかんでも写そうって言うのがさ。自分の世界全部写真にしちまおうって気迫があってさ。お前らしい、面白い写真だと思うよ俺は」
「私らしい?」
「なんか、必死っていうか、背伸びしてるっていうか」
「全然面白くないじゃん!」
「いや面白いよ。そういう必死さって、意外とすぐになくしちまうもんだし」
佐々山の脳裏に、再び狡噛の姿が浮かぶ。
「お前は、大人の世界を共有したいなんて言うけどさ。俺からすれば、お前のそういう気持ちそのものが、貴重っていうか……。隣の芝生、みたいなもんかな」
「隣の芝生?」
「要はうらやましいって話。こんなに欲張りな世界の切り取り方、もう、俺にはできねぇから」
自分から出てくる言葉の素直さに、驚く。ここ数週間自分の底に溜まっていた澱のようなものが、いつの間にかふんわりと溶けて無くなってしまったようだ。
そのくらい、少女の肌の暖かさは、絶大な効力を持っていた。
このままこの暖かさに身を預けていたら、自分はどこまでも優しい人間になれるだろう。
佐々山は自分の現金さに辟易しながらも、今は、この心地よい感覚に全てをなげうって溺れていたいと思った。
「だからそのセンセーっちゅうのも、案外嫉妬してだめ出ししてんのかもよ?」
これが、真実だという保証はどこにもない。しかし安易な方法であっても、彼女を少しでも元気づけられるならそれに越したことはないのだという確信が、佐々山の舌先を滑らかにする。
「えー……ありえない」
そう言う彼女の声色に、少しばかり生気がみなぎるのを感じて、佐々山は安堵した。
「おお、あったあった」
外付け鉄製階段の下の、物置のように段ボールが積み上げられた一角に、瞳子の黒光りするローファーはあった。
瞳子は佐々山の背中から飛び降りると、片足で弾みながらローファーの元へ駆け寄ったが、自分の足下の相棒が、不吉な色をした排水に濡れているのを見てその場で立ち止まった。佐々山はそんな瞳子の様子に、躊躇することなくローファーを拾い上げると、ポケットからくしゃくしゃに丸められたハンカチを取り出して丁寧に汚水をぬぐい、まるでシンデレラにでもするかのように、瞳子の前に跪き恭しく小さな足をその靴に収めた。
瞳子の「ありがとう」というつぶやきが、佐々山を満足させる。
やはり、女性に傅いているときが一番心が和む。そんな現金な思いに口角をゆるませながら、佐々山は扇島の喧噪の中、瞳子を伴い歩いた。彼女の歩幅に合わせて、ゆっくりと。
「おじさんはさぁ」
佐々山のコートの裾を遠慮がちにつかみながら瞳子が口を開く。
その声色に、出会った頃の険はもはやない。
「おい……おじさんはやめてくれヘコむ」
「えー」
「佐々山だ。佐々山光留」
瞳子は口だけ何回か、「ササヤマミツル」と動かすと何かを納得するように頷き微笑んだ。
「光留さんは、カメラ詳しいの?」
ファーストネームにさん付けという呼び慣れない呼称に、佐々山の体温が少しだけ上がる。しかしその呼称以上に、カメラに対する問いが、佐々山の心の深部を鈍く打つ。
今もまだ処分できない大量の写真のことが、佐々山の脳裏をよぎる。
「くわしかないさ。昔、ちょっとやってたぐらい」
あまり歓迎できない話題を早々に切り上げようと、適当に興味ないふうを装う。しかし、瞳子はそんな佐々山の防壁を易々と飛び越えてくる。
「えー。その割には偉そうなこと言ってたよね」
自分の軽口を呪いながら、瞳子の指摘に素直に降伏した。
「お前は基本ができてなさ過ぎんだよ」
「だって、だれも教えてくれないんだもん」
「その、先生とかってのは?」
「写真見せても、つまんないとしか言ってくれないし……」
そういってうつむきながら唇を尖らせる仕草を見て佐々山は、やはりその写真部顧問は気にくわないと思った。
彼女の尖った唇に、諦めきれないという意志が滲む。ようは、佐々山に写真撮影のイロハを教えて欲しいということなのだろう。
先ほど瞳子を鼓舞するようなことを言ってしまった手前、このまま彼女の意志を無視することはできない。
心に鈍い痛みを感じながらも、佐々山は手を伸ばした。
「まあちょっと、カメラ見せろ」
「はい」
期待に満ちた瞳を佐々山に向けながら、瞳子は従順にカメラを手渡した。
ずしりとした重みが佐々山の掌に広がって、心をじんわりと震えさせる。
甘い記憶の数々が蘇って、しっかりと踏ん張っていないと目眩を起こしそうだ。
「まずさー、マニュアル操作にしてる時点で、間違ってんだよなー。素人なんだから、フルオートでいいじゃん」
「だってなんか……それじゃあ、私が撮ってるって感じがしないんだもん。私が見たまんまを撮りたいんだもん。一眼レフって、それが出来るカメラなんでしょ?」
言い返す瞳子の様子に、佐々山の記憶のいくつかが呼応して、ますます心を痺れさせる。
「なるほどね。ほんとに強欲だなお前は」
「さっき、そこがいいって言ったじゃん」
記憶の海にこれ以上足を踏み入れたら危険だと思いながらも、その甘い誘惑に逆らえず歩みを進める。進んでみればやはり心地よく、自分の口先がどんどん軽やかになっていくのを佐々山は実感した。
「ったく、しょうがねえなぁ。いいか、まず写真ってもんが、どういうもんかってことを考えないといけねぇ。写真ってのはな、レンズを通して、いかに光を取り込むかってのがみそなんだ。明るく撮りたきゃ、絞りを開けて、シャッタースピードを遅くする」
「絞り?」
「んなこともしらねぇのかよ」
「だからわかんないって言ってるじゃん!」
男の拳大ほどあるレンズを取り外して、瞳子に覗かせる。佐々山も瞳子の目線に寄り添うように顔を寄せ、透明なレンズを覗く。
佐々山がレンズの外周をなぞると、円筒の奥で六角形の穴が大きくなったり縮んだりした。
「よく見てろよ? 六角形の穴みたいなもんがでかくなったり小さくなったりしてるだろ? これが絞りだ。これが広がれば広がるほど光を多く取り込めるわけだから、明るい写真が撮れる。逆に絞れば暗くなるわな。シャッタースピードもようは、どのくらい長い間光を取り込むかっていうことだ。シャッタースピードを遅くしてより長く光を取り込めばその分写真が明るくなると」
「じゃあ、絞りを広げて、シャッタースピードを遅くしといた方がいいのね?」
「いや、あんまり明るくしすぎると、画面が光で真っ白になっちまう。絞りとシャッタースピードをうまいこと組み合わせて、撮りたい写真を撮るってことだ」
「撮りたい写真」
「そ。お前が感じたままの景色が撮れる。自動で補正された景色じゃなくて。マニュアル撮影ってのは、そういうことだ」
そこまで一気に説明して、佐々山は一息ついた。
もう何年もカメラを手にしていなかったが、自分でも驚くほどよどみなく言葉が出た。
このたぐいの質問には、かつて何度も答えていたのだ。その記憶に課した封印は、瞳子の前にあっさりと解かれてしまった。
「かしてっ」
呆然とする佐々山の手元から、瞳子はカメラを奪い取り、高揚にゆるむ口元を隠すことなく、喜々としてファインダーを覗き込んだ。
シャッターを押しては、撮った写真を画面で確認するという作業を何度も繰り返す。そのうちに、瞳子の喜びの表情は次第に曇り、唇が不満げに突き出る。
「なんかうまくいかない……。どの数値にしたらどういう写真になるのかわかんない……」
この不満も、佐々山はかつて何度も目にしていた。
既視感から来る余裕が、佐々山の声色を優しくする。
「それはもう、撮って撮って撮りまくって、自分の感覚にしてくしかねぇよ。大丈夫、こんだけ大量の写真が撮れるんだ。すぐ摑めるよ」
瞳子の瞳に佐々山に対する尊敬が宿る。
「そっか……。光留さん、すごいね! ねえねえ! 何か写真撮ってみてよ!」
そう言うと佐々山の胸元にカメラを押しつけた。
このやりとりにも、覚えがある。しかし今は拒絶よりも、このまま甘い既視感にとらわれていたいという欲求が佐々山を駆り立てる。
ゆっくりと、カメラを構える。
ずしりとした感覚が、掌に力をみなぎらせる。
ファインダーを覗けば、そこには懐かしい景色があった。
肉眼で見るのとは違う、しかし何よりも世界の真実に近い景色。
被写体を求めて、視線を走らせる。
道行く人々、屋台から立ち上る煙、騒がしいネオンと、その先に浮かぶ白い星。
十分に吟味した上で、佐々山は瞳子にその照準を合わせた。
ファインダー越しに瞳子と目が合う。
彼女は意外そうに目を丸くしたが、すぐに観念して照れた笑いを浮かべた。
弾力ある彼女の髪が風になびき、鼻先で踊る。
その髪を片手で押さえ、恥ずかしそうに視線を泳がせる。その視線が、レンズと邂逅した瞬間に、佐々山はシャッターを切った。
ホッと息をゆるめる。
瞳子は「見せて見せて!」と佐々山からカメラを奪うと、すぐに液晶画面で写真を確認した。
画面の中で微笑む自分の姿に、感嘆し思わず
「かわいい……」
とつぶやいた。不意に出たナルシスティックな発言に自分で驚いて、慌てて訂正する。
「ち、違うよ! 変な意味じゃなくて、なんか普段の私の写真とはちょっと違う感じ……っていうか……」
まごつく瞳子を見ていると、佐々山の嗜虐心が妙に疼く。
「そうか? 俺にはこんな感じに見えてるけどな」
わざと、渋めの声色で優しく語りかけると、瞳子は期待通りに頬を赤らめた。
「なんか……光留さんて、キザだね」
「惚れるなよ?」
「馬鹿じゃないの?」
にやつく佐々山にぴしゃりと言ってのける。
「すいませんね」
「でも……」
カメラを目の前に掲げて、嬉しそうにつぶやく。
「うん。なんか、いい写真撮れそうな気がする」
満足げな瞳子の姿が、佐々山の目にも嬉しい。
「そっか。じゃ、まずは自分の身の回りのもんを撮ってみろ。こんなとこ、もう来るなよ」
そういえば元々は瞳子に説教しようとしてたんだった、と不意に思い出して慌てて補足する。不用意な進言が再び瞳子の反抗心に火をつけやしないかと案じたが、その不安をよそに瞳子はおとなしくうなずいた。
安堵に佐々山の足取りが軽くなる。瞳子自身も、自分の思いの丈を吐露できた安堵感からか、表情は柔らかく、その足下は今にも弾みだしそうに軽やかだ。
「しかしまあ、その先生ってのも妙な奴だな」
「うん、なんかすごい、不思議な雰囲気の人だよ」
「こんなかわいい子が必死になってアピールしてるっていうのに見向きもしないでな」
「ほんとだよ」
お互いの軽口に声を立てて笑う。先ほど一人で扇島を巡っていたときには、自分にこんな安らかな感情が到来するとは思ってもいなかった。自分が恐ろしい事件の調査中だったことを思い出して、はたと立ち止まる。軽やかな気持ちの中に、若干の異物感を感じる。
「でもほんと……、扇島なんかに来て、何やってんだ?」
佐々山の問いに、瞳子はきょとんと首をかしげてみせた。
突如、二人の間に電子音が響く。
佐々山の左腕にはめられた執行官用デバイスが、狡噛からの着信を告げている。
気がつけば再集合時間から三〇分もの時間が経過していた。
くすんだ色を湛えた人混みの中から、佐々山の少し明るめの短髪が覗いて、狡噛は思わず駆け寄った。ここ一ヶ月の佐々山の行動を見れば、『逃亡』という万が一の事態も想定せずにはいられない。その想定が杞憂であったことは狡噛を安心もさせたが、それに呼応して苛立ちが増す。
「おいっ、何してたんだ集合時間はとっくに……」
「わりぃわりぃ」
狡噛の叱咤を、佐々山はどこ吹く風というように片手で制した。どこまで行ってもこの男は、監視官の苦労など顧みるそぶりもない。
「あれー? とっつぁんは?」
「とっくに護送車に下がらせた。お前は俺達を凍死させる気か」
そう言って佐々山に詰め寄ると、彼の背後で見覚えのある黒髪が揺れた。
桐野瞳子だ。
相変わらず、廃棄区画に名門女子校の制服というそぐわない出で立ちで、ばつが悪そうに佇んでいる。
「素行不良少年の補導案件が発生してたんでな」
遅刻の理由はこれか、と溜飲を下げる。不届きな理由でなかったことは評価すべきだが、それでも寒風吹きすさぶ中三〇分も野外で待ちぼうけ食らわされたことには変わりない。怒りの矛先を順当に向け直そうと少女を睨むと、彼女はそそくさと佐々山の背後に顔を埋めた。
狡噛の険を含んだ視線に気がついたのか、佐々山が先回りして狡噛を諭す。
「はいはい、もう説教は俺がひと通り済ませておいたから」
この短時間で二人はずいぶんな信頼関係を築いたようだ。あいかわらず佐々山の、女性とのコミュニケーション能力には驚かされる。これ以上自分が少女に何を聞いても無駄だと悟り、狡噛は黙って補導手続きを始めた。
デバイスから、少女に関する情報を引き出し、非行履歴を確認する。
過去二回、今日を入れれば三回目の補導だ。名門女子校の校風というものがどんなものなのか、狡噛には見当もつかないがそれでも彼女の行動が明らかに異様だということはわかる。青少年の健全育成は狡噛の領分ではないが、それでも少女の行く末に一抹の不安を覚えた。
「これから学校に連絡するから」
狡噛の言葉に、少女はわかりやすくうなだれた。こんなふうにしょげかえるなら初めから深夜徘徊などしなければいいのだ。
真面目が服を着て歩いているような狡噛には、瞳子も佐々山も、理解できない存在だった。
だからこそ今目の前で寄り添うように立っている佐々山と瞳子の間にどんな関係が結ばれているのか、それを思うと妙な疎外感を刺激されてもどかしさが募る。
進まない捜査、好転しない佐々山との関係、それら全てが自分の理解できない理屈に起因しているような気がして、たまらない無力感に襲われる。
その無力感から逃れようと。狡噛は瞳子の資料に当てもなく目を落とした。
桐野瞳子、イタリア系準日本人アベーレ・アルトロマージを父に持つ混血児。
幼少時から桜霜学園に入学、今に至るまで学園生としての経歴を積む。
夏期休業前のサイコ=パス検診では特に問題となる数値は検出されず。
それ以降の測定記録無し。
目立つ非行履歴もなかったが、今年一一月に入ってから二度の補導歴有り。
一度目は、一一月五日未明。赤坂の廃棄区画周辺で巡回ドローンにキャッチされている。
二度目は前回、一一月二四日夜。狡噛と佐々山が扇島解体業者と現地住民のいざこざの鎮圧にかり出された日。
狡噛の背筋に、ぞわりとしたものが走った。
一一月五日未明、一一月二四日夜、いずれも目下捜査中の標本事件の被害者が発見される直前である。
突然の気づきに高鳴る動悸を押さえようと頭を振る。
まさか。
瞳子が補導された日と、被害者の発見された日、これらを結びつけるのはあまりにも短絡的すぎる。それは冷静にならずとも十分に理解できる。
しかし。
女子学生がわざわざ廃棄区画に足を踏み入れる不自然さ。
そして「赤坂」という妙な符号の一致。
夏期休業以降、目立ち始めた瞳子の非行行動。
偶然で片付けるには、あまりにも意味深である。
征陸の言葉が、耳の奥でこだまする。
「情報なんざ、そのうち勝手に飛び込んでくるもんさ」
それが今なのかも知れないという予感が、狡噛の思考を加速させる。
短絡的すぎるかも知れない、浅はかかも知れない、しかし現に狡噛は自分の理屈が及ばぬ人間の存在を目の当たりにしている。ならば、理屈を超えて結びつく符号があってもいいはずだ。
単純な思いつきに飛びつく自分を正当化するために、狡噛は思考を尽くした。
麻雀卓を囲みながら執行官たちが導き出した犯人像を反芻する。
芸術家気取りの青二才。
瞳子の首からぶら下がる、少女には余りに不釣り合いなプロ使用の一眼レフカメラを目にしたとき、狡噛は決心した。
先刻感じていた無力感は、どこかに消え失せていた。
「佐々山……」
緊張で声が震える。
佐々山は、狡噛の異様な様子に怪訝そうに顔を寄せてくる。そんな佐々山に、瞳子の補導履歴のデータを指し示す。しばらくの間があって狡噛の意図を理解したのか、佐々山は目を見開いた。
佐々山の表情の変化を確認すると、狡噛は素早く背面のホルスターからドミネーターを引き抜く。
もちろん、ドミネーターの向く先は瞳子だ。
ドミネーターの起動音が脳内に響き、シビュラに直結されたシステムが瞳子の犯罪係数を割り出そうとしたそのとき、
「おい! 馬鹿、何すんだやめろ!」
怒号と共に佐々山がドミネーターを押さえつけた。
「何するんだ! 離せ!」
「それはこっちの台詞だ! 未成年にいきなりドミネーター突きつけるなんて、正気か?」
佐々山の手の中でドミネーターが軋む。狡噛はドミネーターを引き抜こうと上体を回転させるが、佐々山は執拗に食らいつく。
「確認するだけだ! 彼女の行動はあまりにも不審すぎる」
「だからってなぁ!」
「潔白ならば何の問題もないだろう!」
「未成年の色相はただでさえ不安定なんだ。それをこんな形でドミネーターを突きつけられて、色相に影響がないとは言えないだろ?!」
たしかに佐々山の言うことは正論だ、正論だが、さんざん非協力的な姿勢を見せておいて正論をぶつけられても、反発心しか沸かない。
ドミネーターを離さない佐々山を身体ごとひきよせて睨みつける。
狡噛の視界の端に、二人の様子を脅えた表情で見つめる瞳子が映る。その儚げな様子は、情に厚い佐々山にさぞ訴えかけただろう。
「妙にかばうんだな。情に流されやすいのもいい加減にしろよ!」
「馬鹿野郎! そんなんじゃねぇよ! こいつはあの事件には無関係だ!」
この数週間、狡噛は事件調査に心血を注いできた。
初めから成果を期待されていないであろう無戸籍者の身元特定という案件であっても、そこになにがしかの手がかりがあると言い聞かせ、自らを鼓舞し、終わりの見えない聞き込み作業をまっとうに遂行してきた。
しかし佐々山はどうだ。
その態度はやる気のなさを雄弁過ぎるほどに語り、聞き込み件数は他のどの執行官よりも少なく、ただタバコを空にしては公安局に戻る日々。
そんな佐々山が、確信めいてあの事件を語ることが、今の狡噛にはいかにも腹立たしい。
狡噛の喉元に激しい怒りがこみ上げてきて、呼吸を圧迫する。
震える息で意地悪に問いかけた。
「何を根拠に」
根拠など、佐々山が持つはずはないのだ。少なくとも、今自分が瞳子にドミネーターを向けるのを阻止するだけの根拠など。
狡噛は、佐々山が自分の問いにたじろぐに違いないと思った。
しかし、佐々山は狡噛の期待には応えず、真っ直ぐと視線を定め告げた。
「刑事の勘だ」
途端に、馬鹿馬鹿しいという思いが狡噛の思考を塗りつぶす。ろくに刑事らしい仕事をしていない佐々山の口から「刑事の勘」という言葉が出たのだ。そのことが自分の理論的優位性を補完したように思えて、狡噛は冷笑した。
しかし次の瞬間に、狡噛は自分の表情を悔いた。
他者は自分を映す鏡だ。
だとすれば佐々山の顔に浮かぶ表情が、たった今狡噛が犯した過ちの全てを映し出していた。
佐々山は、怒ってはいなかった。
ただ、悲しそうに眉を寄せ、目を細めた。
彼の唇から漏れた「てめぇ……」と言う声にすでに先ほどまでの覇気はなく、狡噛を見据える瞳には、失望が、ほの暗く宿っていた。
こめかみのあたりにじっとりと冷たい汗が噴き出てくるのを、狡噛は感じた。
二人はいまだお互い距離を詰め合い相対してはいたが、その間にあるのは怒りでも敵意でもなく、ただ深く暗い溝だった。
大変なものを反故にしてしまった、と狡噛は思った。
『刑事の勘』は、執行官と社会を、執行官と監視官をつなぐ鎖だ。それを狡噛は、自分から手放してしまったのだ。
謝らなくては、と思うのに、自分のしでかしたことの重大さにすくんで、身動きがとれない。
頬の上を何かがつたって、狡噛はハッとする。
まもなく幾百幾千もの雨垂れが、行き交う人々と狡噛達の上に降り注いだ。
佐々山は降りかかる雨に小さく舌打ちして身を引くと、狡噛の腕からドミネーターを抜き取って背を向け、ゆっくりと歩き出した。
その後ろを瞳子が小走りについていく。
突然の雨にざわつく人混みに、二人の姿が飲まれていく。
今彼らを見失えば、二度と会うことができなくなるのではないかという予感がこみ上げてきて、狡噛は佐々山の名を叫んだ。
移ろいゆくモザイク画のような景色の中で、佐々山の黒い後ろ姿だけがくっきりと浮かび上がり、振り返る。
「濡れるぞ、早く戻ろうぜ」
佐々山の言葉は雨に滲み、視線は狡噛の足下に落ちていった。