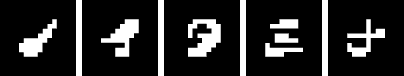NOITAMINA
OFFICAIL WEBSITE
SHARE
ツイート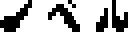 NOVEL
NOVEL
ノイタミナノベル「つり球」 第3話

【前回までのあらすじ】転校続きでコミュニケーションが苦手な男子高校生・真田ユキは、緊張が度を越すと顔が般若のようになってしまう。祖母ケイトとともに新たに引っ越した江の島で、ユキは自称・宇宙人の同級生ハルと出会い、なぜか釣りに誘われる。釣り王子の異名を持つ夏樹に指導してもらうが、そんな彼らを謎のターバンの男・アキラが見張っていた。
「いっただっきま─す!」
晴れ渡る朝の空にハルの声が響き渡った。
ユキの家の表札には、『ハル』という文字が、ユキやケイトの名前を押しのけて大口を開けて笑っている。
こいつ、なんで普通に飯食ってんだ?
ユキはわんぱくな小学生みたいにズズズーっと味噌汁をすするハルを忌々しく見ていた。
「ハル、そんなに音を立てちゃだめよ」
ユキはそう優しく諭すケイトの声を聞きながらさらに気分が沈んだ。自分だけのばあちゃんがハルに半分取られてしまったみたいな気がしたからだ。
「おっ、このお味噌汁、しらす入り! 江の島ってばしらすだよねー!」
ユキは思わず顔をしかめた。ハルの能天気ですっとんきょうな声にはまだ耳が慣れない。
無理もない。ハルが突然この家に押しかけて一緒に住み始めたのは、昨夜のことなのだから。
なんで俺が、こんな奴と……
ユキがその理不尽な同居を許さざるを得なかったのは、大好きなケイトがなぜかそれを望んだからだ。
「ハルが来てくれてよかったわ~」
こうやって時折見せるばあちゃんの能天気さと意味不明さは、自称宇宙人のハルにも全然負けていない。ばあちゃんは時々思いもつかないようなことをして俺を驚かせる。そして一度決めたら決して後戻りはしない。だからこういう時は、抵抗するだけ無駄だ。
今日こそは一人で学校へ行きたいユキだったが、ハルはまるでせっかちな影のように、ユキの前や後ろや隣に忙しく張りついてきた。昨日と同じように、なぜか釣竿をかついで。青空を丸ごと吸い込んだみたいな満面の笑みで。
こいつ、一体何者なんだ?
本当に宇宙人? いや、まさか……
でも、あの水鉄砲。
ハルの腰のベルトには今日も透明で黄緑色の水鉄砲が差さっている。
ユキは思い出す。昨日、教室で水鉄砲を撃たれた。気づくとハルと一緒に知らない踊りを踊っていた。次に撃たれた時は、HEMINGWAYという釣具屋にいた。
あれって、一体なんなんだ?
その時、ハルが突然「ひゃぁー!」と声を上げ、子ザルのようにユキの背中に飛び乗った。
「ちょっ!」
「ユキぃ~、猫怖いよぉ~」
ハルが仲見世通りにたむろする猫たちを見てカタカタ体を震わせている。
ユキはその振動を背中に感じながら思う。
お前の方がよっぽど怖いよ!
江ノ電の中でも、ハルはぴったりとユキにくっついてきた。ユキが恥ずかしくて離れて座っても、すぐにぴったりと距離を詰めてくる。乗り合わせた同じ高校の生徒たちにとっては朝から恰好の見世物だ。
「あれが噂のコンビか」「宇宙人と般若だろ?」
セ、セットにされてる! 頼む。こんな変人、いや、宇宙人と一緒にしないで!
授業中も、休み時間も、異星人の超接近攻撃は収まることはなかった。ノートを写そうと顔を上げると、笑顔のハルが手を振って視界を遮る。休み時間を知らせるチャイムを合図に廊下での追いかけっこが始まる。ギャラリーは徐々に増え、やがて、たった二日目にして注意するのをあきらめた教師たちもその輪に加わった。
あぁぁぁ、もう、耐えられない!
ユキは終業のチャイムを聞くや否や教室を飛び出し、駅までの坂を転がるように駆け下りた。そして江ノ電の中を、長い長い弁天橋を、なりふり構わず走った。それでも涼しい顔で追いかけて来るハルにさすがに恐怖を感じ、ユキは仲見世通りを上り切った先の交番に駆け込んだ。
「す、すいませ……」
勇気を出してそう切り出した瞬間、ユキの目に突然カラフルな物体が飛び込んできた。
そこにいたのは警官ではなく、見たこともない恰好の少女だった。髪は薄ピンク色で、その一部が水色の花みたいな形に染められている。ちょっと大きめのフレームなしの眼鏡、首には浮き輪みたいなマフラー? 上半身は突如セクシーな黒いビキニ、そして古めかしいUFOみたいな形のスカート。
だ、誰!?
その少女はユキを見てニコっと微笑むと、右の太ももに巻かれた布に挟んだ武器のようなものを取り出し、ユキに向けた。
ユキは思わずひるんだが、その武器はひるんだこっちが恥ずかしくなるぐらいの可愛らしい代物だった。黄色い、イルカ?
拍子抜けしたユキがバカだった。
次の瞬間、その可愛いイルカはカチャっと口を開け、ぴゅーっと勢いよく水を噴射した。
あ、これってもしかして、水でっぽ……
気づいた時にはもう遅かった。
「だっ!」
次の瞬間、ユキはやたら視界の広い場所に立っていた。
え、ここって……
何気なく下を見ると、そこには精巧に作られた町のジオラマがある。
え、あれ……江の島?
しかしすぐに気づいた。それはジオラマではなく、現実の江の島だ。
な、なんで!?
慌てて目の前の大きな柱につかまったユキは、気づきたくない事実に気づいてしまった。
そこは江の島を見下ろす展望台。通称シーキャンドルのてっぺんだ!
うわぁ─! た、高い! 死ぬ!
ユキが心の中であらん限りの大声で叫ぶと、柱の陰からハルと、さきほどのカラフル過ぎる少女が姿を現した。
「兄がいつもお世話になっちょります♪」
少女は手と足をゆらゆら動かしながら近づいてきた。それはユキがハルに踊らされた妙な踊りに似ていた。
い、妹!?
少女はユキの疑問などお構いなしに一方的に話し始めた。
「兄から聞いとると思うんじゃが、私んら釣らないかん魚がおるけん、あなたに協力して欲しいんだわー」
方言めちゃくちゃ!
少女はココと名乗った。
ユキは恐怖で徐々に遠のく意識の中でココの言葉を聞いた。
つまりはこういうことらしい。ハルとココには釣らなきゃならない魚がいる。それを釣らないと星に帰れない。だから協力してほしい。もし協力してくれないと大変なことになる。
「た、大変な、ことって?」
やっとの思いでユキがそう絞り出すと、ココは涼しい顔でとんでもないことを言った。
「地球が、滅ぶとです」
は!? ち、ちきゅうが、ほろぶ!?
「それを救えるのは、あなただけなんだてー」
じょ、冗談じゃない! なんで俺が地球を救わなきゃならないんだよ!
ユキは逃げようとしてすぐにそれが愚かな行為だと気づいた。ここはシーキャンドルのてっぺん。逃げることは即、死を意味する。
そしてココに水鉄砲を向けられ、あっさり観念した。
「わかった! やる! 釣りやるから!」
ユキは圧倒的不利な態勢のまま、今日中に魚を一匹釣るという、理不尽な要求を呑まされた。
「約束やで。もし守れんかったら次はスカイツリーの上でっせー」
その時、ずっと妙な踊りを踊っていたハルが「僕も行きたい。スカイトゥリ─!」と叫んで、ユキに水鉄砲を撃った。
「だっ!」
ユキは気づくとまたあのHEMINGWAYの中にいた。もうココの姿はなかったが、厄介な宇宙人がもう一匹残っていた。
「海咲姐【みさきね】ぇー来たよー!」
「あら、偉いじゃん」
海咲が自慢のポニーテールを揺らして言った。
「君は絶対やめると思ってた」
やめたくてもやめられないんです!
「助けてください!」そう海咲に助けを求めればよかったのかもしれないが、ユキは不幸にもよく知らない人と話すことができない。というか、そもそもこの恐怖をどこから説明すればいいのかさっぱりわからない。
店の奥ではエプロン姿の夏樹がユキとハルを見て呆れてため息をついていた。
「あ、王子! 釣り教えてよぉー!」
夏樹にとって『王子』は最大の禁句だ。夏樹は一瞬でピークに達した怒りをぐっとその眼鏡の奥に押し込め、ハルに凄んだ。
「お前、今度それ言ったら、マジで殺す」
ユキは夏樹の醸し出す迫力に驚きながらも、逆に夏樹の身を案じた。
だめだ。そいつには逆らわない方がいい。何を言っても無駄なんだ。言葉も気持ちもまるで通じない。殺されるのは自分の方かもしれないぞ!
ハルはやっぱりハルだった。鋭い睨みで最後の釘を刺そうとした夏樹の意図などお構いなしに、まるでカセットテープを巻き戻したかのように同じ言葉を繰り返した。
「王子! 釣り教えてよぉー!」
一瞬にして鈍感という分厚い壁に押し戻された夏樹は深く息をつき、行き場を失った苛立ちをユキを睨むことで解消しようとした。
いや、違う。俺、仲間じゃないから!
その滑稽ながらも緊迫した状況を、海咲がいとも爽やかに打ち破った。
「教えてあげなよ夏樹。とりあえずシーバスでも狙ってみたら?」
シーバス?
ユキのスマホが答える。『バス(魚)のうち海産のもの』『日本のルアーフィッシングにおいてはスズキのことがシーバスと呼ばれる』。
スズキって言えよ!
「僕もシーバス釣りたい。王子教えて!」
「悪いけど、忙しいから」
夏樹はもはや怒りをあきらめ、無視する作戦に出た。しかしその不機嫌な顔が続いたのは、扉が開いてある少女が入って来るまでだった。
真っ赤なランドセルを背負ったその少女の表情には少し陰があったが、夏樹を見つけるとパっと花が咲いたような笑みを見せた。
「おにいちゃん」
「さくら」
そう返した夏樹の表情はついさっきとは打って変わって穏やかで、その声も嘘みたいに柔らかい響きに変わっていた。
「イモウト?」
「はい」さくらはハルにそう答え、ちょっと驚いたように夏樹を見た。「珍しいね。おにいちゃんがお友達と一緒なんて」
「いや……」
夏樹はまるで恋人に浮気現場を押さえられた気弱な男のごとく、焦り、表情を固くした。
「イエス! 僕ら夏樹のおトモダチ! 僕らこれから夏樹に釣り教えてもらうんだぁ!」
ハルはここぞとばかりにさくらという突然現れた救世主にすがった。
するとさくらの顔にまたパっと花が咲いた。
「へぇ~。おにいちゃん、釣りすっごく上手なんで、きっと釣れると思いますよ」
そう言って夏樹を見るさくらの顔はとても嬉しそうだった。
ユキはそのさくらの視線に、妹という立場を超えた何かを感じた。まるで海岸で光る石を見つけた息子を微笑み、見つめるような。
そして夏樹はといえば、ただただ、ひきつった笑みを返すことしかできなかった。
こいつ、妹の前だと、キャラ違い過ぎ!
そうしてハルは、水鉄砲を使うまでもなく、夏樹を連れ出すことに成功した。
そこは昨日と同じ場所。HEMINGWAYの裏手にある釣り場だ。
ユキも一緒だった。別に来たかったわけじゃない。宇宙人兄妹に無理やり押しつけられたミッションがあるからだ。今日中に魚を一匹釣る。夏樹がいればその可能性はぐんと高まる。
でも、とユキは思う。正直こういうのは苦手だ。ほとんど話したことのない人と一緒に遊ぶこと。子供の頃、断れずについて行くと、いつもみんなの話についていけず、結局一言も話さぬまま一人で帰った。家までの道がやけに長く感じた。ばあちゃんになんて話そう。そればっかり考えた。今日はどんな嘘をつこう。「楽しかったよ」って、ちゃんと笑えるかな……
「言っとくけど、俺は甘くないぞ」
さっきまであんなに渋っていた夏樹が怖い顔でそう言うと、ユキの中にもう一つ大きな不安が生まれた。
そうだ。こいつ、釣りになると性格変わっちゃうんだ。
「釣りってのはな、タックル組むところから始めんだ。いいか、一回しか言わねえぞ」
夏樹は有名塾のスパルタ講師のようにそう宣言し、さっさと実演を始めた。
「まずロッドにリールをつけて、ベイルアームを開ける。ラインを出してガイドに通す」
ユキはその聞き慣れない言葉たちを一つ一つ検索したかったが、夏樹の実演は速過ぎてそんな時間は一秒もなかった。
恐らくだが「タックルを組む」とは釣りの道具を組み立てることで、それをしなければ釣りは始められない。そういうことらしい。
釣りって、めんどくさい!
早くも心が折れかけたが、遠くでココと危険な黄色いイルカがこっちを睨んでいることに気づくと慌てて作業に集中した。そして決死の思いでスパルタ講師について行ったユキの前に、最後の関門が立ちはだかった。
「で、これをユニノットで結ぶ」
ユニノット?
どうやらそれはラインと呼ぶ釣り糸を、ルアーと呼ぶ魚に見せかけた物に結びつける結び方のことらしい。
「この結び方なら魚に引っ張られても簡単にはちぎれない」
夏樹の手つきは実に見事だった。一本の頼りないラインが、あっという間にルアーを固く繋ぎとめ、それは確かにどれだけ強く引っ張ってもちぎれなかった。
ユキも真似てみたが、出来上がりは夏樹のと違ってでこぼこしてカッコ悪い。
なんでだよ……
ハルは早々とあきらめ、何を思ったのか、水鉄砲を出し、夏樹の顔めがけて発射した。
おい、何してんだよ!
「ちょっ!」という短いうめき声を残して、夏樹は魂を抜かれたようにその場にぼーっと立ち尽くした。
ハルは悪びれることなく、夏樹の顔を覗き込んでこう言った。
「王子、もう一回やって♪」
次の瞬間、ユキは目を疑った。
夏樹がまるで操り人形のようにハルのラインをユニノットで結び始めたのだ。
何だこれ。俺のこともこうやって操ってたのか!?
「ほら、ユキもちゃんと見て覚えてね」
しかしユキはとてもそんな気にはなれなかった。淡々とユニノットを続ける夏樹を呆然と見つめ、宇宙人兄妹の不気味な微笑みに挟まれ、一ミリも動けずにいた。
こいつら、マジで怖い。どうしよう、一匹も釣れなかったら……
やがて意識を取り戻した夏樹は、いつの間にか完成しているハルのタックルを見て驚き、まだ全然できていないユキのタックルを見て、呆れたようにユキの顔を見た。
「おい、もう一回説明するか?」
しかしたった一人で宇宙人襲来の危機を背負わされた今のユキには、夏樹の怒りを受け止める余裕などなかった。
「おい聞いてんのかよ。説明するか? もう一回」
ユキはブルブルと首を横に振り、夏樹の前から逃げた。そして無事にユニノットを済ませてルアーを投げるハルと夏樹を見て、そして遠くから片時も目を離さずこっちを見ているココを見て、その焦りはピークに達した。
あぁ、もう、これでいいや!
ユキは適当にかた結びでラインとルアーを結び、ロッドと呼ばれる釣竿を振りかぶり、ルアーを海に投げた。
夏樹が訝しむようにユキを見たが、完全にテンパったユキは気づかない。
その時、ユキのロッドがしなった。
え、嘘!? どうすんだっけ!?
ユキは動揺し、その手と膝がガクガク震え始めた。夏樹が指示らしき言葉を叫んできたが、ユキの耳には届かない。
あぁ! もう、わかんない!
ユキはやけになり、強引にリールを巻いた。
「おい焦んなって!」
やっと夏樹の声が届いたがもう遅かった。気づくと目の前には、魚どころかルアーもなかった。そこにはただ凧を失った糸のように、ラインがぷらぷら揺れているだけだった。
あ、しまった……
「ごめん。弁償する」
それは夏樹が貸してくれたルアーだったからだ。
「そんなんいい」夏樹が険しい顔で詰め寄る。「ちゃんとやったのか? ユニノット」
え……
「やったのかって聞いてんだよ」
「いや、適当に……」
やっとの思いで絞り出したユキの言葉は、夏樹の怒りをさらに増幅させた。
「釣りは適当じゃできねえんだ。俺はそういう奴とは一緒にやりたくねえ」
夏樹はそう言ってユキから釣竿を奪った。
ユキの顔がどんどんしかめっ面になってゆく。それはただテンパっているだけだったが、目の前の夏樹にとっては、いわゆる逆ギレをされているようにしか見えなかった。
「なんだよその顔。お前みたいな奴はな、何やったってだめだよ」
ユキは夏樹のその言葉に、怒りを通り越した何かを感じたが、何も言い返せなかった。
だから嫌だったんだ。
ユキはそう思うことで周りのものすべてから逃げ出そうとした。
俺は釣りなんかやりたくなかった。誰とも関わらずに、ずっと一人でいたかったのに、俺のせいじゃない。俺のせいじゃ……
ハルは目の前に突然現れたヒリヒリした空気をどう受け止めていいかわからず、ぼーっとユキと夏樹を見ていた。たとえば遊園地の帰り道に突然、凄惨な事故を目撃してしまった子供のように……
夏樹はユキを一瞥し、苛立ちを海にぶつけるように荒っぽくルアーを投げた。
もう誰も何も言わなかった。
ユキはすべてをあきらめたように静かにその場を後にした。うっかり持ち帰ってしまったロッドの先に、主を失ったラインが寂しげに揺れていた。
夏樹は呆れたように一瞬ユキに視線を送ったが、ユキは気づくことはなかった。
「ユキぃ─! どこ行くぅ─!?」
ハルがその場に似つかわしくない大きな声で叫んだが、それがユキに届くことはなかった……
もう釣りなんてやらない。絶対。地球なんかどうなったっていい。頼むから俺を一人にしてくれ。頼むから……
ユキは子供の時の帰り道と同じように、ケイトのことを考えた。昨日、「友達と釣りをした」と言った時、ケイトは本当に嬉しそうな顔をした。なのに……
「もう釣りなんてしない」って言ったら、ばあちゃん悲しむかな……
ユキが憂鬱な思いで海沿いの道を歩いて行くと、防波堤の上にココが立っていた。
「釣り、あきらめるとね?」
無理だよ、俺には釣りなんて……
「あなたハルのトモダチ。トモダチ、ヤクソク破っちゃいかんとですよ」
トモダチ? そんなの要らない。こんなに怒られたり、呆れられたり、めんどくさい思いをしなきゃならないなら、そんなの……
そしてユキは力なくココに振り返った。
「別に、友達じゃないし……」
「ゆーきぃ─!」
ユキは部屋のベッドの上で耳を塞いでいた。玩具をせがんで床に座り込んだ子供のようなハルの声に。
やがてハルが体当たりを始めたのか、鍵をかけたドアが押され、ギシギシと鳴り始めた。
「ナンデ釣りやらない!? ナンデナンデ! やってよやってよぉ─!」
ユキは顔をしかめ、頭の先まで布団をかぶった。
その泣き叫ぶようなハルの声は、キッチンで洗い物をするケイトにも届いていた。
ケイトが心配げに二階を見上げると、金魚鉢の中の赤い魚も同じように上を見上げた。
夜のサムエル・コッキング苑は静かだ。色とりどりの植物たちが、明日もみんなを喜ばせようと、静かにその力を溜めている。
ケイトがそんな彼らを起こさないようにそーっと手入れをしている。葉を切る鋏の音さえ、できるだけ立てないように。
しかしその静寂は、まだ玩具をあきらめきれない駄々っ子のハルの声に引き裂かれた。
「ねぇーケイトぉー。ユキ、出て来ないー」
「そのうち出て来るわよ」慰めるようにケイトが言った。
「ユキ、僕とトモダチじゃなくていいって」
ケイトは、初めて聞くハルの寂しげな声に反応し、まるで植物を手入れするように静かに、そして慎重に尋ねた。
「ハルは、ユキと一緒にいて嬉しい?」
「ウレシイ?」
「心が、こう」
ケイトは両脇を可愛らしくきゅっと締めた。
するとハルは嬉しそうにその動きを真似て、
「そう。ワッキワキする!」
ケイトはその聞いたことのない擬音を疑うことなく受け止め、言った。
「だったら、困らせちゃだめよ」
「コマラセ?」ハルはまた地球の片隅の言葉の前で立ち止まった。
しかしケイトは根気強く、そして笑みを忘れず、目の前の駄々っ子に優しく指示を出した。
「ユキが一人でいたい時は、一人にしてあげなさい」
「ナンデ?」
「一人でいたい時は、何かを考えてる時よ。きっと大切なことをね」
「ふーん」
ハルはわかったようなわかっていないような顔でそう答え、笑ってみせた。
「一人にしたら、ユキ、僕とトモダチになってくれる?」
「うん。きっとなってくれるわ」
「そっか、わかった!」
ハルは完全に笑顔を取り戻した。そして突然咳き込んだケイトを見て、嬉しそうに真似てみせた。
「コホンコホン。ケイト、何これ?」
「なんでもないわ」そして微塵も動じることなく、ハルにまた一つ指示を出した。
「ユキの前でしちゃだめよ」
「わかった」
二人は微笑み、いつものハルとケイトに戻った。
ケイトは咳をぐっとこらえた。
ハルは気づかず、ずっと微笑んでいた。
ユキはまだベッドの中から動けずにいた。
目を閉じると、いつものようにその脳裏に今日の出来事が次々と再生された。そしてその映画のフィルムのような映像は、昨日と同じように一時停止した。そのシーンは釣り場。凄い形相で怒る夏樹の姿が何度も再生された。
「ちゃんとやったのか? ユニノット」
「釣りは適当じゃできねえんだ。俺はそういう奴とは一緒にやりたくねえ」
「お前みたいな奴はな、何やったってだめだよ」
やがてそれは記憶を超え、現実でも夢でもない、ユキの妄想となった。その中で何度も夏樹は怒った。しかしユキは立ち尽くすだけで何も言えない。そのうちユキの顔はこわばり、般若となった。しかし夏樹はやめない。同じ言葉で何度も何度もユキを責め続けた。
あぁぁぁぁ! なんだこの気持ち!
ユキは目を開け、空気を求めて水中から飛び出すようにその体を起こした。
「そこまで言うことないだろ!」
ユキは妄想と現実がごっちゃになってそう叫んだ自分に驚いた。やがて我に返ると、苦しげなしかめっ面が現実の空気を吸い込み、徐々に元の顔へと戻っていくのを感じた。
そっか。俺、悔しかったんだ。
ユキはようやく自分を苦しめていた感情に気づいた。
悔しかった。でも何も言えなかった。だから、苦しかったんだ……
「でも」と、冷静になってユキは思った。
もしかして、夏樹も悔しかったのかもしれない。俺が、適当だったから……
次の日の朝。まだ太陽が上がり切っていない浜辺にユキの姿があった。その手はラインとルアーを結びつけようとしている。ユニノットだ。しかしその手つきはまだおぼつかない。こんがらがったり、でこぼこになったり、ラインの違うところを切って台無しにしてしまったり……
「あーもうっ、何やってんだよ」
ユキは自分がそう口に出していることにも気づかず、また新しいラインを出してルアーを結び始めた。
そこへハルが釣竿を担いで駆けて来た。そしてユキがユニノットをやっていることに気づくと、一足早く昇った太陽みたいな笑顔になり、「ユキ!」と呼びかけようとした。しかしその寸前でハルは口を両手で塞ぎ、じっとユキを見守った。そして誰にも聞こえない小さな小さな声でこう呟いた。
ユキ、大切なこと考えてる。一人にしたら、トモダチになれる。
ハルはその日が待ちきれないように、必死で笑みを噛み殺し、静かにその場を去った。
ラインとルアーだけに集中しているユキはそんなハルの計らいに気づくことなく、何度も何度もユニノットに挑んだ。
すると今度は別の誰かがその姿を見た。
夏樹だ。着古したトレーニングウェア姿で、少し息を切らせながら、時折悔しげな声を漏らしながらもあきらめないユキを見ていた。
裏磯と呼ばれるその人気のない海辺はハルとココの秘密の待ち合わせ場所だ。文字通り江の島の裏手にあり、まるでアート作品のように序列なく並んだ岩たちが、穏やかな波を受けて濡れている。
「ねぇ、にいちゃん、なんであのユキって子がええのん?」
ココは風をそーっと撫でるように手と足を動かしながらハルに尋ねた。
「わかんない。でもユキがいい」
そう答えたハルもココと同じ動きをしている。それは江の島に古く伝わる江の島おどりという踊りで、ハルもココも、このまったりした踊りがお気に入りなのだ。
「あの子だめだめやん」ココは早々と釣りをあきらめたユキを責めるように言った。「すぐにヘン顔になるし、約束破るし、あの子に釣らせるのは無理や思うけどなー」
しかしハルは確信に満ちた顔で「大丈夫」と言った。「ユキなら、絶対釣れるしぃー!」
そう言って海に向かって大きくロッドを振った。
満面の笑みのハルとは対照的に、ココは不安げに海のずっと向こうを見た。
「そんな簡単やないよ、『あいつ』は……」
そしてココは、兄というよりは、たとえば、扇風機に指を当てるのが大好きな弟を叱るようにこう言った。
「にいちゃん、あんまり海に近づいたらあかんで」
しかしギュイィィ─ン!と何度も海に向かってロッドを振る今のハルには、何を言っても聞こえるはずがなかった。
その頃、何度もユニノットを失敗し続けたユキは、どうしても摩擦で縮れてしまうラインを見て思い出した。夏樹の、あの見事な手さばきを。そしてそこに一瞬見えたある行為を。あの時、夏樹はラインを舌でなめた。
あれって、もしかして……
ユキは夏樹を真似てラインをなめてルアーに結びつけた。すると閃きはぐっと確信に近づいた。
そうか。こうすれば摩擦がなくなって切れにくくなるんだ!
そして数十回の失敗を経て、ユキのユニノットは完成した。
「できた……できたぞ」
ユキは興奮で震える手でスマホを出し、そのきれいな結び目にカメラを向けた。
裏磯からの帰り道、ハルは浜辺で、必死に笑みを噛み殺して歩くユキの姿を見つけた。
「あ、ユキ! ナンデ笑ってるぅ─!?」
ユキは気づき、慌てて顔をしかめた。そしてココもいることに気づくと、二人の前に来て、右手で水鉄砲を撃つ手つきをした。
「これ、やめろ」
「ナンデ?」
無邪気に尋ねるハルにユキは答えた。
「なんか、嫌なんだよ」
「困る? ユキ、これやると、コマル?」
「そう。困る」
ハルはちょっとだけ黙って、ユキに言った。
「わかった」
「にいちゃん」
諭すようなココの言葉をユキが遮った。
「やるよ。俺、釣りやるから。今度こそ絶対釣るから」
ユキはいつになく熱くなった自分が恥ずかしくなり、そそくさと歩き出した。
「ユキぃ─!」
ハルは飛び上がって喜び、ユキを追いかけた。
ココは二人のやり取りの意味がさっぱりわからず、呆れて別の方向へ歩き去った。
「あんな子じゃあかんと思うけどなぁ」
すると、誰もいなくなったはずの浜辺の砂がガサっと動いた。そして次の瞬間、砂の中からアキラとタピオカがむくっと顔を出した。
「なんか、マズいな。タピオカ」
タピオカは「そうだね」と同意するように、小さくクワッと鳴いた。
「行ってきます」
「行ってくるのだぁ─!」
並んで家を出て行くユキとハルを、ケイトが微笑んで見送った。「行ってらっしゃい」
学校へ向かう途中、ユキとハルは家の近くに見慣れない店が建っているのに気づいた。
それはケイトが働くサムエル・コッキング苑の隣。看板には『DUCK CURRY』。そして風にはためく幟にはこう書かれていた。『しらすカレー 近日オープン』。
「しらすカレー? なんでもアリかよ」
ユキはやたらとしらす推しの江の島という町に、苦笑いで異議を唱えた。
しかしハルは今まで見せたことのない色のない顔で「ないな」と言って歩き去った。
「ないのかよ」
ユキは今日もハルに追いかけられるように学校へ入って行った。逃げるように廊下に出ると、後ろから一人で歩いて来る夏樹に気づいた。
その瞬間、ユキはハルから逃げることなど忘れ、徐々に歩みを遅めた。そして鼓動が見る見る高鳴っていくのを感じた。
どうしよう……
ユキは角を右に曲がり、壁に背をつけ、大きく息をした。
「どうした、ユキ」
ハルは角からそっと歩いて来る夏樹の様子を窺うユキを見て、無邪気な笑みで言った。
「わかった。かくれんぼ?」
ユキは答えず、迷っていた。
やっぱり、やめとくか……
ユキの中に棲む弱気の虫が騒ぎ出した時、目の前を夏樹が歩き去って行くのが見えた。
ユキがあきらめ、うつむいたその時、その心を知ってか知らずか、ハルが角からひょっこり顔を出し、大きな声で夏樹に呼びかけた。
「おはよう王子!」
夏樹が驚いて立ち止まった。
ユキも驚き、角から飛び出した。
そこはちょうどユキたちの教室の前で、クラスメイトたちが一斉に囁き始めた。
「王子?」「宇佐美君のこと?」「なんで?」
夏樹がもの凄い形相で振り返ったその時、
今だ!
ユキはヘヘヘーと微笑むハルを追い越し、夏樹の方へと歩いた。すでにしかめっ面となったその顔は、夏樹をひるませるのに充分なインパクトを持っていた。
「な、なんだよ」
ユキは目を丸くした夏樹の前に立ち、震える手でスマホを出し、一枚の写メを見せた。
「あ、ユニノットぉー!」
ハルが街中で偶然友達に出会った時のような驚きと親しみに満ちた声を上げた。
夏樹はユキの意図を理解したが、どう返していいかわからず、ぶっきらぼうに吐き捨てた。
「それだけかよ」
「でも、できたから……もう俺、適当にやんないから」
夏樹は驚いた。そして、じっと目をそらさずそう言い切ったユキの気持ちに、自分も目をそらさないことで応えた。
クラスメイトたちはただならぬ空気を感じ、じっとユキと夏樹を見ている。
やがて夏樹はその視線に耐え切れず、逃げようとした。「そんなん、できて当然だよ」
しかし今日のユキは昨日までのユキではなかった。飼い慣らした弱気の虫たちがみんな眠ってしまったのか、あるいはテンパり過ぎて周りのものがすべて吹っ飛んでしまったのか。
「あのさ」
この状況に一番驚いているのはユキ自身だ。
こんなことが今まであっただろうか。
俺、自分から話しかけてる。あんまり喋ったことない、誰かに。俺が……
夏樹はもう一度振り返って、ユキの顔を見た。
ユキは朝から、ユニノットに成功したあの時から、ずっと温めていた言葉を口にした。
「釣り、教えて欲しい」
夏樹は戸惑いながらも小さな肯定を残し、足早に教室へと入って行った。
や、やったぁ─!
ユキのその心の叫びに気づいたのは、ユキと、隣で微笑むハルだけだった。
ユキが笑みを噛み殺して席に着くと、えり香が「おはよう」と微笑みかけてきた。
すると眠っていたはずの弱気の虫が一斉に目覚め、ユキに中途半端な会釈をさせて、そそくさと席に着かせた。
今日の俺は、どうかしてる。朝からなんだか心がざわざわして落ち着かない。
そんなユキの心に、突然教室に入って来た見慣れないインド人が、また別のざわめきを呼び込んだ。
アキラだ。制服を着ている。そしてその腕に抱かれているのは、タピオカだ。
え、誰?
生徒たちが唖然と静まり返る中、アキラはまだ教師も来ていないのに、はきはきとした口調で自己紹介を始めた。
「こんにちは。アキラ・アガルカール・ヤマダです。本日からこのクラスに転校してくることになりました。二十五歳ですが気にせず仲良くしてください。よろしくお願いします」
彼が持ち込んだざわめきは、あっという間に教室全体に広がった。「え、二十五歳って言った?」「名前長くない?」「あれターバン?」「アヒル本物?」「どっから突っ込めばいいの?」「てかアヒル超可愛い~♪」
江の島、大丈夫か?
ユキは、自称宇宙人の次にやって来たインド人の転校生を、恐る恐る見た。
するとアキラはユキにニッと微笑んだ。
なんで!?
ユキが慌てて目をそらした先にはハルの怯える顔があった。それは仲見世通りで猫に遭遇した時より、もっと深い怯えに見えた。
なんで?
夏樹は興味なさげに窓の外を見ていた。
なんだこれ、ざわざわする。
何かが始まる。ユキは直感でそう感じた。
俺の知らない、今まで感じたことのない、何かが……いや、もうすでに始まってるのかも……
ユキはもう一度恐る恐るアキラを見た。
アキラはまだこっちを見て微笑んでいた。
(続)