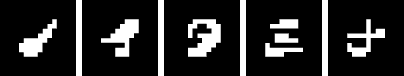NOITAMINA
OFFICAIL WEBSITE
SHARE
ツイート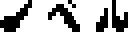 NOVEL
NOVEL
ノイタミナノベル「つり球」 第4話

五月の浜辺は静かだ。まだ海水浴客はいないし、サーファーもそれほど多くはない。ただ海だけが、名作の上映を待つ巨大なスクリーンのようにデンと構えている。
ユキは夏樹に言われるままに釣竿、いや、夏樹がそう呼べと言う『ロッド』を海に向かって振りながら、ここにこうしている自分が信じられなかった。
この俺が、放課後に、友達と一緒にいる。
いや、今、隣で同じくロッドを振るハルや、そんな俺たちをコーチのように腕を組んで見ている夏樹のことを『友達』と呼んでいいのかはわからない。そんなの二人に確かめたわけじゃないし……ただ学校が終わって、夏樹に「行くぞ」とぶっきらぼうに言われてここにいるだけだ。他の人にとってはなんでもないことなのかもしれないけど、俺はこんなこと、少なくとも小学校低学年の時以来、一度もなかった。なんか気恥ずかしいような、胸の奥がくすぐったいような……
しかしユキが今この場にいることをぎこちなく感じるのはその理由だけではない。
くそっ、全然思い通りにいかない!
ルアーを海に投げる『キャスティング』というやつだ。後ろを気にしながら大きくロッドを振りかぶる。それだけで慣れてないからちょっとふらつく。そこからロッドを海に向かって勢いよく振る。そうなるともう体がぐらぐらして、気づくと釣り糸、いや、これも夏樹がそう呼べという『ライン』の先に結ばれたルアーが、自分のイメージとは程遠い場所にバサっと不恰好に落ちる。とにかくこの釣り具たち、いや、これも夏樹に言われる前に慣れておこう、この『タックル』というやつは、本当に思い通りに動いてくれない。
ユキはハルと、その不思議過ぎる妹ココにカッコよく言い放った自分を悔やんだ。「俺、釣りやるから。今度こそ絶対釣るから」そして夏樹にも言ってしまった。「釣り、教えて欲しい」。
なんであんなこと言っちゃったんだろう……
ふぅあぁぁぁぁーー! なんでぇーーー!
隣でハルもジグソーパズルをあきらめた子供のように情けない声を上げている。
そんなユキとハルを高みから見下ろすように夏樹が言った。
「わかっただろ? キャスティングってのは適当に投げてもうまくいかない。魚がいるところに正確に投げられるようにならなきゃ意味がないんだ」
正確に? そんなこと言われたって……
と、その時、背後でヒュンっと鋭く心地よい音がしてユキは振り返った。
夏樹がロッドを振ったのだ。
するとラインは澄んだ空を切り裂くように弧を描き、その先端のルアーが、いつの間に か置かれていた赤いバケツの中へと吸い込まれていった。
夏樹すっげぇーーーー!
ユキもハルのように叫んだりしなかったが、思ったことはまったく同じだった。
マジかよ……
ここからあのバケツまで、十メートルくらいはある。それが一発で入るなんて……
「いいか、一回しか言わないぞ」
夏樹はユキとハルの驚きになどまるで興味がないといった感じで、たった今起こった奇跡を細かく再現し始めた。
「まずリールを持ってる手の人差し指にラインをかけて、ベイルアームを開ける」
ユキは授業中にスマホで復習した言葉をなんとか辿りながら、自分のタックルを見て照らし合わせた。
「逆の手はグリップエンドに添えておく。で、まっすぐ振りかぶって、振り下ろす時にラインを離す」
ユキはその動作を頭の中でなぞりながら、バケツに吸い込まれるルアーを想像してみた。
「はじめは丁寧に三拍子を意識してやれ。1、2、3!」
それはまるで魔法の呪文のようだった。またしてもルアーがバケツに入ったのだ。
「夏樹、天才っ!」
もちろんユキもハルと同じ気持ちだ。二回立て続けで入った。これはもはや奇跡じゃない。
夏樹はハンパなく釣りが上手いのだ。
「あのバケツに入るまで、海には投げさせない」
夏樹はもはやスポ根ドラマのコーチだ。
「ルアーはこれ使え。練習用だ」
「あ、僕これがいいっ!」ハルが赤いルアーにパクっと食いつくと、コーチの眼鏡の奥がギラっと光った。「ふざけるな」
「はいっ!」宇宙人部員ハルのすっとんきょうな声を合図に、ユキとハルはバケツというゴールに向かって走り出した。しかし……全然届かない!
ルアーが上に上がり過ぎてまったく距離が出ないのだ。
「離すのが早い。だから上に上がるんだ」
なるほど。
しかしそれを意識すると今度はルアーがすぐ落ちてしまう。
「それじゃ遅い!」
わかってる。理屈はわかってるんだ。
「だから声出してやれって。三拍子、なんか適当に言葉当てはめて投げろ」
え、こんなとこで声出すの? 絶対無理! いくら人気がないとはいえ、ここは外だ。適当な言葉を叫べるほど俺は大胆じゃない。
「ユキ、ハル、王子ぃー! 釣り、釣り、釣りぃーー!」
あいつには恥ずかしさとかないのか!
ユキは何のためらいもなく適当な言葉を叫び始めたハルを見て自分まで恥ずかしくなった。
どうしよう……なんて言えばいいんだ?
早くもテンパッてかたまってしまったユキの耳に、囁くような声が聞こえた。
エノ、シマ、ドン。
……は?
声の主は夏樹だった。
エノシマドン?
ユキの脳裏にほっかほかの丼が浮かんだ。
江ノ島丼。まだ食べてはいないが、前に検索したから知ってる。確かサザエの身を刻んで卵でとじたものをご飯に乗せた丼のことだ。しらす丼と並ぶ江の島の名物。でも……
ないな。そんなダサい掛け声をこんなとこで口にするなんて……ていうか、夏樹らしくない気がする。なんで? なんで江の島丼?
無意識でその掛け声を囁いていた夏樹は、やがてこっちを見ているユキとハルに気づいて恥ずかしげに目をそらした。しかしすぐに自分がコーチであることを思い出し、ユキの視線を眼鏡の奥から睨んではね返し、開き直ったように吐き捨てた。
「お前らもそれでいけ」
や、やだよ!
ユキは無言で抵抗したが開き直ったコーチはもう引き下がらない。「やれ。叫べ!」
やだって。そんなダサい掛け声!
「エノ、シマ、ドーーーン!」
ハルが弾けんばかりの笑顔で叫んだ。
お、お前、まさか気に入ったのか!?
ロッドを握ったまま立ち尽くすユキを、さらに追い詰めるように夏樹が睨んでいる。
「……エノ、シマ、ドン」
「声が小さい!」
「エノ、シマ、ドーン」
ユキが顔をこわばらせながらロッドを振ると、観光客たちが絵に描いたような半笑いの顔でこっちを見た。
やめて、見ないで!
ユキはさらにテンパり、その顔は般若顔へと着実に近づきつつある。
こんなとこであの顔になりたくない!
危険を感じて人々から目をそらすと、そこには別の意味で自分をテンパらせる男が立っていた。あの謎の転校生とアヒルだ。
あ、あいつ……
まるで我が子のようにタピオカをその胸に抱くアキラは、睨むでも笑うでもない、実に読み取りにくい表情でこっちを見ていた。
「エノ、シマ、ドーーン!」ご機嫌に叫んでいたハルはアキラに気づくと慌ててキャスティングをやめ、背を向けた。その背中は小刻みに震えているようだ。
ハル、なんであいつにビビるんだ?
アキラは最後に、これまた読み取りにくい種類の笑みを残して去って行った。
あいつ、何者なんだろ……
「おいお前ら、サボるな」
夏樹は容赦なく何度もユキとハルにエノシマドン!を叫ばせ、新しい技を教えた。
フェザーリング?
夏樹によれば、キャスティングの時、ラインが出過ぎないように指でブレーキをかけることらしい。ルアーが空中にある間に人差し指でリールのスプールリングに触って調節する。スプールリングとはラインを引っ掛けている輪っかのことだ。
「見てろ」
夏樹はロッドを振り、何度か軽くリングに指を触れた。なるほど確かに飛び過ぎたルアーは急激に速度を落とし、バケツの中へと吸い込まれていった。
す、すげえ。
ユキはハルが叫ぶのを待たずに心の中で驚きの声をあげた。
俺もやってみたい。夏樹みたいに、この、今は厄介でまるで言うことを聞かないロッドやルアーを、自由に操りたい。
ユキはそんなことを感じた自分に驚きながらも何度もキャスティングを繰り返した。集中するうちに徐々に恥ずかしかった声も出始めた。
エノ、シマ、ドン!
しかしその走り始めた心は、ユキの天敵である同世代の男女の笑い声にあっさり屈した。
上陸したばかりの宇宙人のようなウェットスーツ姿のサーファーたちがこっちを見ている。それはクラスメイトのえり香と仲間たちだ!
「あいつら何してんだ?」その明らかに笑いを含んだ囁きが矢のように耳に突き刺さる。
み、見られてた!
ユキは隠せるはずのないロッドを精一杯隠した。
さすがの夏樹も微笑むえり香から目をそらし、背を向けた。
ハルだけが、たった一人で神輿をかつぐお祭り男のように叫んでいた。
「エノ、シマ、ドーーーン!」
叫ぶたびにえり香たちは笑った。「江ノ島丼だって!」「ウケるぅーー!」
「僕とユキ、あのバケツにルアー入れる!」
おいハル、余計なこと言うなって!
笑い混じりの声の矢がまたユキを襲う。「マジかよ」「あんなの入るわけないじゃーん」
「ぜーったい入れるし! ね、ユキ!」
お、俺にフるなぁーー!
ユキの顔はさらにこわばり、ゴールまであと一歩のところまできた。そしてそこに、海をバックに微笑むえり香がとどめを刺し、見事に般若顔が完成した。
「出た、般若!」クラスメイトたちはユキを指さして笑い始めた。
ま、まただ……また見られた、この顔を!
今のユキにとって、彼ら、いわゆるイケてる男子や女子たちは眩しすぎる。サーファーと釣り人。どっちがイケてるかは考えるまでもない。しかしユキは再びキャスティングを始めた夏樹の背中を見て、般若のまま、また大きくロッドを振りかぶった。
「はぁ~~キャスティングむず~~い」
ハルの声はふぬけていたが、その顔はいつものように笑っていたのでそれは「つまらない」という意味ではなさそうだった。
ちょっと鈍い色味のオレンジの夕陽が、奇跡を起こせなかったユキとハルを慰めるようにその頬を照らしている。
「そんな簡単に入ってたまるかよ」
ユキはその勝ち誇ったような夏樹の言葉を聞いてちょっと悔しくなった。
確かにその通りだけど、正直、一回ぐらいは入ると思ってた。
「とりあえず死ぬほど投げろ」
夏樹はそう言って思い出したように腕時計を見た。
「あ、もうこんな時間か。じゃあまた明日な」
「じゃーーねーまた明日ぁ~!」
お別れを言い損ねたユキは、クールな鬼コーチにしては慌てた様子で去って行った夏樹を少し意外に思った。それにしても……
「また明日」か。もちろん何度も耳にした言葉だけど、いざ自分に言われると大分くすぐったい。これが友達か、普通の、みんなと同じの。
ユキは頭に浮かんだそんな思いをすぐに打ち消した。
いや、こんなのは今日だけかもしれない。明日になればまたどうせ一人になって……いや、やめとこう。そんなウジウジした奴に、奇跡なんか起こせるはずがない。
「エノ、シマ、ドン」
ユキは家の前でバケツに向かってキャスティングを繰り返す。ここなら少しは大きな声を出せる。バケツを挟んだ向こう側から声を枯らして叫ぶハルほどではないけど。
「あーっ、なんでだよ」
ユキは何十回も続く失敗に心が折れそうになった。夏樹が教えてくれた理屈はわかる。でもすべての動きが完璧にいかないと、あの小さなバケツにルアーを入れることなんて到底無理だと思った。
「惜しかったじゃない」
いつの間にか見ていたケイトが、落ち込むユキの肩にぽんと優しい言葉を置いた。
「江の島、ドン?」
ケイトはそのフレーズが気になるようだ。
「三拍子で投げるんだ」とユキが言う。「夏樹が、あ、友達が、教えてくれて」
ケイトの目が輝いた。もちろんユキが友達の名前を口にしたからだ。
「そう。よかったわねユキ。二人も友達ができて」
「二人って……」
ユキはバケツの向こう側を見た。そこにはこんがらがったラインをほどこうとして、体ごと巻きつかれているハルがいた。
「何やってんだよあいつ」
「ユキ、ハルといると楽しそうね」
「え? そうかな」
「うまくやっていけそう?」
「そんなの、わかんないよ……」
ユキは恥ずかしくてぶっきらぼうになり過ぎている自分に気づいてはいたが、うまくやっていけるかと聞かれたらわからないと言う他ない。
だってばあちゃん、あいつは宇宙人なんだよ。ばあちゃんには言えないけど、変な武器も持ってるし、恐ろしい妹だっている。本当はどんな奴なのか今はさっぱりわからないんだから。
するとケイトはユキの心を読んだかのように言った。「ハルはいい子よ。すごくいい子」
ユキは何も返せなかった。
なんでばあちゃんにはそんなに確信があるんだろう。どうしてハルを突然家に住ませたり、いい子だなんて言い切ったりできるんだろう。
「エノ、シマ、ドン」
ユキはケイトに答える代わりに、またバケツに向かってロッドを振った。
夏樹の家は仲見世通りの中にある。年季の入った青銅の鳥居をくぐってすぐ右の、『元祖しらす亭』という食堂だ。一階に店があり、その奥の階段を上がったところに家がある。
「おにいちゃん、まだぁ~?」
さくらが大きな鍋でカレーを煮込む夏樹を急かしている。
「早く食べたいな、おにいちゃんカレー」
その甘えた口ぶりは、HEMINGWAYでユキやハルに挨拶した時より大分子供っぽく見える。無理もない。いくら背伸びをしてもさくらはまだ十才で、じゃれ合う相手が必要だ。しかし店の片づけが済むまでは父の保も忙しいし、本来なら今日もご飯を作っていただろう母は今、台所の近くの仏壇の中で永遠の笑みを浮かべている。だから自然と、遊び相手も、甘えたりわがままを言える相手も、七つ上の兄、夏樹ということになる。
「ごめん。今日はちょっと遅くなっちゃったな」
「さくら、もうお腹ペコペコ~」
「わかったよ。もうすぐできるからな」
夏樹はさくらに何を言われても穏やかな口調を崩さない。その笑みは他の誰にも見せられないほど優しさに満ちている。夏樹はさくらにとって兄であり父であり母で、そのすべてを毎日手を抜くことなくやり切ろうとしている。だからどんな日も、たとえ釣りに夢中になった日でも、こうして急いで帰って来てさくらのためにご飯を作るのだ。
「ただいまーー!」
その時、明るすぎる声が、夏樹とさくらだけの空間に割って入って来た。
保だ。その顔は赤らんでいる。店の片づけを終えるとビールを一杯ひっかけるのが日課なのだ。商店街に必ず一人はいるであろう、明るく能天気で声の大きなオジサン。本当に親子なのか疑いたくなるほど、保と夏樹は似ても似つかないキャラクターだ。
「おとうさんおつかれー!」
さくらが弾けるような笑みで保に抱きつく。夏樹は目を伏せる。自分しか頼るところなどないと思っていた子犬が、突然本当の親を見つけ、自分に背を向けて走り去って行くようだ。
夏樹はこの瞬間が嫌いだ。毎日決まって訪れる瞬間だが、いつまで経っても慣れない。
目を伏せた先の「おにいちゃんカレー」も、途端に味気ない、ただ茶色いだけの物体にしか見えなくなってくる。
「夏樹君、おつかれさま」
その届くか届かないかぐらいの控えめな挨拶が、憂鬱な夏樹にとどめを刺す。
『元祖しらす亭』の店員、本田真理子は、いつも保の後ろに隠れるように立っていて、「上がれよ」というちょっと乱暴な保の言葉をやんわりと拒む。まるでそこに危険な柵でもあるかのように決して部屋には踏み入れず、いつも階段を登り切った辺りで立ち尽くす。
そして夏樹が真理子の言葉に何も返さないのも、「おい、夏樹」と、保が夏樹に言うのも、「いいのよ」と真理子が保に目で合図するのも、そのすべてのやり取りをさくらが幼い心で精一杯受け止めるのも、すべて宇佐美家恒例の光景だ。
「マリちゃん、また明日ね~」
さくらは、それがいいことかどうかわからないが、その場の空気を読んだり気を配ることが自然とできるようになっている。もちろんそのことに三人の大人は気づいているが、何も言ったりはしない。
「夏樹、ご苦労さん」
保は返事を返さない夏樹を気にも留めてないといった感じで冷蔵庫から缶ビールを取り出す。
「お前、最近この辺で釣ってんだってな」
夏樹はドキっとするが何も答えない。
「工藤さん言ってたぞ、楽しそうだったって」
それでも答えずカレーを混ぜ続ける夏樹の代わりに、さくらが明るい声で答える。
「おにいちゃんね、釣り教えてるんだよ、お友達に」
「へぇ~、教えてる? お前がか?」
保が今日一番嬉しそうな声を出した。
「どうしたんだお前。またやる気になったのか。釣り」
夏樹は必要以上に顔を近づけて話す保からうんざりと目を伏せ、思う。そういうところが嫌なんだよ、と。
保は相手が言われたくないことをためらいなくズバっと言うところがある。酒が入っていると尚更だ。
夏樹は苛立ちを少しでも和らげようと、おそなえのご飯をよそい、仏壇の母の遺影の前に置いて手を合わせる。しかしその行為も時にその心をさらに憂鬱にさせる。
なんでいないんだよ……
病気だから仕方ない。人には寿命がある。
何度もそう思って自分を納得させようとしたが、いまだにうまくいっていない。
いいよな、いっつも笑ってて……
夏樹は微笑む母にそう呟いてしまう自分が嫌いだ。
「そうか。今度俺も混ぜてくれよ。みんなででっかいの釣ってやるかぁー!」
「さくらも釣りたーい」
その弾けるような笑みがまた夏樹を追いつめる。
「みんなでよく行ったよなぁ」保はまるでそこに妻が生きているかのように仏壇に話しかけ、慣れた手つきでロッドを振る仕草をした。
「エノ、シマ、ドーン! ってな!」
さくらは嬉しそうに笑うが、その視界の隅には今日も夏樹の物言わぬ寂しい背中がある。
「おぉ、カレーか。美味そうだな!」
保がまた夏樹に顔を近づけた。
夏樹はいつもなら何も言わない。しかし保の大きすぎる声や、その口から漏れるビールの匂いやげっぷが、今日はやけに苛立つ。
「どういうつもりだよ」
夏樹は思わずそう口に出した自分に驚いた。せめてもの救いは、ぎりぎり残っていた理性が、居間でテレビを見るさくらに聞かせまいとその声を小さくしたことだ。
「まだ二年も経ってないだろ」
保は夏樹が真理子のことを言っていることにすぐ気づいたが、ひるむことなく亡き妻の遺影をまっすぐ見てボソっと言った。
「もう、二年だろ」
それは酔っているとは思えないほど落ち着いた口調だった。
しかし夏樹からすればそれは新しい女を作って開き直っているようにしか聞こえない。
保は睨む夏樹をまっすぐ受け止め、切り出した。「夏樹、お前な……」
夏樹は軽く身構えた。その先、何を言われるのか想像がつかない。しかし恐らく自分にとって面白いことではないだろう。
「……髪、切れ」
保はそう言って思い出したように笑って、夏樹の髪をくしゃくしゃっとした。
夏樹はその意外な言葉に何も言えず立ち尽くした。
さくらは居間で二人に背を向けてテレビを見ていた。それは世界の不思議な現象を紹介するバラエティ番組だ。ちょっと大げさなナレーションが、スウェーデンでフェリーが行方不明になった事件を伝えている。船長が興奮気味に『気づいたら三時間が経過していた』などと話しているが、今はどんな不思議な事件も、さくらの耳には届かない。その目もテレビ画面に向けられてはいるが、実際は何も見ていない。さくらにとって深刻なのは遠い国の話なんかではなく、自分の家のことだ。毎日この家を覆う憂鬱で気まずい空気。自分の力ではどうすることもできず、今日も見えないふり、聞こえないふりをしてしまった。これ以上、誰一人、悲しい顔をして欲しくないから……
「エノ、シマ、ドン」
ユキはダイニングキッチンでロッドを振る手つきを繰り返していた。
それをキッチンで並んで洗い物をしているハルとケイトが微笑んで見ている。
「ユキ絶対入る。エノシマドン」
ケイトは微笑み、最後のお皿を拭き終えると、「ハル、ありがとう」と言った。
「どーいたしまして!」
ハルは覚えたての言葉を自慢げに返した。
ケイトは微笑み、「エノシマドン」と呟きながら自分の部屋へと去ろうとするユキを呼び止めた。「あ、ユキ」
ユキが「ん?」と振り返る。
「ハルもちょっと聞いて」
「なーに?」
ケイトは二人を見て少し間を置いた。
「明日から、私、ちょっといないから」
「……え?」
ユキは不意を突かれた。
しかしケイトは笑みを崩すことなく、近くのスーパーに買い物にでも出かけるような軽い口ぶりで続けた。「ちょっとね、入院」
少し沈黙があった。それはほんの短い間だったが、ユキの心を不安で満たすには充分だった。
「……また?」
「ニューイン?」
ハルだけが少し出遅れた。無理もない。「ニューイン」という言葉が喜びを意味するのか悲しみを意味するのかさっぱりわからないのだから。
「昨日ね、ちょっと調子悪いって言ったら検査しましょうって。なんか病院も大げさなのよ」
ユキはもはや「エノシマドン」の世界から遥か遠くに立っていた。ついさっきまでロッドを握る手つきをしていたその手は今、意味なく拳を握ったり緩めたりしている。
ハルは急に大人しくなったユキをちょっと不思議そうに見たが、まだ状況がつかめていないようだ。
「ハル、大丈夫よ。ちょっと体を治しに行くの。また戻って来るからね」
ハルはそう聞いて安心したのか、その顔に笑みが戻った。「うん、わかった」
ユキは目の前で微笑む二人を見て、自分だけ取り残された気がした。
なんで笑ってるんだ? これは、笑うようなことじゃない。なんで……
「そういうの、言ってよ。いつも急だから」
ケイトはスネたように思いをぶつけるユキをなだめるように言った。
「ごめんね。心配かけると思って」
「……いいけど。もう慣れてるけど」
ケイトはそんなユキの投げやりな口ぶりさえ笑顔ですっと吸い込み、こう言った。
「でも今度はハルがいるから寂しくないわよね?」
そういうことじゃない。ユキの中にはっきりその言葉が浮かんだ。ハルがいるからとか、そういうことじゃないんだ。
ハルは何も言わず、去って行ったユキを心配げに見送った。
「だいじょうぶよ」 ケイトは微笑んでハルをいつものハルに戻そうとした。「大丈夫」 今度は半分自分に言い聞かせるように言った。
ハルは「うん」と頷いて微笑んだ。
そんな二人を赤い魚がじっと見ていた。
その魚は金魚鉢の中で何か考えを巡らせるようにくるくる回って泳ぎ始めた。
ユキは乱暴にドアを閉め、部屋のベッドに寝転がった。そして、バケツにルアーを入れたいと、それだけを考えていたさっきまでの自分を恨めしく思った。
お前はいいな。もう俺は、そんな気分の俺には戻れない……
ユキは不安を薄めるように頭の中で自分を二つに割って言葉をぶつけ合った。
なんでだよ。ばあちゃん、最近ずっと元気だったじゃないか……どうすればいい? 何言ってんだ、わかってるくせに。ばあちゃんの病気は重いんだ。俺にできることなんてない……もういい。もう、何もしたくない……
「すいません。今日はもう終わっちゃったんですよ~」
頭にターバンを巻いた店員が、訪れた二人組の女性客に申し訳なさそうに頭を下げた。
『絶品!しらすカレー』と書かれた幟がはためくその店は、サムエル・コッキング苑の隣に突如オープンした謎のカレー屋『DUCK CURRY』だ。しかしその店内はとてもカレー屋には見えない。確かにカレーはたくさんあるが、食べているのは客ではなく、ターバンに白装束の男たちだ。彼らはカレー屋の店員などではない。異星人探索機関DUCKの隊員たちだ。
「こちら江の島」
アキラがしらすカレーを食べながら本部と通信を始めた。目の前にはモニター画面が数台あり、それは江の島の様々な場所をライブで映し出している。仲見世通り、夏樹の家である『元祖しらす亭』の店内、HEMINGWAY、サムエル・コッキング苑、などなど……アキラの前のPC画面には、ユキと夏樹の写真と、その詳細なデータ、そして彼らが釣りをしている映像が流れている。
「ターゲット、JF1の学校への潜入に成功しました」
画面にハルとココを捉えた映像が流れ始める。それは明らかに遠くから盗み撮られたものだ。
「妹と称するJF2と共に、人間に擬態しているものと思われます」
モニターに映る本部の会議室には数人の幹部たちがふかふかのソファに悠然と腰かけていて、アキラの直属の上司であろう男がモニター越しにアキラに問いかける。
「そのJF1は江の島で何をしているんだ?」
その上司の風貌は実に特徴的だ。長い金髪に、紫のサングラス、紫のルージュ。そして首にも紫のファーを巻いている。国籍も、性別さえも不確かな、怪しげな人物に見える。
「それが、毎日、釣りをしています」
アキラの答えは会議室に失笑をもたらした。
「釣り? ただの観光エイリアンか」
「先月は名古屋にパチンコしに来た奴らがいましたね」
アキラがその緩い空気を打ち破るように報告を続ける。
「しかし彼らは危険な力を持っています。水を使って人間を操ることができます」
上司たちに一瞬緊張が走ったが、モニター画面にハルが持っていた透明の黄緑色の水鉄砲の写真が映し出されると再び失笑が漏れた。
「操るとは、具体的には?」
「具体的には、クラスメイトの男子に江の島おどりを踊らせたり……」
アキラが緊張感を持って報告すればするほど、失笑ムードは収まらない。
「わかった。後は任せる」上司がアキラの報告を遮る。「こっちはバミューダシンドロームの調査で手一杯だ。ヤマーダ、しばらく高校生活を楽しんでくれ」
「……バカにしやがって」
ふと周りを見渡すと、雑談をしながらのんきにカレーを食べ続けている部下たちがいる。
アキラはうんざりと息をつき、ハルとココの映像を忌々しく見て吐き捨てる。「とっとと星に帰れ。俺はこんなとこでくすぶってるわけにはいかないんだ」
そしてPC画面をバミューダシンドローム関連の資料映像に切り替える。それは世界各国の海で船舶や航空機が突然行方不明になった事件のニュース記事や映像が集められたものだ。
「クワっ」タピオカがアキラを慰めるように鳴いた。
「わかってる。これも任務だ」アキラはむなしさを食い尽くすように、しらすカレーをかき込んだ。
ブクブクブクと泡を吐きながら、ハルがお湯の中に沈んでいく。
そこはユキの家のお風呂だ。
「はぁ~、やっぱり水の中はいいなぁ」
そしてハルはお湯を通じて遙か遠くの妹に呼びかけた。「ねぇココ、インド人怖いよぉ~」
その声は江の島の裏手の洞窟の中にある、ピンクに白い水玉模様の宇宙船へと届いた。その宇宙船の中は丸ごとプールみたいになっていて、黒いビキニ姿のココが気持ちよさげに浮かんでいる。
ハルとココは会話をしているがその口は動いていない。本来、彼ら種族には言葉などない。離れていても、水でつながっていれば互いに意志を伝え合うことができるのだ。
「あの目が怖いんだよぉ~。それにあの白い鳥ぃ~」
「あれはアヒルっていうの。きっと武器だに。目が合ったらウチら消されてまうに」
どうやら今日のココは名古屋訛りがお気に入りのようだ。
「えぇぇぇ~目ぇ合ったかもぉ~!」
「にいちゃん、その家出た方がいいっぺ」
「え、ナンデ?」
「あいつらに目ぇつけられたら面倒じゃけん。それにユキ、まだ一匹も魚釣っとらんし、他の子にしよまいて」
ハルはブクブクブクーっ!といっぱい泡を吐き出して聞こえないふりをした。
「にいちゃん? わかったと?」
ハルは答えない。答えたくなかったからだ。ココの不安はわかる。でも、ユキ以外の子にするなんて、ハルは一度だって考えたことがないのだ。
「また花のオセワ?」
風呂上がりでご機嫌のハルは、サミュエル・コッキング苑で花たちの手入れをするケイトに話しかけた。
「ちょっとの間会えなくなるでしょ? お花の顔、見とかないと」
「ケイト、聞いてもいい?」
「なあに?」
「この花はみんな死ぬよね?」
ケイトは少し驚いた顔をしたが、笑みを崩さず「そうね」と答えた。
「じゃあなんで大事にしてる?」
ケイトはわかっている。ハルに悪気なんてない。そんな概念すら知らないだろう。ハルはただ、この地球の上で、目に見えるすべてのものがなんなのか知りたいだけだ。
「……死ぬからよ」
ケイトは少しだけ迷ってそう答えた。
「……ワカンナイ」
ケイトは花たちを見渡し、根気よく目の前の宇宙人に地球の摂理を説明しようと試みた。
「みんないつか死ぬから、生きてる間は、きれいに、元気に、咲いて欲しいでしょ」
「ナルホド」どうやらそれはハルにとってわかりやすい答えだったようだ。ハルは自分を取り囲む植物たちを見渡し、言った。
「ほんとだ。きれいだね」
ケイトは微笑み、言った。
「ハル、ユキをよろしくね」
「うん。よろしくする!」
「ハル、ありがとうね」
「あれ? それ違う。僕、ケイトに何もしてない」
ハルは不思議そうな顔でケイトを見た。自分のために何かをしてくれたら「ありがとう」と言う。ケイトに教わったのは確かそういうことだったはずだ。
「ハル、『ありがとう』はね、何かをしてもらった時だけに言うんじゃないのよ」
「え、そうなの?」
「ありがとうは、嬉しい気持ち」
ケイトは一つ一つの言葉を、漏らさずきちんと伝えたくて、ゆっくり、そしてまっすぐハルに投げかける。「ハルはユキと友達になってくれた。一緒にご飯を食べて、一緒に学校へ行って、一緒に釣りをして。ユキにはそういう人がいなかったから私は嬉しいの。だから、ありがとう」
ハルの中に、ケイトが奏でる優しい言葉の響きがすっと染み込んだ。そしてその中で最も気に入ったフレーズを繰り返してみた。
「アリガトウは、嬉しい気持ち」
「そう。ユキだって本当は嬉しい気持ちを持ってるのよ。今はそれがうまく出せないだけ」
うん、うん、とハルは頷く。
ハルは何もわかってない。でも全部わかってる。
ケイトはそう思ったからこそ、こう続けた。「でもハルと一緒なら大丈夫。いつかきっと見せてくれるわ、嬉しい気持ちを」
ケイトはそう言って足元に置かれていた花の鉢植えを差し出した。
「これ、私だと思って持ってて」
「これ、ケイト?」
白や黄色やピンクのその花たちは、初めて出会ったハルと握手したがっているように、その花びらを細く長く伸ばしていた。
「何かあったら、この花を見るの」
「ナニカって?」
「たとえば、ユキを困らせそうになった時、ユキと喧嘩しそうになった時、嬉しくない時、何かお願い事をしたい時」
「いっぱいだね。見たらどうなる?」
ケイトはそっと胸に手を当てた。
「嬉しくなるわ」
ハルも真似して胸に手を当てて微笑んだ。
「毎日水をあげるのよ。そうすればしばらくは死なないから」
するとハルが食いついた。「これ、水ないと死んじゃう?」
「そう」
「僕といっしょだ」
ハルは嬉しそうな声でそう言って、花びらたちが作るふかふかのクッションに顔を埋めた。
アキラはそんなハルをじっと見ていた。正確に言えばアキラが見ていたのは、DUCK CURRYの店の中にある監視モニターだ。その鮮明な画像の中で、ハルはケイトがくれた花たちを見て微笑んでいる。そしてアキラの切れ長の細い目は、その無邪気過ぎる笑みを排除するように鋭い光を放っていた。
次の日の朝。江の島の空は、やるせない思いをぐっとこらえるユキのように、今にも降らんとする雨をぎりぎりのところで食い止めていた。
「さ、そろそろ行こうかしらね」
心配のあまり口をきけずにいるユキとは対照的に、ケイトは今日も微笑んでいる。そのいつもと変わらぬ笑みだけではなく、入院初日に似つかわしいとは言えないそのコートの真っ赤な色、そして「オッケー」というハルの能天気な声が、ユキの心をさらに深く沈ませている。
こうやってばあちゃんを病院へ見送るのは何度目だろう。笑顔で見送ってあげたらばあちゃんが安心することはわかっている。でもいつもできない。今度こそばあちゃんは戻って来ないかもしれない。そう思うと胸が締めつけられて何も言えなくなるし、とてもじゃないけど笑うことなんてできない。
ユキがケイトの視線を避けるようにリビングを出ようとした時、ケイトの声がした。
「エノ、シマ、ドン!」
ユキが驚いて振り返ると、ケイトがロッドを持つ手つきをして微笑んでいた。
「やめちゃだめよ、絶対」
ケイトはそう言って、ユキに魔法をかけるようにウインクをした。
ユキが何も答えられずにいると、代わりにハルが言った。「大丈夫。ユキやめない」
お前に何がわかるんだ。
ユキが軽くハルを睨むと、ケイトがハルの言葉をそっと受け継いだ。
「そうよね。やめたら悲しむものね、お友達が」
ケイトが入院する病院はユキとハルが通う高校のすぐ近くにある。
ケイトを見送り、病院から出て来たユキとハルはそのまま学校へと向かった。
ハルは足早に歩くユキに追いついて言った。
「ユキ、大丈夫。みんないつか死ぬ」
ユキはあまりの驚きで思わず立ち止まった。なんだこいつ。何言ってるんだ?
「だから」
ユキはそう言いかけたハルを睨み、歩き去った。
「ユキ?」
今度はハルが驚いてユキを見送った。
ユキは振り返らず、二人の距離は見る見る離れていった。
休み時間。夏樹は一人廊下で佇むユキを見た。
「あいつ、どうしたんだ?」
「おばあちゃん、ニューイン」
少し離れてユキを見ていたハルが、まるで単語を暗記しているかのように無機質に言葉を並べた。
「そうか」夏樹はそう答えてもう一度ユキを見た。
ユキは家に帰ると、すぐに部屋にこもり、ベッドに寝転んだ。スマホを取り出し、慣れた指づかいである言葉を検索する『肺MAC症』。長々と書かれた説明をスクロールする指が、ある箇所に来て止まった。『薬への耐性が強く、完治は難しい』……
ユキはスマホを放り投げ、寝返りを打った。
なんでだよ。なんで俺にばっかり悲しいことが起こるんだ。
目を閉じると、病室へ歩いて行くケイトの背中が浮かんだ。その悲しい記憶はどんどん過去へと遡って、やがてそれはぼやけた絵になった。目を細めて景色をぼやかしたような、涙でにじんで視界が遮られたような……思い出したいけど思い出したくない。もっとよく見たいけど見たくない……その不完全な絵の中に二つの丸が見えた。
またアレだ。顔。一人は男で、一人は女。それは知ってる。その顔を画用紙に描いたこともある。目も鼻も口もあるのに、まるでのっぺらぼうみたい。不思議だけど本当にそうなんだ。うまく言えない。誰かに伝える自信もない。ただいつもその二人は、俺の悲しい記憶の行き止まりに立っていて、黙って俺を見ている。それはどんなことよりも生々しいけど、全然リアルじゃない。俺は俺の中で、いつもその二人に言う。あなたたちは俺からどれだけたくさんのものを奪うつもりなんだ……どいてくれ。頼むからそこをどいてくれ。じゃなきゃ俺はいつまでもその先に行けないんだ!
ユキは苦しくて目を開けた。体は汗ばみ、小刻みに震えている。いつも思う。ここで思いっ切り泣いてしまえば楽なのにと。
でも嫌だ。そんなことしたら、何もかも俺の前からなくなってしまう……
「ケイト」
ハルはダイニングキッチンに置いた花の鉢植えに水をやりながら話しかけていた。
「ユキ元気ない。どうしたらいい?」
まるで本当に目の前にケイトがいるみたいに話すハルを、金魚鉢から赤い魚がじっと見ていた。
その窓際に、ハルが話しかけていたのと同じ鉢植えがある。そこは静かな病室で、ベッドにはケイトが横たわっている。ケイトは、ユキやハルには決して見せない不安げな顔でじっと宙を見つめていた。
「ユキぃー! 起きてぇーー!」
ハルの声が空に響いた。灰色の空は昨日よりも雨をこらえて、今にもはちきれそうだ。
「チコクしちゃうよぉーー!」
ハルがユキの布団をはがす。
ユキは何も言わず、力いっぱいハルから布団を奪い返して、その中にくるまった。
「もぉーーー!」
ハルはもう一度「起きて!」と叫ぼうとしたが、ふと何かを思い出し、ぐっとこらえて口を押さえた。
ユキの机が、主を待ちくたびれてひんやりと佇んでいる。
それを寂しげに見つめるハルを、夏樹が見ている。
そしてそんな二人を、アキラが表情なく見ていた。
ハルは学校帰りの長い坂道をいつになくゆっくり下りながら、今までに感じたことのない感覚に戸惑っていた。
これ、ナンダロウ。ぐにゃぐにゃする。いつもみたいに、力、ハイラナイ。でもそれ、誰にも言えない。これ、ナンダロウ……
「なぁハル」
ハルは突然話しかけられてびくっとなったが、それが夏樹だとわかるとほっとして笑顔になった。そして夏樹が隣に立つと、さっきまでの変な感覚が少しだけ治ったような気がした。
そして夏樹がハルを見て言った。
「どこだっけ? お前らん家」
「ここぉーー!」
ハルがユキの家を指さすと、夏樹は何も言わずにずんずん中へ入って行った。
ハルはぐにゃぐにゃしていた体がしゃんとなっていく気がして、急いで夏樹を追いかけた。
「ユキ、二階だよー!」
夏樹はためらうことなく家に上がり、階段を上り、ユキの部屋のドアを開けた。そしてユキの布団をはがすまで、少しも歩みを遅めることはなかった。
ユキはあまりの驚きで夏樹を見つめる他なかった。
「バケツ、入ったか?」
夏樹は、まだ驚きの中にいて何も答えられないユキに構わず言葉を続けた。
「情けねえなぁ。あんなのできないようじゃまだ釣らせるわけにはいかねえな。キャスティングの次はルアー操ったり、色々あんだからな」
「悪いけど」
ようやく驚きから抜け出したユキが夏樹の言葉を遮った。「今、それどころじゃなくて」
夏樹は布団をかぶったユキを見て少しだけ黙った。そして小さく息を吸って、言った。
「そういう時こそ投げんだよ」
その言葉は、綺麗に軌道を描くルアーのように、すっとユキの真ん中に吸い込まれた。ユキはなぜだか鼓動が高まるのを感じた。
夏樹の短い言葉には、言葉以上の意味があふれていた。そしてそれは自分にだけ投げかけられたものではないようにも聞こえた。
しかしユキは動かない。動けない。
夏樹はユキに背を向けた。何も言わないユキに呆れたわけではない。言ってやったと得意げになったわけでもない。ただ小さく息をついて、床に倒れ込んだロッドを手に取り、ハルに握らせ、部屋を出て行った。
ハルは黙ってロッドを受け取り、ユキの形をした真っ白な布団の塊を見た。
ユキとハルの夕飯は宅配のピザだった。ダイニングキッチンのテーブルに、まだ手のついていない三角形が二つ、少し離れて残されていた。やがてハルがタックルを手にやって来て、膝を抱えて椅子に座るユキに笑顔を見せた。
「ユキ、やろ、エノシマドン!」
ユキは何も答えず、じっと一点を見ている。しかしハルは笑みを崩さない。なぜだかそうしなきゃいけない気がしたのだ。ハルの頭の中には二つの顔が浮かんでいた。ケイトの笑顔と、ロッドを渡してくれた夏樹の顔だ。
「ユキがエノシマドン入ったら、ケイトも夏樹も嬉しい!」
しかしユキは顔をしかめ、ハルを拒んだ。
「お前、宇宙人だろ?」
ハルはなんでユキがそんなことを聞くのかわからなかったが、当たり前の答えを、当たり前に答えた。「そう。僕、宇宙人」
「わかんないだろ、俺の気持ちなんて」
キモチ……ハルはその言葉をなんとなく知っている。でも「わかるよ」とは言えなかった。
だって、ワカラナイ。わからなくちゃいけないのかな。そうしないとユキは困るのかな。
そう思っていると、ユキが苛立ったように言った。「わかるわけないんだよ」
ハルは驚いた。目の前のユキが突然ユキじゃないみたいに感じたからだ。
声が、なんか違う。顔も、違う。なんかまた、ぐにゃぐにゃしてきた。どうすればいいんだろう。今、ユキになんて言えばいいんだろう……
ユキはハルの言葉を待つことなく部屋を出て行こうとした。
「ユキが笑いますように」
ユキは驚き、振り返った。
ハルはこっちを見ていない。見ているのはテーブルに置かれた花の鉢植えだった。
「ユキが嬉しくなりますように。ユキがエノシマドン入りますように」
ユキは、目の前のハルが突然ハルじゃなくなったみたいに感じた。その声も、その表情も、今まで聞いたことも見たこともないようなものに思えた。
「ケイトが、元気になりますように」
その時、ユキの心臓が、そのむすっとした態度とは裏腹にビクっと震えた。
「これ、ケイト」
ハルはようやく笑顔を思い出し、言った。
「みんないつか死ぬ。だから、生きてる時、きれいに、元気に、咲いて欲しい」
ハルはその言葉の一つ一つに思いを込め、それを一滴もこぼさぬように、丁寧に運んでユキに届けた。
ユキはあまりにまっすぐ見つめるハルに耐え切れず目を伏せた。そして突然預けられたそのずしっと重たい言葉たちを、意地でも受け止めぬよう、一つ一つその心から振り払おうとした。
なんだよお前。宇宙人のくせに……どこでそんな言葉……
するとハルがユキの心を読んだかのように続けた。「ケイト、そう言ってた」
ばあちゃんが?
ユキは想像した。ケイトがハルにその言葉たちを預けただろう瞬間を。
ばあちゃん、いつの間に、そんなこと……
それでもユキはまだその言葉たちを拒み、振り払おうとした。それは軽い嫉妬かもしれなかった。自分がいなくて、ハルとケイトだけがいたその瞬間への……
ユキは部屋を出て行く。しかしハルの声はどこまでも追いかけてきた。
「ユキが眠れますように。ユキが起きれますように……」
ハルはユキには振り返らず、鉢植えに語り続けた。
だってケイトが言ってたから。ユキと喧嘩しそうになった時、嬉しくない時、何かお願い事をしたい時、この花に話しかけてって……
金魚鉢の中の赤い魚は、初めて見るハルの表情に驚きながらも、その姿を冷静に見つめていた。
ココに裏磯に呼び出されても、ハルは浮かない顔のままだった。
「にいちゃん、ユキとお別れしてくれるんよね?」
「……お別れ、したくない」
ハルは自分の声が小さくなっていることに驚いた。ナンデダロウ。ユキとお別れするなんて今まで一度も考えたことなかったのに。なんでもっと大きな声で言えないんだろう。
「ユキはそう思っとらんよ」
妹であるはずのココが、聞き分けのない弟を諭すようにそう言った。
「トモダチ、困らせちゃあかんよ」
それ、ケイトが言ってた、とハルは思った。ユキのことが好きなら困らせちゃいけないって。僕はユキを困らせてる? そんなの知らなかった。全然……
と、ココが視線を感じて振り返った。
遠くでアキラがタピオカを抱えて立っている。その後ろにはターバン姿の部下たちもいる。
ハルは怯えてココの後ろに隠れた。完全に兄妹は逆転してしまったようだ。
「もうあきらめよまい、ユキのことは」
ココが最後通告のようにハルに囁いた。
ハルは何か言おうとして口をぱくぱくさせたが、言葉は何も出て来なかった。
ユキ、困ってる? 僕、困らせてる?
なんで? 僕そんなことしたくないのに……なんでそうなっちゃうの……
ユキは自分の部屋のベッドで目を閉じた。
いつものように、その脳裏に今日の出来事が三倍速で再生され始めた。一時停止したのは三つのシーンだった。「みんないつか死ぬ」とハルが言った。「だから、生きてる時、きれいに、元気に、咲いて欲しい。ケイト、そう言ってた」
次はケイトがこう言った。「エノ、シマ、ドン。やめちゃだめよ、絶対」
最後は夏樹だった。「そういう時こそ投げんだよ」
ユキはそこで目を開けた。自分の中に何かがあふれてゆくのを感じて苦しくなった。全部吐き出したい。でもだめなんだ。そうしたら、何もかもなくなってしまうんだ……
「アキラメル。ユキ。アキラメル……」
ハルはその言葉を何度も繰り返し呟きながら歩いていた。
やがてとうとうこらえきれなくなった空がハルの頭をポツポツと濡らし始めた。
ハルは立ち止まって、雨に打たれた。見上げると顔に雨が当たった。
いつもなら気持ちいいのに、とハルは思った。なんで今日は違うんだろう。ナンデダロウ……
タピオカを抱えて歩いていたアキラは、雨降る浜辺に小さな人影を見つけて立ち止まった。
砂浜に置かれた赤いバケツと、微かに響くラインの音で、すぐにそれが誰なのかわかった。
ユキがバケツを目指してキャスティングをしているのだ。
ユキは服が濡れて肌にまとわりつくのを感じながら、何度もロッドを振りかぶり、バケツ目指してルアーを投げ続けた。しかしささくれ立つ心のせいか、その軌道は乱れ、初めて投げた時よりバケツは遠く感じた。
「くそっ!」
悔しくてロッドを投げ捨てたユキの背中に、その熱を冷ますような冷たい声が刺さった。
「もうあきらめたら?」
アキラだった。
「意味ないって、あんなとこ入れたって」
ユキはアキラの冷たい笑みに異議を唱えようとしたが、何も言葉が出て来なかった。それどころか、アキラの言う通りかもしれないとさえ思った。そう思ってしまった自分が情けなくて、ぎゅっと拳を握りしめた。
そしてアキラの憐れむような視線に負け、どんどん顔がこわばっていくのを感じた。
その変化と呼応するように雨が激しくなり、ユキのこわばった顔の皺を滴が伝った。
そこへ歩いて来たハルとココは、ユキと、そしてアキラを見つけた。
「あ」
ハルとココは慌てて身を伏せる。
「にいちゃん、行こまい」
「……だめ。ユキ、考えてる」
ハルは立ち尽くすユキの背中を見ていた。
「ほっとき。にいちゃんにはユキの気持ちなんてわからせんのだから」
「わかる」
ココは、迷いのない口調でそう答えたハルを見た。
「ユキ、一人でいる時、大切なこと考えてる。ケイト、そう言ってた」
その時、浜辺に数人の人影が現れた。雨を避けて騒がしく走って来た、えり香とクラスメイトたちだ。
「あ」
えり香はユキに気づいて立ち止まった。
「またやってんのか」「インドもいるし」
ユキの耳に、クラスメイトたちのちょっと意地悪な囁きが聞こえた。ユキの顔は、さらにテンパって般若へと近づいてゆく。
えり香だけは笑うことなく、ユキを見つめている。どうしたんだろう。何をしてるんだろう。
えり香はさっぱりわからなかったが、何か普通じゃない空気を感じた。
ユキは周りのものすべてを拒むようにそっと目を閉じた。
するとその脳裏に、様々なシーンが駆け巡り始めた。病室へ歩いて行くケイトの背中、花に願いを込めるハル、まっすぐ自分を見据える夏樹、そして記憶はまたどんどん過去へと遡り、また行き止まりに立つ、ぼやけた二つの顔にぶち当たった。
ユキは目を開けたかった。今すぐその二つの顔から逃げ出したい。でもなぜかできなかった。
今、目を開けちゃいけない。ちゃんと、見なきゃ。はっきり、それを……
ユキはすっかり般若になった顔のまま、目を開けまいと、瞼にぎゅっと力を込めた。
すると脳裏に浮かんだぼやけた顔が少しずつはっきり見え始めた。その人たちは、ほんとはのっぺらぼうじゃない。ちゃんとそこにいて、俺を見てる。見せろ。見せてくれ、その顔を! そしてユキは見た。手を振る父と母を。そして二人を見送る幼い自分を……
ユキは何一つ見逃さないように、もう少しだけ瞼に力を込めた。
俺は、覚えてる。あの時、手を振り返したかったけど、そうしなかった。何もできずにただ立ち尽くしていた。これは、何だ? なんだっけ? とぼけるな。本当ははっきり覚えてる。今まではずっとぼやけてたけど、今、完璧に焦点が合って、はっきり見える。
俺は、捨てられたんだ。
なんで? なんであなたたちは俺を一人にしたの? 手を振って、それからどこに行ってしまったの? 本当に、俺に手を振ってくれた? もしかしてそれは、俺が俺をこれ以上傷つけないために、自分自身で創り出した幻かもしれない。
ユキは遠い記憶の中で、絶望の淵へと沈んでいった。
俺は、見てしまった。思い出してしまった……
しかしそんなユキを救ったのは、幼い手が感じていた温もりだった。振り返るとばあちゃんが立っていて、そこにいつもの笑顔があった。そう、ばあちゃんはあの時、ずっと俺の手を握ってくれてた。ずっと俺のために笑ってくれてた……でも、なんでばあちゃんまで、いなくなっちゃうんだ……なんで、なんでだよ!
「あぁーーーーーーーー!」
ユキは目を開けると、般若顔のまま、大きくロッドを振りかぶった。
ハルも、ココも、アキラも、そしてえり香やクラスメイトたちも、突然のことに声を失った。
「エノ、シマ、ドーン!」
ユキは腹の底からそう叫んで、バケツ目指してロッドを振った。
「ユキ」ハルが立ち上がってユキを見る。
「エノ、シマ、ドーン!」
ユキは外しても、外しても、何度も叫んでキャスティングを続けた。
もうクラスメイトたちの顔にはユキを嗤うような笑みはなかった。彼らの目は、まとわりつく闇から逃れるようにもがくルアーを追っている。
「ユキ……ユキ……」
祈るように囁くハルをアキラが見る。
「にいちゃん」
ココが警戒し、今にもユキの元へと駆け出しそうなハルの手を掴んだ。
「ユキぃーーーー!」
ハルはココを振り払って走る。そして叫ぶ。
「エノ、シマ、ドーーン!」
その声に誘われるように夏樹がやって来た。
ランニングで上がった息のまま、トレーニングウェアのフードを上げると、そこにはキャスティングをするユキがいた。「エノシマドン!」と声を合わせるハルがいた。
雨は徐々に激しさを増したが、誰も立ち去ろうとはしなかった。「あきらめろ」と言ったアキラでさえ。
投げ疲れて心が折れかけるユキを救ったのは意外にも雨だった。濡れた指がスプールリングの上で滑って、飛び過ぎたルアーが速度を落とし、バケツの縁に触れて音を立てたのだ。
「あー惜しいっ」
えり香が小さく天を仰いだ。
そうか。今、指が滑ったから……
ユキがロッドを大きく振りかぶった。
夏樹が身を乗り出す。アキラが瞼に流れてきた水滴を指で拭う。そして、ユキとハルが、これ以上ないという大きな声で叫んだ。
「エノ、シマ、ドーーーーーン!」
するとルアーがミサイルのように強く鋭い軌道を描き、ユキは夏樹に教わったフェザーリングを試した。ルアーは一同の祈りに応えるように減速し、底の濡れたバケツの中で勝利の鐘を鳴らした。
「……入った」
その余韻は激しい雨の音さえ消し去り、浜辺一帯を支配した。そして、その静かな余韻を突き破ったのは、ハルの喜びに満ちた声だった。
「やった!やったぁーー!」
ハルは飛び上がってユキに抱きついた。
えり香らクラスメイトたちはほころんだ顔を見合わせた。まるで期待せずに見た映画が素晴らしい結末を迎えた時のように。
その雨の劇場の中、一足先に席を立った夏樹を、ユキが荒い息のまま呼び止めた。
「夏樹」
夏樹は驚き、振り返った。ユキが自分の名前を呼んだのは初めてだ。そう思った次の瞬間、
「ありがとう」というユキの声が聞こえた。
「俺、できた……ありがとう」
その声は、少し離れたところに立つ夏樹に届くか届かないかの小さな声だった。おまけに少し震えていたし、映画のクライマックスの台詞としては実に頼りないものだった。
「なんもしてねえよ俺は」
夏樹は急に観客からスクリーンの中の人物になった自分が恥ずかしく、フードを被り、走り去ろうとした。
「夏樹、それ違う!」
夏樹はそのボリュームを間違えたような大音量の声に振り返り、ハルを見た。
「夏樹、ユキにエノシマドン教えた。だからユキ嬉しい。ユキと友達になった。だからユキ嬉しい!」
夏樹はスクリーンの中の人物になっただけではなく、あっという間に主役に上り詰めてしまったようだ。ユキと気まずく視線を絡ませ、立ち去るにも立ち去れず、目を伏せた。
「アリガトウは、嬉しい気持ち!」
ハルという、雨の中の太陽がそう叫んだ。
何も言葉を用意していなかった夏樹は、頭を真っ白にして心のままに任せた。
「ユキ」
初めて名前を呼ばれて、ユキは夏樹以上に驚いた。
「そんなの、まだ序の口だからな」
その声はユキと同じように震えていて頼りなかった。夏樹は恥ずかしさをごまかすように急いで走り去った。
ユキは夏樹を見送った。そのグレーのトレーニングウェアが闇に吸い込まれて見えなくなるまで。
「ありがとな、ハル」
ユキのその呟きをハルは聞かなかった。「僕も入れたーい!」と、ロッドを振りかぶり、キャスティングを始めてしまったからだ。
その時、ユキはこっちを見て微笑むえり香と初めて目が合った。するとさっきまでのヒーローは、途端に気の弱い主人公へと戻った。
「タピオカ」アキラが砂の上をトコトコ歩いていたタピオカを抱き上げて、誰もが夢中になった物語にケチをつけるように呟いた。
「俺、嫌いだな、ああいう暑苦しいの」
海沿いの道を走る夏樹は、徐々にその速度を上げた。そして、「あ、あ」と、雨の音にそっと忍ばせるように声を出してみた。やがてかすれた声を整え、叫んでみる。
「あぁーーーー!」
それは何の叫びなのか、夏樹自身にもわからなかった。でも夏樹はユキがバケツに向かってルアーを投げたように、この頼りない声を、闇の向こうのどこかへ届かせようと、何度か叫んだ。
浜辺では、飽きるまで同じおもちゃで遊び続ける子供のように、ハルがキャスティングを続けていた。
ユキは呆れたように微笑み、海を見た。そしてそこにルアーを投げ入れる自分の姿を想像してみた。ユキの頭の中で、ルアーは海深く潜り、まだ見ぬ魚たちを目指して消えていった……