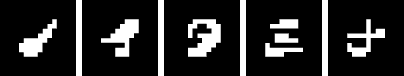NOITAMINA
OFFICAIL WEBSITE
SHARE
ツイート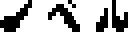 NOVEL
NOVEL
ノイタミナノベル「つり球」 第5話

「ハル、庭の花もな」
ユキは鍋のお湯に赤味噌を溶かしながらハルに言った。
「オッケー♪」
リビングの鉢植えに水をやっていたハルが、手にしたじょうろからポタポタと水をこぼしながら庭へ駆け出して行く。
ケイトが入院してから、ユキとハルの朝は忙しくなった。朝ご飯を食べたら片づけなきゃいけないし、洗濯して、それを庭に干して……
本当はもう少しゆっくりしていてもいいのだが、ユキには学校へ行く前にどうしてもやりたいことがある。釣りだ。
おかげで早起きには慣れた。でも俺にとって大変なのは早起きでも炊事でも洗濯でもない。ハルだ。
ユキが、ハルが床にこぼした水を雑巾で拭き、庭を見ると、ホースで気持ちよさげに水浴びをするハルがいた。
「ふぅ~気っ持ちいいぃー!」
「お前何やってんだよ!」
ハルはなぜか水が好きだ。お風呂は長いし、トイレに入れば延々とお尻を洗い続ける。洗濯をさせれば、入れ過ぎた洗剤で出来た無数の泡でシャボン玉を作り始める。
「お前、洗剤入れ過ぎんなって言っただろ!」
いくら怒ってもハルには通じない。何を言っても「ごめんごめーん♪」と、反省のかけらもない場違いな愛嬌で返されてしまう。悪気はないのはわかってる。だってこいつ宇宙人だし……
「いいかハル、もう余計なことすんなよ」
「オッケー♪」
こんな時は深呼吸だ。そうしないと今にも鼻や口から怒りのマグマがあふれ出してしまう。
朝の浜辺は清々しい。これであのバケツにルアーが入ればもっと清々しい気持ちになるのだろうが、あの雨の夜以来、奇跡は起こらない。
そりゃそうだよな、とユキは思う。釣りなんてまだ始めたばっかりだし。でも小さな奇跡なら今も起きてる。自分がこうやって何かに夢中になり始めているということ。こんなこと今まで一度だってなかった。だから、釣りたい。この手で、俺だけの魚を。
ユキはそんな願いを込めてロッドを大きく振りかぶった。
「エノ、シマ」
「ドーン!」と、いきなり割り込んできた声にユキは驚き、そのせいでルアーはバケツの遥か手前にパタンと落ちた。叫んだのはもちろん自分じゃないし、バケツの向こう側にいるハルでもない。振り返ると、見覚えのある顔が笑っていた。
あ、この人……
それは仲見世通りにあるしらす屋の主人だ。毎朝、学校に行く時に挨拶されるのだが、いつも緊張して、うまく挨拶を返せたことがない。
今日こそ、挨拶しなきゃ。
そう思えば思うほどユキの顔はこわばり、声が出なくなる。
どうしよう……
と、その時、
「保っちゃん、おっはよぉー!」
ハルが保に駆け寄った。
「おはよう、ハル」
驚くユキをよそに、二人は顔を合わせ、まるでリハーサルでもしたかのようにぴったり合った動きを見せた。
「ハイノハイノハイノー!」
その手を左右に動かす動きは見たことがある。確か「江の島おどり」というやつだ。一度江島神社に行った時、神主らしきオジサンを囲んで島の人たちが踊っているのを見たことがある。
ていうか、あいつ、いつの間に仲良くなってんだ?
「保っちゃん、ナンデ『エノシマドン』知ってる?」
「なんでって、俺が考えたんだよそれ」
え? でも、あれは……
「違うよ。エノシマドン、夏樹が考えた」
ハルがユキの心を代弁するかのようにそう言うと、保の目が輝いた。
「夏樹って、うちの夏樹か?」
元祖しらす亭に、というか、夏樹の家に入るのは初めてだ。外に「準備中」の札がかかっていたが「食ってけよ」と保が中に入れてくれた。
「はい、江ノ島丼お待たせー」
白い割烹着が眩しいその女性はここの店員のようだ。
「サンキュー、マリちゃん」
ユキは驚き、ハルを見た。
こいつ、どんだけ顔広いんだ? ていうか、いつの間にこの店来てたんだよ。俺なんてまだ江ノ島丼、一度も食べたことないのに!
ハルは、慣れない場所でかしこまるユキとは対照的に、座敷にあぐらをかき、「いっただっきまーす!」と、丼をかきこみ始めた。
ユキはといえば、「いただきます」すら言えずに真理子に目で会釈をした。
ご飯、食べたばっかりなんだけど……
そう思いながらも、スマホの画面で見ただけの江ノ島丼が目の前にあると、やはり食べたくなってしまう。
「そっかー」保が首にかけたタオルをごしごしこすりながらユキのすぐそばに椅子を持って来て座った。
ち、近い!
ユキはよく知らない人にいきなり近づかれるのも、そして声が大きい人も得意じゃない。でも保はずっとニコニコしていて、きっと悪い人じゃないんだろうなとユキは思った。
「夏樹が釣り教えてる友達って、ハルと」
保が、丼の中に隠れんばかりに縮こまっているユキの顔を覗き込んだ。
ユキがテンパって何も言えずにいると、ハルが無意識の助け舟を出した。
「ユキ」
「ユキ君、だったのか。夏樹よろしくな。あいつムスっとしてるけど悪い奴じゃないから」
ユキは「ええ。そうですよねー!」という、強い同意の意味を込めて頷いたが、ちゃんと伝わったかどうかは自信がない。
「おい夏樹ぃー! 友達来てんぞー!」
保が、ユキがびっくりしてサザエをこぼしそうになるほどの大声で二階に呼びかけると、真理子がその笑顔と同じくらいの柔らかさでそれを咎めた。「まだ寝てるんじゃない?」
この真理子さんって人も、なんかいい人っぽいな。
ユキは何も言えずにそんなことばかり考える自分にちょっと嫌気がさした。おかげでせっかくの人生初の江ノ島丼をちっとも味わえてない。
「夏樹ぃー! アサネボーだめだよー!」
お、お前、余計なこと……
しかし保も真理子も楽しそうに笑っている。
え、そっか。俺も笑えばよかったのかな……
ユキがまたそんなことを気にしていると、店の奥の階段を誰かが駆け下りて来る音がした。え、夏樹? にしては、勢いが……それは夏樹ではなく妹のさくらだった。
「ハルちゃーん」
「あ、さくらぁー!」
ユキはまた江ノ島丼から意識が離れた。無理もない。ハルとさくらがハイノハイノハイノー!と声と動きをぴったり揃えたのだ。
なになに? それ流行ってるの? 俺の知らない間に!?
「ハルちゃん声おっきいからすぐわかった」
「なんだ、さくらも仲良しか?」
「うん。ハルちゃんチョー面白い」
どういうことだよハル。このさくらって子に初めて会ったの、ついこの間じゃないか。ったく、いつの間に……
「ユキ、夏樹の家族チョー仲いい!」
ユキはこっちを見る四人の笑顔に押され、ぎこちない笑みで頷いた。
「保っちゃんとマリちゃんもチョー仲良し」
「だって、マリちゃん」
さくらが悪戯っぽく真理子の顔を覗き込むと、真理子がふと顔を赤らめた。そしてそれはあっと言う間に保にも伝染した。
「ま、まぁな」
ユキは、首にかけたタオルをちょっと強めにごしごしし始めた保を見て感づいた。え、この二人って、そういう関係?
「あ、そうだ。私、洗い物」
明らかな棒読みでなんとかその場を離れた真理子だったが、いきなり動いたからか足を滑らせて危うく転びそうになった。
「お、おい、大丈夫か?」
さくらが、真理子よりも数段ひどい棒読みでそう言った保を見てクスクス笑い始めた。
二人の緊張はなぜかユキにまで伝染し、もう江ノ島丼どころではなくなってしまった。
「ハル、お前、余計なこと言うなよ」
そんなユキの囁きを、ハルが何倍もの音量で増幅させた。
「え、余計なことってなにー!?」
「シーっ」
するとさくらのクスクスがケタケタに変わった。
「そうだ。お前ら」保が照れ臭さからなんとか抜け出そうとして言った。「何狙ってんだ?魚」
「あのね、すっごいの狙ってる!」
「すっごいのって?」
「江の島の海にいる、チョーでっかいヤツ!」
そう言って目を輝かせるハルを、アキラがDUCK CURRYの監視モニター越しに見ていた。
「でっかい魚? それを釣れば帰ってくれるのか? 宇宙人」
するとタピオカが「そうかもしれないね」と言わんばかりに「クワっ」と一鳴きした。
「でっかいのってどのくらい?」
モニター画面の中のさくらが言った。
ハルが「あのね」と身を乗り出すと、アキラもその答えを知りたくて身を乗り出した。
釣りには自信がある。任務とは関係ない趣味の範疇だが、地球の魚を珍しがる観光宇宙人を満足させるだけのものを釣ることは可能だ。その大きな魚を見せてやれば、あのハルという、恐らく地球でいえば五歳児程度の知能しか持ち合わせていないだろう宇宙人は喜んで星に帰って行くだろう。任せろ。どのくらいの大きさだ? 江の島ならクロダイか、あるいはシーバス、シイラあたりか……
しかしハルの答えはアキラの想像を遥かに超えていた。ハルは店の中を端から端まで走り回ってこう言ったのだ。「このお店よりも、もっともーっとでっかいの!」
目測を、誤った。
アキラは恐らく同じことを感じたであろうタピオカと目を合わせた。
あいつは三歳児、いや、それ以下だ。そんなにでかいとしたらそれは魚じゃない。ただの化け物だ。
アキラは苛立つ気持ちを抑えようと、まだ湯気の立つチャーイをゆっくりと口に含んだ。
「そっかぁ。釣れるといいなぁ」
保が元気いっぱいの孫をあやすようにそう言うと、ハルはいいアイデアを思いついたとばかりに目をキラキラさせて切り出した。
「保っちゃんも一緒にやる?」
「え?」保は不意を突かれた。
「僕と、ユキと、夏樹と、一緒に釣りやる?」
保の顔に浮かんだ笑みは、単純な喜びを表す笑みではなかった。それは恐らく、相手を傷つけぬようにどう断ろうかと思案する時のそれだ。
こいつ、また余計なこと……
ユキは江ノ島丼を楽しむことは次に持ち越そうと決めて、心の中で頭を抱えた。
「あぁ、いいけど、夏樹がウンて言わねぇんじゃねぇかなぁ」
「ナンデ?」
「あいつ、最近付き合い悪いからなぁ」
ユキはお茶を飲むふりをしながらこっそりと見た。苦笑いするしかない保と、気まずく目を伏せた真理子と、そして、その顔からクスクスもケタケタも消えてしまったさくらを……
そんなしらす亭の光景をこっそり見ていたのはアキラだけではなかった。いや、正確に言えば見てはいない。階段の途中で座り込み、その気まずい沈黙をじっと感じている。それはトレーニングウェアに身を包んだ夏樹だ。夏樹は朝の日課であるジョギングをあきらめ、軋みやすくなった階段を、音を立てぬようにそっと上り始めた。
「ハルったらおかしいわね」
ユキは、ケイトの思ったより元気そうな笑い声に安心した。学校の帰り、ハルを撒ま
いてケイトの見舞いに来たのだ。ケイトに聞いて欲しかった。ハルが毎日どれだけ余計なことをして自分を困らせているか。しかしどのエピソードもケイトにとっては愉快な笑い話にしか聞こえなかったようだ。
「笑い事じゃないって。大変だよ。朝から大騒ぎだし、誰にでも余計なこと言うし」
「でもそれがハルのいいところじゃない」
「え?」
「ハルには不思議な力があるのよ。みんなの心を溶かす力」
「……でも一緒にいる方はたまったもんじゃないよ」
なんでだよばあちゃん。
ユキはいつだってケイトに味方してもらえるハルに軽い嫉妬を覚えた。今、視線の先にある植木鉢の花たちも、ハルがケイトにもらったものとおんなじだ。そう思うと、知らない間に自分のいない世界が出来上がりつつある気がして、さらに気分が沈んだ。
「でももしハルがいなかったらどう?」
ユキの心を察したのか、ケイトは笑うのをやめ、ユキの色を失った目に問いかけた。
「毎日、楽しいかしらね」
ユキは何も答えなかった。これ以上ハルを悪く言っても仕方ないし、ばあちゃんを心配させるのはもっと嫌だ。でも正直に言えば、ハルと二人きりの毎日は楽しいとは言い難い。
ばあちゃん、早く帰って来てよ。
ユキは一番言いたかった言葉をぐっと飲み込んで、ケイトに曖昧に笑ってみせた。
「エノ、シマ、ドーン!」
ユキは目を疑った。ハルが投げたルアーがバケツに入ったのだ。
「はじめて入ったぁー! ユキ見た?」
「まぐれだよ」
ハルは悔しさいっぱいにそう返したユキをよそに、浜辺を駆け回って喜んだ。
「よし、二人とも入ったことだし、そろそろ本番といくか」
ユキとハルのキャスティングを見守っていた夏樹が言った。
「本番って?」
ユキがそう尋ねると、夏樹は眩しげに海を見た。「投げるんだよ、海に」
「え、いいの?」
「ああ。だって約束だろ」
沈んでいたユキの心に太陽が射し込んだ。
やった。やっと海に投げられる!
するとハルがその心を見透かしたようにユキの頬っぺたを突っついた。
「ユキ、チョー嬉しそーう!」
「う、うるさいよお前」
ユキは慌てた自分が恥ずかしくて、こっちを見て微笑む夏樹から目をそらした。
「お前らはまだ釣りの醍醐味を知らない」
小道を抜けてたどり着いた釣り場で夏樹がユキとハルに言った。
「ダイゴミ?」
ハルにとっては初めて耳にする言葉だ。
「釣りの本当の楽しさだよ」
ユキは少し慣れてきた手つきでラインとルアーをユニノットで結びながらコーチの言葉に耳を傾けた。
「釣りってのは、ただ釣れればいいってもんじゃない。自分の頭で考えて釣るから楽しいんだ。まずは狙いを定める」
夏樹は目の前に広がる海を見渡した。
「さぁシーバスはどこにいる?」
シーバスとは、この辺りの海で釣れるスズキのことだ。夏樹はユキとハルに初めて釣らせる魚をシーバスにしようと決めたのだ。
ユキは前に魚を釣りかけて、寸前でラインを切らせてしまったことを思い出し、ラインを結ぶ指に少し力を入れた。でも……
あいつらがどこにいるかなんて、さっぱりわからない。
「お前らキャスティング練習したんだからどこにだって投げられるはずだろ?」
ユキが何も答えられずにいると、ハルが一方を指さして「あそこっ!」と叫んだ。
ユキはやれやれと息をつく。クラスに一人は必ずいる。答えがわからないくせに何でもかんでも「はい! はい!」と手を挙げる奴。
「どうしてそう思う?」
今日の夏樹はどうやら鬼コーチではなく、でたらめの答えにも付き合ってくれる優しい教師のようだ。
ハルが指さした場所はここからさほど遠くない岩の辺りだった。
「だって、太陽熱いから!」
なんだよそれ。また適当なこと……
「いい線ついてるな」
「え?」ユキは夏樹の言葉に耳を疑った。
いくら優しいコーチでも、嘘はよくない。
しかし夏樹は、ハルの答えを支持するように説明を始めた。「シーバスは岩とか障害物に集まりやすいんだ。あいつらは光を嫌うし、ああいう場所なら敵からも身を守れて餌も食べやすい」
ハルが「へへへー」と得意げにユキを見た。
ユキはキャップを被り直し、気づかないふりをした。
「じゃあ、あそこに何を投げる?」
「ご飯っ!」
「そうだ」
二問立て続けに正解して、ハルのテンションはさらに上がった。
「シーバスの飯はこれだ」
夏樹はルアーボックスから色とりどりのルアーを出した。シーバス釣りの基本はミノーというルアーだ。小魚の形をしていて、口のところにリップという舌のようなものがついている。これがあれば深く沈んでいくのだという。
「僕これー!」ハルは赤いミノーを選び、顔ぎりぎりまで近づけ、なぜか唾をごくりと飲み込んだ。「本物のサカナみたいー!」
「こいつに芝居をさせればもっと本物に近づく」
「芝居?」
そう尋ねるユキに夏樹が答える。
「海の中で魚を誘うように動かすんだ。いわゆるリトリーブってやつだ」
リトリーブとはリールで巻き取るという意味だ。その巻き方によってルアーは様々な動き方をする。それを夏樹は「芝居」と呼んだのだ。
「エノ、シマ、ドーン!」
ユキとハルは早速練習の成果を見せた。前よりも明らかに狙い通りにルアーが飛んで行く。そして「ただ巻き」という、文字通りただ巻くだけの操作でルアーに芝居をさせる。一定のスピードで巻くだけで、ルアーは小魚のように泳ぎ、狙った場所がよければ魚はそれを餌だと思ってくれるのだ。
「次は、想像する」夏樹が次のステップへユキとハルを導く。「水の中のルアーが今どこを動いてるか。魚がそれを見てどう感じるのか」
ユキはじっと海面を見て、小魚に成りきったつもりでまだ見ぬシーバスを誘い続けた。
「で、アタリがきたら合わせる」
アタリとは魚がルアーに食いつくことだ。
「反応を感じたら、すぐにロッドを立てて魚に針をかけるんだ」
「痛たたーっ!」
ユキはハルの大きすぎる声に顔をしかめた。
お前、魚の気持ちになってどうすんだよ!
「それまでは、集中」と夏樹が言う。「魚はいつ食いついてくるかわかんねえぞ。集中してアタリを見逃すなよ」
ユキは気を引き締めるようにロッドのグリップを握り直した。いつ敵が迫って来るかわからない。これが釣り独特の緊張感なのかもしれない。そう思うとあっという間に全身が汗ばんでくるのを感じた。
するとユキはその手に、想像していたよりも強い振動を感じた。
「あ、なんか……」突然のことで言葉が出ない。もしかしてと思った時にはもうロッドの先が大きく動いていた。
「ユキ来たぁー!」
ハルの大声がさらに緊張を高めた。
夏樹が叫ぶ。「合わせろ!」
マジで!?
ユキが夢中でロッドを立てると、大きな魚が水面から跳ね上がり、銀のうろこが光るのが見えた。
「シーバスだぞ」夏樹が「覚悟を決めろ」とでも言わんばかりにユキに告げた。
「わっ、ちょっ!」あまりの衝撃でそんな情けない言葉しか出てこない。あのシーバスはこの前釣れそうになった奴よりもっと大きいかもしれない。引っ張られるたびに汗ばんだ手が滑って体ごと海に持って行かれそうになる。
「踏ん張れ!」
ハルが夏樹の言葉を真似て叫ぶ。
「ユキふんばれぇー!」
わかってるって! お願いだから黙っててくれよ!
「無理すんな! 引っ張られたら巻くな!」
え、巻いちゃだめなの?
「今、無理に巻いたら魚を逃す!」
夏樹は決して手は貸さず、ユキを操縦するかのようにその背中に声をかけ続ける。
「こっからはあいつとの駆け引きだぞ。巻きたくなっても今は我慢」
我慢。
「自分だけの感覚で動いても相手は思い通りになってくれないぞ。感じろ、相手を」
ユキは焦るなと自分に言い聞かせ、針から逃れようと泳ぐシーバスの力を全身で受け止めた。
と、次の瞬間、
「あれ、なんか」
「どうした!?」
すっかり鬼コーチに戻った夏樹が問い詰める。
「なんか、力が、スっと抜けたみたいな」
「今だ、巻け!」
ユキは、目の前のシーバスと、背後の鬼コーチのプレッシャーに挟まれて顔をこわばらせながら必死でリールを巻いた。
す、すごい力!
ハルが徐々に近づいてくるシーバスに興奮を隠せず、叫ぶ。「来た来た来たぁー!」
「近づいても焦るな。エラ洗いするぞ」
そうだ。あいつらめちゃくちゃ暴れるんだ。
その記憶がさらにユキを追いつめる。そして再び手元に来た強い振動に過剰に反応し、「来た。来た!」と、必死でリールを巻く。
「ダメだ、巻くな!」
しかしもはや般若顔寸前になったユキには何も聞こえない。
「わっ、ちょっ、とぅあー!」
シーバスはユキの意味不明の雄叫びをあざ笑うかのように猛烈にエラ洗いし、無事に針から逃れ、再び自由を手にした。
「あ……」
「最後に焦ったな」
夏樹のその言葉が、ユキには「まだまだだな」に聞こえて、たまらなく悔しくなった。
「ユキどんまいっ!」
その空気を読まぬ言葉にイラついたユキは思わず言葉を返した。
「お前がうるさいからだろ」
するとハルはいつものように笑って言った。「ごめんごめーん♪」
ユキは深呼吸で怒りのマグマを抑え、その場にがっくりと座り込んだ。
夏樹はそんな二人を、いないはずの弟たちを見るように微笑ましく見つめていた。
「わー、すっご~い!」
HEMINGWAYの前の駐車スペースで、海咲が甲高い声を上げた。
目の前には、世界各国から取り寄せた様々な釣り具たち。釣り具マニアの海咲からすればよだれが止まらない代物ばかりだ。それらはすべてアキラが運転するDUCKの黄色いワンボックスカーのバックシートに積まれている。
もちろんその宝の持ち主は、車のボディによりかかって自慢げに微笑むアキラだ。
「出た、ステラSW!」
海咲が宝石の中から一番お気に入りの指輪を見つけ、そっと指にはめるように、そのリールを手に取った。
「この光沢、色っぽいよねー。惚れちゃう♪」
その最後のフレーズに過敏に反応したその男は思わず熱い紅茶を噴き出しそうになった。
井上歩は、開け放たれた店のドアの向こうのカフェスペースから、突然現れたインド人の恋敵を訝しむように見ていたのだ。
あのインド人、何モンだ……
眉をしかめるたびに右眉を横切るようにできた傷がぐにゅっと動き、彼の明るさを象徴しているはずの鮮やかな金髪とピンクのTシャツさえすっかりくすんで見える。
「これで大きな魚を釣りたいんですけど」
と、アキラはまんまと餌に食いついた乙女に本題を切り出した。
「この辺で大物って言ったら……」
その瞬間、業を煮やした歩がカウンター席から立ち上がり、最愛の人を守るべく恋敵の前に立ちはだかった。「今、なんつった?」
「はい?」
すると、歩の恋物語にまったく気づいていないだろうヒロインが言う。
「あ、そこの釣り船の船長さん。歩ちゃん」
「はぁ」
歩は少しひるんだように見えたアキラに追い打ちをかけるように顎を突き上げ、言った。
「大物がどうとか言わなかったかい?」
「言いました」
「歩ちゃんね、大物釣りが得意なの」
歩は最愛の人の援護を受け、ここぞとばかりに声を張り上げる。
「俺に言わせりゃ六〇センチ以下は魚じゃねえ」
「はぁ」
アキラは別にひるんだわけではなく、突然割って入って来た、自分とまるで違うタイプの熱い男に引いているだけなのだが、物語に入り込んでいる歩はもう止まらない。
「俺の船に乗りゃあ、なんだって釣らせてやるさ。シイラ、カツオ、マグロにカジキだって」
「はぁ。今度是非連れてってください」
アキラが社交辞令という冷たい水をかけたが、歩の熱は一向に冷める気配はない。
「構わねえよ。ただ一言、言わせてくれ」
「なんですか?」
「釣りってのは道具じゃねえ」
そして歩は、細身の割にはたくましい二の腕を拳でゴンと叩いた。「腕よ」
アキラは返す言葉が見つからず、海咲を見た。
「歩ちゃんカッコいい~♪」
アキラは驚いた。助けを求めたつもりの海咲が、歩に水をかけるどころか火をつけてしまった。
「ちょっと失礼」
歩はアキラに勝ち誇ったようにそう言って、店の裏手へと走り、安っぽい青春ドラマのように海に向かって叫んだ。
「やったぞぉー!」
なんだ、この茶番は……
「ああいう、人なんですか?」
アキラが脱力したように尋ねると、いつの間にか青春ドラマのヒロインとなった海咲は、ステラSWを手に取った時と同じくらいの温度で言った。「そうなの。可愛いでしょ?」
またもや言葉を失ったアキラの足元に、目の前の茶番劇に退屈したのか、タピオカがトコトコ歩いて来て、早く帰ろうとばかりに「クワっ」と鳴いた。
「あの、お名前は?」
アキラはこの安っぽい青春ドラマに自分もキャスティングされてしまったような気がして気恥ずかしかったが、答えない理由もないので正直に答えた。「あ、アキラです」
「あ、いや」
見ると海咲はしゃがみ込んでタピオカと目を合わせていた。
そ、そっちか!
アキラは少し顔を赤らめ、何事もなかったかのように答えた。「……タピオカです」
「タピオカ~♪」
海咲は微笑み、タピオカの小さな頭を撫でた。そこへ店長という名の、茶色い飛行船のような猫がやって来て、突如縄張りを荒らしに来た未知なる敵に睨みをきかせた。
「じゃあ、明日の朝な」
陽が落ちた仲見世通りの入口で夏樹が言った。
「うん」
「明日こそ釣ったるでぃ!」
ユキとハルに微笑み、立ち去ろうとする夏樹を、ハルが呼び止めた。
「夏樹、明日、保っちゃんも連れて来て」
夏樹の背中がビクっとなった。
「保っちゃん、夏樹と釣りしたいんだって」
「お前、やめろって」
ユキは夏樹の背中が醸し出す不穏な空気に気づき、ハルに囁いた。
「ナンデ? みんないた方が楽しいじゃん」
「悪いけど」夏樹がめいっぱい気を使った笑みで振り返った。「それは無理。じゃあな」
「ナンデー?」
ユキは夏樹を追いかけようとするハルを引き止め、軽く睨んだ。ハルは「ナンデ?」と、不思議そうにユキの顔を見た。
「ハルちゃんって面白いよねー」
さくらが夏樹お手製のグラタンを口に運びながら言った。
「さくら、すぐ仲良くなっちゃった」
「まぁ、ちょっと変わってるけどな」
夏樹が口元についたチーズをティッシュで拭う。「あいつ誰とでもすぐ仲良くなるんだよなぁ。俺には絶対できねえ」と、そこへ鼻歌交じりの保が帰って来た。
「あ、おかえりー」
夏樹はいつものように一瞬で表情を曇らせ、保の後ろから会釈する真理子を一瞥し、まだ熱いグラタンにスプーンを突き刺した。
「おい夏樹」保は上がって来るなり、手にした袋を夏樹に差し出した。「これ、冷蔵庫入れとけ。しらすボール、チリトマト味三人前だ」
そして、答えず、グラタンをかき回す夏樹に構わずこう続けた。
「明日も行くんだろ? 釣り」
さくらは黙り込む夏樹を背中で感じていたが、その顔は真理子を見て微笑み、そっと立ち去ろうとする真理子の手をふざけたように引っ張っている。
「でもよかったなぁ、いい友達できて」
保は冷蔵庫を開け、しらすボールの入った袋を小さく畳んで空いたスペースに詰めた。
「要らねえよ、そんなん」
夏樹はさくらに聞こえないようにそう言って、空いた皿を下げるついでに、しゃがみ込んだ保の耳元に囁いた。「今朝、変な電話あった」
保はすぐに何の話か感づいて、冷蔵庫のドアを静かに閉めた。
「この店、どうにかする気かよ」
保は足早に自分の部屋へ去る夏樹を見送り、ぐちゃぐちゃに崩れたグラタンを見た。そしてこっちを心配げに見る真理子を安心させるように微笑み、呟いた。「なんだよ。しらす嫌いならいいじゃねぇか、この店どうしようが……」
少し酔いの回った保の声はそれほど小さくなく、確実にさくらの耳に届いた。
さくらはそれでも微笑んでいた。
しかし真理子は、自分の手を引っ張るさくらの手の力が、少し弱くなった気がした。
夏樹は襖を開けて部屋に入る。
そこは夏樹とさくらが一緒に使っている部屋で、釣り具やぬいぐるみなどがアンバランスに置かれている。
机に向かう。目の前の『バスプロ入門』と書かれた本を裏返し、苛立ちを鎮めるようにパソコンにヘッドフォンをつなぎ、マウスを操って曲を再生する。そして夏樹は目を閉じ、周りのものすべてを拒むように左右のヘッドフォンを強く耳に押し当て、グランジロックしか聴こえない世界へと潜り込んでいった。
「ねぇ、夏樹、なんで保っちゃんと釣りシナイ?」
ハルが少し焦げてしまったハンバーグを丸ごと箸で刺して口に放り込もうとしながら言った。
「そりゃ色々あるんだよ」
「イロイロって何?」
「色々は、色々だよ」
ユキは、なんだかつまらない大人みたいだなと思いながらも、そうとしか返せない自分を許そうとしていた。
「ワカンナイ。みんな仲いい方がいい」
「そりゃ、そうだけど」
「だってユキもケイトと仲良しでしょ?」
「そうだけど」
ユキは歯切れの悪い自分にというより、当たり前のことばっかり言って自分を困らせるハルにちょっとイラついた。
「でもユキ、パパとママいない。ナンデ?」
ユキは不意を突かれ、箸を止めた。
「……ハル」
「なあに?」
「もう二度と、余計なこと言うな」
「余計なことって?」
こうやって間髪入れず質問されるのも、もううんざりだ。
「わかったな」
ユキは強引に話を終わらせた。
ハルはユキの元気のない顔を見て、何か変なこと言っちゃったのかなと思ったが、すぐに微笑んだ。そして「ごめんごめーん」と、ハンバーグを丸ごと口に放り込み、ングングともがき始めた。「ほら、見て、ユキ。お口いっぱい!」
ハルはユキが笑ってくれると思ったが、ユキは笑うどころか睨むようにこっちを見ただけだった。
「ケイト、ユキナンデ怒る?」
ハルはユキがいなくなったダイニングキッチンの花たちに話しかける。
「みんな仲いい方がいいのに……」
毎日楽しくて仕方ないのに、ユキは笑ってくれない。「ユキにも嬉しい気持ちがある」ってケイトは言ってたのに。エノシマドン入った時、ユキは笑ってくれたのに……ユキのことが大好きなのに、いつもユキを怒らせちゃう。なんでだろう……
「ねぇ、なんで? なんでなの?」
ハルは答えてくれない花たちを見て、ケイトに会いたいなと思った。
「ハル!?」
次の朝、ユキはハルを起こしに行ったがハルはいなかった。家中探してもどこにもいない。
なんだよあいつ。先行っちゃったのか?
ユキが釣り具を持って釣り場へ行くと、案の定ハルは先に来ていた。
「お前、勝手に先行くなよ」
するとハルは悪戯っ子のように微笑み、一方を指さした。
ユキは思わず声を失った。
な、なんで……
堤防に並ぶ二つの背中。それは夏樹と保だ。
「夏樹と保っちゃん、仲良し!」
ユキは恐る恐る二人に近づき、覗き込む。
二人は無表情でロッドを握っていた。
ユキが声をかけていいのか迷っていると、気配に気づいた夏樹がユキを見た。
「あれ、ユキ」
そして夏樹は我に返ったように自分を見て、隣に立つ保を見た。
すると保も我に返り、驚いた顔で夏樹を見た。
「あ、ごめん。邪魔しちゃった、かな」
ユキが動揺を隠せぬまま立ち去ろうとすると、夏樹の不機嫌な声が聞こえた。
「何しに来たんだよ?」
振り返ったユキの目に、うろたえる保の顔が映った。
「何しにって、あれ? 俺、なんでここに」
怒ったように立ち去ろうとする夏樹に、保が慌てて声をかけた。「おい夏樹」
保はこの滅多にないチャンスを逃さぬよう、微笑み、言った。「せっかくだ。釣ってくか」
しかし夏樹は振り返らない。
そこへ立ちはだかったのはハルだった。
「夏樹だめ。保っちゃん、夏樹と一緒に釣りしたい!」
ハルがまた当たり前のことを言った。
わかってるよ、とユキは思う。それは本当のことだけど、でも……
一瞬の沈黙の後、夏樹はハルを押しのけ、去って行った。
その時、ユキは見た。その顔からすっと笑みが消えた保の顔を。
「夏樹! ナンデー?」
ユキは追いかけようとするハルを制した。「やめろって」
それが正しいことかどうか、ユキにはわからなかった。でも今夏樹を追いかけて連れ戻すのはもっとよくない。そんな気がしたのだ。
「いいんだよ」保が沈む心を精一杯持ち上げて言う。「ありがとな、ハル」
夏樹とは反対の方へ去って行く保の背中は、ユキには少し小さく見えた。
「……ハル、お前まさか」
ユキは少し前から芽生え始めていた疑念をハルにぶつけた。
ユキの悪い予感は的中した。
ハルは悪びれることなく水鉄砲を出した。「うまくいくと思ったのにな」
そののんきで無責任な言葉が引き金となり、ユキの中で何かが弾けた。今までずっとため込んでいたマグマが、一気に喉元まで駆け上がってくる。
「それ、もう使うなって言ったろ」
「でも、ユキにはしなかったよ」
「そういうことじゃないだろ!」
ハルはユキをまた怒らせてしまったと思ったが、どうしても自分が悪いことをしたとは思えなかった。
「でも保っちゃん喜んでた。ユキだってみんな仲いい方がいいって言ったじゃん」
そうだよ。その通りだよ。でも、色々あるんだ。わかんないくせに、何やってんだお前は。
「ユキ怒った? ごめん。ごめんごめーん」
その何度目かの軽すぎる謝罪が、ユキという火山をとうとう噴火させてしまった。
「いい加減にしろよ! なんでそうやって余計なことばっかりするんだよ!」
ハルは口を挟もうと息を吸い込んだが、ユキの噴火は収まる気配がない。
「そんな簡単じゃないんだよ! 宇宙人だからわかんないんだろ、人間の気持ちなんて!」
また言ってしまった。ユキはそう思ったが、仕方ないとも思った。今このマグマを吐き出さないと、そのうち自分がどうにかなってしまう。
「ワカンナイけど、ワカリタイ」
ハルが必死で吐き出したその言葉も、ユキの噴火を収めるには力不足だった。
「無理だよお前には。約束も破るし、最低だよ。もう知らないよお前なんて!」
途端に心細くなったハルは、飼い主に捨てられた子犬のように、ユキの後を追いかけようとした。
「来るな!」
ハルはまた体がぐにゃぐにゃするのを感じた。楽しくしようと思っただけなのに、また楽しくなくなっちゃった。
「もう帰っちまえよ」ユキは勢い余ってそう言ってしまった。「宇宙でもどこでも」
「ユキ……」なんとか振り絞ったハルの声は震えていた。さっきより体がもっとぐにゃぐにゃして、立っていられなくなって、とうとうその場にしゃがみこんでしまった。
その日、ハルは学校に来なかった。
ユキは見たくないと思いながらも、さっきから何度も、騒がしい主を失った机を見てしまっている。振り切って目をそらすと夏樹がこっちを見ていた。ユキはそこからも目をそらし、その視線はとうとう行き場を失ってしまった。
「ケイト、どうしよう……」
ハルがすがるところはケイトしかなかった。
「うーん。約束を破っちゃったのは、ハルが悪いわね」
ケイトは、病室の窓から射し込む午後の光を眩しそうに見ながらそう言った。その口調は柔らかかった。子供相談室の相談員のように、事態をこれ以上深刻にさせないように。
「うん。悪い。ユキすごく怒った」
ケイトはこんなに深刻なハルを見るのは初めてだと思いながら、今は仕方のないことだと思った。ユキとハルはまるで違うタイプの男の子だけど、友達というものに慣れてないのは同じだ。すぐにわかり合える魔法なんてない。時に感じ合ったり、背き合ったり、そういう歴史を積み重ねていくことでしか前に進めないのだ、と。
だからケイトは、止まってしまったオモチャの船にネジを巻くようにこう言った。
「でもユキ、今頃きっとハルのこと心配してるわ」
今必要なことはハルに同情することではない。もう一度船を前に向かせることだ。
「シンパイ?」ハルの頭の単語帳に、また一つ新しい言葉が加わった。
「今ユキは、ハルのことを考えてる。会って話したいと思ってる」
「でもユキ、『来るな』って言ったよ。『ごめん』って言っても、ずっと怒ってたよ」
するとケイトは、恐らく犯しただろうハルの過ちを見越し、そっとそれを訂正した。
「ハル、『ごめんなさい』はね、言葉じゃないのよ」
「え? 『ごめんなさい』は言葉だよ」
ケイトはハルのその当たり前の言葉に小さく噴き出しながら、それでも根気よく続けた。
「でもそれじゃ伝わらない時もあるの」
ケイト先生の課外授業はそこまでだった。
満足いく答えを得られなかった宇宙人の生徒は、地球に来てから一番小さな声で呟いた。
「……ワカンナイ。僕、宇宙人だから」
ユキは、ハルが戻らない空っぽの家の中にいた。目を閉じると、ケイトの言葉が甦った。
「もしハルがいなかったらどう? 毎日楽しいかしらね」
ユキは目を開け、大好きなばあちゃんに珍しく反発した。
「平気だよ、あんな奴いなくたって」
朝になっても、ハルは戻って来なかった。
一人きりだと家が広く感じる。ユキがそう感じるのは初めてではない。ケイトが入院をする時はいつも一人だった。だから平気だ。そう思えば思うほど、そうじゃないという気持ちも自分の中で同じぐらいの大きさになった。それがハルがいないからだとは思いたくないし、思っても仕方がない。
だって、あいつは宇宙人だから。いつまでもここにいるとは限らないから……
漠然と感じていたことだが、はじめてはっきりそう思うと、ユキは不覚にも胸が締めつけられるのを感じた。
なんでだよ。あんな奴、元々いなかったのに……俺となんの関係もなかったのに……
その日、ユキは一回しかハルの机を見なかった。しかしその代わりに、夏樹は昨日より多くユキのことを見た。
帰り道。騒がしい生徒たちの声にうつむいて歩くユキの足元に、見慣れた靴が並んだ。
「なんか、釣りしたくね?」
夏樹だった。
ユキは立ち止まって、気づいた。自分も同じことを思っていた、と。
ユキと夏樹が並んで海にルアーを投げた。
そしてリールを巻いてルアーを操り、そこに魚が食いつくのを待った。
「……静かだな、あいついないと」
ユキも同じことを思っていたが、そう悟られまいと慌てて笑みを作った。「楽でいいよ」
ユキは夏樹の目が自分を疑っているような気がして、ダメ押しのようにこう続けた。
「知らないよ、あんな自己チューな奴」
すると夏樹が小さく笑った。
「そういうこと、言うようになったんだな」
「え?」
「お前、会った頃、いっつもムスっとして何考えてんだか全然わかんなかった」
そっちこそ。ユキはそう思ったが、そんなふうにふざけて返す元気はなかった。
「なんか、変わったよなお前。ハルのおかげかもな」
ユキはドキっとしてしまった自分をすぐに打ち消した。でも慌てて作った笑みはちょっとだけ間に合わなくてぎこちなくなったはずだ。
「あいつってさ」夏樹がまるで本物の小魚のように泳ぐ赤いルアーを見ながら言った。「ほんと図々しいっていうか、ガンガン人ん中入って来て、余計なことばっかするけど、なんか笑えるっていうか、許せちゃうだろ?」
ユキはちょっと驚いた。夏樹がハルについて話すのを聞いたのは初めてだ。そんなふうにハルのことを思ってたなんて知らなかった。
「不思議な奴だよなぁ、ほんと」
ユキは夏樹の意図になんとなく気づいた。だからハルを許してやれよ。そう言ってくれてるのかもしれない。でも……
「もういいよ、あいつのことは。それより早く釣りたい」
半分意地を張って言った言葉だったが、「釣りたい」というのは本当だった。
「思い出せよ、俺が教えたこと」
「うん」
ユキは夏樹が教えてくれたことを頭の中で繰り返した。まず想像する。今、水の中でルアーがどう動いてるか、魚にはどう見えているか。
そして、集中。いつアタリが来るかわからない。グリップを握る手に集中して力を込める。
その時、ユキの手元に振動が来た!
「来た!」
ユキが慌ててリールを巻き始める。
「焦んな! ロッド立てろ!」
しまった。また慌てちゃった!
ユキははやる気持ちを抑え、ロッドを立てて腰に力を入れて踏ん張る。
その時、シーバスが海面からぬっと顔を出した。
で、でかい! でも、ここで慌てたら負けだ。
リールについたドラグが、ジージーと音を立ててラインを送り出す。
「止まるの待てよ」
我慢。とユキは思う。想像、集中、我慢。
夏樹が教えてくれたこの三つをちゃんと守れば、今日こそこの手で、自分だけの手で、魚を釣ることができるはずだ。
その時、ドラグの音が止み、ラインの送り出しが止まった。
「まだ慌てるなよ。ライン保て」
ユキはシーバスの動きをじっと見て、リールを巻いてラインをたるませないように調節した。
「人と魚には、これしかないっていう絶妙な加減があるんだ」
絶妙な、加減。
夏樹は前にこう言った。「自分だけの感覚で動いても相手は思い通りになってくれない。感じろ、相手を」
なんか俺とハルみたいだ。
ユキはふと芽生えたその思いを、慌てて目の前の海に沈めた。
ハルはもういない。俺は一人でシーバスを釣り上げるんだ!
と、その時、突然シーバスが走った!
「わっ!」
「ユキ、慌てんな!」
シーバスはひよっ子アングラーのユキを試すかのように激しく左右に走る。
ユキは焦らずにラインを保つ。
「今度は逃がすなよ」
夏樹の声が、焦るユキの首根っこを.んだ。
大丈夫。今度こそ……
やがてユキは手元からスっと力が抜けるのを感じた。
今だ!
ユキはリールを巻いた。猛烈に暴れるシーバスに負けじと、必死で踏ん張りながら。
「いいぞ。上げろよ、お前の魚だぞ!」
そうだ。あれは、俺の魚なんだ!
「大丈夫! 逃がさない。今度こそ、絶対!」
夏樹はユキの強い決意をはじめて聞いた。そして、絶対に釣って欲しい。そう思った自分に驚いた。釣りは基本、一人でやるもので、誰かと一緒に行っても、自分以外が釣れたら悔しいものだ。
でも今、俺は、ユキに絶対に釣り上げて欲しいと思っている。
「とぅあぁー!」
夏樹は、額に汗をにじませて叫ぶユキを見て、あとは待つだけだと、タモを握った。
身体をそらせてリールを巻くユキの前に、大きなシーバスが迫って来た。
夏樹は落ち着いてタモを構えた。そしてユキが生まれてはじめて手にした宝物を、いつもよりうんと慎重にすくい上げた。
「やった、釣れた!」
ユキは一気に脱力し、ロッドを握ったまま、ペタンとその場に尻もちをついた。
それを遠くから見ていたココは、赤点ギリギリでなんとか進級した生徒を見るように、
「まぁ、よしとするばい」と頷いた。
「見ろ、けっこうでかいぞ」夏樹がまだ暴れるシーバスの口からルアーを外した。
ユキは一瞬だけ成功の余韻に浸ったが、突然思い出したように呟いた。「……写真」
「え?」
「夏樹、撮って。ハルに、ハルに見せなきゃ」
夏樹は夢中でそう言うユキを見て、微笑み、ポケットから携帯を取り出した。
ライトアップされたシーキャンドルの下、ユキの弾むような声が響く。
「ハル、やったぞ。シーバス釣ったぞ!」
しかしハルはまだ帰って来ていなかった。
ユキはため息をつき、リビングのソファに寝転がった。まだ全身が脈打っている。信じられない。自分が魚を釣ったなんて。でも……ったく、ハルの奴、なんでこんな肝心な時にいないんだよ。
ユキは遅れてやって来た疲労感に包まれ、そのままソファで眠ってしまおうかと思ったが、眠りに落ちる寸前でパっと目を開けた。
「ハル、ハル!」
ユキは江の島中を駆け回った。夜とはいえ外で、いつもより大きな声を出している自分に驚いたが、そうでもしないと興奮が収まらない。
俺はシーバスを釣ったんだ。誰かにそれを伝えたい。いや、誰かじゃない。もう認めよう。ハルだ!
あいつ、どこ行っちゃったんだよ。
ユキはふと頭に浮かんだ最悪の予感に震え、灯台の近くで立ち止まった。
あいつ、まさかほんとに宇宙に帰っちゃったのか?
立ち止まると、さっき追い払った疲労感がまた体を包みかけた。いや、つらいのは体だけじゃない。今まで感じたことのない心細さが一気に胸に迫り、息が苦しくなった。
ハル、ハル……
見渡しても誰もいない。家に帰ってもハルもばあちゃんもいない。その事実がユキをたまらなく寂しい気持ちにさせた。
もういいよ、あんな奴。
だってそうじゃないか、とユキは思う。
あいつは宇宙人なんだ。いつかいなくなることはわかっていたはずじゃないか……
あきらめて立ち去ろうとしたその時、ザバン!と海から大きな音が聞こえた。
振り返ると、灯台の灯りに照らされた海面に、うつぶせに浮かぶ人影が見えた。
「……ハル?」
間違いない。あれはハルだ。
そう思った途端、テンパって、顔がこわばり始めた。足がガクガク震え、動けなくなった。
どうしよう。俺、泳げないんだよ!
しかしユキは、海面でゆらゆら揺れるハルの背中を見て、自分の中にあるありったけの覚悟をかき集め、海に近づいた。
なんとかなる。今日の俺はいつもと違う。
だってこの手でシーバスを釣ったんだ!
「とぅあぁー!」
ユキは般若顔になりながら海に飛び込んだ。
ザッバーン!
ユキの覚悟はあっという間に海面で弾けて粉々になった。ハルを助けるどころか、そのまま溺れかけてしまったのだ。
「あれ、ユキ?」
ハルが事もなげにスイスイ泳ぎ始めた。そして手足をバタつかせるユキを不思議そうに見た。「何してんの?」
ユキは、海面から顔を出したり沈んだりしながら叫ぶ。「何してんのじゃねえよ! お前こそこんなとこで何やってんだよ!」
「ちょっと乾いちゃったから水浴び。ユキも?」
「み、水浴びってお前! なんだよそれ!」
ハルはケイトの言葉を思い出し、嬉しそうに尋ねる。「ユキ、僕のことシンパイで来た?」
「当たり前だろ! ちょ、俺、泳げないんだよ!」
それでもハルは嬉しくて、ユキに確かめる。
「僕のこと考えた? 会って話したかった?」
「バカ、今そんなこと。ちょ、ヤバイって。助けてぇー!」
防波堤の手すりにかけられたユキとハルの服がパタパタと風になびいている。
「はーっくしょん!」
ユキが大きくくしゃみをすると、ハルが真似してもっと大きなくしゃみをした。
「ユキ、まだ怒ってる?」
「当たり前だろ。勝手なことばっかしやがって!」
ユキは身振り手振りで思いきりハルに怒りをぶつけた。そうでもしていないと寒くて死んでしまいそうなのだ。
「でももう僕ごめんなさい言わない」
「は? お前反省してないのかよ」
「ううん、違う」
ハルはそう言って水鉄砲を取り出し、ためらうことなく海に投げようとした。
「おい何やってんだよ!」
ユキが間一髪止めると、ハルは真顔で言った。「だってこれなくなれば、約束破らない。ユキ怒らない」
ユキは予想外のその言葉に驚いた。
こいつ、一体どこまでわかってるんだ? 宇宙人のくせに……
「いいよ。もうわかったよ。ほんとしょーがねーな、お前は」
ユキは怒りも寒さも忘れ、芝生の上に大の字に寝転がった。
ハルも真似してその隣に寝転がった。
「ユキ、許してくれた?」
「……俺も、ごめんな」
ユキは恥ずかしくてハルの顔を見られなかったが、これだけはちゃんと言おうと思っていたのでそう言った。
「なんでユキ謝る?」
「だって、なんか怒ってばっかだったからさ。お前宇宙人だもんな。わかんなくて当然だもんな」
ユキはとうとう白旗を上げた。ハルと一緒にいるということは、釣れるかわからない魚を釣ろうとするようなものだ。わからなくて当然。少しでも感じ合うことができたら、嬉しい。
それが俺の、俺なりの結論だ。
「でも、ワカリタイ」ハルは二人のドタバタをずっと黙って見ていただろう星空を見上げて言った。「そしたら、もう喧嘩しない」
ユキはハルを見た。その横顔はいつもの軽くて能天気なハルじゃないように見えた。そして「お前変わったよな」という夏樹の言葉を思い出した。
だったらハルだって、もしかしたら、ちょっとは変わったのかな……
「……そうだ!」
ユキはハっと思い出し、ポケットからスマホを取り出した。
「俺、釣ったんだ。シーバス! でっかいの」
しかし嫌というほど海水に浸かったスマホは、一瞬だけシーバスを抱えるユキの写真を見せて、すぐにシャットダウンしてしまった。
「あっ」
「ユキ、嘘よくない」
「嘘じゃないって! ほんとに釣ったんだって!」
ユキは必死にスマホを再起動させようとするが、それはもはやスマートフォンなどではなく、ただの長方形の小さな板だった。
「ユキ嘘ついたぁー。ケイトに言っちゃうよー!」
「だから嘘じゃないって!」
その子供じみた喧嘩を、海の上からものものしい双眼鏡で覗き込む男がいた。アキラだ。そこは彼が所有するクルーザーの上で、その背後にはターバン姿の部下たちが立っている。
アキラにはわからない。ハルが地球にやって来た目的が。監視すればするほどますますわからなくなっていく。釣りをしたり、江ノ島丼を食べたり、ユキと喧嘩したり、時々悲しい顔をしたり……
「タピオカ、あいつまさか、友達作りにきたんじゃないよな」
「クワっ」
タピオカが何と答えたのか、アキラにしかわからないが、アキラの苛立ちはさらに大きくなってしまったようだ。
「調子乗んなよ、宇宙人が」